ADHDと時間感覚|不正確さの原因・日常生活への影響と対策を解説


ADHDの方は、時間感覚が独特であると言われています。約束の時間に遅れやすかったり、気づいたら長時間が経過していたりと、日常生活のさまざまな場面で影響が出ることがあります。これは単に「だらしない」ということではなく、ADHDの脳機能と深く関わる特性のひとつです。
本記事では、ADHDと時間認知の関係や、時間感覚のズレによって起こる問題、その具体的な対策について詳しく解説します。さらに、医療機関や訪問看護などの専門的サポートについても紹介します。ご本人やご家族が少しでも生活しやすくなるためのヒントとしてご活用ください。
ADHDの方は時間感覚が不正確なのか?
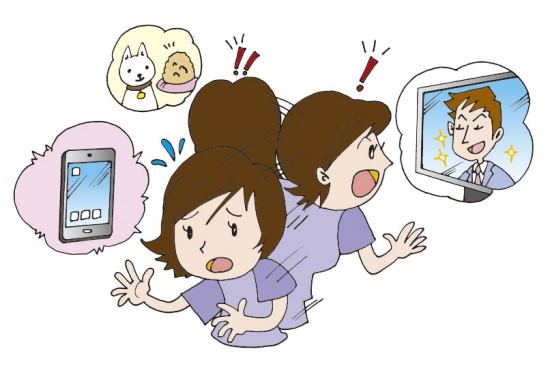
ADHD(注意欠如・多動症)は、不注意や多動性・衝動性を主な特徴とする発達障害です。そのなかでもよく指摘されるのが、「時間感覚が不正確になりやすい」という点です。
一般的に、ADHDの方は「先延ばし」をしてしまう傾向が強いと言われます。これは怠けているのではなく、脳の機能特性によって時間の経過を客観的に捉えにくいことが原因と考えられています。
ADHDの脳機能と時間認知の関係
ADHDの方は、脳の前頭前野や報酬系といった部分の働き方に特徴があることが分かっています。そのため「今の作業にどれくらい時間がかかるか」「締め切りまであと何分あるか」といった見積もりが難しくなります。
結果として、予定よりも長く作業を続けてしまったり、逆に時間が足りなくなって慌ててしまうことが少なくありません。この時間感覚の不正確さは、仕事や学習だけでなく、日常生活全般に影響を与えるのです。
時間感覚のズレが起こりやすい場面(仕事・勉強・日常生活)
例えば、仕事では「メール返信のつもりが気づいたら1時間経過していた」、勉強では「テストまで時間があると思っていたら直前になってしまった」、日常生活では「出かける準備に思った以上の時間がかかり遅刻してしまう」といったケースがよく見られます。
このように、ADHDの時間感覚のズレは多くのシーンで表れ、人によっては生活リズム全体の乱れにつながることもあります。
ADHDと時間盲(タイムブラインドネス)の違い
近年では「時間盲(タイムブラインドネス)」という言葉も広がってきました。これは時間の経過を感覚的に捉えられない状態を指し、ADHDの特性の一部として見られることがあります。
ただし、すべてのADHDの方が時間盲を持つわけではありません。ADHDの特徴である不注意や衝動性と組み合わさることで、時間認知の困難さがより強く表れるケースがあるのです。
次の章では、時間感覚が不正確なことで実際にどのような問題が生じるのかを具体的に解説していきます。
時間感覚が不正確なことで起こる問題

約束の時間に間に合わない
ADHDの方は、衝動性や不注意の影響で「あと何分で出発しなければならないか」を把握しにくい傾向があります。そのため、準備に時間がかかりすぎたり、直前まで別のことに集中してしまい、結果的に遅刻につながります。これは時間感覚が不正確であることが大きく関係しており、本人にとっては努力しても改善が難しいケースがあります。
スケジュールの管理ができない
カレンダーや手帳に予定を記入しても、その通りに行動するのが難しいのもADHDの特徴です。優先順位を誤ったり、作業に想定以上の時間をかけてしまうため、予定全体が崩れやすくなります。また、他者との約束や連絡を忘れてしまい、スケジュールのずれや混乱が生じることもあります。時間管理の困難さが積み重なると、仕事や学習のパフォーマンスにも影響を及ぼすでしょう。
気づいたら長時間経過している
興味のあることに集中しているうちに、気づけば数時間が経過していた――このような経験はADHDの方に多く見られます。特に締め切りが迫っていない場合や楽しい作業の場合、脳が「今この瞬間」に強く引き込まれてしまい、時間の流れを感じにくくなるのです。その結果、やるべきことを後回しにし、直前になって慌ててしまうことも少なくありません。
生活リズムの乱れ
睡眠や食事のタイミングがずれるのも、ADHD特有の時間感覚のズレの影響です。「少しだけ」と思っていた作業が深夜まで続いてしまい、翌朝の起床が遅れるなど、生活リズムが乱れやすくなります。この不規則なリズムは体調やメンタルにも影響し、さらに集中力の低下や不注意の増加を招くという悪循環につながります。
人間関係での誤解やトラブル
時間感覚の不正確さは、人間関係にも影響を与えます。例えば「待ち合わせに遅れる」「締め切りを守れない」といった行動が続くと、周囲から「ルーズな人」と誤解されやすくなります。本人は努力していても改善が難しいため、相手に理解してもらえないとストレスや孤立感につながることもあります。こうした誤解は信頼関係の構築を妨げ、仕事やプライベートでの人間関係の悩みを深める要因となります。
このように、ADHDにおける時間感覚の不正確さは、単なる遅刻や忘れ物にとどまらず、生活全般や人間関係にも影響を与える重要なテーマです。次の章では、この課題に対して実際に取り組める対策について解説していきます。
ADHDで時間感覚が不正確な時の対策

タイムログをとる
スマホやストップウォッチで計測
かかった時間を振り返る
まず有効な方法のひとつが「タイムログ」をとることです。タイムログとは、日常の行動にどれくらい時間をかけているかを記録するものです。ADHDの方は時間感覚が不正確になりやすいため、実際の所要時間を可視化することで、自分の認識と現実の差に気づきやすくなります。朝の準備や通勤、家事などを細かく書き出し、繰り返し確認することで、徐々に時間の見積もり精度が高まります。
作業時間・優先順位づけを考え直す
・作業を小さな単位に分ける
・優先度を色分けや番号で整理
・集中できる環境を整える
ADHDの方は、スケジュールを立ててもその通りに進められないことが少なくありません。そのため「作業を小分けにする」「重要度の高いタスクから始める」など、優先順位を再考することが大切です。大きな作業を細分化すれば、達成感を得やすくなり、集中が途切れにくくなります。さらに、締め切り直前になって慌てるのを防ぐ効果も期待できます。
都度計画の立て直しを図る
・計画が崩れることを前提に修正案を準備
・進捗を見て短いスパンで調整する
立てた計画が想定通りに進まないのは自然なことです。特にADHDの方は、突発的な出来事や集中の偏りによって予定が崩れやすい傾向があります。そこで、あらかじめ「進まなかった場合の代替案」を用意しておくと安心です。都度計画を見直し、柔軟に調整することでストレスを軽減し、実行力も高めることができます。
アラームやタイマーの活用
スマートフォンやタイマーを利用し、作業時間を区切る方法も効果的です。例えば「30分作業+5分休憩」のサイクルを繰り返すことで、ダラダラと時間を浪費せず集中を維持できます。音だけでなく、バイブレーションや画面の色が変わるアプリを使うと、より効果的に時間を意識できるでしょう。
アプリやガジェットを使った時間管理
近年は時間管理に役立つアプリやデジタルガジェットが豊富に登場しています。スケジュール管理アプリ、タスク管理ツール、集中をサポートするポモドーロアプリなどを活用することで、自分に合った方法を見つけやすくなります。視覚的に「残り時間」が表示されるツールは、ADHDの方に特に相性が良いといえます。
視覚的に時間を把握できるツール(タイムタイマーなど)
「タイムタイマー」と呼ばれる視覚的に時間を表す時計は、ADHDの方に人気のあるツールです。残り時間が色や形で直感的にわかるため、「あとどれくらいで終わらせなければならないか」を把握しやすくなります。学校や職場、自宅でも使いやすく、子どもから大人まで幅広く活用できます。
対策を立てる際の注意点
- 仕組みやルールを明確にして習慣化する
- 重要な予定は事前にシミュレーションする
- 家族や同僚に協力をお願いする
- 遅刻しないために余裕を持ったスケジュールを設定する
時間管理の工夫は「一度で完璧にできること」ではありません。少しずつ試行錯誤しながら、自分に合った方法を見つけていくことが重要です。次の章では、ご本人だけでなく家族や周囲ができるサポート方法について紹介します。
家族や周囲ができるサポート
声かけやリマインドの工夫
ADHDの方は、時間感覚の不正確さによって約束やスケジュールを忘れやすくなります。そのため、家族や周囲が定期的に声をかけたり、リマインドを工夫することが大切です。
例えば「あと10分で出発だよ」と具体的に伝える、スマホのリマインダーを共有する、予定をホワイトボードに書き出すなどの方法が有効です。こうした工夫は「本人の努力不足」ではなく「脳の特性に合わせた支援」であることを理解することが重要です。否定的な言い方ではなく、前向きなサポートを心がけることで、本人も安心して取り組めるようになります。
一緒にスケジュールを立てるサポート方法
本人が一人でスケジュールを立てるのが難しい場合は、家族や支援者が一緒に計画を立てることが役立ちます。特にADHDの方は「どの作業を優先すべきか」「どれくらいの時間をかければ良いか」を見積もるのが難しいため、第三者が関わることで現実的な予定に近づけることができます。
たとえば「宿題は30分で終わるかな? じゃあ次に休憩を入れて、また30分作業しよう」といった具体的な区切りを設けると効果的です。仕事や家事の場合も「一緒に計画を確認してから行動する」だけで、見通しが立ちやすくなります。
また、スケジュールを立てた後も「進捗を振り返る時間」を共有することが大切です。「予定通りに進んだ部分」「予想外に時間がかかった部分」を一緒に確認することで、次の計画に生かすことができます。これは本人の自己理解を深めるだけでなく、家族がADHD特有の課題を理解する良い機会にもなります。
このように、周囲の関わり方によってADHDの方の生活は大きく変わります。ADHDの方の時間感覚のズレを本人だけに解決させるのではなく、家族や支援者が協力して補い合うことで、日常生活や社会生活をよりスムーズに送れるようになるのです。次の章では、医療機関で行われているADHDの治療方法について見ていきましょう。
医療機関でのADHDの治療方法は?

薬物療法
ADHDに対する薬物療法は、症状を完全に治すものではなく、注意力や集中力をサポートするための補助的な手段です。薬の効果によって「気の散りやすさ」や「衝動性」が軽減されると、生活リズムや時間感覚の調整にも良い影響が期待できます。
ただし、副作用が出ることもあるため、必ず医師の指導のもとで適切に使用することが大切です。薬を使うことで本人が生活を送りやすくなる一方、環境調整や日常的なサポートと併用していくことが推奨されています。
心理社会的治療
心理社会的治療には、環境調整や行動療法、ソーシャルスキルトレーニング(SST)などがあります。
例えば環境調整では「集中できる場所を整える」「予定を視覚化する」など、ADHDによる時間感覚の不正確さを補う工夫を取り入れます。行動療法では「うまくできた行動を褒める」「望ましくない行動が起きる前にきっかけを減らす」といった方法で習慣を身につけやすくします。
SSTでは、対人関係のスキルを練習し、社会生活での困難を減らしていくことが可能です。薬物療法とあわせて取り組むことで、よりバランスの取れた支援が行えます。
ADHDの方をサポートしている機関
ADHDの方やご家族が相談できる場所は、医療機関だけではありません。地域ごとに設置されている支援センターなどでも、専門的なアドバイスや生活サポートを受けることができます。特に、時間管理や生活リズムの調整は一人で抱え込むのが難しいため、専門機関のサポートが有効です。
発達障害者支援センター
発達障害のある方やその家族を対象に、相談や生活サポートを行う施設です。社会福祉士などの専門職が在籍しており、具体的な対策を一緒に考えることができます。
児童(子ども)発達支援センター
子どもを対象とし、医師や心理士による相談、検査、リハビリテーションを行います。時間の見通しをつける練習や学習支援も提供されています。
児童(子ども)家庭支援センター
家庭の悩みや子どもの生活リズムについて相談できる総合窓口です。ショートステイや一時預かりなどの在宅サービスもあります。
地域障害者職業センター
就労に関する支援を行う施設で、ハローワークと連携しながら職業生活の安定を支えます。ADHDによる時間管理の難しさを考慮したアドバイスを受けられることもあります。
このように、医療機関と地域の支援機関を上手に組み合わせることで、ADHDの方の生活全体を支えることができます。次の章では、在宅で利用できる精神科訪問看護について詳しく紹介します。
精神科訪問看護も利用してみる

| サービス名 | 精神科訪問看護 |
|---|---|
| 職種 | 看護師 ・准看護師 ・作業療法士 |
| 訪問日数 | 週1〜3回(状況により週4回以上も可能) |
ADHDの診断を受けている方や、時間管理の困難さで日常生活に支障が出ている方には、精神科訪問看護の利用もおすすめです。医師の指示書があれば、在宅で専門職による支援を受けることができます。特にADHDによる時間感覚のズレが原因で生活リズムが乱れやすい場合、定期的な訪問は生活の安定につながります。
精神科訪問看護では、服薬管理や通院のサポートだけでなく、日常生活の時間の使い方を一緒に振り返る支援も行います。例えば「朝の準備にどれくらい時間をかけているか」「食事や睡眠のリズムがどのように崩れやすいか」などを確認し、具体的な改善策を一緒に考えます。本人が気づきにくいパターンを第三者の視点で見直すことで、より現実的な工夫が見つかるのです。
また、ご家族に対しても「どのように声をかけると良いか」「リマインドを負担なく続ける工夫」などを助言します。本人だけでなく周囲の人のサポート方法を整えることで、家庭全体の安心感が高まりやすくなります。特に家族の負担軽減は長期的なサポートに欠かせない要素です。
さらに、精神科訪問看護は在宅で行えるため、外出が難しい方や、通院に強いストレスを感じる方にも適しています。専門職が定期的に訪問することで、症状の悪化を早めに察知し、再発を防ぐ効果も期待できます。
このように、精神科訪問看護はADHDの特性による生活の困難を軽減するための有効な選択肢です。次の章では、シンプレ訪問看護ステーションが提供するサービスや対応エリアについて紹介します。
精神疾患をお持ちならシンプレへ

当ステーションの特徴
シンプレ訪問看護ステーションは、精神疾患に特化した訪問看護を行っています。日常生活の支援に加えて、服薬確認や通院サポート、再発予防などを通じて、ご利用者さまが安心して生活できる環境を整えています。特にADHDによる時間感覚の不正確さによって生活リズムが乱れやすい方に対しては、定期的な訪問で行動や習慣を一緒に見直す支援も可能です。
また、ご家族に向けた相談対応や、社会資源の活用方法に関するアドバイスも行っており、「本人と家族の両方を支える」ことを大切にしています。
対象となる精神疾患
・うつ病・統合失調症・発達障害(ADHDを含む)
・知的障害・PTSD・双極性障害
・不安障害・薬物依存症・アルコール依存症
・パニック障害・ひきこもり・適応障害・強迫性障害
・自閉スペクトラム症・認知症
このように幅広い精神疾患に対応しており、疾患の特性に応じた支援を受けることができます。服薬や生活リズムのサポートはもちろん、社会復帰や人間関係の改善など、生活全般に寄り添う看護を提供しています。
シンプレの対応エリア
対応エリアは、東京23区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、府中市、東久留米市、さらに埼玉県の一部地域です。近隣の市区町村についても訪問可能な場合があるため、詳細はぜひお問い合わせください。訪問は週1〜3回を基本とし、状況に応じて週4回以上の対応も行っています。祝日や土曜日も訪問可能なため、ライフスタイルに合わせて柔軟に利用できます。
シンプレ訪問看護ステーションは、病気の特性を理解しながら生活に寄り添うサポートを提供しています。「日常生活がうまく回らない」「服薬や通院が不安」「家族としてどう支えていいかわからない」といったお悩みを抱えている方は、まず一度ご相談ください。次の章では、記事全体のまとめとして、ADHDと時間感覚に関する理解と支援のポイントを整理します。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

ADHDと時間感覚の不正確さの理解が第一歩
ADHDの方にとって、時間感覚の不正確さは避けられない特性のひとつです。約束に遅れてしまう、気づいたら長時間が経っている、生活リズムが崩れてしまう――これらは本人の努力不足ではなく、脳の働き方の違いから生じるものです。そのため、本人も周囲も「怠けているのではなく特性によるもの」と理解することが最初の一歩となります。
日常での工夫と専門的サポートの両立が大切
タイムログをとる、アラームやタイマーを活用する、優先順位を細かくつけ直すなど、日常でできる工夫はたくさんあります。さらに、家族や支援者が声かけやスケジュール調整を手伝うことで、本人の負担を軽減できます。セルフケアと外部からのサポートの両立こそが、ADHDの時間感覚に伴う困難を和らげる鍵といえるでしょう。
困った時は医療機関・支援サービスに相談
工夫や努力だけでは解決が難しい場面もあります。その場合は、医療機関での薬物療法や心理社会的治療を検討したり、地域の発達障害者支援センターや家庭支援センターに相談することが有効です。また、外出が難しい方や生活全般の支えが必要な方には、精神科訪問看護という選択肢もあります。専門職が定期的に訪問し、服薬や生活リズムをサポートすることで安心感が得られるでしょう。
ADHDの方が社会や日常生活で自分らしく過ごすためには、ADHDによる時間感覚の特性を理解し、無理なく続けられる対策を積み重ねることが大切です。ご本人やご家族が困ったときは、医療機関や訪問看護サービスなどの支援を活用しながら、より良い暮らし方を一緒に見つけていきましょう。
ご相談の問い合わせはこちら▼

Words-HATCH.Create
医師:八巻孝之
医師歴37年、適応障害と随伴する抑うつ・不安・睡眠障害対応が得意。外科医から地域医療にて、うつ病、適応障害・アルコール依存・不安障害・パニック障害・などを相談受けております。
本記事へのコメント
記事はADHDと時間感覚の関連性について分かりやすく説明しており、実生活への影響や対策方法について具体的に提案しています。
最新の研究結果や医学的根拠、治療法に関する詳細な情報については、下記の参考文献をご参照ください。
参考文献:
(1)成人ADHDにおける時間知覚: 10年間のレビューからの所見
(2)Functional Connectivity Dynamics show Resting-State Instability and Rightward Parietal Dysfunction in ADHD
(3)A Network Theory Investigation into the Altered Resting State Functional Connectivity in Attention-Deficit Hyperactivity Disorder
(4)注意欠陥多動性障害(ADHD)の身体性研究の鳥瞰図を描く
(5)注意欠陥多動性障害ADHDが示す「落ち着きつきのなさ」の再考
監修日:2025年11月7日
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (5)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



