学習障害は遺伝するの?関係性や特徴について簡易チェックしよう
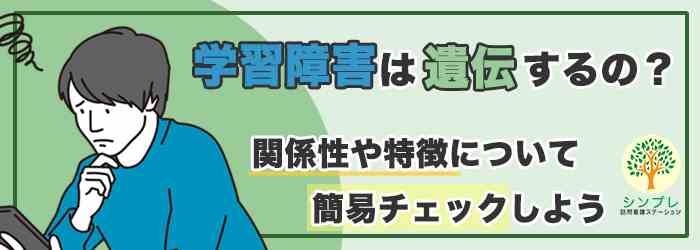
学習障害(LD)は、生まれつきの脳の働きや情報処理の特性によって、読み書きや計算などに困難が生じる発達障害の一つです。
最近では「学習障害の遺伝」という言葉が注目され、親から子へ遺伝するのか気になる方も多いのではないでしょうか。
実際、学習障害は生まれつきの要因と環境的な要因の両方が関係しているとされており、家族の中に似た特性を持つ人がいることも少なくありません。
ただし、遺伝だけで決まるわけではなく、環境や成長過程によって症状のあらわれ方が変わるため、早期に気づき適切な支援を受けることが重要です。
この記事では、学習障害と遺伝の関係、特徴、そして支援方法についてわかりやすく解説します。
もし生活の中でサポートを必要としている場合は、精神科訪問看護に特化したシンプレ訪問看護ステーションまでお気軽にご相談ください。
学習障害と遺伝の関係を知ろう

学習障害の遺伝確率について
- 学習障害は生まれつきの特性である
- 遺伝的要因が関係するが、環境要因も影響する
学習障害は、脳の情報処理の一部に特性があることで、読み・書き・計算などに困難が生じる発達障害です。
研究では、親子や兄弟姉妹間で同様の特徴がみられることが報告されており、遺伝的な関与があると考えられています。
ただし、特定の遺伝子が直接原因とされているわけではなく、
複数の遺伝的要素と環境的要素が複雑に影響しあって発症する可能性が高いとされています。
同じ家庭で育っても学習障害がある子とない子がいるのは、このような環境要因の違いによるものです。
たとえば、周囲の理解や学習のサポートが得られない場合には症状が強く出やすくなることもあります。
そのため、早めの気づきと適切な環境づくりが何より大切です。
学習障害は男児に多いといわれる理由
統計的には、学習障害は女児よりも男児に多くみられる傾向があり、男女比はおよそ2〜3:1とされています。
この理由として、脳の発達過程における性差や、言語発達に関係する脳領域の働き方の違いが関係していると考えられています。
また、学校生活の中で「文字の読み書きが苦手」「計算が極端に遅い」などの特徴が男児で顕著に見られることが多く、早期発見につながるケースもあります。
学習障害の遺伝との関連性に加え、性別による発症傾向も理解しておくことで、より的確な支援が可能になります。
学習障害は発達障害のひとつ

学習障害とはどんな障害か
学習障害(LD)とは、知的発達に遅れは見られないものの、読む・書く・計算するといった特定の学習分野で困難が現れる発達障害の一種です。
脳の働き方に個性があることで情報処理のスピードや方法が異なり、学校での学習内容が理解しづらくなる場合があります。
この特性は「努力不足」や「怠け」と誤解されがちですが、本人の意思ややる気の問題ではありません。
むしろ、本人は理解されないつらさや自信の低下に苦しむことが多いのです。
学習障害は発達障害の一つであり、生まれつきの脳機能の特性によるものと理解することが、支援の第一歩となります。
また、「学習障害の遺伝」という観点から見ても、親やきょうだいに同様の傾向がみられることがあります。
家庭の理解と環境の調整により、子どもの困難さは大きく軽減できる可能性があります。
学習障害の種類を解説
学習障害には主に3つのタイプがあり、それぞれ特徴が異なります。
これらは単独で現れることもあれば、複数が重なるケースもあります。
以下で詳しく見ていきましょう。
読字障害
文字を読むことに困難があり、音読に時間がかかる、文字の形が似ていると混乱してしまうなどの特徴がみられます。
幼児期には発音が不明瞭で、言葉の理解に時間がかかることもあります。
読字障害は学習障害の中で最も多く、英語圏だけでなく日本でも注目されているタイプです。
書字障害
書くことに困難があり、文字が不揃いになる、誤字脱字が多い、鏡文字を書いてしまうといった特徴があります。
手先の動きや空間認識にも関係しており、ボタンを留める・はさみを使うなどの動作にも苦手さが見られることがあります。
算数障害
数や量の概念がつかみにくく、計算手順の理解が難しいタイプです。
「繰り上がり・繰り下がり計算が苦手」「文章問題の意味が理解しづらい」などが特徴で、
数学的思考が必要な場面でつまずきやすい傾向にあります。
小学校就学前にみられる学習障害
就学前の段階では、「言葉を覚えるのが遅い」「バランス感覚が弱い」「指先が不器用」といった様子から気づかれることがあります。
ただし、幼児期の成長スピードには個人差が大きいため、この段階では明確な診断は難しく、
経過観察を続けながら小学校入学後に判断されることが多いです。
成人してからわかる学習障害
学習障害は子どもだけのものではなく、大人になってから診断されるケースもあります。
社会人になって「指示の理解に時間がかかる」「数字や書類処理が苦手」などの困りごとから、初めて自身の特性に気づくこともあります。
特に近年は、発達障害への理解が進んだことで、成人期に診断を受ける人も増えています。
学習障害の診断方法

出生前や乳児期での診断は難しい
学習障害は外見上の特徴がなく、知的発達にも遅れが見られないため、出生前や乳児期に診断することは非常に難しいとされています。
発達のスピードには個人差があり、幼少期の段階では「まだ成長途中」と判断されることも多いです。
しかし、「ことばの発達が遅い」「手先が不器用」「集団で遊ぶのが苦手」といった兆候は早期に見られる場合があります。
こうした傾向が見られる場合は、成長を見守りながら、必要に応じて専門機関に相談することが大切です。
学習障害の診断は成長に合わせて総合的に行われるため、焦らず観察を続けることが重要です。
児童期以降に判明することが多い理由
本格的な学習が始まる小学校入学以降に、読み書き・計算などの課題が明確に現れることから、児童期に診断されるケースが多く見られます。
「何度練習しても漢字が覚えられない」「計算が極端に苦手」といった困りごとがある場合、家庭のしつけや努力不足の問題ではなく、学習障害の可能性を考える必要があります。
また、学習障害の遺伝による特性がある場合でも、支援や学習方法の工夫によって大きく改善することがわかっています。
子ども一人ひとりに合った学び方を見つけることで、学習意欲や自信を取り戻すことができます。
学習障害の検査で行われること
| 学習障害の検査項目 | 検査方法 |
|---|---|
1.知的機能検査
|
全体的な知的発達を確認し 学習のつまずきとの関連を判断。 |
2.読み書き検査 |
音読や文字の理解力を測定し、 読字・書字障害の有無を確認。 |
3.その他補足検査(心理検査) |
認知能力や注意力、 記憶などを評価し、 日常生活への影響を把握。 |
これらの検査は、小児科や発達外来、心理検査室などで行われます。
医師や臨床心理士が問診を通して成長の経過や家庭環境、学校での様子を総合的に判断します。
また、必要に応じて脳波検査やMRI検査を行い、他の疾患の可能性を除外します。
学習障害の簡易チェックリスト
「もしかしてうちの子も?」と感じたときは、以下のような簡易チェックを行うと目安になります。
該当する項目が多い場合は、専門機関への相談を検討しましょう。
読字障害
発音がはっきりしない
文字や数字、色などの名前を覚えるのが苦手
計算はできるが、単語の問題が苦手
書字障害
鏡文字や雰囲気で書く
誤字脱字が多い
漢字が苦手で、覚えられない。
黒板やプリントの字が書き写すのが苦手
鏡文字を書く
雰囲気で「勝手文字」を書く
算数障害
計算(繰り上げ、繰り下げなど)が苦手
数の大小の理解が困難
文章問題の理解が困難
図形やグラフの理解が困難
読字障害・書字障害の合併
・「ね」「れ」「わ」が似ているように見える
カタカナの読み書きが苦手
「ソ」「ン」、「シ」「ツ」が似ているように見える
特殊音節(拗音・長音・促音)の読み書きが苦手
・拗音
「ゃ」「ゅ」「ょ」など
・長音
母音の1つを長く伸ばした音節
「ー」がつくことで表される
・促音
「っ」「ッ」など
学習障害をお持ちならシンプレ訪問看護ステーションへ

シンプレ訪問看護ステーションの特徴
- 利用者様の自主性を尊重
- 精神科・発達障害に特化した訪問看護
- 利用者一人ひとりの生活背景に寄り添ったサポート
- 医療機関・行政・家族との連携体制
シンプレ訪問看護ステーションは、精神科・発達障害領域に特化した訪問看護サービスを提供しており、看護師・准看護師・作業療法士がチームで連携し、症状だけでなく生活面や社会的サポートまで総合的に支援します。
訪問時間は30〜90分、週1〜3回から利用でき、土曜日や祝日も対応しています。
「学習障害の遺伝」など、生まれつきの特性が原因で生活に困難を抱える方が安心して暮らせるように、利用者の意思を尊重しながら支援計画を立て、「その人らしく」家庭や地域社会での自立を促すことを目的にサポートしています。
精神科訪問看護とは?
・精神科・心療内科に通院している方
・発達障害や学習障害をお持ちの方
・医師が訪問看護を必要と判断した方
訪問職員
・看護師・准看護師・作業療法士
訪問時間
・1回30〜90分/週1〜3回(※必要に応じて週4回以上も可)
精神科訪問看護では、医師の指示のもとで看護師やリハビリ専門職がご自宅に伺い、病状の観察や服薬支援、生活リズムの調整、家族支援などを行います。
発達障害や学習障害を持つ方の場合、日常生活の中で「集中できない」「感情のコントロールが難しい」などの困難をサポートし、安心して過ごせる環境づくりをお手伝いします。
シンプレで対応している精神疾患
- うつ病・双極性障害
- 統合失調症・不安障害
- 発達障害(学習障害・ADHD・自閉スペクトラム症)
- PTSD・パニック障害
- アルコール・薬物依存症
- 認知症・適応障害 など
シンプレは、これらの疾患に対して幅広く対応しています。
特に発達障害や学習障害をお持ちの方に対しては、症状に応じた訪問スケジュールの調整や、生活習慣のサポート、社会復帰のための支援も行っています。
ご家族からの相談にも応じ、医療機関との連携を図りながら最適なケアを提供します。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレは東京都23区を中心に、西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・東久留米市・埼玉県の一部地域を訪問エリアとしています。
近隣地域であれば訪問可能な場合もあるため、まずはご相談ください。
訪問看護の利用を検討している方、また「学習障害の遺伝」などの特性をもつお子さまやご家族のサポートを希望される方は、電話やメールでお気軽にお問い合わせください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ|学習障害と遺伝の関係を正しく理解して支援につなげよう

学習障害は、生まれつきの脳の情報処理の仕組みに特性があることによって起こると考えられています。
そのため、学習障害の遺伝という言葉が注目されるように、家族間で似た特性がみられるケースもあります。
しかし、遺伝だけが原因ではなく、成長過程や環境の影響によっても発症の有無や程度が変わるため、生活環境の整備や周囲の理解がとても重要です。
たとえ学習障害があっても、本人の能力が低いわけではありません。
適切な支援と理解があれば、自分の得意分野を生かして社会で活躍している人も多くいます。
家庭や学校、地域全体でのサポートが、本人の成長と自立を大きく後押しします。
学習障害は「できない」ではなく「やり方が違う」という個性と捉え、特性に合わせた支援を行うことが大切です。
もし、学習や生活面での困りごとがあり、家族だけで支えるのが難しいと感じたら、専門的な支援を受けることをおすすめします。
精神科や発達支援に特化した訪問看護を行う「シンプレ訪問看護ステーション」では、学習障害や発達障害を含むさまざまな精神疾患に対応しています。
訪問看護では、看護師や作業療法士がご自宅に伺い、生活のサポートや服薬管理、再発予防などを行いながら、ご本人とご家族が安心して過ごせるよう支援します。
特に、社会との関わりが難しく感じる方にとって、自宅で支援を受けられることは大きな安心につながります。
「学習障害」や発達障害に関する不安を抱えている方、また支援を必要としているご家族の方は、ぜひ一度シンプレまでご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (5)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



