ADHDは発達障害の一種。特徴や症状を持つ方への接し方について解説
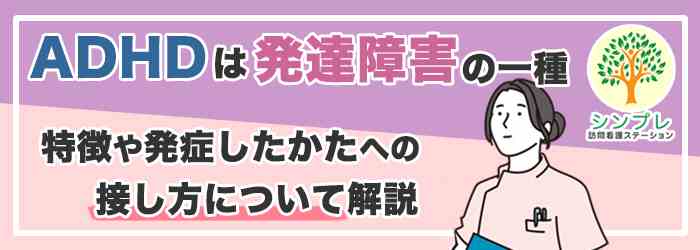
ADHDは、発達障害の一種で、物忘れが多かったり定位置にじっと座っていられなかったりなど、日常生活にも支障をきたすことがあります。子供の頃に症状が見られ、子供のうちに気付いて療養をすれば改善することもあります。
子供がADHDだと気づいたあと、どのように接すればよいのでしょうか。今回は、ADHDを発症した子供への接し方を紹介します
発達障害「ADHD」とは
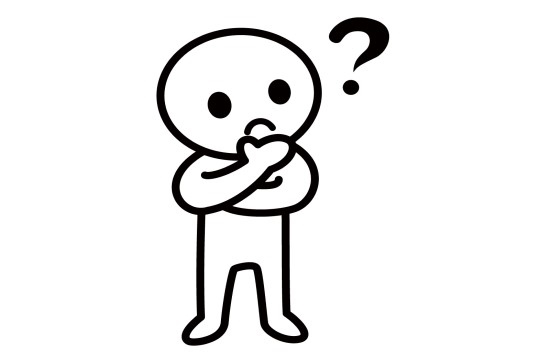
ADHDとは
ADHDは、不注意や多動性、衝動性の症状が特徴的な発達障害です。不注意、多動性、衝動性の症状があり、元気な子供と見られることもある一方で、はしゃぎすぎると見られることもあります。
ADHDの症状としては、集中力が続かない、じっとしていられない、こだわりが強い、対人関係を築くのが難しいなどがあります。脳に原因があると考えられています。
治療法としては、おもに療育(集中できる環境づくりや集団行動、自己コントロールの練習など)が行われますが、症状によっては薬物療法を行うこともあります。
ADHDを発症する割合は?
割合:3~7%程度
成人期
割合:3~4%程度
ADHDは、子供だけのものではありません。成長しても症状が続く方や、大人になってから気づく方も増えています。
特に、成人の3〜4%が持っていると言われており、診断を受ける大人も増えており、症状が軽い場合や、周囲の環境によっては見過ごされてしまうこともあります。
大人になり、職場でミスを繰り返してしまうなど、日常や社会生活でADHDの症状が表面化することで気づくこともあります。
ADHDの特徴
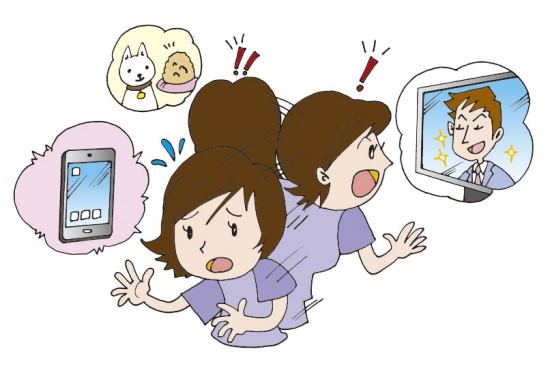
不注意
・長い時間集中できない
・外からの刺激で気がそれる
不注意の特徴が強いと、気が散りやすく集中力が続かないため、毎日のように宿題を忘れたり、授業中でも別のことをやりだしたり、途中でどこかへいってしまうことがあります。
自分の好きなことや興味があることに対して集中力が増すので、話しかけても反応しないことが多く、満足するまで作業を続けますが、思い通りにならないと怒りだしてしまうことも少なくありません。
大人になると仕事でケアレスミスを多発してしまうなど、上司や周りから真面目に仕事をしていないと思われたり、人間関係に思い悩んでしまうことが多くなり、働きづらくなってしまうこともあります。
多動性
・多動性の傾向が強い
・落ち着きがない
多動性の特徴は、授業が終わるまで座っていられない、大人になるとデスクワーク中でも、常に身体を動かしているなどがあり、とにかくじっとしているのが苦手なようです。
たとえば、授業中や仕事中、食事中であっても、急にやりたいことを思いつき深く考えずに実行に移すので、自己コントロールが苦手な傾向があります。
また、落ち着いて話を聴くのが苦手で、会話の中で割り込んだり、自分の話を一方的にしたりすることもあります。
衝動性
・衝動性の傾向が強い
・無意識に身体が動く
衝動性の特徴は、子供だと急に高いところに登ったり、危険なことを考えずに行動したり、我慢することができずに感情的になったりすることがあります。
感情のコントロールが苦手で衝動を抑えることが難しく、自分の嫌なことをされると乱暴になってしまい、トラブルを起こしてしまうことがあります。
また衝動を抑えることが難しく、自分の意見を押し通そうとして、周囲との衝突につながることもあります。
ADHDを発症する原因
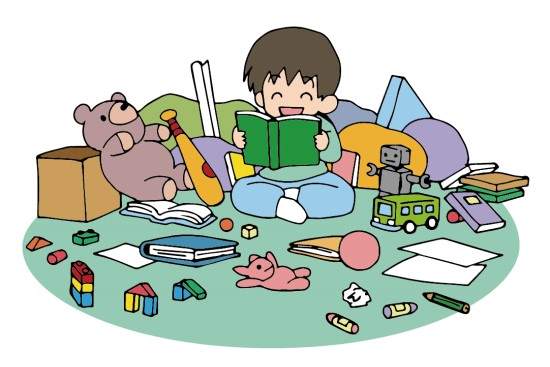
前頭前野の機能調節に偏りがある
ADHDの原因は、生まれつきの脳の機能障害であると考えられており、前頭前野という部分の機能が注目されており、ドーパミンなどの神経伝達物質がうまく働かないことで、集中力や注意力が欠け、衝動的な行動などの症状が現れます。
具体的には、授業や宿題などの興味のないことに集中できず、ゲームや遊びなどの興味のあることへの集中力が高すぎるといった特徴があります。
育て方が悪いからと悩んでしまう方もいますが、決して誰かのせいではないのです。
脳内の神経伝達物質が不足
その他のADHDの原因に、神経伝達物質の量が不足したり、働きが異常になったりすることで、脳の機能がうまく働かなくなり、ADHDの症状が現れる考えられています。
ADHDの方は、ノルアドレナリンやドーパミンなどの神経伝達物質の量が少ないことが指摘されています。
ノルアドレナリンは意欲や興奮に関わる神経伝達物質で、ドーパミンは集中力や注意力に関わる神経伝達物質です。
また、衝動性や情緒のコントロールに関わるセロトニンなどの抑制性神経伝達物質の働きも異常になっていると考えられています。
ADHDの方への接し方

「できること」に着目する
できないことばかりが気になったり、注意をしたり叱ったりすることが多くなると、ADHDの子供は自信を失ってしまうので、その子ができることに目を向けるようにしましょう。
不得意なことにばかり目が行ってしまうこともあるかもしれませんが、時にはその子の良いところや頑張っているところに目を向け、褒めてあげることが大切です。
褒められることで自分自身に自信がつき、不得意なことにもチャレンジする意欲が育まれていきます。
細かく声かけを行おう
ADHDの子供は傷つきやすかったり、否定的な言葉で叱られると、自信を失ったり、反抗的になることがあります。
また、叱り方によっては怒られているということだけしか頭に入ってこなかったりすることがあります。
注意をするときは、きつい口調で感情的に叱らず、人格を否定しない表現で、ミスが多くても細かいことあれこれと一度に注意しないことが大切です。
具体的には、割り込みをする子には「順番をまもろうね」、静かにしなくてはいけない場所では「ここでは静かにしようね」と、わかりやすく短い言葉で声かけするようにしましょう。
。
時間や行動にメリハリをつける
授業中など静かにしなければならない時間でも、ADHDの子供は、じっとしていらなかったり、動き回りたくなります。無理に静かにさせるのではなく、授業の途中で休憩をとり、体を動かせる時間をつくってあげましょう。
たとえば、先生の手伝いをしてもらったり、黒板をきれいにするなど、役割を与えることで、体を動かしていい時間と課題に集中するなど、静かにする時間のメリハリをつけることができます。
また、ADHDの子供は、失敗を恐れて、チャレンジすることをためらうことがあります。周囲の大人は、子供と一緒に失敗しない対策を考え、ADHDとうまく付き合っていける方法を話し合い、成功体験がたくさん経験できるようサポートしましょう。
ADHDを相談できる場所はあるの?

相談機関
ADHDを相談できるところは、どのような場所があるのかをみていきたいと思います。
学校
自分の子供にADHDの症状に似た行動があるけど、どの程度で病院にいけばいいかわからないと迷ってしまうときは、学校や幼稚園など担任の先生に相談してみましょう。
先生は子供たちをつねに見ているので、学校や幼稚園の様子を聞いてみることで、ADHDの症状はどの程度でているかがわかることが多いでしょう。
児童家庭支援センター
児童相談所や児童福祉施設と連携をとりながら、家庭や市町村からの専門的な相談や支援を行う、地域の相談機関です。
メンタルケアを専門とする職員も在籍しているところもあり、子供たちや保護者へのアドバイス、市町村への技術的なアドバイスや援助を行っています。
家庭児童相談室
家庭での子供のしつけ、子供の不登校や非行などのなやみ、心配ごとにたいする相談に応じ支援をおこなうため、市町村の福祉事務所に設置されています。
家庭相談員や社会福祉主事の資格をもつ職員が相談にのり、児童相談所や学校と連携をとりながら、家庭児童相談が円滑におこなわれます。
医療機関
小児神経科
小児神経専門医は、子どもの脳や神経の病気を診る専門医です。子どもの運動や知能、こころの問題など、神経系の機能障害を起こす病気の治療を行います。
全国に約1000人程度の小児神経専門医がおり、心身障害や知的障害、広汎性発達障害などの子どもの療育にも力を入れています。福祉や教育機関と連携して、子どもたちがよりよい療育を受けられるようにしています。
児童精神科
児童精神科は、子どものこころの病気や発達障害を診る専門の病院です。主に幼児から中学生までを対象としており、症状に応じて、検査や投薬、カウンセリングなどの治療を行います。
また、保護者のこころのケアにも力を入れている病院が多く、ADHDを持つ子どもの接し方などにお悩みの場合、相談に乗ってもらうことも出来ます。
精神科訪問看護
| サービス名 | 精神科訪問看護 |
|---|---|
職種 |
・看護師 ・准看護師 ・作業療法士 |
訪問日数 |
原則週3日以内 (※例外もあります。) |
精神科訪問看護とは、精神障害があり、日常生活に支障がある場合に、医師の指示でスタッフが自宅を訪れて必要な支援を行うことです。
相談内容としては、食事や服薬の管理、人付き合い、話し相手、引きこもり、身の回りのことなど、さまざまなものがあります。
具体的な支援内容としては、日常生活のサポート、服薬状況の確認、対人関係の相談、治療の相談、気分転換の支援、健康管理などがあります。
訪問看護を受けたい場合は、かかりつけの医師や病院に相談してください。かかりつけの医療機関が訪問看護を行っていない場合は、訪問看護を実施している医療機関に問い合わせするのも良いでしょう。
精神疾患をお持ちならシンプレへ

当ステーションの特徴
シンプレは、精神疾患の方の訪問看護を行っています。スタッフが定期的に自宅を訪問し、利用者様の状態やご希望に合わせて、さまざまな支援を行います。
医療機関と連携して、利用者様の治療がよりよい方向に進むようサポートし、利用者様のご家族の相談に乗ったり、助言や支援を行います。
緊急時にも迅速に対応できるよう、バックオフィスが関係機関と連携し、利用者様が日常生活をサポートします。
精神疾患の一例
・不注意さ、多動性、衝動性が特徴
うつ病
・気分の落ち込みや意欲の低下
・体のだるさや痛み
自閉スペクトラム症
・他人と目を合わせることが苦手
・相手や状況に自分の行動をあわせることが苦手
・言葉の裏の意味や抽象的な言葉の意味を理解するのが苦手
PTSD
・トラウマとなった記憶が突然よみがえる
その他精神疾患全般
ADHDなどの発達障害は、それぞれに苦手なことが異なりますが、子供の場合は、その特性から勉強についていけなくなることがあります。
その他の精神疾患には、うつ病、てんかん、摂食障害、解離性障害、パニック障害、アルコール依存症、強迫性障害、睡眠障害、統合失調症などがあります。
シンプレは訪問看護サービスを通して利用者の不安を受け止め、治療への頑張りを一緒に共有し、心から安心できる居場所づくりをお手伝いします。
シンプレの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
上記が対応エリアですが、上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っており、年齢に関わらず利用することが可能です。
また、TwitterやLine、TikTokなどのSNSでも情報を発信していますので、あわせてぜひご覧ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

ADHDは、発達障害の一種で12歳頃までに症状が現われることが多い傾向にあります。ADHDの子供は、注意力や集中力、衝動性、多動性などの特徴があり、学校や家庭での支援が必要です。
ADHDは、大脳の前頭前野にある神経伝達物質の働きが原因で、情報をうまく処理できなくなるためと考えられています。
ADHDの子供は、その特徴から、周囲から誤解や注意を受けやすい傾向があります。症状に悩んでいる場合は、学校の先生や地域の福祉施設、病院に相談するようにしましょう。
シンプレでは、精神科に特化した訪問看護を提供しています。ご自宅での様子を関係機関と連携しながら、サポートさせていただきます。お気軽にご連絡ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



