ADHD特有の時間感覚とはどんなもの?

ADHDの方は特有の時間感覚を持っており、時間や予定の管理が苦手な傾向があります。そのため遅刻をしてしまうなど、様々な問題を抱えることも少なくありません。
では時間感覚を正しくつかめないADHDの方が、このような問題を解決するにはどうすればよいでしょうか?
今回は、ADHDの方に役立つ時間管理のコツなどについて紹介していきます。
ADHDの方は時間感覚が不正確なのか?
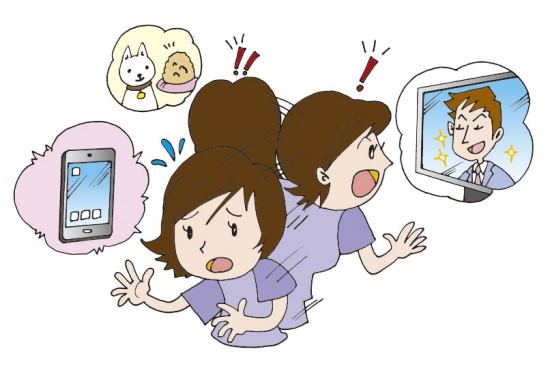
ADHDとは「不注意と多動性・衝動性の2つの特性を中心とした発達障害」と定義されています。
ADHDの方の時間感覚は、一般的に「先延ばし」の傾向があるとされています。しかし、これは時間感覚そのものが不正確であるためではありません。
ここからADHDの方の特有の時間感覚について、またその時間感覚が不正確なことで起こる問題やそのときの対策について紹介していきます。
時間感覚が不正確なことで起こる問題

約束の時間に間に合わない
ADHDの方は、約束の時間に間に合わないことが多い傾向があります。その理由は、衝動性と不注意の特性によって、出発までの準備をスムーズに進めることができないためです。
出発予定時刻が近づいても、衝動性があると目の前のことに集中しすぎて、先のことを考えることができません。そのため、約束の時間まであとどれくらい時間があるのかを把握できず、遅刻してしまうのです。
また、不注意があると、細かいことに注意が向きづらく、物忘れや計画の立て忘れなどが起こります。
スケジュールの管理ができない
ADHDの方は、スケジュールの管理ができないことが多い傾向があります。この原因は、衝動性、不注意、そしてコミュニケーションの特性が関係しています。
衝動性があると、目の前のことに集中しすぎて、先のことを考えることができません。そのため、スケジュールを立てても、それを実行することができず、締め切りに間に合わなくなることがあります。
また、不注意があると、細かいことに注意が向きづらく、忘てしまったり、計画の立て忘れなどが起こります。そのため、仮にスケジュールを立てることができても、それを実行することができません。
さらに、コミュニケーションの特性があると、他者との約束や連絡を忘れてしまうことがあります。そのため、スケジュールがずれたり、予定が変更になったりしやすくなります。
気づいたら長時間経過している
ADHDの方は、目の前のことにすぐに気が向きやすく、興味のあることや楽しいことにはすぐに取り掛かってしまいます。
そのため、締め切りが迫るまでは、やらなければならないことに気が回らず、先延ばししてしまう傾向があります。
また、ADHDの方は、時間の流れをうまく把握することが苦手です。そのため、締め切りがいつなのか、どれくらいの時間がかかるのかが分かりにくく、ギリギリになってから慌てて作業を始めることもあります。
たとえば、「12時までにやっておいて」と言われた場合、12時までの残り時間や、作業にかかる時間を正確に把握できないため、何をすればよいのか判断がつかず、焦ってしまうことがあります。
ADHDで時間感覚が不正確な時の対策

タイムログをとる
スマホのストップウォッチ機能を起動
各行動にどれだけ時間をかけているか計測
まず1つ目の対策は「タイムログを取る」ということです。
タイムログとは、簡単に言うと自分の行動とそれにかかった時間を記録し、どれだけ時間がかかっているか把握することです。
例えば、仕事に行く時間まで、朝食は7:00~7:30、着替えは7:30~7:40、仕事の準備は7:40~8:00など行動と時間を細かく記録し、それを繰り返し行います。
ADHD の特徴である時間感覚が不正確であっても、タイムログを取ることで正確な時間を把握し、少しずつ計画的な行動に近づけることができます。
作業時間・優先順位づけを考え直す
対処例
・作業を小さくして、どれから手を付けるか決める
・作業する場所を決め、集中できる環境を作る
・予定を細かく決めず、言われたことを順番にやる
2つ目の対策は「作業時間、優先順位づけを考え直す」ことです。
作業を小分けにすることで、作業全体が少しずつこなしやすくなります。また、優先順位をつけることで、どの作業から手を付けるべきか判断しやすくなります。
スケジュールがうまく管理できない背景には、予定や計画そのものに無理がある場合があります。そのため、仕事に取りかかる前に、一度作業の優先順位を決め直すことが大切です。
締め切りが近い仕事や、重要度の高い仕事は、優先的に取り組むようにしましょう。
都度計画の立て直しを図る
・予定や計画は適切だが想定通りに進まない
対処例
・計画が進まなかった時の対策を事前に組み込む
最後の3つ目の対策は「都度計画の立て直しを図る」ことです。
作業時間、優先順位付けを考え直し予定を立てても、仕事を進めていく中で想定通りに進まないことがあります。
万が一の時、進捗状況が悪い時になってもその場で判断し修正することは難しいため、計画通りに進まなかった時の対策を事前に組み込んでおくことが大切です。
事前に想定しておくことで、万が一の状況に混乱することなく、計画通りに仕事を進めることができます。
対策を立てる際の注意点
- 仕組みやルールを決める
- 事前シミュレーションをしておく
- 周りの人に協力を求める
- 遅刻をしない時間に予定を入れる
これら4つの注意点を考慮し計画を立てることで、仕事を計画通りに進めることができ、想定外のことが起きた場合でも対処しやすく、仕事を進めることができます。
まずは普段の生活リズムを整え、習慣にできるような仕組みやルールを作って、日常の中に取り入れてみましょう。
まどろむ時間もシュミレーションの中にいれた上で対策しておくと安心できます。
毎日はこの方法が難しいという人も、約束があるときなどの重要な日にだけでも、周りの人に協力を求めながら進めていくことも大切です。
医療機関でのADHDの治療方法は?

薬物療法
ADHDの薬物療法は、症状の軽減を目的とした補助的な手段です。ADHDを治したり、特性をなくすような治療薬は現在ありません。
薬の効果によって、注意力や集中力、衝動性などの症状が軽減され、生きづらさを感じにくくなるでしょう。また、親や周りの方とも適切な関わりができるようになります。
生活をより送りやすいよう環境を整えるために、環境調整や行動療法を用いて症状の緩和を図ることも大切です。また、薬の効果だけではなく、副作用にはどのような症状があるのか知っておくことも大切です。
心理社会的治療
環境調整とは、患者さんの生活環境を整えることで、症状や生活の困難さを軽減する治療法です。
行動療法は、行動をよく見て、言葉でほめたりご褒美を与えたりして、その行動を繰り返すように促します。
また、望ましくない行動をしたときには、否定したり叱ったりせず、繰り返さないようにその行動に繋がるきっかけを減らしたり、その行動の後の対応を工夫するなど方法を考えます。
SSTは、患者さんにコミュニケーションスキルや対人関係スキルを身につけることで、社会生活を送る上での困難さを軽減することができます。
ADHDの方をサポートしている機関
病院の小児科や精神科以外にもADHDの方をサポートしている機関があるため、ここで紹介していきます。
精神科はなかなか受診しずらいと感じる方もいるかもしれません。
しかし、ADHDの特性が周囲の環境と合っていない場合、放っておくことで生活や仕事での困難が生じ、場合によっては抑うつなどの二次障害を併発する可能性があります。
そのため、相談できる機関やサポートしてくれる相談者を見つけ、対処方法について知っておくことが大切です。
発達障害者支援センター
発達障害者支援センターとは、ADHDに限らず発達障害の早期発見・早期支援を目的とし、発達障害のある人やその家族への日常生活のサポートを行っている施設のことです。
窓口は生活している各都道府県や政令指定都市の自治体となっている場合がほとんどですが、それから委託された事業所でも相談を受けています。
施設によって違いはありますが、専門の職員の他に、社会福祉士が在住しているため、専門的なサポートを受けることができます。
児童(子ども)発達支援センター
児童(子ども)発達支援センターとは、発達障害のある子どもを対象に、医師や心理士などの専門の職員が発達の相談や医療相談を行う施設のことです。
相談だけではなく、医師の診察や検査を受けることができたり、日常生活が自立できるように作業療法や言語聴覚療法などの訓練を行っているところがあります。
児童(子ども)家庭支援センター
お子さまやご家庭の悩みや困りごとを、地域に密着した総合的な窓口として、お聞きしサポートする施設です。
18歳未満のお子さまや、お子さまがいるご家庭の、どんなことでもご相談いただけます。
また、ショートステイや一時預かりなどの在宅サービス、ケース援助、サークル支援やボランティア育成なども行っています。
地域障害者職業センター
地域障害者職業センターは、障害のある方が、働きたいという希望を実現できるように、専門的な支援を行う施設です。
職業紹介はしていませんが、ハローワークと連携して、就職に必要な様々な支援を行います。
精神科訪問看護も利用してみる

| サービス名 | 精神科訪問看護 |
|---|---|
| 職種 | 看護師 ・准看護師 ・作業療法士 |
| 訪問日数 | 原則週3日以内 (※例外もあります。) |
精神科訪問看護を利用してみるのも1つの手です。
病院を受診し、ADHDなどの診断を受け、医師の指示書をお持ちであれば、精神科訪問看護を利用することができます。
精神科訪問看護は、ADHDの方やそのご家族の生活をサポートするサービスです。外出が難しい方や精神科への入退院を繰り返している方、ご家族がどのように関わっていけばいいか困っている方は訪問看護を検討してみましょう。
精神疾患をお持ちならシンプレへ

当ステーションの特徴
シンプレ訪問看護ステーションでは、日常生活の介助だけではなく心のケアを受けることができる精神疾患に特化した訪問看護を行っています。
ご利用者さまが自分らしく生活できるように、病気とうまく付きあう方法を一緒に考えます。病気のせいで生活リズムがくるってしまった人には調整を行います。
また、症状が悪化するのを防ぐために、通院の支援や服薬の確認、生活状況の観察を行い、病気の回復を目指していきます。
さらにシンプレでは、ご利用者さまのご家族への支援も行っており、必要であればなやみ相談や社会資源の活用の仕方などをアドバイスします。
対象となる精神疾患
・不注意さ、多動性、衝動性が特徴的
発達障害
・物事に集中しやすい
・細かい部分まで注意を払う傾向がある
・相手の表情や態度などよりも
文字、図形、物の方に関心が強い傾向がある
うつ病
・気分が落ち込み憂うつになってしまう
・その他精神疾患全般
シンプレは精神疾患に特化した訪問看護ステーションで、ADHDの他、うつ病や摂食障害など、幅広い疾患を対象としています。
また、病院、行政、在宅との情報共有を行い、それぞれの専門性を活かしながら治療や社会復帰のサポートができるのも特徴です。
シンプレは訪問看護サービスを通して利用者の不安を受け止め、治療への頑張りを一緒に共有し、心から安心できる居場所づくりをお手伝いします。
シンプレの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションが対応しているエリアは東京都内が中心となっています。
近年の精神科訪問看護の需要の高まりに伴い、今後さらに範囲を拡大していきます。
上記エリア以外で生活している方も利用可能な場合があるため、気になった方は1度相談してみてください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

今回はADHDの方の特性の1つである時間感覚が不正確であるために3つの問題を起こしてしまうことが分かったと思います。
タイムログを取ったり、作業時間、優先順位付けを考え直すなどの対策により、ADHDの方がよりスムーズに日常生活を送ることができるようになります。
また、自治体ではADHDの方や家族の精神的な負担を軽減をサポートするための継続的な支援を受けることができる環境が整えられています。
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神科に特化した訪問看護を提供しておりますので、訪問看護のご利用検討されたい、一度話聞いてみたい等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



