精神疾患をもつ子供との関わり方はどうしたらいい?特徴や治療方法を解説
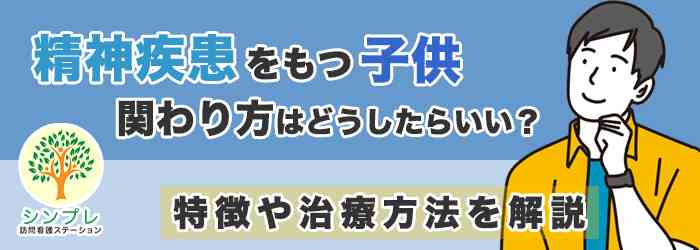
精神疾患は大人だけの問題ではありません。未成年の子供でも、精神疾患を患っていることは少なくありません。
子供は精神疾患を患っていることに気づかないことがあるため、周囲にいる大人がしっかり気を配る必要があります。
そこで今回は、子供の精神疾患の特徴や治療方法、周囲の大人に向けた子供の関わり方について紹介します。
子供の精神疾患例

①先天的な精神疾患
疾患一覧
・不注意症状
・衝動性
・多動
自閉スペクトラム症
・コミュニケーションが苦手
・強いこだわりがある
15歳以下の子供は、発達障害の診断や治療は、児童精神科で受けることができます。 ADHDは、同年齢の子供に比べて、不注意や多動の症状が強い状態です。
不注意とは、注意を集中させるのが苦手で、気が散りやすい状態です。多動とは、じっとしていられなかったり、動き回ったり、他人の邪魔をしたりしてしまう状態です。
自閉スペクトラム症は、遺伝的な要因や脳の機能障害が原因で、人口の約1%の人にみられる障害です。
コミュニケーションや対人関係の困難から、社会生活で困難を感じることがあります。
二次障害の可能性
ADHDや自閉スペクトラム症は、発達障害の一種です。これらの障害には、さまざまな重症度があり、併発することもあります。
障害の重症度や併発する障害の種類によって、生活のしづらさや人間関係でのストレスは大きく異なります。
このような生活上のストレスが長期的に続くことで、うつ病や不安障害、素行障害といった二次的な障害を発症することがあります。
二次障害は、障害の症状を悪化させるだけでなく、日常生活や社会生活に大きな支障をきたす可能性があります。
②後天的な精神疾患
うつ病
・気分が落ち込む
・夜寝つけない
・食欲減退
統合失調症
幻想や妄想の症状
PTSD
・トラウマ体験の記憶が突然よみがえる
・不安や緊張が続く
・めまいや頭痛がある
・眠れない
子供の精神疾患には、うつ病、統合失調症、PTSDなど、さまざまな種類があります。うつ病は、気分が落ち込み、何事にもやる気が出ない、食欲や睡眠の乱れなどの症状がみられる病気です。
統合失調症は、幻覚や妄想などの症状や、思考や行動のまとまりのなさなどの認知機能障害などの症状がみられる病気です。
お子様にこれらの症状がみられる場合は、早めに専門の医療機関を受診することが大切です。適切な治療を受けることで、症状の改善や再発の予防が期待できます。
子供が発する精神疾患のサイン

ジッとできない
感情のコントロール
・突然怒ったり、泣いたり、暴れたりする
・理由もなく恐怖する
落ち込みや極端な不安
・落ち込み
・常に不安を感じている
子供が発する精神疾患のサインとは、子供が精神的な苦しみや困難を感じているときに、周囲に示すサインです。
いつも元気だった子供が、最近急にジッとしていられなくなるといった行動が目立つようになったら、何か困っていることがある可能性があります。
また、突然怒ったり泣いたり、恐怖したりするなどの行動も、子供が精神的な苦しみや困難を感じているサインかもしれません。
子供が発するサインに気づいたら、まずは子供の様子をよく観察しましょう。必要に応じて専門機関に相談することも大切です。
子供が安心して過ごせるように、周囲の大人たちがサポートしましょう。
子供の行動に精神疾患のサインがないか読み取る

子供の行動に精神疾患のサインがないか気づくためには、子どもの様子を普段からよく観察することが大切です。
子供の発するサインは言葉だけとは限らないこともあります。特に低学年の子どもは、言葉で自分の気持ちを表現することが難しいため、行動であらわれることがあります。
時に子供の行動は、自分勝手や怠けていると捉えてしまいがちですが、気になる子供の様子が見られたときには、なぜそういった言動をするのかなど、言動の意味を理解しようとすることが大切です。
早期に気づき適切な支援を行うことで、子どもの心の健やかな成長を促すことができるでしょう。
精神疾患を抱える子供の二次被害
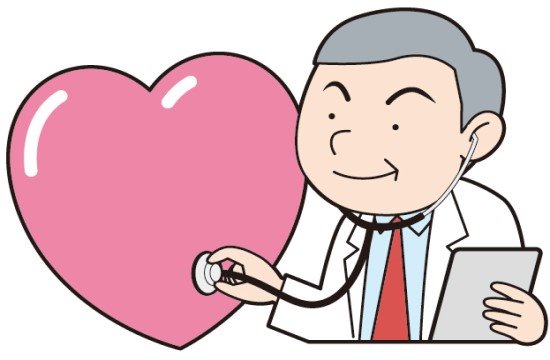
①学校でのいじめ
精神疾患を抱える子供は、人間関係に課題を抱えることから、いじめの対象になったり、逆にいじめる側になったりすることがあります。
いじめられる側になることは、対人恐怖やPTSDなどの精神疾患を発症する原因になる場合があります。ひどい場合には、自殺などの深刻な結果を招くこともあります。
いじめる側になる場合には、反社会性パーソナリティ障害などの精神疾患になったり、非行少年や犯罪者になってしまうことがあります。
②コミュニケーションの拒否
精神疾患がある子供は、人間関係に難しさを感じることが多いといわれています。このため、コミュニケーションを拒否して引きこもってしまうことがあります。
このことは、人間関係からさらに遠ざかるきっかけになり、人との関わりがさらに難しくなります。
コミュニケーションを拒否して、長い間引きこもってしまうことで、社会的にも個人的にも大きな機会損失になります。
児童期にこのような状況になると、不登校や引きこもりの原因になります。
③自身の否定・自信が持てない
周囲と自分を比較してしまい、人間関係で自信を無くしてしまうことがあります。自己否定的な考えを強く持つことがあります。
このような考えを持つことで、自身を否定してしまいます。例えば「生きる価値がない」などといった、自分に対してかえってストレスになるような否定的な思いを、抱き続けることになります。
自分が否定的な存在として自己認識されてしまうことで、支援者などに相談をすることなどもあきらめてしまうことにつながります。
親の苦悩

精神疾患の発症
・ストレスから飲酒
・次第に飲酒量が増える
うつ病
・子供への不安
・父母どちらかが非協力的
・心労から発症
子供が精神疾患を抱えている場合、子供の症状や行動が家庭に大きな影響を与えます。親は、保護者としての責任を感じたり、子供の将来に不安を感じたりします。
このような親の気持ちは、なかなか気軽に相談できるものではありません。相談できずに、悩みを抱え続けると、親にも大きなストレスがかかります。
ストレスの対処として飲酒する場合には、アルコール依存症となり、心身に悪影響が及ぶ可能性があります。
また、ストレスを抱え込みすぎ、疲弊しきってしまい、うつ病になることもあり注意が必要です。
親側が苦しまないためには
子供の精神疾患は、ご家族にとっても大きな負担となります。子供の症状や行動を近くで見ると、ご家族ご自身も精神的に不安定になり、うつ病などの精神疾患を発症する危険性があります。
このような場合には、ご家族ご自身も専門家に相談することが大切です。場合によっては、ご家族も治療を受けることも大切です。
また、辛い状況が続くことに慣れてしまうと、諦めてしまうことにもつながり、マイナス思考が強くなる悪循環に陥ることがあります。そうなる前に、支援者とつながることで、必要な医療などをうけることが重要です。
子供を支える方法とは
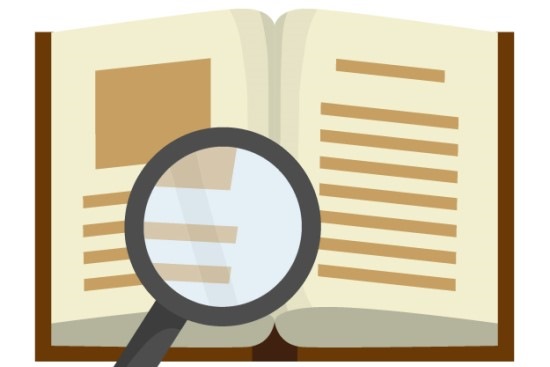
子供の育て方と環境
子供の精神疾患は、遺伝的要因や環境的要因などの家庭環境、学校や地域の環境が複雑に絡み合って起こると考えられています。
必ずしも親のみの責任ではありません。しかし子供の育て方や環境が、症状の程度などに影響を与える可能性もあります。
例えば、子供の行動や症状に対して、過度に叱ったり、否定したりすると、子供のストレスや不安を増大させることがあります。
医療機関や教育センターなどでは、子供の特性に応じた関わり方のコツなどを聞くことができます。
関わり方を工夫することで、親も子供も安心して過ごすことができたり、ストレスを減らしたりすることができるでしょう。
相談・対処できる施設を探す
子供の精神疾患に悩む家族は、一人で抱え込むのではなく、専門家に相談したり、同じような経験をした人とつながったりすることが大切です。
一人で抱え込もうとすると、親子関係の悪化してしまったり、家族の生活の質の低下など、さまざまな問題につながる可能性があります。
子供の精神疾患の症状や治療について、医療機関に相談することで、適切な治療を受けることができます。
また、医療機関では、子供の特性や症状に合わせた関わり方のアドバイスを受けることもできます。
以下に、それぞれの施設の特徴や相談内容について、具体的に説明します。
①病院・診療所への通院と治療
子供が精神疾患をお持ちの場合、専門的な検査や診察によって、子供の状態を正しく把握し、必要な治療を受けることができます。
また、病院や診療所によっては、カウンセリングルームや、心理士のカウンセリングや集団精神療法を受けることができるところもあります。
②地域の保健所や保健センター
子供の精神疾患を支える方法の一つとして、地域の保健所や保健センターに相談するという方法があります。
相談では、子供の状態や家族の状況などを詳しく聞き取り、必要な支援やアドバイスを受けることができます。また、必要に応じて、医療機関の紹介や、地域の支援団体との連携なども行ってくれます。
③訪問看護の利用
子供が精神疾患を抱えている場合、病院や診療所に通院するだけでなく、訪問看護を利用することも一つの方法です。
訪問看護は、看護師が患者の自宅を訪問して、看護やケアを行うサービスです。精神科訪問看護では、子供の状態やご家族の状況などを把握し、必要な支援を行います。具体的には、以下のようなものがあります。
精神科訪問看護とは

自宅で受けられる精神科ケア
・精神科・心療内科に通院中の方
・精神疾患の診断を受けた方
・診断がなくとも医師が必要と判断した方
訪問する人
・看護の専門職
・リハビリテーションの専門職
訪問時間
・医療保険
(30分から90分程度)
精神科訪問看護は精神科や心療内科に通院され精神疾患と診断されている方、診断はなくとも睡眠障害などで医師が訪問看護が必要と判断された人で、年齢制限はなく、子供も対象です。
看護師や作業療法士などの医療スタッフが医師の指示のもと自宅へ訪問し、病状観察や日常生活指導、また家族支援などのサポートを行います。
通常、訪問は医療保険を利用し週3回まで可能で、1回の訪問は30分から90分と決められています。体調や病状に合わせて訪問回数や時間を調整します。
外出が難しい方や精神科への入退院を繰り返している方、ご家族がどのように関わっていけばいいか困っている方は訪問看護を検討してみましょう。
精神科訪問看護の仕事内容
・自立した生活を営めるための支援
・規則正しい生活リズムへの調整
症状の悪化防止・服薬支援
・病状や普段の様子を観察
・受診や服薬を支援
社会復帰へのサポート
・主治医や関係機関と連携
・社会復帰を支援
家族の方への支援
・ご家族へのアドバイスや相談
・社会資源の活用などを支援
精神疾患を持つお子様は、病状や症状によって、日常生活に支障をきたすことがあります。また、家族も精神的な負担を抱えやすく、孤立感を感じていることもあります。
精神科訪問看護は、そのようなお子様やご家族が、住み慣れた地域で安心して生活できるように支援いたします。
具体的には、お子様の心身の状態や生活状況を把握し、必要な支援を行い、症状の悪化を防ぐための服薬管理や、社会復帰に向けた支援などを行い、お子様の健やかな成長をサポートいたします。
また、ご家族へ相談やアドバイスを行うことで精神的な負担を軽減し、保護者が安心して子育てを続けられるように支援します。
精神疾患のお子様のことでお悩みならシンプレ訪問看護ステーションへ

当ステーションの特徴
シンプレ訪問看護ステーションは、精神科疾患に特化した訪問看護ステーションです。
シンプレでは、利用者さんの自主性を尊重して、利用者さんの生活がより良くなるように訪問看護を行っています。
これらのことは、訪問看護だけでは行えません。主治医を中心とした医療機関や市町村の担当者など地域の支援者と連携をとり利用者さんをサポートします。
お子様の精神疾患やそれに伴う生活上の悩みがある場合は、シンプレ訪問看護ステーションにご相談ください。
疾患の一例
・気分が落ち込む
・眠れない・疲れやすい・食欲がない
統合失調症
・幻覚や妄想という症状が特徴的
不安障害
・些細なことに不安や恐怖を感じ日常生活に支障がでる
・イライラや恐怖で夜よく眠れない
アルコール依存症
・酒類(アルコール)に依存する
・アルコール中心の生活になってしまう
その他精神疾患全般
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神科疾患全般に対応可能です。統合失調症や不安障害など、生活に困難を感じていらっしゃる場合の相談も可能です。
これらの障害から、うつ病といった気分障害など二次的障害になってしまったお子様への対応も可能です。どのような生活をしていくか、精神科看護として相談にのることができます。
子供だけでなく親御さんも安心して生活できるように一緒に考えることができます。子供の精神疾患で悩む方の生活がよりよくなるように、主治医や地域の支援者とともに患者さんを支援します。
シンプレの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリアは、上記の地域になります。
上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っており、年齢に関わらず利用することが可能です。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

子供の精神疾患について、障害の種類や特徴について解説しました。大切な自分の子供に、障害にともなう辛さがあることは家族としてはとても辛いことです。
子供の精神疾患は、本人だけでなく家族にとっても大きな負担となります。子供が障害によって辛い思いをしているのを見るのは、親御さんにとってとても心が痛むことでしょう。
シンプレでは、子供の精神疾患の理解や社会復帰への支援、親御さんのサポートなど、一人ひとりの状況に合わせた支援を提供します。
子供の精神疾患で悩まれているご家族は、ぜひシンプレへご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



