精神疾患を持つ方への対応方法

余計な一言をかけて症状を悪化させたくないため、精神疾患に悩まされる人に対してどのように対応すればよいか分からない人も多いはずです。
ただ、家族や友達、同僚など身近な人に精神疾患の症状が見られるなら、どうにかして助けてあげたいですよね。
そこで今回は、精神疾患を患った人への対応方法を紹介したいと思います。
主な精神疾患の特徴も紹介するので、該当するものがないか合わせて確認してみましょう。
精神疾患の対応方法

家族や友人などが精神疾患を患ってしまった場合は、以下の対応方法で対応するようにしましょう。些細なことで相手を傷つける可能性がありますので慎重な行動が大切です。
声をかけて信頼関係を築く
心の病気である精神疾患は、一緒に生活や仕事をしている家族や職場、友人などが「困っているのではないか?」と気づいてあげることが大切です。
気づいた後の対応方法としては、心配していることを直接伝え、信頼関係をつくることから始めてみましょう。
いきなり「病院へ相談してみては?」と質問を投げかけるのではうまくいかないので、まずは他愛のない会話から信頼関係を築くことが大切です。
問題を一緒に探して解決法を考える
精神疾患の方に対応するには、本人の生活上の問題を探し、解決する方法を一緒に考えることです。
例えば、仕事や人間関係で悩んでいる場合は、相談相手になってあげたり、一緒に解決策を考えたりしましょう。また、症状が重い場合は、病院への受診を勧めましょう。
ただし、本人が自覚していない場合もありますので、唐突に話すのではなく、徐々に相手から悩みを話してくれるのを待ちましょう。
相手を責めない
精神疾患の方への対応方法として、本人や自分を責めたり悲観したりしないことが大切です。
精神疾患は、誰でも発症する可能性がある病気です。本人が精神疾患に苦しんでいることを責めたり、自分を責めたりしても、状況を改善することはできません。
むしろ、本人をさらに追い詰めてしまう可能性があります。精神疾患の方への対応は、まず本人の話をよく聞くことが大切です。本人が安心して話せる環境を整えてあげましょう。
本人の話を聞いた後は、本人の気持ちを理解し、共感することが大切です。否定したり、批判したりするのではなく、一緒に解決できる方法を考えましょう。
主な精神疾患の特徴

精神疾患と一口にいっても、その種類は様々。そこでここからは、様々な精神疾患の特徴や対応方法などについて解説していきます。
統合失調症
・妄想
・幻覚
・認知障害など
ボックス:治療法
・抗精神病薬
・リハビリテーション
・精神療法
統合失調症の患者さんに接するときは、まず、統合失調症そのものへの理解が大切です。
統合失調症は、心や考えがまとまりづらくなってしまう病気で、幻覚や妄想などの症状が特徴的な精神疾患です。
発症の原因は正確にはわかっていませんが、統合失調症は仕事や人間関係のストレスなどの、人生の転機などで感じる緊張がきっかけになるのではないかと考えられています。
統合失調症の患者さんに接するときは、患者さんの心理や行動、生活のしづらさに共感し、寄り添ってあげることが重要です。
薬物依存症
・自己制御の困難
・離脱症状
治療法
・薬物療法
・認知⾏動療法
・自助グループへの参加など
薬物依存症は、大麻や麻薬、シンナーなどの薬物を繰り返し使いたい、あるいは使ってはいけないと不快になり、やめたくてもやめられないという状態になる精神疾患です。
依存性は非常に強く、薬物の危険性を理解しているのにやめることができません。
回復への対応方法としては、薬物依存について学び、専門機関に相談し、医師による治療や適切なサポートを受けることが重要です。
睡眠障害
・不眠
・過眠
・睡眠リズムの問題 など
治療法
・睡眠薬
・睡眠改善指導
・睡眠習慣の見直し など
睡眠障害とは、睡眠に何らかの問題がある状態を言います。原因には、環境や生活習慣によるもの、精神的・身体的な病気から来るものなど様々です。
睡眠障害によってに日中の眠気やだるさ、集中力低下などの症状が引き起こされ、日常生活や社会生活に支障が出てしまいます。
寝つきが悪いなどの不眠症状に対しては、睡眠薬が使用されたり、他にも抗不安薬、向精神薬なども使用される場合があります。
医療機関をはじめ、専門家に相談することで睡眠障害の改善につながるでしょう。
摂食障害
・極端に痩せようとする
・食事、体重増加を毛嫌いする
・自分が病気になっていると思わない
過食症の症状
・食事のコントロールができない
・食事のあと自分を責める
治療法
・心理療法
・栄養指導
・薬物療法
摂食障害には、食事をほとんどとらなくなってしまう「拒食症」と、極端に大量に食べてしまう「過食症」があります。
こうした極端な摂食行動の以上が表れるのは、体重への極端なこだわりや、「自分は醜い(細い・太い)」などの極端な思い込みなどの心理的背景があります。
摂食障害は自身では治療に納得することが難しいので、家族や友達などが専門医が協力し合いながら治療を続けられるように対応することが大切です。
認知症
・以前はできたことに手間取るようになる
・意欲の低下
・怒りっぽくなったなど
治療法
・薬物療法
・認知機能のリハビリテーション など
認知症とは、様々な原因によって脳の神経細胞が破壊・減少することにより、日常生活が送れなくってしまう状態のことを言います。
認知症にはいくつか種類があり、脳梗塞や脳出血・くも膜下出血が発症の原因になる場合があるのも特徴です。
中でも脳にある特殊なタンパク質が蓄積することで発症するアルツハイマー型認知症は、最も患者数が多いと言われています。
認知症を根本的に治療する方法はありませんが、早期に診断を受けて適切な治療を受けることで、症状の進行を遅らせることができます。
精神疾患の治療方法

精神疾患の治療方法として、「薬物療法」「心理療法」「環境調整法」という3つの対応方法があります。それぞれの治療内容について解説していきます。
薬物療法
精神疾患の治療において、薬物療法は最も基本的な治療方法の一つです。薬物療法の目的は、症状の改善と再発予防です。
薬物療法は、幻覚や妄想などの陽性症状、抑うつや不安などの陰性症状、不眠や食欲不振などの身体症状など、様々な症状に効果があります。
また、薬物療法は、症状が安定した後も再発を予防するために継続的に行う必要があります。
ただし、薬物療法には副作用が出ることもあります。副作用が出るかどうかは、薬の種類や個人差によって異なります。
副作用が気になる場合は、医師に相談するようにしましょう。
心理療法
- 認知行動療法
- 対人関係療法
- 瞑想・マインドフルネス療法など
精神疾患の治療において、心理療法は薬物療法と並んで重要な役割を果たしています。
心理療法は、患者さんの考え方や行動を改善することで、症状を改善する治療法です。
認知行動療法では、患者さんの間違った考え方や行動を修正することで、症状を改善します。
対人関係療法では、患者さんの対人関係を改善することで、症状を改善します。
瞑想やマインドフルネス療法では、患者さんの心を落ち着かせることによって、症状を改善を目指します。
環境調整法
環境調整法は、患者さんの生活環境を改善することで、症状を改善する治療法です。
このように見直しを行い改善・調整していく治療方法は「環境調整法」と呼ばれ、職場や家庭、学校などの人間関係や生活環境を整えるための対応を取ります。
休養・睡眠の改善、栄養バランスの改善、運動の習慣化、ストレスの軽減など、様々な方法があります。
精神疾患の場合に利用できる施設の一例
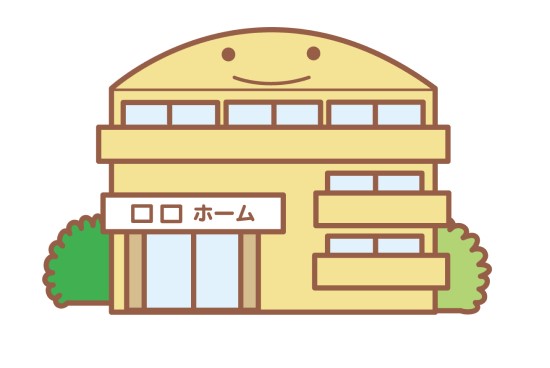
精神疾患への対応方法として、施設を利用するという選択肢もあります。家族だけのサポートでは難しい場合に利用される方が多いです。
グループホーム
グループホームとは、認知症などの精神疾患を患っている方に対して、共同生活住居で、地域住民との交流の元、能力に応じ自立した日常生活を営めるようにするものです。
入浴・排泄・食事などの基本的に自分でできることは自分で行い、自立した生活を目指します。
サービス内容は施設ごとに異なるので、入所希望の方はサポート内容などを確認することをおすすめします。
精神科の訪問看護
精神訪問看護とは、精神科勤務経験や研修を受け資格を持っている看護師や作業療法士等が精神疾患をもつ方の自宅に直接訪問して、在宅医療を提供するサービスです。
看護師や作業療法士などの医療スタッフが医師の指示のもと自宅へ訪問し、病状観察や日常生活指導、また家族支援などのサポートを行います。
訪問看護を利用するメリットは外出が難しい方や治療を中断してしまう方も、継続的に専門的な支援を自宅で受けられることです。
病状や内服状況など、医療機関やかかりつけの医師と連携し情報を共有できます。
精神疾患の対応ならシンプレ訪問看護ステーションにお任せください!

精神科訪問看護の利用を検討されている方へ、当シンプレ訪問看護ステーションの詳しいサービス内容や対応エリアをご紹介します。
シンプレ訪問看護ステーションって?
自立した生活を営めるための支援
症状の悪化防止・服薬支援
生活状況を観察しながら受診や服薬を支援
社会復帰へのサポート
・主治医や関係機関と連携
・社会復帰を支援
家族の方への支援
・家族へのアドバイスや相談
・社会資源の活用などの支援
シンプレ訪問看護ステーションは精神科に特化した訪問看護を提供しており、さまざまなこころの健康問題を抱えている方の訪問看護を行っております。
日常生活の介助や心のケアだけではなく、服薬の管理や、ご相談があればご家族様へのサポートなども行っています。
訪問時に生活状況や症状を確認し、ご利用者様の主治医や関係機関と連携を取ることで、治療の前進を支援します。
シンプレは訪問看護サービスを通して利用者の不安を受け止め、治療への頑張りを一緒に共有し、心から安心できる居場所づくりをお手伝いします。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
現在の対応エリアは、上記を中心となっております。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っており、子供から大人まで年齢に関わらず利用することが可能です。
上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

精神疾患に悩み苦しむ方への正しい対応方法というのは、その症状や状況によって異なります。
精神疾患の種類によって原因や対応方法が異なりますので、適切な対応がとれるように周りが支援してあげましょう。
シンプレは精神疾患に特化した訪問看護サービスで、家族とともに本人に寄り添い、本人らしく生きていけるようサポートします。
もしもどこに相談をしたらいいかわからなくて困っている、訪問看護のサービスについて聞いてみたいなどございましたら、わたしたちへお気軽にご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



