うつ病で薬物依存に陥ってしまう原因とは?
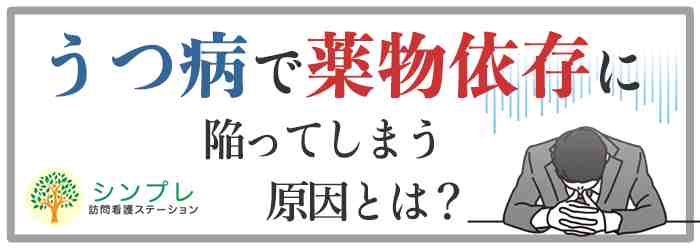
うつ病は、気分の落ち込み、やる気が出ないなどの症状が続く精神疾患です。薬物依存は、薬物を使って快感や陶酔感を得るために、やめられなくなる状態です。
うつ病と薬物依存は、一見すると関係がないように思われますが、実は両者は深い関係にあると言われています。
本記事では、うつ病と薬物依存の関係、原因や注意点についても紹介しています。うつ病や薬物依存に悩んでいる方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
うつ病治療で使われる向精神薬が薬物依存の原因に
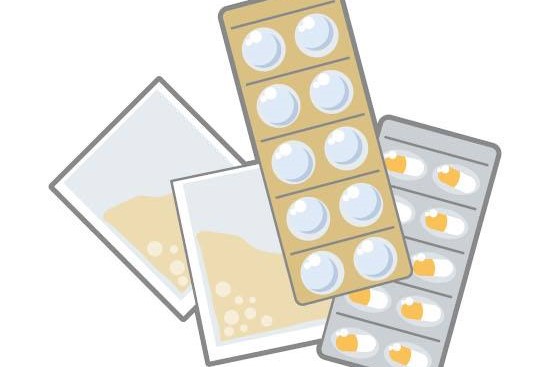
向精神薬の依存性や耐性に注意
向精神薬が薬物依存の引き金となるケースは、近年増加傾向にあり、覚醒剤や危険ドラッグに次いで3番目に多い原因であると報告されています。
向精神薬は、睡眠薬や抗不安薬などの種類があり、適切な使用であればさまざまな症状を改善する効果があります。
しかし、過剰に使用すると、耐性や離脱症状が現れ、通常用量以上を求めるようになってしまいます。
また、1つの医療機関では決められた用量しか処方されないため、薬を求めて処方してくれる他の医療機関を訪れるケースも少なくありません。
薬物依存の原因となる代表的な向精神薬
- 鎮静薬
- 睡眠薬
- 抗不安薬
薬物依存を引き起こす可能性があると考えられているうつ病の治療で用いられる主な向精神薬としては、鎮静剤、抗不安薬、睡眠薬が挙げられます。
向精神薬依存が原因の薬物依存の診断の基準となる症状は、薬の使用量が医師の指示を超えて多くなる、薬の使用量を減らそうとしても、コントロールできない等が挙げられます。
その他にも薬を使わなければ、イライラや不安などの禁断症状が現れるといった症状が現われます。
うつ病の治療で用いられる薬の種類は?

新しい抗うつ薬
・パキシル(パロキセチン)
・ジェイゾロフト(セルトラリン)
・レクサプロ(エスシタロプラム)
・デプロメール(フルボキサミン)
SNRI
・サインバルタ(デュロキセチン)
・トレドミン(ミルナシプラン)
・イフェクサー(ベンラファキシン)
NaSSA
・リフレックス(ミルタザピン)
現在、日本国内で承認されている新しい抗うつ薬は、主に上記の表のものがあり、依存性はないと言われています。
薬である以上、副作用のリスクは避けられませんが、吐き気、眠気、消化不良などの副作用は、古い抗うつ薬に比べて比較的少ないと言われています。
患者さんの症状や体質に合わせ、医師が適切な処方を行いますが、薬に関する基本的な知識を身につけておくことは大切です。
歴史のある抗うつ薬
・アナフラニール(クロミプラミン)
・トフラニール(イミプラミン)
・トリプタノール(アミトリプチリン)
・ノリトレン(ノリトリプチリン)など
四環系抗うつ薬
・ルジオミール(マプロチリン)
・テトラミド(ミアンセリン)など
その他の抗うつ薬
・レスリン(トラゾドン)
・ドグマチール(スルピリド)
・エビリファイ(アリピプラゾール)など
三環系抗うつ薬や四環系抗うつ薬は、依存性がないと言われています。
しかし、薬を飲み忘れてしまったり、服用を止めてしまった時などに、めまいや頭痛、吐き気、不安、不眠などの症状が現われることがあります。これを離脱症状といいます。
この離脱症状は、再発や依存ではありません。薬の効き目がなくなることで起きる症状のことをいいます。
薬の効果が薄れたと感じて、量を自分で増やしたり、もっと欲しいという気持ちが湧いたりした場合は、依存の可能性があり注意が必要です。
依存の症状が現われた場合は、主治医に相談するようにしましょう。
各抗うつ薬の副作用
・吐き気
・食欲不振
・下痢
SNRI
・不眠
・便秘
・尿が出にくい
・吐き気
・頭痛
NaSSA
・眠気
・体重増加
・食欲増進
三環系抗うつ薬
・便秘
・口の渇き
・ふらつき
・眠気
・体重増加
四環系抗うつ薬
・眠気
・ふらつき
抗うつ薬を初めて飲んだときや、量を増やしたときには不安感が高まったり衝動的に考えずに行動してしまうなどの副作用が現れることがあります。
まれに重篤な副作用が出ることもあるため、上記のような副作用が現れたら、すぐに医師に相談することが重要です。
薬物依存になってしまうとどうなる?

薬物を使いたい強い欲求が現れてしまう
薬物依存のよくある症状は、薬物への強い欲求です。
この欲求は、薬物使用をやめていても起こり得ます。何かのきっかけで、突然「薬を使いたい」という強い衝動に駆られるのです。
この欲求は、止まらないことが特徴です。薬を手に入れるために、病院や薬局を何軒も回ったり、時には万引きや強盗などの犯罪行為に走ったりします。
薬物の使用を止めると離脱症状が出る
薬物依存が進むと、薬物をやめたときに離脱症状(禁断症状)が起こることがあります。
離脱症状は、睡眠障害(不眠や過眠)、食欲の変化(食欲亢進や下痢・嘔吐)、幻覚や妄想など、さまざまな症状が現れます。
離脱症状は、重症になると日常生活に支障をきたすこともあるため、軽視せずに対処する必要があります。
薬物に耐性ができ使用量が増えてしまう
薬物依存になると、薬物の効果が薄れてきて、より多くの薬物が必要だと感じるようになります。
そのため、薬物の使用量が増えていく傾向があります。
薬物使用に費やす時間が増え、仕事や学業、趣味など、他のことに興味や関心がなくなることもあります。
うつ病の薬を飲む際に注意するポイント

医師の指示に従って服用する
うつ病の薬を服用するときは、必ず医師の指示に従うようにしましょう。
副作用を心配して、勝手に量を減らしたり、飲むのを忘れたりするのは危険です。
指示通りに服用しないと、薬の効果が十分に得られず、症状が長引いてしまう可能性があります。
また、うつ病の薬は即効性がなく、効果が出るまでには2~4週間かかります。焦って自己判断で飲み方を変えないようにしましょう。
絶対に自分の判断で服用量を調節しない
症状が良くなったからといって、自己判断で薬の量を減らしたり、服用をやめたりするのは危険です。
症状が良くなっているのは、薬のおかげです。勝手に飲み方を変えると、症状がぶり返したり、重症化したりすることがあります。
必ず医師の判断を受けて、服用を続けるか、量を減らすか、服用をやめるかを決めましょう。
気になることは医師や薬剤師に相談する
うつ病の薬を服用していて、何か気になることがある場合は、我慢せずに医師や薬剤師に相談しましょう。
上記で解説したように、うつ病の薬には、飲み始めに軽い副作用が出ることがあります。副作用が続く場合は、医師に相談しましょう。
また、飲み始めや増量のタイミングで、不安や興奮、怒りっぽくなる、不快などの症状が出ることもあります。この場合も、医師に相談しましょう。
向精神薬の依存症はどこに相談すればいい?

専門家の相談先
- 保健所
- 精神保健福祉センター
- 依存症相談拠点機関
- 民間のリハビリ施設
- 自助グループ
薬物依存は、本人や周囲に大きな影響を与える深刻な問題です。もし薬物依存症に陥っているのではないかと感じたら、一人で抱え込まず、専門の相談先に相談することが大切です。
主な相談先としては、保健所や精神保健福祉センターなどがあります。これらの機関では、専門職が対応しサポートを提供しています。
薬物依存は、周囲と馴染めない、病気を認められないといった理由で、相談が遅れてしまうケースもあります。しかし、早期の相談が、回復への第一歩となります。
精神科訪問看護を利用するという選択肢も
| サービス名 | 精神科訪問看護 |
|---|---|
| ケア内容 | ・日常生活の維持 ・生活技能の獲得 ・拡大 対人関係の維持、構築など |
| 訪問日数 | 原則週3日以内 |
薬物依存症になった場合の相談機関についてご紹介しましたが、近年、自宅にいながらケアを受けられる精神科訪問看護の利用も注目されています。
精神科訪問看護では、患者様の日常生活や対人関係維持のフォロー、服薬管理、症状の観察・記録などのケアを提供しています。
また、医師の指示のもと、看護師などの医療従事者が対応するため、安心して自宅療養できる環境を整え、再発を予防していきます。
訪問は基本的に週に3日以内となっており、患者様のご都合に合わせて柔軟に対応します。また、家庭や地域での療養に必要な指導や援助を、個別に提供するため、患者様はより安定した生活を目指すことができます。
精神科訪問看護ならシンプレ訪問看護ステーションへ!

シンプレ訪問看護ステーションの特徴
シンプレ訪問看護ステーションは精神科に特化した訪問看護サービスを提供しており、うつ病のほかに、統合失調症などの訪問看護も行っております。
自宅で看護を受けることができるので、外出が難しい方でも自宅でリラックスしながらサービスを受けることができます。
日常生活の介助や心のケアだけではなく、服薬の管理や、ご相談があればご家族様へのサポートなども行っています。
看護内容をチェック
・双極性障害
・不安障害
・パーソナリティ障害
・精神疾患全般
主な看護内容
・生活支援、自立支援
・症状の悪化防止、服薬支援
・社会復帰へのサポート
・家族の方への支援
シンプレの主な看護内容は上記の表の通りとなっております。
利用者様の抱える病気と向き合いながら、ご本人が望む生活を送れるよう、自主性を尊重した看護サービスを提供しています。
また、病院、行政、在宅の各機関と連携し、それぞれの専門性を活かして、治療や社会復帰をサポートしています。
訪問看護を通して、利用者の不安に寄り添い、治療への取り組みをともにし、心から安心できる居場所づくりのお手伝いをさせていただきます。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの訪問エリアは、上記中心に行っています。
訪問対応エリアを順次拡大しています。上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。
また、TwitterやLine、TikTokなどのSNSでも情報を発信していますので、あわせてぜひご覧ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ
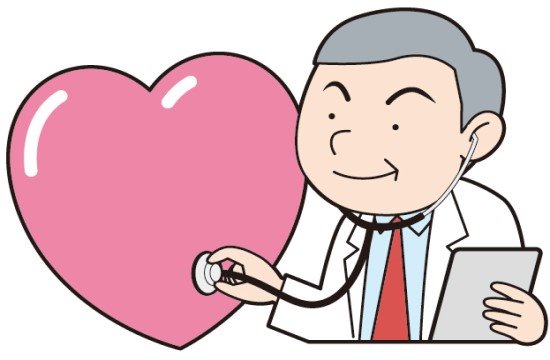
うつ病と薬物依存は、どちらも社会に大きな問題となっている精神疾患です。うつ病の患者さんは、薬物依存に陥りやすい傾向があります。
うつ病と薬物依存は、密接に関係している深刻な問題といわれています。薬物依存に陥らないためには、うつ病などの精神疾患の早期発見・治療や、ストレスや不安の適切な対処など、予防に努めることが大切です。
シンプレでは訪問看護サービスを通して、利用者さまが持つ病気とどう向き合っていくかを一緒に考え、治療への頑張りを一緒に共有し、心から安心できる居場所づくりをお手伝いします。
うつ病や薬物依存症でお悩みの方は、わたしたちにご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



