三環系抗うつ薬の副作用について知ろう。副作用の現われ方や注意点
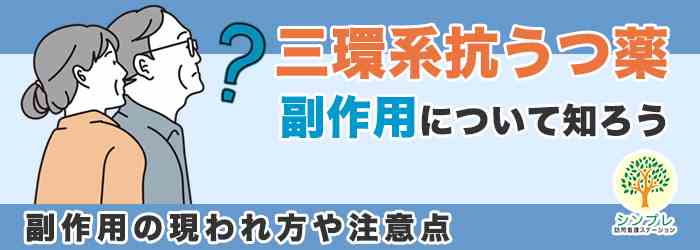
三環系抗うつ薬の副作用についてご存知でしょうか?
古くからうつ病などの治療に用いられてきた三環系抗うつ薬ですが、副作用が心配で服用を躊躇しているという方もいらっしゃることでしょう。
今回は、三環系抗うつ薬の副作用や注意点などについて詳しく紹介します。三環系抗うつ薬の副作用が不安という方はぜひ参考にしてくださいね。
三環系抗うつ薬の主な副作用は?

抗コリン作用
副作用
・目の渇き
・口渇
・便秘
・眼圧上昇
・排尿障害
三環系抗うつ薬の副作用の代表的なものに、抗コリン作用があります。三環系抗うつ薬の内服で、この様な症状が現れることがあります。
抗コリン作用とは、具体的には、口の乾き、便秘、尿閉や頻尿などの排尿障害といった症状です。これらの症状は、とても不快なものといえます。
三環系抗うつ薬の中でも、抗コリン作用が強い薬があります。トリプタノール、アナフラニール、トフラニールなどが代表的です。これらの薬は、効果が高い一方で、副作用も強いと言われています。
抗ヒスタミン作用
・眠気
・倦怠感
・体重の増加
三環系抗うつ薬には、抗ヒスタミン作用という副作用があります。抗ヒスタミン作用とは、眠気やだるさ、ふらつきなどの症状です。
これらの副作用が強いと、日常生活が難しくなることがあります。
三環系抗うつ薬は、抗コリン作用や抗ヒスタミン作用によって、せん妄状態(意識障害や幻覚・妄想などの症状が現れる状態)を引き起こすことがあります。
せん妄状態は、服用量が多いほど起こりやすくなると言われています。抗うつ薬によって生じたせん妄状態は、うつ病の悪化と見分けがつきにくいため、精神科医の診察が必要です。
抗アドレナリンα1作用
副作用
・立ち眩み
・ふらつき
・転倒
抗アドレナリンα1作用も、三環系抗うつ薬の副作用です。アドレナリンα1受容体が遮断されることによって、血圧低下、ふらつきなどの症状が現れます。ひどい場合には、転倒の原因になる場合があります。
この副作用も、三環系抗うつ薬がアドレナリンの働きを抑えるため、血圧が下がりやすく、立ちくらみやふらつきが起こることがあります。
アドレナリンは、血管を収縮させて血圧を上げ、血液の循環をよくする働きがあります。抗うつ剤は、このアドレナリンの働きを抑えるため、血管が広がり、血圧が下がります。
そのため、立ち上がったときに血圧が下がり、頭に血がまわらなくなり、立ちくらみやふらつきの副作用が起こる可能性があるのでちゅいあ必要です。
副作用リスクを抑えた第二世代の抗うつ薬
三環系抗うつ薬は、脳内の神経伝達物質であるノルアドレナリンの再取り込みを抑えることで、うつ病などの治療に効果があります。しかし、この薬には、眠気、口の渇き、便秘、めまいなどの副作用が起こることがあります。
第一世代の三環系抗うつ薬は、特にノルアドレナリンの再取り込みを抑える作用が強いため、副作用も起こりやすい傾向があります。
一方、第二世代の三環系抗うつ薬は、第一世代に比べて副作用が起こりにくいように作られていることが特徴です。
三環系抗うつ薬の副作用の現れ方と副作用

飲み始めに現れやすい
環系抗うつ薬の副作用は、服用を開始したばかりの時期や、服用量を増やしたときに現れやすい傾向があります。
特に服用を開始したばかりの時期の症状には注意が必要です。自己判断で服用を中止したり減らすなどは避け、医師に相談するようにしましょう。
また、服用を開始したばかりの時期は副作用が現れやすいため、服用は少量から開始するのが一般的です。さらに、日々の体調や気分の変化を記録に残しておくと、副作用の有無を判断しやすくなります。
1~2週間ほど経過すると落ち着く
三環系抗うつ薬の内服を開始したばかりの頃に現れる副作用は、1〜2週間で落ち着くことが一般的です。上記でもご説明しましたが、日々の体調や気分の変化を記録しておくとよいでしょう。
また、抗うつ薬の効果は、数週間経たないと現れない場合もあります。そのため、副作用が現れたからといって内服を中止することは避け副作用や不安、焦りなどを感じた場合には、主治医に相談しましょう。
経過とともに副作用が顕著になることも
高齢者や身体合併症をお持ちの方は、体内の薬の濃度が上がりやすいため、強く副作用が出ることがあります。そのため、副作用が目立たなくても、注意が必要です。
経過とともに副作用が顕著になっている自覚症状がある場合には、早めに主治医へ相談しましょう。
副作用が現れたときの注意点
副作用が現れても、薬の内服は続ける場合もあります。副作用が現われたときの注意点について整理します。
自己判断で薬を中止しない
副作用が現れたとしても、うつ病への治療効果や患者さんの体調などを総合的に判断する必要があります。そのため、薬の中止については医師が、状態を診察したうえでの判断になります。
症状が良くなってきているのは、うつ病が治ってきたのか、薬のおかげなのか、自分ではわかりません。
症状がよくなってきたからといって、すぐに薬を減らしたり、飲むのをやめたりすると、効果が十分に発揮されず、うつ病が再発したり、症状が悪化したりする可能性があります。
不安や判断に迷う時は医師に相談
うつ病自体の症状や薬の副作用が辛い場合には、不安や迷いが伴います。そういった時に、大切なことは、十分に医師と相談することです。
主治医の医師との信頼関係を大切にして、ささいな変化や不安でも相談する事が大切です。気のせいかもしれないと軽視してしまわないことが大切です。
新たに開発された薬
・副作用は少ない
・効果は三環系抗うつ薬には及ばない
SSRI・SNRI
NaSSA
新しい抗うつ剤は、セロトニンやノルアドレナリンなどの働きを調節することで、うつ病の症状を改善します。
作用が比較的絞られているので、従来の抗うつ剤に比べて副作用が少ない傾向にあります。しかし、性機能障害や吐き気、下痢、不眠などの副作用が現れることもあります。
また、従来の抗うつ剤に比べて離脱症状が現れやすい傾向にあり、薬を急に中止したときに、頭痛やめまい、吐き気、不安、イライラなどの症状が現れることがあります。
慣れると副作用が少なくなる場合もありますが、やめるときには、慎重に減量していく必要があります。
うつ病や精神疾患に関する相談窓口は?

保健所・精神保健福祉センター
保健所には、地域ごとに担当保健師がいます。担当保健師以外にも、保健所には医師や精神保健福祉士が在籍しています。
相談方法は、電話や面接があります。それぞれの方の希望や状態に応じて、相談方法を決めることができます。
精神保健福祉センターは、各都道府県と政令指定都市にひとつずつあります。こころの健康についてや、社会復帰についての相談ができます。
相談を希望する場合には、電話で予約をすることでスムーズに相談ができるでしょう。
(社)日本産業カウンセラー協会
日本産業カウンセラー協会の電話無料相談のサービスにも、相談することができます。「働く人の悩みホットライン」という電話相談です。患者さんや家族、企業からの相談をうけています。
うつ病などの症状や薬の副作用で辛いときでも、外出せずに電話で相談をすることができます。協会に所属する産業カウンセラーに相談ができます。
一人で抱え込まずに、悩みについて話すことはうつ病の治療にとって大切です。そのためには、話せる場を一つでも多く持つことが必要です。
いのちの電話
うつ病などのの辛い症状、否定的な感情などで思いつめてしまう前に、相談することが大切です。しかし、どこかに相談に行くことも難しい状況の場合は、いのちの電話に相談することも一つです。
内服による副作用の影響や、精神の症状で辛い時には、外出も難しい場合があります。そのような場合でも、電話で相談ができることを覚えておきましょう。
精神科病院・クリニック
うつ病や精神疾患かもしれないという方は、精神科病院やクリニックで支援を受けることができます。
近隣のクリニックを受診して、相談や診察を受けることができます。薬物療法などの治療を受けることもできます。
また、必要に応じて、入院などの設備がある精神科病院を紹介してもらうこともできます。
クリニックには、内科的な診療やカウンセリングルームを併設しているところもあります。精神科病院も、さまざまな病院があり、通いやすさなどを考慮して選ぶことができます。
精神科訪問看護
- 日常生活の維持
- 生活技能の獲得・拡大
- 対人関係の維持・構築
- 家族関係の調整
- 精神症状の悪化や増悪を防ぐ
- ケアの連携
- 社会資源の活用
- 対象者のエンパワーメント
うつ病や精神疾患で悩んでいる方は、精神科訪問看護を利用することができます。精神科訪問看護は、主治医の指示が必要です。
精神科訪問看護では、薬の管理や副作用の相談、バイタルサインの測定など、さまざまな支援を受けることができます。
薬の副作用は、体の不調として現れることがあります。定期的に看護師などの医療従事者が訪問することで、体の不調を早期に発見でき、早くに治療を受けることが出来ます。
精神科訪問看護では、患者さんの住み慣れた地域で、その人らしく生活するためのサポートも行います。
精神疾患をお持ちならシンプレへ

シンプレ訪問看護ステーションとは?
シンプレ訪問看護ステーションは、精神科疾患に特化した訪問看護ステーションです。うつ病や摂食障害など、幅広い疾患を対象としています。
病気と付き合いながら自分らしい生活ができるように、自主性を尊重した看護サービスを提供しています。
また、病院、行政、在宅との情報共有を行い、それぞれの専門性を活かしながら治療や社会復帰のサポートができるのも特徴です。
シンプレは訪問看護サービスを通して利用者の不安を受け止め、治療への頑張りを一緒に共有し、心から安心できる居場所づくりをお手伝いします。
対応している精神疾患の例
・一日中気分が落ち込んでいる
・何をしても楽しめない
・眠れない・食欲がない・疲れやすい
統合失調症
・幻覚や妄想という症状が特徴的
・生活に支障をきたしてしまう
ADHD
・不注意さ、多動性、衝動性が特徴的
PTSD
・トラウマとなった記憶が突然よみがえる
その他精神疾患全般
シンプレ訪問看護ステーションは、精神科に特化した訪問看護ステーションです。訪問看護師が、お宅を訪問して、精神科看護をサービスとして提供します。
上記の他にも様々な精神疾患に対応しています。うつ病で内服中の方、薬の副作用などに不安を感じている方への訪問も可能です。
内服管理や医師への報告や連携など、患者さんが安心して生活するお手伝いをさせていただきます。
シンプレの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
上記のエリアが、対応可能なエリアになります。現在、訪問エリアを拡大中です。
上記のエリア以外でも、対応可能な場合があります。訪問看護をご検討中の方は、ぜひお問い合わせください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

ここまで、三環系抗うつ薬と副作用について整理しました。また、副作用が見られたときの注意点について述べてきました。新たに開発され、広く使われている薬についても取り上げました。
精神科疾患の方は、生活に困難を感じることがあります。治療には、医師とよく相談して、薬の量や種類を調整してもらうことで、症状を改善したり、再発を防ぐことができます。
シンプレ訪問看護ステーションでは、訪問看護を通して薬の管理や副作用の症状や病状の確認ができます。うつ病やその薬の副作用でお困りの方は、シンプレ訪問看護ステーションにご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



