アルツハイマー病の診断基準とは?
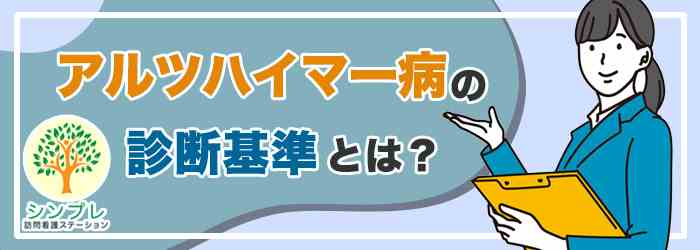
ご自身・ご家族の物忘れがひどくなり、アルツハイマー病ではないかとお悩みではありませんか?
アルツハイマー病は記憶や思考能力に障害が起こる病気で、悪化すると日常生活を送ることすら困難になってきます。アルツハイマー病かどうかを判断するにはどうすればいいのでしょうか?
今回は、アルツハイマー病の診断基準について紹介します。
アルツハイマー病の診断基準は大きく3種類
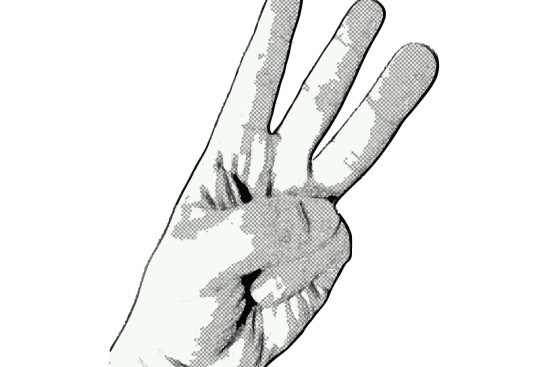
DSM-5の診断基準
DSM-5の診断基準は、これから説明する4つの項目をすべて満たした場合、アルツハイマー型認知症と診断されます。
一つ目は、記憶、言語、注意、実行機能、視覚空間機能、社会認知機能などの認知機能が、以前から比べて低下していることが必要です。
二つ目は、認知の低下が日常生活や社会生活に支障をきたしていることが必要です。例えば、買い物や料理、家事、交通機関の利用、服薬管理などができなくなる等が挙げられます
三つめは、アルツハイマー型認知症は、せん妄と区別できる必要があります。せん妄とは、認知機能の低下や意識障害を伴う精神症状のことです。
最後に、うつ病や統合失調症などの他の精神疾患によって説明できないことが必要です。
NINCDS/ADRDAの診断基準
NINCDS/ADRDAもまたよく使用される診断基準ですが、こちらは1984年からずっと修正されることなく用いられて来て、2011年に27年ぶりの改定となったものです。
改定後は「日常生活や仕事に支障をきたしている」という点に大きく注目した基準に変更となっていて、「認知機能の低下」よりもそちらにフォーカスしています。
時代が進むにつれて、この「生活障害(ADL障害)」がアルツハイマー病であることの診断基準として注視するべきポイントであるという考えにシフトしたと言えるでしょう。
ICD-10の診断基準
ICD-10という判断基準においては、「認知症の症状の存在」や「認知機能の低下が徐々に進行する」などの複数の特徴が必須となります。
また、「認知症の原因となり得る他の全身性疾患や脳疾患が原因の異常が見受けられない」なども見極める必要があり、専門的な知識や知見が必須となります。
前述の2点の診断基準も同様ですが、これらを元にした診断はあくまでも医師がおこなうもので、一般の方が安易に判断する材料にしても正確な判断にはならないのでやめましょう。
アルツハイマー病の症状をチェック

前兆(軽度認知障害)の症状
・物忘れ
・記憶障害
・判断力の低下
アルツハイマー病の発症の前兆は、物忘れなどの記憶障害が現れることがあります。しかし、これらの症状は日常生活に支障をきたすほどではありません。
そのため、本人や家族は「年齢のせい」と軽く考えてしまい、認知症の前兆であることを見過ごしてしまうことがあります。
アルツハイマー病の前兆は、軽度認知障害(MCI)とも呼ばれています。MCIは、認知症の初期段階に位置する状態です。放っておくと、症状が進行して認知症へと移行する可能性が高まります。
そのため、アルツハイマー病の初期症状が疑われる場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。
初期の症状
・直前の出来事を忘れてしまう
・勘違いや同じことを何度も繰り返す
・時間の感覚や、現在の日付や曜日などが分からない
・判断力が低下し、できないことが増える
・意欲が減退し、もの事を面倒くさがる
・物盗られ妄想
アルツハイマー病の初期になると、症状がさらに進んで「記憶障害」や「実行機能障害」なども見受けられ、単なる「もの忘れ」とは異なり、日常生活にも少しずつ支障がでてきます。
また、「今日は何月何日だろう」「今は何時だろう」など、時間に関する見当識障害が見受けられるようになるのも、この時期の特徴の1つです。
上記のような症状が現われるようになってきたときはアルツハイマー病を疑いましょう。
中期の症状
・場所・時間・季節などがわからなくなる
・徘徊・妄想が増える
・家事の手順・買い物の段取りがわからなくなる
・言葉の意味が分からなくなる
・食事・入浴・着替えなどに介助が必要となる
・失禁などの不潔行為が見られる
・衝動的な行動を起こす
中期になると「人物や場所を認識できない」「言語使用、簡単な行為ができない」などの症状も見られるようになり、日常生活を送る上で大きな支障となります。そのため、家族や介護者のサポートが必要となります。
具体的には、食事や服装、家事などをサポートしたり、徘徊や妄想を予防したりするために、生活リズムを整えるなどの工夫が必要です。
また、アルツハイマー病は進行性疾患であるため、症状は次第に悪化していきます。中期になると、ご家族だけでのケアが難しくなるケースも少なくありません。
サポート体制を整え、患者さんと家族のQOL(生活の質)を維持することが重要です。
末期の症状
・家族の顔が分からなくなる
・表情が乏しくなり反応がなくなる
・会話を通した意思疎通ができなくなる
・尿・便の失禁が常態化する
・歩行・座位が保てなくなり寝たきりになる
アルツハイマー病の後期症状は、上記のような日常生活に障がいが現れ、病状が進行して末期になると、最終的には寝たきりの状態になってしまいます。
アルツハイマー病の後期は、初期や中期と比べると記憶障害はさらにひどくなり、コミュニケーションをとること自体が困難になり、時には支離滅裂な発言をしてしまうこともあります。
歩行障害や運動障害が深刻になってくると、1日の大半を寝たきりの状態で過ごすようになり、免疫力が低下して感染症に感染しやすくなります。
そのため、より手厚い介護と支援が求められ、家族や介護者は、患者さんの状態に合わせて、食事や排泄、入浴、移動などの日常生活のサポートを行う必要があります。
アルツハイマー病の診断を受けるには何科に行けばいい?

神経内科
神経内科は脳や神経の疾患を専門とする科であり、認知症の診断と併せて、内科的なアプローチも行うことができます。
例えば、糖尿病や高血圧などの内科疾患が原因で認知症の症状が現れている場合、内科的な治療で症状を改善できる可能性があります。
また、アルツハイマー病の疑いがある場合は、かかりつけ医に診てもらうと、専門医を紹介してくれる場合があります。
アルツハイマー病の専門医としては、下記でも解説する、老年科医や老年精神科医、神経内科医などがあり、専門医はもの忘れ外来やもの忘れセンターなどを通じて探せます。
精神科
精神科もまたアルツハイマー病に対応しているわけですが、「妄想」「幻覚」などの精神的症状が極めて強い場合でない限り、最初に受診するのには向かないようです。
理由としては、精神科では、妄想や幻覚などの精神症状を抑制することに重点が置かれます。そのため、アルツハイマー病の症状である認知機能の低下や、日常生活の支障などの問題に十分な対応ができない可能性があります。
ただし、最初に神経内科などで受診していても、妄想や幻覚、暴力行為がひどいなどの症状が見られる場合は、精神科にバトンタッチするケースもあります。
老年科
アルツハイマー病は、高齢者に多く発症する疾患です。そのため、高齢者を総合的に診る老年科が、アルツハイマー病の診察も行うケースが増えています。
ただし、老年科医がすべてアルツハイマー病の専門家であるとは限りません。そのため、老年科を受診する際は、事前に認知症の知識や実績がある医師がいるかどうかを確認しておくことが大切です。
もし認知症の知識や実績がある老年科医がいれば、アルツハイマー病の診断や治療を専門的に受けることができます。
アルツハイマー病を診断する流れ
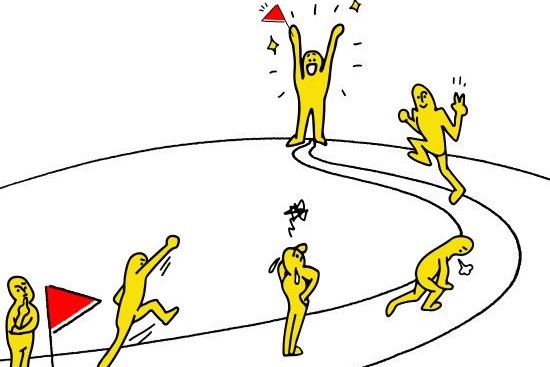
問診
まずは問診をおこない、患者さん本人とご家族からこれまでの経緯について詳しく聞き取りながら情報を整理していきます。
主に、「いつどんな症状に気付いたか」「日常生活で困っていること」「家族が困っていること」「病歴や薬の服用状況」「家族構成や環境の変化の有無」などを聞き取ります。
また、患者さん本人が自身の症状にあまり気付いていないケースも多いので、ご家族や身近な方からの情報が非常に重要になってくるようですね。
診察
問診で詳しい情報の聞き取りをおこなった後は診察に入り、患者さん本人の身体の状態を確認していきます。
血圧測定、聴診などの基本的な部分はもちろんのこと、手足の麻痺、不随意運動の有無、補講状態や発語状態なども併せてしっかりと診ていきます。
問診で得た情報に加えて身体の状態を把握することも非常に重要なので、この「診察」もとても大切な工程であると言えるでしょう。
検査
そして最後に必要な検査をおこなうわけですが、記憶障害の度合いを調べるために患者さん本人に簡単な質問に答えてもらうようなものから実施します。
また、頭部CTやMRIの画像検査で脳出血や脳梗塞の有無や脳萎縮の程度を調べたり、脳血流が保たれているかどうかの検査をおこなう場合もあるようです。
さらに、必要に応じて心電図検査や血液検査をおこなうこともあり、これらが完了したら最終的な診断に入るという流れになるので、しっかり覚えておきましょう。
アルツハイマー病に関する支援を受けるには?

アルツハイマー病の相談窓口
- 保健所・保健センター
- 地域包括支援センター
- 高齢者総合相談センター
- 認知症の人と家族の会
- 認知症110番
- 若年認知症サポートセンター
アルツハイマー病となった場合、ご家族のみで抱え込むのではなく、地域の相談窓口を利用して適切なサポートを受け、無理なく生活していくのがとても大切です。
主に上記のような専門機関で相談を受け付けてもらえ、例えば保健所や保健センターでは医療機関を教えてもらえますし、介護に関する相談に乗ってもらえるところもあります。
また、「認知症の人と家族の会」では、他の認知症の方やそのご家族と交流することもできるので、情報交換や人間関係の構築などにとても良い環境と言えるでしょう。
訪問看護を利用するという選択肢も
訪問看護では、「健康状態の観察」「病状悪化の防止・回復」「服薬の管理」など、症状の改善に向けてさまざまなポートを受けることができます。
病状や内服状況など、医療機関やかかりつけの医師と連携し情報を共有できます。
そのほかにも必要に応じて、医師や保健師、ケースワーカーなどの関係機関と連携し、病状の悪化の防止や早期回復につながるようサポートを行います。
訪問看護ならシンプレ看護ステーションへ!

シンプレ訪問看護ステーションとは?
シンプレは精神疾患に特化した訪問看護ステーションで、うつ病や摂食障害など、幅広い疾患を対象としています。
精神科訪問看護は精神科や心療内科に通院され精神疾患と診断されている方、診断はなくとも睡眠障害などで医師が訪問看護が必要と判断された人が対象です。
看護師や作業療法士などの医療スタッフが医師の指示のもと自宅へ訪問し、病状観察や日常生活指導、また家族支援などのサポートを行います。
通常、訪問は医療保険を利用し週3回まで可能で、1回の訪問は30分から90分と決められています。体調や病状に合わせて訪問回数や時間を調整します。
アルツハイマー病のほかにも精神疾患をお持ちの方の場合は医療保険の訪問看護になります。アルツハイマー病のみの場合、介護保険の適応となります。
看護内容
・うつ病
・アルコール依存
・薬物依存
・精神疾患全般
主な看護内容
・生活支援、自立支援
・症状の悪化防止、服薬支援
・社会復帰へのサポート
・家族の方への支援
シンプレ訪問看護ステーションの看護内容ですが、上記の表のように、幅広い精神疾患をおもちの患者さんも対象です。
病状が悪化しないようにするためのケアはもちろんのこと、日常生活を送る上でのサポートや、社会復帰への支援などご利用者様の状態にあわせた支援をします。
アルツハイマー病のほかにも精神疾患をお持ちの方の場合は医療保険の訪問看護になります。アルツハイマー病のみの場合、介護保険の適応となります。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
現在の対応エリアは、上記を中心となっております。これらのエリア以外も近隣のエリアであれば対応できることもありますので、お気軽にお問い合わせください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っており、年齢に関わらず利用することが可能です。
TwitterやLine、TikTokなどのSNSでも情報を発信していますので、ぜひご覧ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

アルツハイマー病であると診断された場合は、早めに専門機関へ相談し、適切なサポートやケアを受けることが大切です。
わたしたち、シンプレ訪問看護ステーションもきっとお役に立てることがあります。
現在アルツハイマー病で悩んでいる方や、そういった方がご家族におられる場合は、訪問看護の利用をぜひご検討くださいね。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



