精神疾患の身内が暴れてしまった場合の対処法

一部の精神疾患には自身の感情などがコントロールできなくなり、人や物にあたるなど暴力的になってしまうという症状が見られます。
そういった方が暴れてしまったとき、周りの方はどうしたらいいのか悩んでしまうこともあるでしょう。
今回はそんな時にどう対処したらいいか、また、頼ることが可能な施設・サービスなどを紹介していきます。
精神疾患を持つ方が暴れてしまう場合の対処法

対処方法一覧
対処①疾患者から逃げる
精神疾患を持っている方が暴れる場合の対処法として、速やかに患者さんから離れて逃げることが大切です。
患者さんが殴りかかってきた場合は、手や物(大きめの本やバインダーなど)で顔を守り、掴まれないように注意して素早く逃げるようにします。
暴れる患者さんから素早く逃げるには、普段から「危機離脱技法」などのトレーニングを受けておくことが大切であり、精神科の医師や看護師に相談されると良いでしょう。
対処②反論・挑発などをしない
怒りの感情をコントロールできずに暴れる患者さんには反論や挑発などをせず、黙って話しを聞いてあげましょう。もし、暴力を振るってきたら、素早く逃げてください。
怒りの感情を爆発させている患者さんに対して、反論や挑発をすると火に油を注いでしまうことになり、患者さんはますます怒りを爆発させてしまいます。
反論・挑発をしないためには、患者さんの精神疾患について正しく理解し、正しい接し方を身につけることが大切です。
対処③落ち着くまで放置
感情をコントロールできずに暴れる患者さんは、時間が経過すると自然に落ち着きます。そのため、まずは安全な距離をとり、患者さんを落ち着かせるまで静観しましょう。
ただし、患者さんが暴れ続け、身の危険を感じる場合や、周囲に危害を加える恐れがある場合は、警察を呼ぶなどの対応が必要です。
専用施設に頼ることを視野に入れてもいい

専門施設の一例を紹介
①入院
暴れる患者さんは、自分でも周りの人も危険にさらす可能性があるため、精神科に入院することができます。
入院では、薬物療法や心理療法などの治療を受けることができます。入院の必要性と期間については、精神科医の診察を受け、判断してもらうことが必要になります。
②保健所
保健所は、地域の保健衛生に関する相談窓口です。暴れる患者さんについて相談することもできます。
保健所に家で暴れていることを相談することで、医療機関や支援機関を紹介や、患者さんや家族の支援などの相談に対応してくれます。
③精神科救急情報センター
精神科救急情報センターは、精神疾患に関する緊急時の電話相談窓口です。都道府県によっては設置されていない所や設置場所によっては営業時間が異なるため、事前に調べておくと良いでしょう。
ただし、暴れたり、自分を傷つけたりする可能性がある場合は、警察へ通報するようにしましょう。
暴力的な言動が見られる精神疾患

自らをコントロールできなくなる疾患が多い
疾患①統合失調症
統合失調症は、妄想や幻覚などの陽性症状が特徴の精神疾患です。
陽性症状は、実際には存在しないものを見たり聞いたり、あるいは自分の考えや行動が他人に操られていると考えたりするような、現実感の欠如した症状です。
統合失調症の患者さんは、陽性症状によって興奮状態となり、暴力を振るうことがあります。暴力は、患者さん自身や周囲の人々を傷つける原因となるため、注意が必要です。
疾患②アルコール依存症
アルコール依存症とは、多量飲酒が原因で節度ある飲酒ができなくなってしまい、家族や仕事よりもお酒を飲むことを優先させてしまう依存症をいいます。
アルコール依存症になると、離脱症状(禁断症状)や不安・不眠などの精神症状、精神・身体合併症などの症状が現れ、強い中毒症状が出ると暴れることがあります。
疾患③うつ病
うつ病になると、気分が落ち込み、意欲がわかず、何をやってもうまくいかないなど、さまざまな症状が現れます。
うつ病の方が攻撃的になると、言動が激しくなり、暴力に発展したり、自分自身を傷つけることもあります。
周囲だけで支えきれなくなったときは、専門医の力を借りることも大切です。
暴れる前兆を見逃さず早期治療を進めよう
暴力は、上記のような精神疾患の患者さんの他にも、認知症や発達障害などの患者さんで起こることがあります。
これらの患者さんは、現実を正しく認識できなくなったり、自分の感情をコントロールできなくなったりして、暴力を振るうことがあるのです。
暴力に発展しやすい場面や会話は、患者さんによってさまざまですが、暴力に発展しやすい場面や会話を見逃さないようにすることで、暴力行動を予防することができます。
治療は投薬治療が一般的
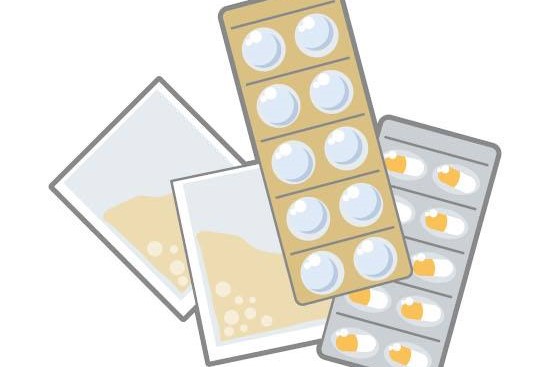
服薬によって症状が改善される場合が多い
抗精神病薬は、統合失調症や双極性障害の躁状態の治療に用いられる薬です。脳内のドーパミン神経の活動を抑制することで、興奮を抑えます。
抗精神病薬は、長期間にわたって服用する必要があり、服用するとのどの渇きや便秘、排尿障害などの副作用が出ることがあります。
副作用に注意し、医師の指示に従って抗精神病薬を継続して服用するこが大切です。
興奮を抑える薬一覧
抗精神病薬は大きく分けて3種類があります。では、抗精神病薬を種類ごとに見ていきましょう!
治療薬①非定型抗精神病薬
非定型抗精神病薬
治療薬例
・リスペリドン
・ペロスピロン塩酸塩水和物
・ブロナンセリン
非定型抗精神病薬は「新規抗精神病薬」ともいい、ドーパミン神経以外の神経伝達物質に働きかけることが特徴です。
統合失調症の症状は妄想や幻覚などの陽性症状と、意欲の減退や閉じこもりなどの陰性症状がありますが、非定型抗精神病薬は陰性症状の治療のために使用されます。
非定型抗精神病薬はリスペリドンやペロスピロン塩酸塩水和物、ブロナンセリンなどがあり、患者さんの症状に応じて最適なお薬が処方されます。
治療薬②定型抗精神病薬
定型抗精神病薬
治療薬例
・スルピリド
・スルトプリド塩酸塩
・チアプリド塩酸塩
定型抗精神病薬は、脳内のドーパミン神経の活動を抑制させて興奮を抑えるためのお薬で、統合失調症の陽性症状や双極性障害の躁状態の治療によく使用されます。
ドーパミンは意欲や快楽に関係する神経伝達物質ですが、過剰に分泌されると興奮状態がひどくなり、暴れることの原因になることがあります。
定型抗精神病薬にはスルピリドやスルトプリド塩酸塩、チアプリド塩酸塩などがあり、これらのお薬を服用することで興奮が抑えられます。
治療薬③注射剤
抗精神病薬は経口剤と注射剤があり、経口剤は飲み薬で注射剤は注射で注入するお薬です。
抗精神病薬の注射剤は筋肉に注射をすることで、有効成分が長期間にわたって筋肉内に留まり、1回の注射で効果は2~4週間続きます。
抗精神病薬は、飲み忘れに注意をしなければなりませんが、飲み薬を注射に置き換えることで飲み忘れによる症状の悪化も防ぐために使用されることがあります。
あくまで定期摂取が前提
患者さんが暴れるのを防ぐには、抗精神病薬の服用を続けることが必要です。
自己判断で服用を中断すると、効果が減退し、再び暴れるようになる可能性があります。
自宅療養をしている患者さんは、主治医などと相談しながら、投薬管理をしっかりと行うことが非常に大切です。
精神科訪問看護のサポートを得ることも可能

精神科訪問看護とシンプレ訪問看護ステーション
| サービス名 | 精神科訪問看護 |
|---|---|
| 職種 | ・看護師 ・准看護師 ・作業療法士 |
| 訪問日数 | ・原則週3日以内 |
精神科訪問看護は精神科や心療内科に通院され精神疾患と診断されている方、診断はなくとも睡眠障害などで医師が訪問看護が必要と判断された人が対象です。
看護師や作業療法士などの医療スタッフが医師の指示のもと自宅へ訪問し、病状観察や日常生活指導、また家族支援などのサポートを行います。
通常、訪問は医療保険を利用し週3回まで可能で、1回の訪問は30分から90分と決められています。体調や病状に合わせて訪問回数や時間を調整します。
家庭での療養状況やご家族の疲労を確認し、デイサービスやショートステイ、介護サービスの導入も提案できます。
精神科訪問看護の内容
- 日常生活の維持
- 生活技能の獲得・拡大
- 対人関係の維持・構築
- 家族関係の調整
- 精神症状の悪化や増悪を防ぐ
- ケアの連携
- 社会資源の活用
- 対象者のエンパワーメント
精神科訪問看護では、「健康状態の観察」「病状悪化の防止・回復」「社会復帰の支援」など、症状の改善に向けてさまざまなポートを受けることができます。
訪問してご本人様と面会ができない場合でも、ご希望があればご家族様からの相談を受けることも可能であったりと、それぞれの利用者様にあった看護を行います。
外出が難しい方や精神科への入退院を繰り返している方、ご家族がどのように関わっていけばいいか困っている方はご相談ください。
そのほかにも必要に応じて、医師や保健師、ケースワーカーなどの関係機関と連携し、病状の悪化の防止や早期回復につながるようサポートを行います。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応地域はおもに上記が中心で、訪問活動をおこなっています。該当エリアにお住まいの方はぜひご検討ください。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。電話やメールなどで相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

精神疾患をもつ患者さんは暴れることがありますが、反論や挑発をしないことや患者さんが暴れたら速やかに逃げることで対処しましょう。
また、精神疾患をもつ方から家庭内で暴力があった場合、専門医など外部の機関に相談するようにしましょう。
どこに相談をしたらいいかわからなくて困っていた、訪問看護のサービスについて聞いてみたいなどございましたら、シンプレ訪問看護ステーションまでお気軽にご連絡ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



