知的障害はIQでどう分類される?くわしい診断基準や相談窓口のまとめ
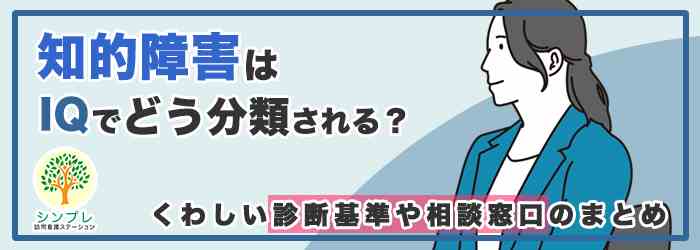
IQがどの程度のレベルになると知的障害と判断されるのだろうか?と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
IQとは知能指数のことで、知的障害の重症度を分類するうえで重要な指標となります。しかし、IQが低いからといって必ずしも知的障害とは限りません。
そこで今回は、知的障害と診断する際のIQ以外の要素などについて解説します。
知的障害はIQでどう分類される?
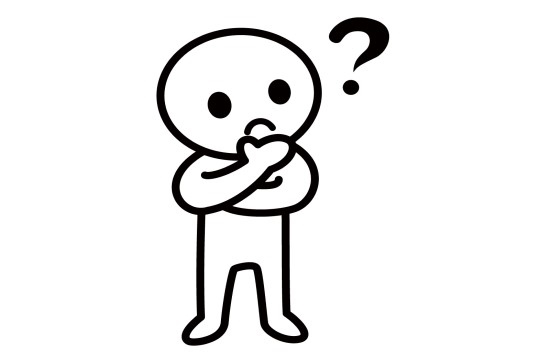
50〜55 70程度
中等度
IQ35〜IQ40
IQ50〜IQ55
重度
IQ20〜IQ25
IQ35〜IQ40
最重度
IQ20〜IQ25以下
軽度・中等度・重度・最重度の4つにわかれ、知的能力をあらわすIQから判断する場合は、上記のようになります。
知的障害とは、知的能力や社会生活への適応機能が低く、日常生活をおくるのが困難な状態をいいます。知的障害の診断は、知的能力を表すIQと日常生活への適応機能などを総合的にみたうえで、判断していきます。
日常生活への適応機能とは、日常生活の動作や社会生活を営む上で必要な能力のことです。具体的には、言語能力、学習能力、自立生活能力、社会性などが挙げられます。
IQだけでは判断できない?IQ以外の要素

適応機能の欠陥または不全
読み、書き、計算における判断能力領域
社会的領域
・他者の思考、感情、体験の認識領域
・対人コミュニケーションに関する領域
実用的領域
実生活での学習および自己管理の領域
(セルフケア、行動の自己管理など)
適応機能とは、日常生活や社会生活を営むために必要な能力です。適応機能障害の評価は、上記の3つの領域を総合的に判断して行われます。
具体的には、対人関係におけるコミュニケーション能力や、お金の管理や食事の準備など日常生活を過ごすうえで必要となる能力などがあげられます。
発症が18歳以前
知的障害の発症率は、人口の1%~2%程度でであると言われています。
軽度知的障害では男性に多い傾向があり、男女比は2:1程度です。重度知的障害では、男性と女性の差は小さく、男女比は1.5:1程度です。
知的障害は、生まれつき(先天性)の場合と、生まれた後に脳の障害などによって起こる(後天性)場合があります。
先天性の知的障害は、乳児期までに明らかになることが多く、軽度知的障害の場合でも、3歳までに何らかの形で明らかになる傾向にあります。
後天性の知的障害は、脳外傷や脳炎髄膜炎などの疾患によって起こり、発症年齢にかかわらず、発症後に知的障害が引き起こることあります。
知的障害の診断はどのようにされる?

標準化知能検査
- ウェクスラー系
- ビネー系
知能や思考能力をみるためには「発達知能検査」が使われます。一般的に、知能検査では主にウェクスラー系やビネー系の2つが用いられており、それぞれが違った特徴があります。
ウェクスラー系は、年齢ごとに分類され3歳10ヶ月〜7歳1ヶ月まで検査が可能なWPPSI、5歳から16歳11カ月まで検査が可能なWISC、16歳~成人まで検査が可能なWAISの3つにわかれます。
ビネー系は、現在は田中ビネー知能検査Ⅴとよばれ、2歳から成人まで検査が可能です。
適応機能
知的障害の判断は、知能検査の結果だけでなく、日常生活での適応能力も考慮します。適応能力とは、日常生活の中で、一人でできることや、周囲の人と協力してできることです。
適応機能検査では、概念、社会性、実用性の3つの能力を測定します。概念スキルは、会話や読み書き、学力などの能力です。
社会性スキルは、遊びや集団行動、対人関係、ルールや法律を守ることなどの能力です。
実用スキルは、食事や排泄、掃除などの身辺自立、仕事やお金の管理などの能力です。それぞれのスキルについて、問診などによって評価を行い、支援の必要度を判断していきます。
医学的検査
- 血液生化学検査
- 尿検査
- 脳波
- 発電位検査
- 頭部CT
- 神経画像検査
知的障害の診断には、心理検査に加えて、医学的検査が行われることがあります。医学的検査は、知的障害の原因や程度を正確に診断するために行われます。
具体的には、脳の構造や機能、染色体や代謝状態などを調べます。脳の構造や機能に異常がある場合は、脳波検査や画像検査などによって調べます。
また、遺伝的な原因が疑われる場合は、遺伝子検査を行うこともあります。
知的障害と併存してしまう疾患は?

自閉スペクトラム症
発達障害のひとつである自閉症は、知的障害が併合してあらわれることは少なくありません。
自閉スペクトラム症は、コミュニケーションをとることが苦手なことやこだわり行動のあることが特徴です。
また集中力がないことやじっとしていられない症状がある注意欠陥・多動性障害(ADHD)も併合することが多い傾向にあります。
そのほかにも読む事や書くことが困難な学習障害(LD)なども知的障害と併存する可能性が高いことが知られています。
睡眠障害
- 不眠
- 過眠
- いびき、無呼吸
- 睡眠中の異常行動
睡眠障害とは、上記のような症状をいい、なにかしらの睡眠に関する問題があることをさしています。
自閉症やADHDなどを診断されたかたは、睡眠障害が併合していることが多いです。
とくに乳幼児期では、寝つきがわるかったり、ちょっとの音で目を覚ましたり、睡眠リズムが確立しにくい傾向がいちじるしくみられることなどが知られています。
原因のひとつとして、成長の過程において脳の機能が不十分であり、睡眠と覚醒を調節する中枢神経系の機能不全の可能性がかんがえられています。
てんかん
てんかんの症状は、脳の中で異常な電気信号がおこり、その症状はじつにさまざまです。
たとえば脳の一部でおこった場合では、ひかりがチカチカ見えることや手がピクピク動くなど、患者さん自身がかんじられる症状にちがいがあります。
知的障害に関する相談窓口

・福祉事務所
・知的障害者更生相談所
・知的障害者相談員
知的障害がある子どもについて
・保健所、保健センター
・児童相談所
・市区町村の相談窓口
・児童発達支援センター
仕事について
・ハローワーク
・地域障害者職業センター
・障害者就業、生活支援センター
・就労移行支援事業など
知的障害に関する相談窓口は、障害や暮らし、仕事など、さまざまな分野に対応しています。
障害や暮らしに関する相談窓口は、主に福祉事務所、知的障害者更生相談所、知的障害者相談員が担っており、福祉サービスを利用したい、施設に入りたいなど、障害をお持ちの方の様々な相談に応じています。
保健所、保健センター、などでは子どもの発達や教育に関する相談、療育の利用方法などについて相談することができます。
仕事に関する相談窓口は、ハローワーク、地域障害者職業センターなどがあり、就職や職業訓練に関する相談、就労支援の利用方法などについて相談することができます。
知的障害に関するお役立ち情報

生活を支援する制度やサービス
まず初めに、療育手帳や障害福祉サービスなど生活を支援するサービスについて紹介します。
療育手帳(障害者手帳)
障害者手帳とは、身体障害手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳の3つにわかれ、そのうち療育手帳は「愛の手帳」ともよばれています。
療育手帳は、児童相談所などで知的障害があると判定されたかたに交付され、障害者雇用の応募、就労に関するサポートや交通運賃の割引などをうけることが可能です。
障害福祉サービス
ホームヘルプ(入浴・排泄などの介護、料理・そうじなどの家事の援助)、外出の介護や施設へのショートステイなど、さまざまな福祉サービスを利用することができます。
障害福祉サービスを利用するには「障害福祉サービス受給者証」の交付が必要となり、お住まいの市区町村へ申請して認められると交付されます。
支援団体・ネットワークなど
次に、支援団体などのサービスについて紹介いたします。
全国手をつなぐ育成会連合会
知的障害者の権利擁護や政策の提言を行う団体です。全国各地の「手をつなぐ育成会」が連合して、知的障害のある人やその家族の支援を行っています。
「手をつなぐ(月刊誌)」の発行、生活の場で起こるトラブルを相談できる「障害者110番」や研修会など、知的障害のあるかたやその家族にむけたサポートをおこっています。
全国重症心身障害児(者)を守る会
1966年に設立された、重症心身障害児(者)とその家族を支援する団体です。
全国各地に支部があり、幼児から成人にいたるまで、重症心身障害に関する情報提供や、療育相談事業を行っています。
精神科訪問看護を利用するという選択肢

| サービス名 | 精神科訪問看護 |
|---|---|
職種 |
・看護師 ・准看護師 ・作業療法士 |
訪問日数 |
原則週3日以内 (※例外もあります。) |
精神科訪問看護は、精神疾患を抱える方や精神的な理由でサポートが必要な方が、自宅で受けられる看護サービスです。
看護師などの医療従事者が自宅を訪問し、身の回りの世話や食事、心のケアなどの支援を行います。
また、家族へのサポートも行っています。家族の不安や悩みを聞き、利用者を取り巻く環境を整えていきます。
入院や通院と異なる点は、自宅でライフスタイルに合わせて看護を受けられることです。症状や困りごとに応じた看護を行います。
精神科訪問看護ならシンプレへ!

当ステーションの特徴
精神科に特化した訪問看護サービスを展開しています。精神疾患から依存症まで、さまざまな症状に対応しています。
看護師などのスタッフが訪問し、利用者様の希望や目的に合わせてサポートします。
また、利用者様本人だけでなく、ご家族の精神的なフォローにも対応します。一緒に前向きに生活を改善することを目指しています。
訪問看護により、利用者様の病状をしっかり管理・治療しながら、一人ひとりの利用者様が心から安心できる居場所づくりをお手伝いします。
精神疾患の一例
・他人と目を合わせることが苦手
・相手や状況に自分の行動をあわせることが苦手
・言葉の裏の意味や抽象的な言葉の意味を理解するのが苦手
うつ病
・気分が落ち込む
・罪の意識を感じて自分を責める
・希死念慮
発達障害
その他精神疾患全般
上記は、精神疾患の一例です。
精神疾患とは、精神に何らかの問題が生じている状態のことをいいます。具体的には、自閉症やうつ病、統合失調症など、さまざまな症状があります。
シンプレは精神疾患に特化した訪問看護サービスで、家族とともに本人に寄り添い、本人らしく生きていけるようサポートします。
ご利用をご検討の際はお気軽にご連絡ください。
シンプレの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応地域はおもに上記が中心で、訪問活動をおこなっています。該当エリアにお住まいの方はぜひご検討ください。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
年齢に関わらずご利用することが可能で、サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。
電話やメールなどで相談を受けつけていますので、まずはお気軽にご連絡ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

知的障害とは、知的能力や適応行動に遅れや障害がある状態のことです。IQなど総合的に検査を行い診断されます。
精神疾患を抱える方の中にも、外出や社会参加が困難な方がいます。そのような方々は、不安や困難感を抱えながら、一人で悩んでいるケースが多くあります。
シンプレ訪問看護ステーションは、そうした人たちの不安や困難感に寄り添い、チームでサポートする体制を整えています。
精神科訪問看護について詳しく知りたい方は、ぜひシンプレ訪問看護ステーションにお問い合わせください。
ご相談の問い合わせはこちら▼



