引きこもりと精神疾患の関係
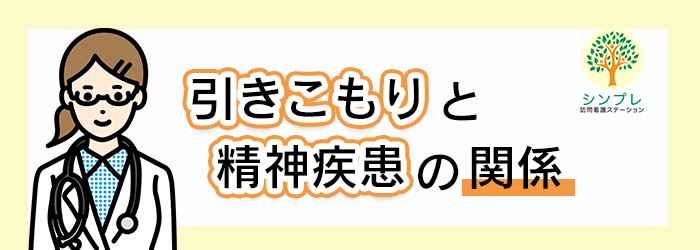
近年は、大人の引きこもりが社会的な問題になっている「引きこもり」。実は、引きこもりと精神疾患には深い関係があることを知っていますか?
精神疾患の症状が悪いと、突発的な自殺に至る可能性もあるため早めの治療が大切です。そこで今回は、引きこもりと精神疾患の関係性や支援を受けられる場所を紹介します。
一人で問題を抱えずに、まずは支援を受けられる場所に相談しましょう!
引きこもりとは?精神疾患との関係性

「引きこもり」という言葉はよく聞きますが、精神疾患との関係性が深いといわれています。まずは引きこもりと精神疾患との関係性を見ていきましょう。
引きこもりとは
・満40歳から満64歳
・61.3万人(人口の1.45%)
平成27年度調査
・満15歳から満39歳
・54.1万人(人口の1.57%)
引きこもりの定義は、様々な要因の結果として社会的参加(学校への通学、アルバイトなどを含む就労、家庭外での交遊など)を回避している状態のことを言います。
加えて概ね6か月以上にわたって家庭しとどまり続けている状態を指します。
しかし近年では引きこもりの長期化や、社会に出た後に引きこもりになってしまうケースなどにより、30歳代以上も増加の傾向にあるのです。
引きこもりと精神疾患の関係
・幻覚や妄想という症状が特徴的
・生活に支障をきたしてしまう
双極性障害
・気分の高揚(躁状態)と低下(うつ状態)を繰り返す
うつ病
・気分の落ち込みや意欲の低下
・体のだるさや痛み
パニック障害
・突然恐怖や不安を伴う発作が起こる
引きこもりの約8割は、何らかの精神疾患が原因であると考えられています。
医学的な治療は、引きこもりの原因となっている精神疾患の症状を改善し、社会復帰を促す上で有力な支援となります。
統合失調症は、およそ100人に1人弱が発症すると言われており、幻覚や妄想などの症状が現れます。
双極性障害は、気分障害の一種で、躁状態と抑うつ状態を繰り返す精神疾患です。
他にも、うつ病、強迫性障害、パニック障害、社交不安障害などの精神疾患が引きこもりとの関係が深いとされています。
特に注意すべき精神疾患は?
引きこもりの原因となる精神疾患には、上記でも解説しましたが、うつ病などの気分障害、統合失調症などがあります。
これらの精神疾患は、適切な治療を受けることで症状を改善し、社会復帰を促すことができます。
引きこもり状態を長引かせないためには、周囲の人間が引きこもり状態の原因となる精神疾患の存在を理解し、本人の治療を支えていくことが重要です。
引きこもりは4つのタイプに分かれる!解決策は?
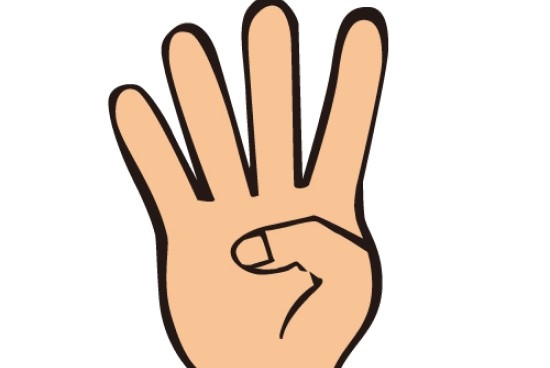
引きこもりと一口に言っても、人それぞれその特徴が異なります。大きく分けて4つのタイプ/がありますので、一つずつ解説していきます。
①仕事探しが面倒で家に引きこもる
友達もいて、人間関係に問題があるようではない、また何かやらせてあげると、できないわけでもない。
でも働くように周囲が助言すると「めんどくさい」と引きこもってしまうタイプ。親としては原因が分からないという方が多いです。
またこのタイプの大きな特徴としては、子供自身は困っているようには見えない事。はっきりした理由がないのに、なんとなく引きこもってしまっている状態のことを指します。
②仕事や学校、資格などある特定に固執する引きこもり
2つ目は「夢追いタイプ」です。すぐ他人と比較し、特定の仕事や学校、資格などに固執し、夢にこだわり続けるがあまり膨大な時間をかけてしまいます。
このタイプは少ない経験の中で育まれた狭い価値観を持っており、アルバイトなどの社会体験も拒否する場合が多いです。
夢を追うことはもちろんいいことですが、色々な体験をさせて色々な話を聞かせてみて価値観を広げることが有効的な対策となります。
③親に暴力や暴言を吐いて部屋に引きこもる
3つ目のタイプは、親に暴力や暴言などがある引きこもりです。このタイプの特徴は、自分の親が暴力や暴言を受けている、という自覚が薄い場合があるということです。
なのでこのようなタイプの引きこもりであれば、親は子供との距離をとり、介入しないようにしましょう。
第三者に相談し、介入してもらうことが大切です。親子だけでの解決は諦め、様々な機関の支援を受けることをおすすめします。
④親子の関係が友達関係になっている
食事も楽しく会話しながら一緒に取り、時には一緒に外出したりもするタイプで、一見引きこもりではないようなタイプがあります。
しかし友達のように親子の関係性が出来上がっているので、「働きなさい」といった肝心な話がいつまでたってもできずにいる場合があります。
親は子に、子は親に依存してしまっている「共依存」の状態で、長期化すると子供側が依存に気が付いて暴力や暴言に発展してしまうケースがあります。
心理・社会的な支援方法

引きこもりの状態を脱するには、様々な治療方法や支援方法があります。引きこもりのタイプに合わせて治療方法を選ぶことが大切です。
個人療法
引きこもりをしている当事者が相談や治療に参加できる場合にできるのが、「個人療法」です。
引きこもり支援において、個人療法の位置付けは他の精神疾患とはやや異なり、家族支援の比重がとても大きくなっています。
当事者が集団的な生活をできるまでを支援し、デリケートな多様な葛藤の克服を支援します。
そうしてもともと当事者に備わっている自我・活力の回復を目指し、集団療法へと移っていくのです。
集団療法
引きこもりの当事者は、他者とのコミュニケーションが不足していたり、仲間経験が不足、仲間経験の中で気う付いた過去を持っている場合があります。
そこで効果的な集団療法では、出席や発言を強制されない、発言に対して少なくとも支援スタッフからは非難されない、といった支持的な枠組みが確立されています。
しかし、当事者は、人前で話すことや、新しい人と交流することに慣れていないため、最初は疲労感や不安を感じやすくなります。そのため、回復には時間がかかります。
家族やスタッフは、当事者の気持ちを理解し、無理をさせないように配慮することが大切です。
デイ・ケア
デイ・ケアとは、スポーツや音楽などの表現活動、社会見学、そしてディスカッションなどを通じて社会復帰に必要な様々なスキルを身につけるための支援方法です。
上記のような様々な取り組みに他者と一緒に活動することで経験をつみ、他者と折り合いを付けながら適切に自己主張をするスキルを身につけていきます。
これらのデイ・ケアを通じて親密な仲間関係の経験と、社会参加のきっかけを得るということの支援効果があります。
教育機関による支援
引きこもりによって不登校になっている子供を支援するために、教育機関による支援が、様々な内容で行われます。
中でも教育相談機関では、生徒・児童およびその保護者の精神療法やカウンセリングと呼ばれる個別支援を行う役割と、学校や担当教師に支援方法をアドバイスする役割を持っています。
適応指導教室では、現役の職員に加えて、心理学や教育学に精通する指導員などが支援に当たり、個人の事情に合わせて柔軟な支援を行い、その内容は様々です。
引きこもりの相談場所を教えて!

自分の子供が引きこもりかもしれないと悩んでいる方は、以下の相談場所へ相談してみる事をおすすめします。それぞれの役割や特徴を解説していきます。
引きこもり地域支援センター
ひきこもり
地域支援センター
相談方法
・電話
・面談
相談相手
・社会福祉士
・精神保健福祉士
・公認心理師など
ひきこもり地域支援センターとは、引きこもりに特化した専門的な相談窓口として全国各都道府県、指定都市に設置・運営運営されています。
このセンターでは、地域における関係機関とのネットワークの構築や、地域における引きこもり支援の拠点としての役割を担っているのです。
社会福祉士・精神保健福祉士・臨床心理士の資格を有する支援コーディネーターが、引きこもりの状態にある方や家族へ相談支援を行っています。
精神保健福祉センター
精神保健福祉センター
相談方法
・電話
・面談
相談相手
・医師
・看護師
・保健師
・精神保健福祉士
・臨床心理技術者
・作業療法士
精神保健福祉センターは、引きこもりなどの精神疾患に関する相談に対応する公的機関です。
センターには、精神保健福祉士や臨床心理士などの専門職が在籍し、相談者の話を聴き、必要な支援につなげてくれます。
各都道府県に設置されていますが、地域によって支援内容や対象が異なる場合があります。そのため、お住まいの地域のセンターの情報を事前に確認しておきましょう。
精神科訪問看護
精神科訪問看護
相談方法
・電話
・面談
相談相手
・訪問看護師
・作業療法士など
精神科訪問看護とは、引きこもりになる原因となる統合失調症やうつ病、適応障害などの精神疾患に特化した訪問看護を行うことです。
引きこもりで支援が必要、また服薬による精神疾患の治療が必要な場合に、専門資格を有した看護師や作業療法士が自宅へ訪問し、療養上のお世話や看護を行います。
また、社会復帰に向けて治療を後押しし、いずれ自立していくための支援もしてくれるので、家族だけでは支援しきれない場合に利用を推奨します。
引きこもりと関係が深い精神疾患を治療するならシンプレ訪問看護ステーションにお任せください!

家族だけでの支援が難しい場合は、当シンプレ訪問看護ステーションの利用を検討ください。
シンプレ訪問看護ステーションって?
自分らしく自立した生活を
営めるための支援
症状の悪化防止・服薬支援
生活状況を観察しながら
受診や服薬を支援
社会復帰へのサポート
主治医や関係機関と連携を
取りなが社会復帰を支援
家族の方への支援
家族へのアドバイスや相談、
社会資源の活用などを支援
シンプレ訪問看護ステーションは、精神疾患に特化した訪問看護を提供しており、引きこもりとの関係の深い統合失調症やうつ病の方などの支援を行っております。
訪問時に生活状況や症状を確認し、ご利用者様の主治医や関係機関と連携を取ることで、治療の前進をサポートします。
専門知識や経験が豊富な、精神疾患に対する看護を行いたいという気持ちの強いがスタッフが集まっており、精神科訪問看護サービスを受けるのが初めての方でご利用いただけます。
利用者様の主治医や通っている医療機関とも密に連携をとりながら、ご利用者様が家庭や地域社会で安心して日常生活を送れるようしっかりとご支援いたします。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションは、現在の対応エリアは、上記を中心となっております。
上記のエリア以外での利用を希望される場合でも、利用できる可能性がありますので、利用を検討している方はお気軽に相談ください。
引きこもりを引き起こす精神疾患は、周りが気付き、早期に適切な治療・支援を施すことが大切です。ひとり・家族だけでは抱え込まず、周囲の関係機関に相談しましょう。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

引きこもりと精神疾患の関係性について解説しました。
引きこもりの約8割は、精神疾患が関係しています。早期に診断を受け、適切な支援を受けることで、引きこもり状態が改善し、社会復帰が促されます。
精神疾患の治療には時間がかかります。家族だけで抱え込まずに、関係機関に相談しましょう。
シンプレ訪問看護ステーションでは、引きこもりの方への支援・訪問看護を行っています。ご相談・ご利用をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



