精神疾患の方が障害年金を受け取れる条件とは?
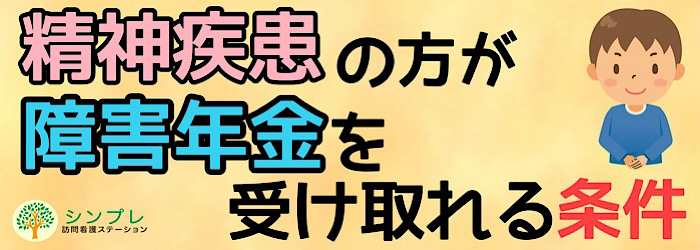
精神疾患を抱えてしまった場合、仕事ができずに生活に支障をきたしてしまうことは珍しくありません。そんなときに支えとなるのが障害年金です。
精神疾患の種類によっては、障害年金の支給対象となりますが、対象となる疾患や条件などを正しく把握しておくことが大切です。
そこで今回は、精神疾患で障害年金を受け取る条件や申請方法などについて解説していきます。
精神疾患で障害年金の受給を考えている方は、ぜひこの記事を最後まで読んでみてくださいね。
どんなときに精神疾患が障害年金の支給対象となる?
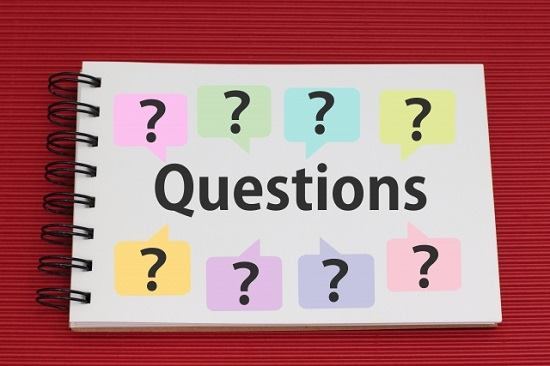
日常生活や労働に支障をきたしている状態
精神疾患が障害年金の支給対象となるのは、日常生活や労働に支障をきたしている状態である場合です。
障害年金の制度には、障害年金の対象となる状態がどうかを判断する障害認定基準が設けられています。
等級が1~3級があり、基準を簡単に説明すると、1級の方は他人の介助が無ければ日常生活に支障をきたす状態。2級の方は物事によっては介助が必要で、仕事をして収入を得ることがほぼ不可能な方を指します。
3級は日常生活に問題が無くても、就労に関しては制限がかかる状態です。最後の障害手当金は、傷病が治ったと診断されても、労働に関して制限が加えられる状態になります。
障害年金の適用となる精神疾患は?
- 統合失調症
- 双極性障害
- 認知障害・発達障害
- てんかん など
上記のような精神疾患は障害年金の適用となり、いずれも生活や仕事に大きな影響を与える可能性があります。
障害年金は精神疾患で苦しんでいる方の生活を支える重要な制度です。
障害年金の受給には条件があり、さかのぼって請求する場合、初診日から5年を過ぎると受給ができなくなります。
具体的な条件や手続きについては、厚生労働省や社会保険事務所などの公的機関に相談することが重要です。
不安障害やパーソナリティ障害は対象外
- パーソナリティ障害
- 不安障害
- パニック障害など
精神疾患を患っていても、すべても方が障害年金の対象となるわけではありません。人格障害や神経症は、原則として対象外となります。
対象外とされている疾病は、パーソナリティ障害・パニック障害・PTSD(心的外傷後ストレス障害)・適応障害・摂取障害などです。
例えば、幻覚や幻聴など統合失調症の症状が出ていて、診断書に明記されていればそちらの症状が受理される可能性もあります。
それ以外の症状が出ていないかを確認することが大切になります。また、どんな疾患であっても、一定の基準より重症でなければ、支給の対象とならない可能性もあります。
精神疾患で障害年金を受け取るのに必要な条件は?

公的年金を納めている期間中に発病
まず1つ目は、公的年金を収めている方です。ただし、過去に加入し収めていたとしても条件を満たしていることにはなりません。
公的年金の加入者で、保険料を納めている時期に発病したと診断された方が対象となります。発病してから加入して保険料を納めても条件を満たしたとは認められません。
日本の公的年金は、国民年金・厚生年金・共済年金の3つです。基本的には無職であったとしても、20歳以上であれば国民年金に加入することが義務づけられています。
保険料を2/3以上は納めている
2つ目は、保険料の2/3以上をきっちり収めているかどうかです。公務員や会社員、またはその配偶者は会社側が納付するので問題ありません。
問題は、自営事業者や学生、無職の方が加入する国民年金です。個別に納付するので、自分で責任をもって納付しなくては万が一の際に障害年金の対象外となる可能性があります。
国民保険の保険料は一律で決まっています。収入によって差があるわけではありません。全額納付が苦しい方には免除や納付猶予が認められています。
制度に定められた精神疾患の診断書がある
最後の条件は、診断書の提示です。制度に定められている状態、疾病があるかどうかを、医師が診断し診断書を作成してもらいます。
この診断書をもとに受給事項を満たしているかを判断するので、診断書はとても重要です。診察では軽い症状でも、嘘偽りなくすべてを話すようにしてください。
言葉で伝えることが難しい場合、事前にメモするなど記録して医師に伝えるなどしましょう。
障害年金で受け取ることのできる金額は?

障害基礎年金
障害基礎年金とは、国民年金加入時に発病した際に対象となる年金です。定額制で、基本となる2級、1級は2級の1.25倍が支給される仕組みになります。
また、子供がいる際は子供の人数に合わせた金額が支給されます。子供の定義は、18歳までです。高校を卒業する年齢までを指します。
子供にも障害がある場合には19歳までが対象です。ただし、障害の程度が1級もしくは2級の障害条件に当てはまると判断された方のみが対象となります。
障害厚生年金
報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
(+配偶者がある場合は更に加算額)
2級
報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
(+配偶者がある場合は更に加算額)
3級
報酬比例の年金額
障害手当金(一時金)
報酬比例の年金額×2年分
配偶者の加算額
222,400円
厚生年金対象者の障害厚生年金は、定額ではなく加入の期間や給与額によって支払われる金額が決まります。計算式は表にまとめられている通りです。
3級は年金額が低い場合、満足な障害年金を受け取ることができません。そのため、最低支給額が定められています。
また、どの等級でも保険の加入期間が短いと支給額が少なくなります。そのため、加入期間が300月未満の場合は300月で計算を行う仕組みです。
厚生年金は国民年金に上乗せする仕組みのため、国民年金の障害年金である障害基礎年金も加算されます。
障害年金を申請する際に用意する必要のある書類

診断書
診断書は医師に記載してもらう必要があります。診断書は記入する項目が多いため、早めに主治医に障害年金の受給を希望していることを伝えましょう。
障害年金の申請には、初診日が必要です。初診日を確認した後、年金事務所、市役所、町村役所に相談しましょう。
初診日が国民年金第3号被保険者の期間中であった場合は、市町村ではなく年金事務所に先に先に相談が必要となります。
国民年金第3号被保険者とは、配偶者が厚生年金被保険者である人です。配偶者が厚生年金被保険者である期間は、国民年金の第3号被保険者として保険料を納めます。初診日がこの期間中であった場合は、市町村ではなく年金事務所に相談してください。
病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書は、障害年金の申請に必要な書類です。この書類は、本人または家族が記載します。基本的には、発病から診察日までの経過を記載します。
また、現在の状況や生活で困っていること、就労が困難な理由もまとめておきましょう。診断書と似ていますが、医師が記載する診断書は病状に重きを置いています。
病歴・就労状況等申立書は患者本人が感じている生活の苦しさや困難な状況を伝えることができます。特に医師に話していないことや、発症の原因やきっかけが分かれば詳しく記載してください。
受診状況等証明書(初診日証明)
症状が出て初めて受診した医療機関と、現在通院している医療機関が異なる場合はこの「受診状況証明書」が必要です。
初診日証明ともいわれる書類で、何度も転院している場合は初めて受診した医療機関で記載してもらいます。
ただし、過去にさかのぼって障害年金を請求する場合など、初診時の医療機関の証明を取得するのが難しい場合があります。そのような場合は、請求者の状況に応じて、別途の初診日を証明できる書類を用意することとなります。
精神疾患の障害年金はどこに申請すればいい?

申請窓口:市区町村役場
国民年金(第3号被保険者期間)
申請窓口:社会保険事務所(事務所管轄)
厚生年金
申請窓口:社会保険事務所(所在地管轄)
共済年金等
申請窓口:各共済組合等
障害年金の申請窓口は、初診日に加入していた年金の種類によって4つに分かれています。初診日と現在の年金の種類が異なる方は、窓口を間違えないように注意してください。
各公的年金の申請窓口は表を参考にしてください。公的年金に加入していない20歳以下の方は、市区町村役場に障害基礎年金を請求できます。
障害年金の受給までには審査に3カ月ほど時間がかかります。また、診断書など種類の内容などを照会することもあり、その際はもっと時間が必要です。
そのため、書類に不備がないかなど、しっかりと確認してから申し込みを行ってください。
精神疾患でお悩みなら訪問看護の利用もおすすめ

精神科訪問看護とは?
| サービス名 | 精神科訪問看護 |
|---|---|
| ケア内容 | ・日常生活の維持 ・生活技能の獲得、拡大 |
| 訪問日数 | 原則週3日以内 |
精神科訪問看護とは、精神科の知識を持つ医療従事者が精神疾患をもつ方の自宅に直接訪問して看護を行います。
訪問時に生活状況や症状を確認し、利用者様の主治医や関係機関と連携を取ることで、治療の前進をサポートします。
訪問してご本人様と面会ができない場合でも、ご希望があればご家族様からの相談を受けることも可能であったりと、それぞれの利用者様にあった看護を行います。
精神疾患と診断され、外出が難しい方や精神科への入退院を繰り返している方、ご家族がどのように関わっていけばいいか困っている方は訪問看護を検討してみましょう。
訪問看護を利用するにはどうすればいい?
- 精神科・心療内科(主治医など)
- 自治体の福祉課・ケアマネジャー
- 訪問看護ステーション
訪問看護の窓口は様々です。主治医から直接勧められることもありますし、家庭環境の状況から主治医に相談することもあります。
また、自治体の福祉課やケアマネジャー、訪問看護を行っている施設に直接相談することも可能です。
相談することで使用できる保険の種類や、サポート内容をきちんと確認できます。手続きについては、次の項目で詳しく説明していきます。
利用までの流れは?
精神科訪問看護は精神科や心療内科に通院され精神疾患と診断されている方、診断はなくとも睡眠障害などで医師が訪問看護が必要と判断された人が対象です。
医療保険の場合は、主治医からの指示書を用意してください。各機関に相談した時点で依頼をしておくと、スムーズに手続きを行うことができます。
介護保険は、要介護度判定が必要です。事前に申請し、要介護度が確定してから訪問介護サービスを申請するような流れとなります。
精神科訪問看護ならシンプレ訪問看護ステーションへ!

シンプレ訪問看護ステーションの特徴について
シンプレは、精神疾患に特化した訪問看護サービスを提供しており、自宅で看護を受けることができるので、外出が難しい方でも自宅でリラックスしながら看護を受けることができます。
対象となる精神疾患は、うつ病や統合失調症や各種依存症などです。依存症の場合は、後遺症に悩まれている方のサポートも対応しております。
また、精神疾患の治療には家族の協力が重要になっていきます。医療機関と連携をとりながら、利用者様の治療がよりよい方向に進むようサポートをしたり、ご相談があれば利用者のご家族様のサポートもいたします。
対応している精神疾患を紹介
統合失調症・双極性障害・うつ病など
看護内容
生活支援・自立支援・症状の悪化防止・服薬支援など
当シンプレ訪問看護ステーションが提供するサポートは多岐に渡ります。生活リズムの調整や服薬管理など利用者さまの状態にあわせた支援をおこないます。
シンプレは訪問看護サービスを通して利用者の不安を受け止め、治療への頑張りを一緒に共有し、心から安心できる居場所づくりをお手伝いします。
また、病院、行政、在宅との情報共有を行い、それぞれの専門性を活かしながら治療や社会復帰のサポートができるのも特徴です。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの現在の対応エリアは、上記を中心となっております。
上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合もありますので、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。
子供から大人まで年齢に関わらず利用することが可能です。
年齢に関わらずご利用することが可能です。サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

精神疾患を患っても、生活をしていかなければなりません。日常生活や就労に支障をきたすほどの症状が出ている場合は、障害年金の対象かどうかを確認してみてください。
対象となればまとまったお金が支給され、落ち着いて病気の治癒に努めることができます。審査には時間がかかるので、迅速な申請がおすすめです。
シンプレでは利用者さまへのサポートを通じて社会復帰に向けての一歩をお手伝いします。
訪問看護のサービスについて聞いてみたい、どこに相談をしたらいいかわからなくて困っていた、などございましたらお気軽にシンプレ訪問看護ステーションまでお問い合わせください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



