訪問看護に利用したい医療保険と介護保険の特徴

訪問看護でどのような保険が利用できるかご存じでしょうか?
保険を利用すると利用料金の負担額が軽くなるため、訪問看護を利用するなら確実に適用したいところですよね。
今回は医療保険と介護保険について、自己負担額や申請の流れ・必要なものなどについて解説していきます。
訪問看護に利用する場合の医療保険と介護保険
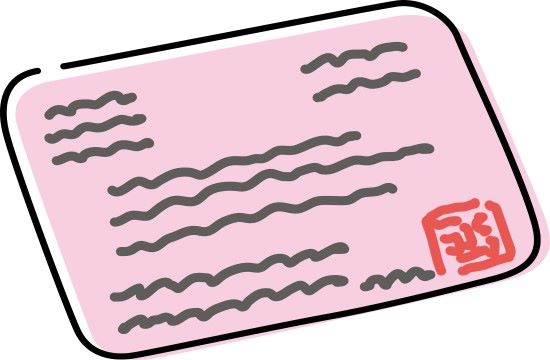
訪問看護に利用する場合の医療保険と介護保険の違い
医療保険と介護保険はどちらも保険ですが、訪問看護で利用する場合、3つの違いがあります。その違いについて一つずつ解説していきます。
違い①対象者
訪問看護で利用する医療保険と介護保険では、対象者の年齢と健康状態によって異なります。
医療保険は、0歳から64歳までのすべての人が対象です。65歳以上でかつ要介護の認定を受けた人は、介護保険の対象となります。
40歳から64歳までの人の場合は、がん末期等の疾病等で、かつ訪問看護が必要と認められた場合は、医療保険の適用となります。
違い②訪問看護の利用上限
訪問看護やデイケアなどの看護・介護サービスは、医療保険と介護保険によって利用できる上限が異なります。
医療保険の場合は、1日1回、週3回以内、1か所の事業所でしか利用できません。
介護保険の場合は、要介護・要支援の状態によって、週4回以上の利用や、2か所以上の事業所の併用が可能になります。
違い③自己負担額
医療保険と介護保険の違いの一つは、利用上限額の有無です。医療保険には利用上限額が設定されていません。一方、介護保険には利用上限額が設定されており、支給限度額を超えると自己負担が発生します。
介護保険の支給限度額は、介護サービスごとに異なり、1か月の利用料が支給限度額を超えた場合、自己負担額が発生します。
2つの保険の特徴
医療保険と介護保険の特徴を具体的に見ていきましょう。医療保険と介護保険では、特徴に違いがあります。
特徴①医療保険
医療保険は、病気やけがをしたときにかかる治療費の一部を助けてくれる制度です。日本では、国民全員が健康保険や国民健康保険などの公的医療保険に加入しています。
70歳以上は原則2割負担、75歳以上は原則1割負担と、年齢を重ねるにつれて負担が軽減されます。
特徴②介護保険
介護保険は、少子高齢化や核家族化などの社会変化により、介護が必要な高齢者を支える家族の負担を軽減するために、2000年に創設された制度です。
40歳から介護保険料の納付が始まり、要介護認定を受けた人は、訪問看護やデイサービスなどの介護サービスを利用できます。
介護保険は、介護サービス費の9割(一定の所得者は8割または7割)を給付し、残りの1~3割は利用者負担となります。施設サービスを利用した場合は、食費および居住費も利用者負担となります。
訪問看護の利用前にしたい!医療保険と介護保険の申請方法とは
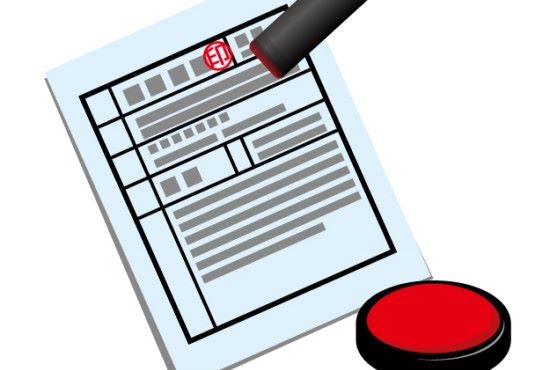
医療保険と介護保険の申請方法
医療保険と介護保険の申請方法について解説していきます。医療保険には種類が複数ありますので、国民健康保険を例に見ていきます。
①医療保険
国民健康保険は、市町村や国民健康保険組合が運営する医療保険です。申請できる方は、住民登録をしている市町村に居住している方です。
申請は、基本的に市役所で行います。転入や会社の健康保険を脱退した時、出産した時、生活保護を受けなくなたときなどによって、必要な書類が異なります。
国民健康保険は世帯主が届け出る義務がありますが、同一世帯の方も届け出できます。役所に行けない場合は、特別出張所などで手続きできます。
②介護保険
介護保険の運営は市区町村が行っています。申請は、お住まいの自治体の介護保険課、高齢者支援課などで受け付けています。
65歳以上の方は、被保険者証が郵送で交付されます。40歳から64歳までの方は、通常は発行されません。ただし、特定疾病に該当する場合には、介護認定を受けた後、被保険者証が発行されます。
介護被保険者証が発行されても、要介護認定を受けていないと、介護保険サービスを利用できないので注意しましょう。
注意!2種類の保険の併用は出来ない
訪問看護などのサービスを利用するには、医療保険または介護保険が必要です。
ただし、医療保険と介護保険の併用はできません。すでに医療保険と介護保険の2種類を取得している場合は、介護保険が優先されます。
どちらの保険を利用するかは、制度として定められており、利用者が決めることはできないため、自分や家族が取得している保険を事前に確認しておくことが大切です。
介護保険の申請に必要!要介護認定を取得するには

要介護認定が認められるまでの流れ
- 必要書類の準備と申請
- 認定調査・主治医意見書の依頼
- 審査判定
- 認定
要介護認定を受けるには、必要書類の提出のほかに、認定調査や主治医意見書の依頼などが必要です。それぞれの流れを具体的に解説していきます。
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証
- マイナンバー書類
- 申請者の身分証明書
- 主治医の情報証明書類
- 代理権が確認できるもの
- 印鑑
- 代理人身元証明書類
①要介護認定の必要書類の準備・申請
65歳以上の申請者の場合は、介護保険被保険者証が、40歳から64歳までの申請者の場合は、医療保険者証の提示が求められます。
そのほかに「要介護・要支援認定申請書」、「マイナンバーが確認できるもの」、「申請者の身元が確認できるもの」、「主治医の情報が確認できるもの(診察券など)」が必要です。
もし入院中の場合は、家族居宅介護支援事業者などの代理人を通じて行うことも可能です。
②認定調査・主治医意見書の依頼
要介護認定を申請すると、市区町村の担当者が、自宅や施設、病院を訪れて、本人や家族から生活状況や健康状態について聞き取りを行います。また、申請書に指定した医師から、要介護認定に必要な「主治医意見書」を提出してもらいます。
「主治医意見書」は、申請するタイミングか、それより少し前にかかりつけ医に相談しておくと、スムーズに申請を進めることができます。
③審査判定
聞き取り調査の結果や主治医意見書の一部の項目は、コンピューターに入力し、全国一律の方法で要介護度の判定が行われます。
これを「一次判定」といい、その結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます(二次判定)。
申請から認定結果が出るまでの期間は30日以内とされていますが、制度上は申請した時点から介護サービスの利用が可能です。
④認定
要介護認定調査員が聞いた内容や、医師の意見書の一部をコンピューターに入力し、全国一律の方法で要介護度を判定します。これを「一次判定」といいます。
一次判定の結果と医師の意見書を基に、介護認定審査会が要介護度を判定します。これを「二次判定」といいます。
申請から認定結果が出るまでの期間は原則30日以内ですが、申請した時点から介護サービスを利用できます。
要介護認定の有効期間に注意を!
要介護認定には、原則として6か月または12か月の有効期間があります。有効期限が切れると、介護保険の給付を受けられなくなるため、注意が必要です。
有効期間は、要介護認定を受ける際の状況や、その後の状態変化によって異なり、新規申請の場合は6か月、更新申請の場合は12か月です。
有効期間が切れると、介護保険が使えなくなります。そのため、引き続き介護サービスを利用される場合は、有効期間が終わる60日前から終わる日までの間に、更新申請をする必要があります。
精神科の訪問看護なら当ステーションにお任せください!

シンプレ訪問看護ステーションについて
シンプレ訪問看護ステーションは、精神疾患に特化した訪問看護を行っており、医療保険の中でも自立支援の制度を利用しています。
専門知識や経験が豊富な、精神疾患に対する看護を行いたいという気持ちの強いがスタッフが集まっており、患者さんが持つ病気とどう向き合っていくかを一緒に考え、自立した生活を営めるようにご支援いたします。
主治医や各種関係機関との連携を取りながら、精神疾患に悩む方だけでなく、ご相談があればご家族様のサポートもお受けしています。
精神科訪問看護を扱っています
| サービス名 | 精神科訪問看護 |
|---|---|
| 職種 | ・看護師 ・准看護師 ・作業療法士 |
| 訪問日数 | ・原則週3日以内 |
シンプレが扱っている「精神科訪問看護」とは、精神に障害や疾患を持ちながら、医療機関で治療をしている方の自宅へ訪問し、治療や生活を支援するサービスです。
看護師や作業療法士、精神保健福祉士が訪問し、看護および社会復帰指導など、ご利用者様に寄り添い、目標に向かい支援を行います。
精神症状で悩まれている方に対して、生活が少しでも安心したものになるようにお手伝いします。
精神科訪問看護の料金
| 負担割合 | 月の初回訪問 | 2回目以降 |
|---|---|---|
1割負担 | 1,299円/回 | 855円/回 |
2割負担 | 2,598円/回 | 1,710円/回 |
3割負担 | 3,897円/回 | 2,565円/回 |
上記は週3回までの訪問料金となります。週4回以上訪問となる場合には料金が異なります。
精神科訪問看護では、医療保険を利用することにより自己負担を軽減できるメリットがあります。
30分を一区切りに利用可能。かかった費用については、年齢や所得によって変わり、医療費の1〜3割が自己負担となります。
また早朝や深夜などの時間外に依頼する場合や、長時間の訪問を行う場合は別途料金が発生します。
また自立支援医療制度いう制度を利用すると料金が1割負担になるほか、所得に応じて自己負担が0円になる場合もございます。
自立支援医療(精神通院医療)
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 生活保護 |
0円 |
| 低所得1 |
2,500円 |
| 低所得2 |
5,000円 |
| 中間所得1 |
5,000円 |
| 中間所得2 |
10,000円 |
| 一定所得以上 |
20,000円 |
表の料金は所得に応じた医療費の月額自己負担額の上限額となっております。
表の料金を超えた場合には、自己負担なしで医療が受けられます。
精神科訪問看護では、自立支援医療制度(精神通院)という助成制度を利用できます。
自立支援制度は、障害のある方の自立を助けるための公費負担医療費制度です。精神に障害のある方の、障害の軽減などのために医療の自己負担費が補助されます。
助成の内容としては精神科にかかわる医療費が1割負担になることと、所得に応じて月の自己負担上限額が設定され上限額を超えた分に関しては自己負担がなしとなります。
通院費やお薬にかかる費用も、自立支援医療の対象になります。そのうえで、精神科デイケアや精神科訪問看護を利用した場合に、その費用が補助されます。
シンプレの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの訪問エリアは、上記中心に行っています。
上記のエリア以外での利用を希望される方も、対応が可能な場合がありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
また、医療保険と介護保険の両方を有している場合の相談や、サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っています。
TwitterやLine、TikTokなどのSNSでも情報を発信していますので、あわせてぜひご覧ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ
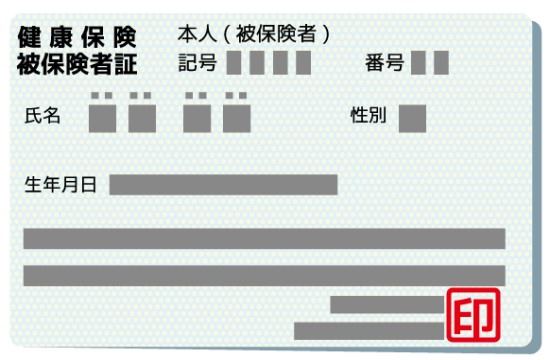
訪問看護やデイケアなどの介護・看護サービスを利用するには、保険が必要です。
医療保険と介護保険では対象者や利用上限、自己負担額が異なるため、事前に確認しておきましょう。
シンプレは、精神疾患に特化した訪問看護サービスを提供しており、自宅で看護を受けることができるので、外出が難しい方でも自宅でリラックスしながら生活を送れるようにするためのサポートします。
精神科訪問看護サービスを受けるのが初めての方でも、ご不安やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



