チェックしてわかるアルコール依存症の重症度
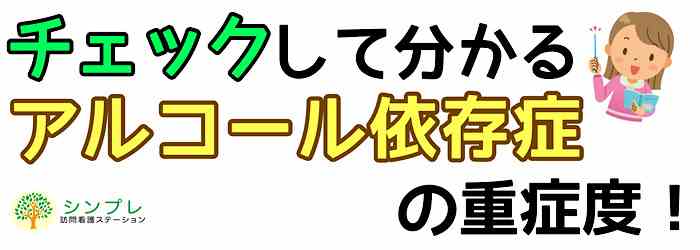
飲酒をされる方の中には、自分がアルコール依存症ではないかチェックしたい方も多いのではないでしょうか?
アルコール依存症になる原因はさまざまなのですが、一度陥ると自分では抜け出せなくて悩んでいる人も少なくありません。
この記事では、アルコール依存症の症状についても触れているので、自身が該当しているかどうか確認してみましょう。
アルコール依存症のチェック項目

チェック項目リスト
- どのくらいの頻度で飲みますか?
- 1日平均でどのくらいの量を飲みますか?
- 6ドリンク以上飲酒するのはどのくらいの頻度でありますか?
- 飲み始めると止められない頻度はどれくらい?
- 飲酒後にあなたが行うはずだったことができなかった回数
- 飲み過ぎた翌朝、飲酒しないと動けない頻度はどのくらい
- 飲酒後に後悔する頻度はどのくらい?
- 飲酒のため前夜の出来事を思い出せなかった頻度は?
- 飲酒であなた自身か他の誰かがケガをした頻度は?
- 飲酒を控えるように注意されたことがある
上記はAUDITといい、WHO(世界保健機関)が開発したアルコール依存症のスクリーニングテストです。
このテストは、あなたの飲酒習慣に問題ないか、アルコール依存症の予備軍にないかを早期に発見するために役立ちます。
テストには10個の質問があり、各質問に当てはまるものを選んでください。
1問あたり2点として、合計点数を計算します。結果は以下で解説していきます。
点数ごとの結果
非飲酒者群
1〜9点
危険性の低い飲酒者群
10〜19点
危険性の高い飲酒者群
20点
アルコール依存症群の危険性あり
15点以上の方はアルコール依存症を疑いがあるレベルです。現在の飲酒習慣を見直したり、必要に応じて専門機関に相談する必要があるでしょう。
8点〜14点の方も要注意です。すでに周囲からアルコールの量を控えるように忠告されていたり、将来的に飲酒での問題が起こる可能性があります。
1〜7点の方はお酒を嗜む程度に済ませたり、適量を飲んでいてそれほど問題ない場合が多いですが、徐々に飲酒量が増えないように意識しましょう。
アルコール依存症とは?患者数は?

アルコール依存症とは
アルコール依存症とは、お酒を飲む量や飲むタイミングを自分でコントロールできなくなった状態のことで、誰でもなる可能性がある病気です。
アルコールに対する耐性が徐々に形成され、以前と同じ飲酒量では酔わなくなるなど、最終的にアルコール依存症になるケースが報告されています。
自己コントロールができなくなりトラブルなどに発展するケースも多く、重症化すると家族関係や仕事など社会生活が困難になります。
また、アルコール依存症はさまざまな身体障害やうつ病などの精神障害を合併しやすいため、できるだけ症状の軽いうちに医療機関を受診し回復を目指すことが大切です。
アルコール依存症の患者数
約100万人以上
アルコール依存症の専門治療を受けている方
約5万人
アルコール依存症の予備軍
1000万人を超える
アルコールは、私たちの生活に豊かさや楽しみを与えてくれますが、飲みすぎると健康障害の原因になり、本人だけでなく家族や社会にも問題を起こす可能性があります。
日本には約100万人以上のアルコール依存症患者がいると推定されています。
しかし、そのうちアルコール依存症の専門治療を受けている方は、わずか5%と言われています。
また、アルコールが原因になり、精神や身体的に問題や障害を引き起こす可能性のある方や、すでに引き起こしている方は1000万人を越えるとも言われています。
アルコール依存症の症状
アルコール依存症の症状にはどのようなものがあるのでしょうか?アルコール依存症の症状をご紹介します。
渇望と飲酒行動
「お酒なしではいられない」「飲み始めると止められない」このような強い飲酒欲求を「飲酒渇望」と呼びます。
アルコール依存症になるとこの強い渇望にさいなまれ、飲酒にばかり気を取られて他のことに関心がいかなくなります。
お酒を飲む量や飲む頻度が増え、「お酒をやめなければいけない」と理解しているのにやめることができません。
これまでの飲酒量では満足できず、ついつい飲み過ぎてしまう状態が続き、どんどん症状は悪化してしまいます。
離脱症状
離脱症状とは、飲酒をやめた際に生じる様々な身体的・精神的症状のことで、飲酒をやめると発汗や震え、不安、イライラといった離脱症状が出てくるようになります。
中枢神経がアルコールに依存しているためにこのような症状が出るのですが、離脱症状は日常生活にも支障をきたすようになります。
飲酒をやめると離脱症状が出てくるようになるので結果的にお酒を飲まずにいられない、というケースが多いです。
症状は軽いものから重いものまでさまざまで、重症になると禁酒1日以内に離脱けいれん発作が起こることもあります。
否認と自己中心性
否認とは、自分の問題をまったく認めないか、または過小評価することです。
自分の飲酒量や飲酒の影響を認めようとせず嘘をつく、ふてくされるなどといった行動をとります。
自己中心性とは、物事を自分に都合のよいように解釈し、他の人に配慮しないことです。
自分の飲酒を正当化したり、周囲の人を責めるなどといった行動をとります。
アルコール依存症の治療法
精神・身体合併症と離脱症状の治療を行う
リハビリ治療
精神・身体症状の回復後に断酒に向けての治療を行う
治療法としては「断酒」が原則ですが、いきなり飲酒をやめるのではなく「減酒」を目標とすることもあります。
まずは精神・身体合併症と離脱症状の治療を行い、精神・身体症状が回復してきたらリハビリ治療として断酒に向けての本格的な治療を開始します。
解毒治療(体内からアルコールを抜く治療)も重要ですが、お酒のない生活を維持していくことも非常に重要です。
そのため、カウンセリングや集団精神療法などで断酒を決意させ、断酒継続のための治療を続けていきます。
アルコール依存症の経過・治療に関する転帰

アルコール依存症の経過
常習的な飲酒や飲酒機会が増え、次第に飲酒の制御が困難になる病気がアルコール依存症です。アルコール依存症の経過は男性と女性とで異なるとされています。
女性の体は、アルコールを分解する能力が男性よりも低いため、同じ量のアルコールを飲んでも、血中アルコール濃度が高くなります。
これは、女性の体脂肪率が男性よりも高いこと、肝臓のサイズが小さいことなどが原因です。
依存症になると男女に関わらず飲酒が生活の中心になってしまう人が多いですが、長期にわたり断酒したり飲酒量をコントロールすることは困難であるとされています。
アルコール依存症の治療後の転帰
28~32%
5年前後
22~23%
8~10年
19~30%
一度アルコール依存症になると長期にわたり断酒や減酒を継続するのは難しく、専門家などのサポートが必要になります。
アルコール依存症を治療して、行きつくところはどこなのか?治療後の年数と断酒率のデータは上記のとおりです。
もともと治療前の飲酒量が少ない、配偶者がいる、仕事をしているなど、社会的なつながりあることの関係が多い傾向にあり、アフターケアの必要性も重視されています。
治療に精神科訪問看護を活用する選択肢も
精神科訪問看護とは?
・精神科・心療内科に通院中の方
・精神疾患の診断を受けた方
・診断がなくとも医師が必要と判断した方
訪問する人
・看護の専門職
・リハビリテーションの専門職
訪問時間
・医療保険
(30分から90分程度)
精神科訪問看護は精神科や心療内科に通院され精神疾患と診断されている方、診断はなくとも睡眠障害などで医師が訪問看護が必要と判断された人が対象です。
看護師や作業療法士などの医療スタッフが医師の指示のもと自宅へ訪問し、病状観察や日常生活指導、また家族支援などのサポートを行います。
通常、訪問は医療保険を利用し週3回まで可能で、1回の訪問は30分から90分と決められています。体調や病状に合わせて訪問回数や時間を調整します。
外出が難しい方や精神科への入退院を繰り返している方、ご家族がどのように関わっていけばいいか困っている方は訪問看護を検討してみましょう。
精神科訪問看護ってどんなことをしてくれるの?
・自立した生活を営めるための支援
・規則正しい生活リズムへの調整
症状の悪化防止・服薬支援
・病状や普段の様子を観察
・服薬の管理や受診の支援
社会復帰へのサポート
・主治医や関係機関と連携
・社会復帰を支援
家族の方への支援
・家族へ接し方のアドバイスや相談支援
・社会資源の活用などを支援
精神科訪問看護では、「健康状態の観察」「服薬の管理」「社会復帰の支援」など、症状の改善に向けてさまざまなポートを受けることができます。
訪問してご本人様と面会ができない場合でも、ご希望があればご家族様からの相談を受けることも可能であったりと、それぞれの利用者様にあった看護を行います。
また住み慣れた自宅で療養できるので、安心感が得られることや訪問看護の職員が定期的に自宅に訪問することによって孤立や孤独感が軽減され、心の支えを得られるというメリットもあります。
そのほかにも必要に応じて、医師や保健師、ケースワーカーなどの関係機関と連携し、病状の悪化の防止や早期回復につながるようサポートを行います。
シンプレ訪問看護ステーションにお任せください!

シンプレ訪問看護ステーションって?
シンプレは精神疾患に特化した訪問看護ステーションで、アルコール依存症や、うつ病、摂食障害など、幅広い疾患を対象としています。
患者さんが病気と付き合いながら自分らしい生活ができるように、自主性を尊重した看護サービスを提供しています。
また、病院、行政、在宅との情報共有を行い、それぞれの専門性を活かしながら治療や社会復帰のサポートができるのも特徴です。
シンプレは訪問看護サービスを通して利用者の不安を受け止め、治療への頑張りを一緒に共有し、心から安心できる居場所づくりをお手伝いします。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションでは、上記エリアを中心に対応しています。
上記以外にお住いの方でもサービスのご利用が可能な場合もありますので、アルコール依存症でお困りであればお気軽にお問い合わせください。
こころの健康問題を抱えて悩んでいる方やそのご家族様への継続的なサポートを通じて解決への一歩をお手伝いします。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

アルコール依存症のは重症化すると仕事や社会生活が困難になるため、できるだけ症状の軽いうちに医療機関を受診し回復を目指すことが大切です。
アルコール依存症は一人で治すことは難しいので、精神科訪問看護という選択肢も含め専門機関に早めに相談しましょう。
シンプレ訪問看護ステーショは、精神疾患に特化した訪問看護サービスを提供しており、アルコール依存の方の訪問看護も行っております。
現在アルコール依存症で悩んでいる方や、そういった方がご家族におられる場合は是非一度わたしたちにご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



