アルコール依存症と患者数をチェック
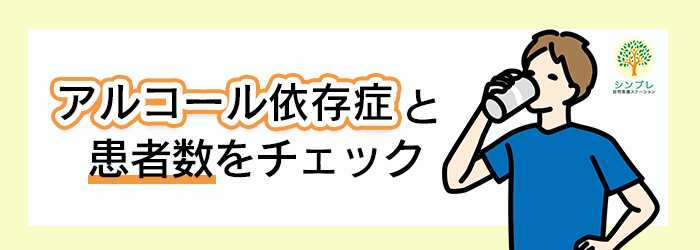
アルコール依存症の患者数がどれくらいいるのか知っていますか?
アルコール依存症の症状が重くなると、仕事はもちろん日常生活にまで影響が出ることも少なくありません。
また、一人で治すのが難しい精神疾患でもあるので、アルコール依存症の正しい知識を身につけて深みにハマらないように普段から気をつけることが大切です。
その第一歩として、まずはアルコール依存症の患者数から知識を深めていきましょう!
アルコール依存症の患者数は?

日本にはアルコール依存症の患者数はどれくらいいるのでしょうか?詳しい患者数と、大量飲酒者の患者数も観ていきましょう。
アルコール依存症の患者数
約9万5千人
入院患者
約入院2万5千人
潜在的な依存症者
約57万人
日本国内のアルコール依存症患者は、2022年時点で約100万人と推定されています。このうち、外来患者は約9万5千人、入院患者は約2万5千人と言われています。
アルコール依存症は、飲酒をコントロールできなくなり、日常生活に支障をきたす状態です。重度のアルコール依存症になると、肝臓病や脳神経障害などの健康被害を引き起こす可能性があります。
潜在的な依存症者も多数存在しており、アルコール依存症の診断基準を満たすものの、自覚がないか、治療を受けていない人々のことです。
アルコール依存症以外の患者数は?
14.2万人
統合失調症
約80万人
うつ病・統合失調症
約112万人
アルコール依存症以外の患者数は、ギャンブル依存症が14.2万人、統合失調症が約80万人、うつ病・統合失調症が約112万人と言われています。
ギャンブル依存症は、近年増加傾向にあり、特に若者の患者数が増えています。統合失調症は、生涯にわたって発症する可能性のある病気です。うつ病は、誰でも発症する可能性があります。
これらの疾患にかかるリスクを減らすために、早期発見・早期治療の重要性がますます高まっています。
アルコール依存症とは?

大量のお酒を長期にわたって飲み続けることで、お酒がないといられなくなる状態が、「アルコール依存症」です。
その影響が精神面にも、身体面にも表れ、仕事ができなくなるなど生活面にも支障が出てきます。
飲み過ぎが習慣化してからアルコール依存症になるまでの期間は、男性で20年程度、女性はその半分の期間といわれています。
早い人で1年程度の短い飲酒期間でアルコール依存症になってしまいます。
飲み過ぎが習慣化している人の中には、飲み始めたら辞められなくなるといった状態に陥る人もいるのです。
アルコール依存症の症状

アルコール依存症になると、精神的・身体的症状が表れてきます。具体的な症状の特徴を見ていきましょう。
アルコールを飲まないと落ち着かない
アルコール依存症になると、アルコールに対して精神的な依存が現れます。強い飲酒欲求とそれに基づくコントロールの効かない飲酒で特徴づけられます。
お酒を飲むべきではない時にも飲みたいと強く思ったり、飲み始めるとついつい多興飲んでしまうのも症状の一つです。
そしてだんだん手元にお酒がないと落ち着かなくなったり、ひどい人だと数時間ごとに飲酒する「連続飲酒」をしてしまう人もいます。
手のふるえや多量の発汗など禁断症状が出る
アルコール依存症になると、アルコールが体から抜ける際に、手の震えや発汗、吐き気などの禁断症状が現れます。
これらの症状を抑えるために、また飲んでしまうことで、悪循環に陥ります。
アルコール依存症の禁断症状は、アルコールが体内に入った際に、脳がアルコールの存在を認識し、それが正常な状態だと認識するように変化するため起こります。
アルコールが抜けると、脳はアルコールが不足している状態だと判断し、禁断症状が現れるのです。
禁断症状は、アルコール依存症の特徴的な症状であり、また命に関わることもあるため、注意が必要です。
アルコール依存症の治療法

・合併症の治療
・離脱症状の治療
リハビリ治療
・通院
・抗酒薬の服用
・自助グループへ参加
退院後
・アフターケアの三本柱の継続
アルコール依存症の治療は、入院治療が主体です。入院治療は、3つの段階に分かれています。
1つ目の解毒治療では、アルコールが体から抜ける際に起こる禁断症状を抑え、身体の回復を促します。具体的には、抗不安薬や睡眠薬などの薬物療法などです。
2つ目のリハビリ治療では、個人精神療法や集団精神療法、家族療法などが行われ、本人に飲酒問題の現実を認識させ、断酒の決断へと導きます。
3つ目の退院後のアフターケアでは、退院後も断酒を継続できるようにサポートします。具体的には、病院やクリニックへの通院、抗酒薬の服用、自助グループへの参加などです。
アルコール依存症のチェックリスト

- どのくらいの頻度で飲みますか?
- 1日平均でどのくらいの量を飲みますか?
- 6ドリンク以上飲酒するのはどのくらいの頻度でありますか?
- 飲み始めると止められない頻度はどれくらい?
- 飲酒後にあなたが行うはずだったことができなかった回数
- 飲み過ぎた翌朝、飲酒しないと動けない頻度はどのくらい
- 飲酒後に後悔する頻度はどのくらい?
- 飲酒のため前夜の出来事を思い出せなかった頻度は?
- 飲酒であなた自身か他の誰かがケガをした頻度は?
- 飲酒を控えるように注意されたことがある
アルコール依存症チェック項目リストとは、アルコール依存症の疑いがあるかどうかをセルフチェックするためのリストです。
このリストは、世界保健機関(WHO)が作成した「AUDIT」がベースになっています。AUDITは、10個の質問に答えることで、アルコール依存症のリスクを判定できるテストです。
アルコール依存症チェック項目リストは、アルコール依存症の早期発見に役立つツールです。
もし、自分にアルコール依存症の疑いがある場合は、このリストを使ってセルフチェックを行い、必要に応じて医療機関を受診しましょう。
点数ごとの結果
15点以上の場合、アルコール依存症の疑いがあります。飲酒をコントロールできなくなり、日常生活に支障をきたしている可能性があります。
現在の飲酒習慣を見直したり、必要に応じて専門機関に相談しましょう。
8点〜14点の場合、要注意です。すでに周囲からアルコールの量を控えるように忠告されていたり、将来的に飲酒での問題が起こる可能性があります。
飲酒量を減らす努力をしたり、専門機関に相談することも検討しましょう。
1点〜7点の場合、問題は少ないと考えられます。しかし、徐々に飲酒量が増えないように意識しましょう。
アルコール依存症の相談窓口について

アルコール依存症で悩んでいる方やその家族の方は、以下の相談場所へ相談するようにしましょう。
保健所・保健センター
・保健所
・保健センター
相談方法
・電話
・面談法
相談相手
・保健師
・医師
・精神保健福祉士
保健所や保健センターは、地域の住民の健康や福祉を守る役割を担っています。
そのため、アルコール依存症の相談にも対応しており、専門の相談員が、本人や家族からの相談に応じています。
アルコール依存症は、本人や家族のみならず、周囲の人々にも大きな影響を与える問題です。
もし、アルコール依存症の疑いがある場合は、まずは保健所や保健センターの相談窓口に相談してみてください。
精神保健福祉センター
精神保健福祉センター
相談方法
・電話
・面談法
相談相手
・医師
・看護師
・保健師
・精神保健福祉士
・臨床心理技術者
・作業療法士
精神保健福祉センターは、各都道府県・政令指定都市ごとに1か所ずつあり、精神保健福祉に関する相談や支援を行う機関です。
精神保健福祉センターでは、アルコール依存症の家族の相談にも対応しており、電話や面接により相談を受け付けています。
相談内容は、アルコール依存症の本人への対応や、家族自身の心身の健康など、多岐にわたります。
相談窓口では、専門職が対応し、一人ひとりの状況に応じたアドバイスや支援を行っています。
精神科訪問看護
精神科訪問看護
相談方法
・電話
・面談法
相談相手
訪問看護師
精神科訪問看護は、アルコール依存症などの精神疾患や障害を抱える方が、安心して地域で生活できるよう、自宅や入所施設に訪問して支援するサービスです。
看護師や作業療法士などの有資格者が、バイタルサインの測定や服薬管理などの看護業務を行うほか、生活援助や相談支援などのサポートを行います。
医療機関や保健所などの他機関と連携することで、利用者の状況に応じた支援を継続的に行うことができます。
アルコール依存症で悩んでいるならシンプレ訪問看護ステーションにお任せください!

精神科訪問看護の利用を検討しているなら、当シンプレ訪問看護ステーションへご相談ください。
シンプレ訪問看護ステーションって?
自分らしく自立した生活を
営めるためのサポート
症状の悪化防止・服薬支援
生活状況を観察しながら
受診や服薬を支援
社会復帰へのサポート
主治医や関係機関と連携を
取りながら社会復帰を支援
家族の方への支援
・家族へのアドバイスや相談
・社会資源の活用などをサポート
シンプレは、精神科に特化した訪問看護サービスを提供しており、アルコール依存症や統合失調症、様々な精神疾患を抱える方の自立した生活を支援しています。
また、主治医や関係機関と連携を取り、利用者の状況に応じた支援を継続的に行うことで、治療をサポートします。
アルコール依存症の方は、飲酒をコントロールできなくなり、日常生活や仕事に支障をきたすことがあります。
シンプレでは、アルコール依存症との付き合い方を一緒に考え、利用者が自分らしく自立した生活を営めるようにサポートを行います。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
現在の対応エリアは、上記を中心となっております。子供から大人まで年齢に関わらず利用することが可能です。
上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。
こころの健康問題をひとりで抱えて悩むのではなく、相談することが大切です。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

アルコール依存症の患者数は、近年増加傾向にあり、特に女性や高齢者の患者数が増えています。
アルコール依存症かどうかをチェックするには、WHOのアルコール依存症チェックリストが便利です。
シンプレ訪問看護ステーションは、精神疾患に特化した訪問看護サービスを提供しており、アルコール依存症の訪問看護も行っています。
アルコール依存症の方の生活を支援し、自立した生活を営めるようにサポートしています。
現在アルコール依存症で悩んでいる方や、そういった方がご家族におられる場合は、ぜひ一度シンプレにご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



