病院でおこなうアルコール依存症の治療法をチェック
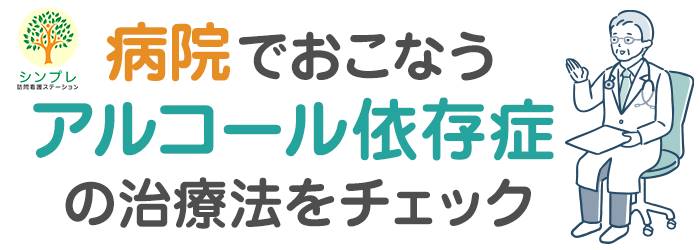
アルコール依存症の治療をするにはどの病院へ行けばいいのか情報をお探しですか?アルコール依存症は飲酒習慣のある方なら誰もがかかる恐れのある病気です。
本人の意思の弱さや性格的な問題だと誤解されがちですが、克服するためには病院で治療を受ける必要があります。
今回は、アルコール依存症の治療をするにはどの病院へ行けばいいのか?どのような治療をするのかについて見ていきましょう。
アルコール依存症でお悩みの方は、ぜひこの記事を最後まで読んでみてくださいね。
アルコール依存症の治療ができる病院は何科?

精神科
まず1つ目が「精神科」です。アルコールを飲んでいないとイライラしてしまう、気分の浮き沈みが激しいなどの症状が現れた場合は、精神科に相談するようにしましょう。
精神科では、アルコール依存症の原因や症状を理解し、適切な治療を行います。
アルコール依存症は、うつ病を併発することが多い傾向にあります。精神科では、アルコール依存症とうつ病の両方を治療することができます。
アルコール依存症は、一人で克服することが難しい病気です。精神科の専門家に相談することで、適切な治療を受けることができます。
心療内科
心療内科は、心の問題が身体に影響を及ぼした場合に受診する診療科です。
心の健康に関連する症状が、体の不調として現れることがあります。例えば、過度のストレスによって引き起こされる頭痛、吐き気、胃痛などです。
アルコール依存症の身体の症状がはっきりとある場合には心療内科に相談すると良いでしょう。
内科
アルコール依存症は、糖尿病など他の疾患へのリスクが高まる病気の為、症状によっては、内科を治療の入り口にされる方もおられるかもしれません。
可能ならば通常の内科よりも、アルコール依存症に特化した医療機関を受診するようにしましょう。そうした医療機関にはアルコール依存症外来があります。
アルコール依存症外来では、体からアルコールを排出するための治療からリハビリまで、一貫した治療を行うことができます。
個別に合わせた治療プランを立てるなど専門知識と経験を持ったスタッフがサポートし、治療を進めることができます。
アルコール依存症の診断基準は?

- 強迫的飲酒欲求
- コントロール障害
- 離脱症状
- 耐性
- 飲酒中心の生活
- 有害な結果が起きてもやめられない
アルコール依存症の判断基準は、WHOの診断ガイドラインで定められています。現在の判断基準ではリストの6つの項目の内、3つに当てはまればアルコール依存症です。
2022年からの判断基準では、診断項目が1.コントロール障害、2.飲酒中心の生活、3.生理学的特性に簡略化されます。
3つ目の生理学的特性とは、離脱症状や耐性の有無についてです。この3つの内の2つが当てはまればアルコール依存症と診断されます。
比較的わかりやすい判断基準ではありますが、自己判断はせずに専門医の指示に従ってください。アルコール依存症は、適切な治療で症状を緩和することができます。
アルコール依存症を治療するには?

断酒治療
| 治療期 | 目的 | 内容 |
|---|---|---|
解毒期
|
身体・ 精神症状 の治療 |
・離脱症状の 治療 ・併存疾患の 治療 |
| リハビリ テーション期 
|
社会生活に戻る 訓練 |
・精神療法 ・集団生活 |
| アフター ケア 
|
・状態の維持 ・再発防止 |
・医療機関への通院 ・自助グループへの参加 |
断酒治療は3つの段階を経て行われます。1つ目が「解毒期」で、アルコールの離脱症状や併発している病気の治療を行う期間です。
2つ目が「リハビリテーション期」、この期間は社会復帰へ向けて訓練を行います。行われる精神療法は、集団精神療法・個人精神療法・認知精神療法などです。
アルコール依存症はリハビリがある程度進み、社会復帰を果たした後のアフターケアも重要になります。できれば自助グループなどに参加して、仲間と共に治療を続けるようにしましょう。
減酒治療
| 治療期 | 目的 | 内容 |
|---|---|---|
導入期
|
疾患理解 | ・疾患を理解 ・離脱症状 ・併存疾患の確認 |
治療開始時
|
治療継続 | ・飲酒量の設定 ・併存疾患や・社会 家庭生活問題の 経過確認 |
維持管理期
|
・状態維持 ・再発防止 |
・飲酒量目標の見直し ・併存疾患や 社会や家庭生活問題 の経過確認 ・医療機関への通院 |
最近では、急に飲酒をやめることは難しいかもしれませんが、減酒を試みること、あるいは断酒を目指す前段階として飲酒量を減らす減酒治療があります。
アルコール依存症の治療として最終的な目標は断酒ですが、途中目標として減酒を掲げることで緩やかに治療を進めていくことができるでしょう。
アルコール依存症を病気として理解することから治療は始まります。本格的な治療開始後も通院で治療は進むので、家庭の事情などで入院が難しい方にもおすすめです。
アルコール依存症の相談先

心の健康、保健、医療、福祉に関する相談
精神保健福祉センター
こころの健康についての相談
アルコール依存症は身近な病気のため、相談窓口は多数存在します。
自分や家族がアルコール依存症だと感じる方や精神科に相談することに抵抗があるという方は、まずは相談から始めてみてはいかがでしょうか。
特に保健所や精神保健福祉センターなどは、アルコール依存症のみならずさまざまな症状に対して相談することができます。専門の医療機関や自助グループの情報を得ることも可能です。
初期の段階で早めに相談し、適切な治療が受けられるようにサポートを得ることが重要です。
アルコール依存症の自助グループ

自助グループとは?
自助グループとは、同じ障害や疾病を抱えている仲間が集まり励ましあいながら障害を克服していくグループのことを言います。
下記で説明する断酒会やAAは大きな自助グループです。2つ以外にも、各地域で地域に根差した活動を行うグループも存在します。
同じ悩みがある仲間との出会いは、よりアルコール依存症からの回復に大きく影響します。自助グループは全国各地にあるので、各種専門機関に相談してみてください。
断酒会
断酒会は、日本で発症したアルコール依存症に対する自助グループです。アルコホーリクス・アノニマスを参考に1950年代に発足しています。
家族のみで例会を行う断酒例会の会場もあります。また、会員制をとっていることも特色のひとつです。
断酒会は、アルコール依存症の患者やその家族が回復を目指すための場所です。断酒会について詳しく知りたい方は、各地の断酒会のホームページをご覧ください。
アルコホーリクス・アノニマス(AA)
各種自助グループの原型とされているのが、1930年代にアメリカで発足したアルコホーリクス・アノニマス(以下AA)です。日本には1970年代に導入されています。
正式な統計が無いので所属人数やグループ数は不明ですが、都市部を中心に参加者が増えているグループです。
AAは、飲酒を止めたいという気持ちがあればメンバーになれます。また、会費や料金を払う必要がありません。メンバーの寄付で長年独立性を守ってきたグループです。
そのため、大きなグループではありますが各種団体や宗教、政党に関係はありません。
精神科訪問看護を利用するという選択肢も

精神科訪問看護とは?
| サービス名 | 精神科訪問看護
|
|---|---|
| ケア内容 | ・日常生活の維持 ・生活技能の獲得 ・生活技能の拡大など |
| 訪問日数 | 原則週3日以内 |
訪問看護とは、自宅で療養中の病気や障害を抱えている方に看護を行うサービスです。
精神科訪問看護は、訪問看護の中でも精神疾患に特化したサポートを行います。
通常、訪問は医療保険を利用し週3回まで可能で、1回の訪問は30分から90分と決められています。体調や病状に合わせて訪問回数や時間を調整します。
外出が難しい方や精神科への入退院を繰り返している方、ご家族がどのように関わっていけばいいか困っている方は訪問看護を検討してみましょう。
アルコール依存症に対する看護内容
アルコール依存症患者に対する看護は、治療の環境を整えることから始まります。
アルコール依存症のご本人やご家族へ依存症に対しての正しい知識の断酒のメリットやデメリットを説明することで、断酒の決断を支援します。
訪問し、「服薬の管理」「健康状態の観察」「病状悪化の防止・回復」「社会復帰の支援」など、症状の改善に向けてさまざまなサポートを受けることができます。
必要に応じて、医師や保健師、ケースワーカーなどの関係機関と連携し、病状の悪化の防止や早期回復につながるようサポートを行います。
精神科訪問看護ならシンプレ看護ステーションへ!

シンプレ訪問看護ステーションの特徴
シンプレは精神疾患に特化した訪問看護ステーションで、アルコール依存症やうつ病や摂食障害など、幅広い疾患を対象としています。
精神科勤務経験のあるスタッフが在籍し、病気と付き合いながら自分らしい生活ができるように、自主性を尊重した看護サービスを提供しています。
また、病院、行政、在宅との情報共有を行い、それぞれの専門性を活かしながら治療や社会復帰のサポートができるのも特徴です。
シンプレ訪問看護ステーションの看護内容
・自立した生活を営めるための支援
・規則正しい生活リズムへの調整
症状の悪化防止・服薬支援
・病状や普段の様子を観察
・受診や服薬を支援
社会復帰へのサポート
・主治医や関係機関と連携
・社会復帰を支援
家族の方への支援
・ご家族へのアドバイスや相談
・社会資源の活用などを支援
治療においては、家族のサポートや安心できる環境作りが重要なため、精神科訪問看護では安心して自宅療養できる環境を整え、再発を予防していきます。
訪問してご本人様と面会ができない場合でも、ご希望があればご家族様からの相談を受けることも可能であったりと、それぞれの利用者様にあった看護を行っております。
シンプレは訪問看護サービスを通して利用者の不安を受け止め、治療への頑張りを一緒に共有し、心から安心できる居場所づくりをお手伝いします。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの現在の対応エリアは、上記を中心となっております。
年齢に関わらずご利用することが可能です。サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。
上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合もありますので、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。
TwitterやLine、TikTokなどのSNSでも情報を発信していますので、ぜひご覧ください。
まとめ

お酒の量が増えた・お酒を飲んでいないと暴力的になるなどの症状がみられた際は、アルコール依存症を発症している可能性があります。
アルコール依存症は、適切な治療を受けることで良くなっていく症状です。そのため、できるだけ早くから治療を始めることが望ましいと言われています。
こころの健康問題は抱えかかえこむのではなく、相談することが大切です。
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神疾患に特化した訪問看護を提供しておりますのでアルコール依存症でお悩みで訪問看護のご利用検討されたい、一度話を聞いてみたい等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



