アルコール依存症と離脱症状の関係とは?
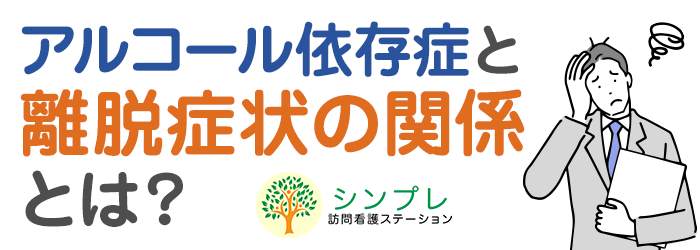
アルコール依存症には、体内のアルコール量が減ったときに離脱症状というものがあらわれます。
アルコール依存症は1人での治療が難しい疾患と言われており、特に離脱症状は進行すると仕事でトラブルを起こしたり家庭崩壊を招くこともあります。
この記事では離脱症状だけではなく、治療方法や治療中のサポートについても紹介していきますので最後まで読んでくださいね。
アルコール依存症の離脱症状は怖い

離脱症状とは?
離脱症状とは、飲酒をやめることであらわれる症状です。アルコール依存症では主に、早期離脱症状と後期離脱症状があります。
早期離脱症状は、飲酒をやめて数時間から数日以内に現れます。主な症状は、手足の震え、発汗、頭痛、吐き気、嘔吐、不眠、不安、イライラなどです。
後期離脱症状は、飲酒をやめて数日から4~5日以内に現れます。主な症状は、幻覚、妄想、幻聴、発作、意識障害などです。
離脱症状は、アルコール依存症の身体的・精神的依存が深いほど重くなります。離脱症状が重い場合、生命に関わることもあります。
離脱症状の主な症状
・手のふるえ
・悪寒、寝汗
・イライラ、不安
・焦燥感など
後期離脱症状
・幻視
・幻聴
・記憶障害
・意識がもうろうとする
早期離脱症状は飲酒をやめて数時間で現れ、手や身体の震え・不眠・吐き気・イライラなどの不快な症状が現れます。
後期離脱症状は飲酒をやめて2、3日後にあらわれ、幻視・意識がもうろうとするなどの症状が出ることが特徴です。
また、飲酒をやめることでと抑うつ状態になることもあります。
アルコール依存症の症状

アルコール依存症の流れ
ほとんど毎日飲み、酒がないと物足りない
依存症初期
初期離脱症状が起こる
(手の震え・イライラなど)
依存症中期
・離脱症状を抑えるために飲酒する
・酒によるトラブルが起こる
依存症後期
・抑うつや幻聴などの離脱症状がでる
・仕事や家族の崩壊
アルコール依存症は習慣的に飲酒をするようになることから始まります。就寝前などの飲酒が日常生活の中で欠かせなくなっていくのです。
飲酒が習慣的になると、次は飲むお酒の量が増えていきます。就寝前のみだったのが昼間や飲むべきではない場面にも飲酒行為に奔る、など回数も増えるようになっていきます。
次第に以前の量では酔えなくなり、飲酒量が増えたり、徐々に離脱症状が現れてくるというのが主な流れです。
アルコール依存症によってリスクが高まる疾患
アルコール依存症になることによってリスクが高まる疾患があります。そちらについて詳しくご紹介していきます。
肝硬変
肝硬変とは、肝臓に慢性的な炎症が起こり、徐々に線維化し、肝臓としての機能を失ってしまう病気です。
また、アルコールは、肝臓の代謝機能を低下させ、脂肪肝や糖尿病を引き起こします。これらの疾患は、肝硬変のリスクを高めます。
糖尿病
糖尿病には初期症状がほとんどなく、発見が遅れると失明や手足の壊死など深刻な症状が現れます。アルコールは、適量であれば糖尿病の発生を抑えると考えられています。
しかしアルコールは、インスリンの分泌を抑制する作用があり、過度に飲酒をすると、血糖値を上昇させ、糖尿病のリスクを高める可能性があります。
がん
アルコールは、がんの原因となる発がん物質を生成したり、免疫力を低下させたりすることで、がんのリスクを高めると言われています。
アルコール依存症の人は、がんになるリスクを減らすために、アルコールの摂取量を減らすことが大切です。また、アルコール依存症の人は、定期的に健康診断を受けるなどして、早期にがんを発見することが重要です。
アルコール依存症は治る?

アルコール依存症の治療は入院
・体内からアルコールを抜く
・身体を障害から回復させる
リハビリ治療
・自分の飲酒欲求を振り返る
・お酒のない生き方の探索
・健康な身体や感性の回復を目指す
基本的にアルコール依存症の治療は専門の施設や病院に入院し、社会から切り離した環境で行われます。
治療内容は解毒治療とリハビリ治療を中心とし、アルコールを完全に断った環境で集中的に治療していきます。
解毒治療はアルコールが原因で起きてしまった身体への障害を取り払い、健康的な身体を目指すことが目的です。
リハビリ治療は今後アルコールを断つことができるよう、カウセリングなどを受けながら心の治療をしていきます。
退院後のアフターケアはあるの?
アルコール依存症治療専門病院へ通院
薬の服用
抗酒薬を退院後も継続する
自助グループへの参加
・本人やその家族が同じ立場の人たちと交流
・断酒継続の助けとする断酒会等へ参加
退院後のアフターケアとしては、通院・薬の服用・自助グループへの参加などがあります。
中でも通院は身体のチェックをしてもらえるという面でも、アルコール依存症を克服した方にとっては大切なアフターケアとなります。
また、自助グループへ参加することで、同じ経験をしてきた仲間と自分を見つめ直し再発することがないよう強い心を作ることも可能です。
アルコール依存症に用いられる薬
・ジスルフィラム
・シアナミド
飲酒欲求を減らす薬剤
アカンプロサート
飲酒量を低減させる薬剤
ナルメフェン
アルコール依存症の治療には、薬物療法が用いられます。薬物療法には、飲酒に対する欲求を減らす効果がある薬や、アルコールの分解を抑える効果がある薬などがあります。
これらの薬は、アルコール依存症の治療に効果的とされていますが、人によっては副作用が強く出る場合があります。
副作用は、ほとんどの場合、数日で治まりますが、長引く場合副作用が辛い場合は、担当の医師に相談し、勝手に服用をやめてしまうのは避けるようにしましょう。
訪問看護で治療をサポート

アルコール依存症は1人では治せない?
アルコール依存症は克服するのが大変であり、1人で治すことは難しいと言われています。
私たちの生活には日常的に飲酒をする機会が多く、お酒を口にする機会は度々訪れるからです。
アルコール依存症を克服するには完全に、お酒を断つ必要があります。1口でも飲んでしまうと、また同じことを繰り返してしまいます。
そのため、家族や周りの人にサポートしてもらい、お酒を口にしないことを徹底して行う必要があるのです。
訪問看護とは?
訪問看護とは、看護師や作業療法士などの医療スタッフが医師の指示のもと自宅へ訪問し、病状観察や日常生活指導、また家族支援などのサポートを行います。
訪問看護を利用するメリットは、外出が難しい方や治療を中断してしまう方も、継続的に専門的な支援を自宅で受けられることです。
外出が難しい方や精神科への入退院を繰り返している方、ご家族がどのように関わっていけばいいか困っている方は訪問看護を検討してみましょう。
訪問看護でできること
・自立した生活を営めるための支援
・規則正しい生活リズムへの調整
症状の悪化防止・服薬支援
・病状や普段の様子を観察
・服薬の管理や受診の支援
社会復帰へのサポート
・主治医や関係機関と連携
・社会復帰を支援
家族の方への支援
・家族へ接し方のアドバイスや相談支援
・社会資源の活用などを支援
訪問看護では、「健康状態の観察」「病状悪化の防止・回復」「服薬の管理」など、症状の改善に向けてさまざまなポートを受けることができます。
病状や内服状況など、医療機関やかかりつけの医師と連携し情報を共有できます。
そのほかにも必要に応じて、医師や保健師、ケースワーカーなどの関係機関と連携し、病状の悪化の防止や早期回復につながるようサポートを行います。
アルコール依存症の治療ならシンプレがサポート

当ステーションについて
・精神科・心療内科に通院中の方
・精神疾患の診断を受けた方
・診断がなくとも医師が必要と判断した方
訪問する人
・看護の専門職
・リハビリテーションの専門職
訪問時間
・医療保険
(30分から90分程度)
シンプレ訪問看護ステーションは精神科に特化した訪問看護サービスを提供しており、アルコール依存症でお悩みの方も利用することが可能です。
スタッフが定期的に訪問し、ご利用者様が家庭や地域社会で安心して日常生活を送れるよう、ご利用者様の考えに寄り添い、目標に向かい支援を行います。
訪問してご本人様と面会ができない場合でも、ご希望があればご家族様からの相談を受けることも可能であったりと、それぞれの利用者様にあった看護を行っております。
対応エリアを紹介
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションでは、上記のリストを対象エリアとしています。
訪問対応エリアは順次拡大しています。サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。
上記のエリア以外に自宅がある場合でも対応できる場合がありますので、まずはお気軽に電話や問い合わせフォームでお問い合わせください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

アルコール依存症は離脱症状があらわれたりと、1人で克服することは難しく、専門の知識を持った人からサポートを受けて治療を行うことが大切になります。
こころの健康問題は抱えかかえこむのではなく、相談することが大切です。
わたしたち、シンプレ訪問看護ステーションもきっとお役に立てることがあります。
現在アルコール依存症で悩んでいる方や、そういった方がご家族におられる場合は是非一度わたしたちにご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



