アルコール依存症の治療薬で用いられているものや効果について紹介
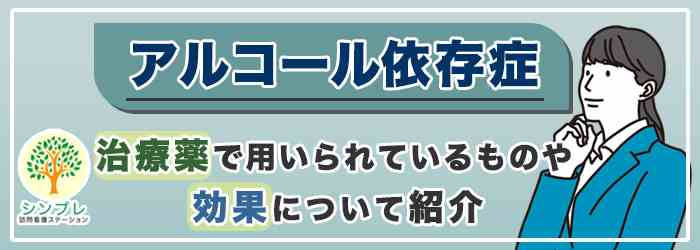
アルコール依存症の治療には治療薬が使われます。治療のサポートとして用いるためです。
身体がアルコールに依存するため、再びお酒を飲んでしまう可能性があります。治療薬は、飲酒すると身体が拒否反応を示したり、飲酒欲求を減らすことも可能です。
今回この記事では、そんなアルコール依存症に用いられる治療薬を詳しく紹介します。
アルコール依存症で用いられる治療薬

①抗酒薬
・ジスルフィラム
・シアナミド
効き目
身体のアルコール拒否反応
(嘔吐、頭痛、動悸など)
抗酒薬は2種類ありますが、どちらも内服している時にお酒を飲むと、血液のなかのアセトアルデヒド濃度が高くなることで、身体に不快なアルコール拒否反応をおこします。
アルコール拒否反応がおこる理由は、抗酒薬によってアルデヒド脱水素酵素の作用が阻害されるからです。そのため、抗酒薬を内服している患者さんは、お酒を飲むと吐き気や頭痛、動悸など不快な症状を経験します。
これらの効果は、お酒を飲むことへの嫌悪感を覚えさせるため、継続して断酒をしやすくなります。
②飲酒欲求を抑える薬
アカンプロサート
効き目
・脳内の神経活動を抑制
・飲酒欲求を減退
アカンプロサートとは、アルコール依存症の治療に用いられる薬です。海外では20年以上前から使用されていますが、日本では2013年に発売されました。
アカンプロサートには、脳内の神経伝達を抑制して、飲酒欲求を減らす効果があります。そのため、断酒している人が服用すると、継続して断酒をしやすくなります。
飲酒しても不快な反応は起こらないことが特徴で、飲みたい気持ちを減らすことで、断酒継続に役立ちます。
副作用も存在する
アルコール依存症の薬にも副作用がありますので、みていきましょう。
抗酒薬
抗酒薬には、アレルギーによる皮疹や肝障害などの副作用が起こることがあります。そのため、服用前には必ず血液検査を受けて、副作用のリスクを把握することが大切です。
また、重症な肝硬変や心臓・呼吸器疾患のある方は、抗酒薬の使用できないとされています。
飲酒欲求を抑える薬
服用により、下痢や軟便などの副作用が起こることがあります。ただし、多くは一時的なもので、しばらくすると症状が改善することがほとんどです。
また、腎臓に重い障害がある方は使用できないとされています。
併用して使われる場合もある
これらの薬は、どちらか一方を単独で使用するのではなく、効果を高めるために併用することもあります。
薬物療法の効果を向上させるためには、アドヒアランスの向上が重要です。アドヒアランスとは、患者さん本人がなぜ薬が必要なのかを理解して、積極的に治療に参加し、正しく薬を服用することをいいます。
アドヒアランスの向上のためには、家族に見てもらいながら薬を飲んだり、薬箱を作って服用したかどうかチェックできるようにするなどの工夫を行うとよいでしょう。
アルコール依存症の治療と治療薬

①断酒治療
アルコール依存症からの脱却
治療概要
・断酒を実行
・様子を見つつ精神療法
・投薬治療
・治療後経過観察
アルコール依存症の治療をおこなう際には、原則としてお酒をのまない断酒治療をおこなう必要があり、多くの場合は入院治療が選択されます。
治療には入院しておこなう「解毒期」、「リハビリテーション期」、通院しておこなう「アフターケア」と3つのステージがあり、経過にあわせた治療が必要です。
まずは断酒をおこなって、治療の経過であらわれるアルコール離脱症状に対応するための薬物治療や心理社会的治療をおこなうことで、心身の状態を落ち着かせます。
アルコール依存症は治療後にも再発することがありますので、通院して経過を観察したり、予防するための行動が大切です。
②減酒治療
・いきなり飲酒をやめられない方向け
・依存症予防として酒量を減らしたい
・軽度のアルコール依存を改善
治療概要
・減らす酒量を設定
・酒量を観察しつつ投薬治療
・治療後経過観察
減酒治療とは、アルコール依存症の患者さんが、いきなり断酒をせずに、徐々にお酒の量を減らすことを目的とした治療です。
減酒治療には、断酒治療と同様、導入期、治療開始時、継続管理期の3つのステージがあります。
減酒治療では、心理社会的治療を中心に、アルコール依存症への理解や、目標とするお酒の量の設定、治療の継続を目指します。
また、必要な場合には、専門の施設と協力して治療を進めることもできます。
減酒治療は、断酒治療よりもハードルが低く、いきなり断酒が難しい人でも、お酒の量を減らすための第一歩として、検討できる治療法です。
治療で用いられる薬とは
アルコール依存症の治療では、断酒や減酒をサポートするために、薬物治療が用いられることがあります。
大量に飲酒した後に急にお酒をやめると、アルコール離脱症状が起こることがあります。アルコール離脱症状は、吐き気、嘔吐、頭痛、発汗、不眠などです。重度の場合は、けいれんや意識障害を起こすこともあります。
アルコール依存症の治療には、薬物治療だけでなく、心理社会的治療も重要です。心理社会的治療とは、カウンセリングやグループセラピーなどによって、アルコール依存症の原因や治療方法を理解し、再発を防ぐための方法を学ぶことです。
もし依存症の治療をしなかったら
・酒を執拗に探す
・常に飲酒する
離脱症状
・手のふるえ
・イライラ
・焦燥感
・睡眠障害
心理特性
・屁理屈をいう
・周囲を過小評価する
行動異常
・暴言、暴力
・徘徊、行方不明
アルコール依存症の患者さんは、飲酒をコントロールできず、お酒を飲みたくなる衝動に駆られます。
震えやイライラなどの離脱症状が現れたり、自分の飲酒量や行動を正当化する「否認」や、物事を自分の都合よく解釈する「自己中心性」などの特性を示すことがあります。
アルコール依存症の患者さんは、暴言や暴力行為、その他の行動異常を示すことがあり、本人だけでなく、家族や周囲の人に大きな苦痛を与えます。
アルコール依存症の治療

治療カリキュラム
薬のほかにどんな治療カリキュラムがあるのか、それぞれ見ていきましょう。
①解毒治療
アルコール依存症の解毒治療は、離脱症状に対処し、断酒を維持することを目的としています。
解毒治療では、離脱症状を軽減するために、抗酒薬や鎮静剤などの薬物療法が行われます。また、患者様の体調や症状に応じて、入院治療や外来治療が行われます。
②リハビリ治療
アルコール依存症のリハビリテーションは、離脱症状が落ち着いてから開始されます。
アルコール依存症は、再発しやすい病気です。リハビリテーションでは、心理社会的治療が中心となり、患者さんの断酒を維持・支援するために、さまざまな療法が組み合わせて行われます。
③アフターケア
アルコール依存症の治療が完了した患者さんは退院し、通院によって状態を維持しつつ、再発を予防するためのアフターケアをおこないます。
同じ問題や悩みをかかえた人が集まる「自助グループ」に参加し、仲間に自分の体験を語ったり、人の体験を聞いたりして支えあうことで、継続した治療につながるとされています。
特定非営利活動法人を利用する
アルコール依存症の予防には、特定非営利活動法人であるaskなどの行う再発防止・予防のための講演に参加することも有効とされています。
アルコール薬物問題に関しては、集会や講演などを行うことでアルコール依存症をはじめとした依存症の治療・回復支援を行っている特定非営利活動法人が複数あります。
同じ病気からの回復に取り組む意思をもった仲間と会ったり、コミュニケーションをとる場に参加したりすることで、治療に前向きに取り組むきっかけをつかむことができます。
療養者の方のみでなく、その家族の方も交えて相談を受けている団体もあるため、悩みをもつ方、そのご家族は利用してみることも1つの方法です。
精神科訪問看護も利用してみる
| サービス名 |  精神科訪問看護 |
|---|---|
| 職種 |  ・看護師 ・准看護師 ・作業療法士 |
| 訪問日数 |  原則週3日以内 (※例外もあります。) |
精神科訪問看護は精神科や心療内科に通院され精神疾患と診断されている方、診断はなくとも睡眠障害などで医師が訪問看護が必要と判断された人が対象です。
看護師や作業療法士などの医療スタッフが医師の指示のもと自宅へ訪問し、病状観察や日常生活指導、また家族支援などのサポートを行います。
通常、訪問は医療保険を利用し週3回まで可能で、1回の訪問は30分から90分と決められています。体調や病状に合わせて訪問回数や時間を調整します。
外出が難しい方や精神科への入退院を繰り返している方、ご家族がどのように関わっていけばいいか困っている方は訪問看護を検討してみましょう。
精神疾患をお持ちならシンプレへ

当ステーションの特徴
シンプレでは、精神科に特化した訪問看護サービスを提供しています。さまざまな精神疾患や障害をお持ちの方の在宅生活を、専門知識を持った看護師等がサポートします。
訪問してご本人様と面会ができない場合でも、ご希望があればご家族様からの相談を受けることも可能であったりと、それぞれの利用者様にあった看護を行っております。
そのほかにも必要に応じて、医師や保健師、ケースワーカーなどの関係機関と連携し、病状の悪化の防止や早期回復につながるようサポートを行います。
精神疾患の一例
・酒類(アルコール)に依存する
・アルコール中心の生活になってしまう
統合失調症
・幻覚や妄想という症状が特徴的
・生活に支障をきたしてしまう
うつ病
・気分の落ち込みや意欲の低下
・体のだるさや痛み
その他精神疾患全般
シンプレ訪問看護ステーションは、限られた疾患だけでなく、精神疾患全般の患者様にご利用いただいております。
今回ご紹介したアルコール依存症のほかにも、統合失調症や双極性障害なども対象です。
ほかにも、ADHDや自閉症、発達障害、はたらく世代のうつ病や適応障害など、お子様から高齢の方まで年齢や内容にかかわらず訪問します。
精神疾患で治療を受ける利用者様や社会復帰を目指す利用者様本人だけでなく、自宅でその支援をおこなう、ご家族のご相談もお受けしています。
シンプレの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの現在の訪問エリアは、上記中心に行っています。
訪問対応エリアを順次拡大しています。上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合もございます。
こころの健康問題をひとりで抱えて悩むのではなく、相談することが大切です。お気軽に電話や問い合わせフォームにてお問い合わせください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

アルコール依存症では、抗酒薬やお酒をのみたいという欲求を抑える薬などを併用することで、お酒をのむ量や行動の改善をめざします。
アルコール依存症は再発する可能性もあり、治療後も周りの人の助けやサービスを利用して、再発を予防していくことが大切です。
治療を継続するために有効な方法として、自助グループに参加したり、精神科訪問看護を利用することもできるため、有効に活用しましょう。
訪問看護のサービスについて聞いてみたい、どこに相談をしたらいいかわからなくて困っていた、などございましたら当ステーションへお気軽にお問い合わせください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



