PTSDの診断と診断基準は?診断後の治療方法や治療期間について解説
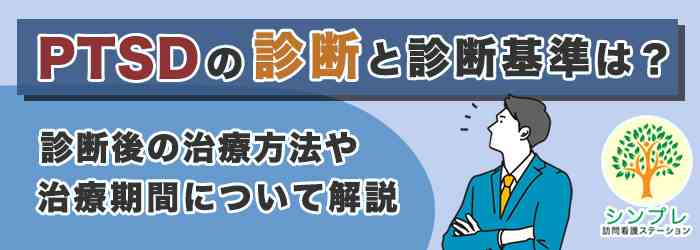
PTSDの診断についてご興味をお持ちの方へ、当記事ではその概要や症状、治療法について解説いたします。
PTSDは、天災や事故、犯罪、虐待などの極度のストレス体験によって引き起こされる精神疾患です。症状が長期にわたって続く場合には、専門家の治療を受けることが重要となります。
ご自身やご家族がPTSDに苦しんでいる方は、ぜひ本記事を参考にして、適切な対処方法を見つけてみてください。
PTSDの診断方法
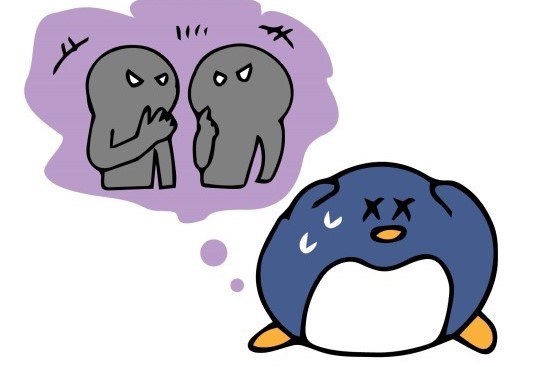
問診表・患者の状態をもとに診断
PTSDの症状がある場合、診察に行く前に、どのような問診や診察が行われるのか、不安に感じる方もいるのではないでしょうか。
PTSDの診断は、問診票と診察に基づいて行われます。問診票は、診断基準に基づいた質問用紙や、心理的ストレス反応を評価するための問診票などがあります。
具体的な診断までの内容を知ることで、安心して治療に向き合うことができるようになります。
診断の流れ
診断は、まず問診から始まります。次に診察が行われます。
ステップ①問診表の記入
PTSDの診断には、ご自身の体験やご症状について詳しく患者様にお伺いする必要があります。
問診表は、来院して記入することも可能ですが、クリニックによっては、事前にWEB問診やダウンロード問診をご用意しているところもあります。
WEB問診表を記入すると診察までがスムーズになったり、自宅で都合の良い時間に、ゆっくりと記入できます。事前にクリニックのホームページを確認してみるといいでしょう。
ステップ②医師との診察
記入いただいた問診票の内容をもとに、医師が改めて症状について詳しく伺います。
その際、困っていることや、症状を疑ったエピソードなどを話しましょう。
診断基準をもとに患者を診察する
PTSDの診断は、診断基準に基づいて行われます。診断は、細かく規定されています。基準に達していない軽症の患者さんが過剰診断されることがないよう、慎重に診断されます。
症状が悪化してしまうことを防ぐためにも、早い段階で受診するようにしましょう。
PTSDの診断と診断基準

基準①侵入症状の診断
・つらい体験など心を乱す記憶がある
・つらい出来事を再体験しているように感じる
・つらい出来事を思い出す
PTSDの診断基準の1つに、侵入症状があります。侵入症状は、再体験症状ともいわれ、外傷的な出来事について、日常生活の中で、再体験をするようなことを繰り返します。
結果的に、心理的ストレスや緊張感が高い状況になります。そのため、胸がドキドキしたり、汗が出たりといった体の症状を伴います。
基準②回避症状の診断
・特定の考え、記憶を避ける
・トラウマにまつわる場所、人物を嫌う
回避症状についても、上記の症状が1ヶ月以上継続して、1つ以上あるかということが確認されます。
回避症状は、上記のようにトラウマにまつわる出来事を思い出したり、体験したりすることを恐れているため、関連する出来事や状況を避けることで、不安や恐怖を回避しようとするものです。
回避症状があると、日常生活に支障をきたすことがあります。例えば、トラウマにまつわる場所や人物を避けることで、仕事や学校に行けなくなったり、家族や友人との関係が悪くなったりといったことがあります。
基準③認知・気分に対する悪影響の診断
・記憶障害
・過剰な否定的確信、予想
・持続的な歪んだ思考
・孤立感、疎遠感
認知・気分に対する悪影響は、上記のような症状が1ヶ月以上継続して、2つ以上あるかということが確認されます。
否定的な感情や気分がつづき、以前のようには楽しめなくなることです。不安や恐怖、自責の念などの否定的な感情や思考に支配され続ける状態です。
そのため、日常生活を楽しむことができなくなったり、周囲の人々との関係が希薄になったりすることがあります。
基準④覚醒度・反応性の変容の診断
・睡眠障害
・怒りの爆発
・無謀または自己破壊的な行動
・集中困難
覚醒度および反応性の変容についても、上記のような症状が1か月以上継続して、2つ以上あるかということが確認されます。
心身が過敏になり、神経が常にはりつめたような状態や、常に危険にさらされていると感じてしまう状態です。
過度の覚醒状態から睡眠障害や怒りなど、日常生活の中で些細なことでも脅威と感じてしまい、過剰に反応してしまうことがあります。
また、集中力が低下したり、注意力が散漫になる状況もみられることがあります。
診断の結果他の疾患である可能性も
PTSDは上記にあげた症状が、1ヶ月以上続き、不安感や緊張感を強くします。
このように、PTSDはさまざまな症状を引き起こすため、診断が難しい病気です。また、物質使用障害を併発している場合、PTSDの症状が隠れてしまう可能性もあります。そのため、早期の診断と治療が重要です。
診断と治療が遅れた場合、PTSDは慢性的に悪化する可能性があります。そのため、きっかけとなるような出来事を体験した方は、早めに医療機関を受診するようにしましょう。
診断結果から治療方法が決定
診断結果から、症状の具合をみて治療方法が決定されます。認知行動療法やカウンセリングなどの治療と薬物療法を組み合わせて治療されます。
PTSDの患者さんがうつ病などの精神疾患を併存していることがあります。そのような場合についても、検査や診察で総合的に診断していきます。
また、自分を傷つける行為などが見られる場合には入院治療も検討されます。
PTSDの診断後の治療と治療期間について

治療は大きく分けて二通り
・ものの考え方(認知)や行動を修正することで
感情を改善する治療法
投薬治療
・内服薬を飲み症状を和らげる
・抗精神病薬など
PTSDの治療は、2つの方法を組み合わせて行います。
認知行動療法では、ものの捉え方や考え方(認知)を修正することで、感情や行動を改善することを目的としています。
認知の歪みとは、ものの捉え方が現実と異なることを指します。例えば、PTSDの患者さんは、トラウマを感じた出来事に恐怖や不安を感じながら捉えてしまうことがあります。
このような認知の歪みによって、日常生活に支障をきたしてしまうことがあります。
認知行動療法では、こうした認知の歪みを修正することで、トラウマの記憶に対する感情的な反応を弱め、症状を改善することを目的としています。
3カ月以内で回復することが多い
PTSDの症状は、一般的に3か月以内に自然回復するといわれています。
しかし、すべての方に当てはまるわけではなく、発症して3か月以内で回復できる方もいれば、慢性化してしまい、長期的な治療が必要となり、回復までに長い時間が必要な方もいらっしゃいます。
PTSDの回復には、早期治療が重要です。早期に治療を受けることで、症状の悪化や慢性化を防ぐことができます。
診断を受ける際のポイント
なにか外傷的な出来事があったときに、PTSDの症状がある場合、我慢や頑張りでは良くならないことがあります。
セルフチェックを行い、自分の心の傷を軽視しないことが大切です。ありのままの状態を医師へ伝えることが受診や診断につながるポイントです。
ポイント①早期に病院を受診する
公衆衛生の統計からは、外傷的な出来事があった場合、今まで述べてきた症状が出ることはよくみられることです。
しかし、この症状が1ヶ月以上つづいたり、ひどくなったりする場合には注意が必要です。
症状が慢性化してしまう場合には、このような症状のあるストレスフルな状況に対して諦めの気持ちが強くなって悪循環におちいる場合があります。
また、慢性化するとうつ病や不安障害を合併することも多く、治療による治癒率が低下します。
ポイント②サイン・言動を見逃さない
このようなPTSDの症状が、自分にないか、セルフチェックすることも大切です。セルフチェックすることで、慢性化する前に自分で自覚することができます。
そうすれば、早期治療につながります。早期発見後の治療では、治療の効果が出やすくなります。
また、大切なお身内や友人の変化などに気がついた際にも、ご本人になにか困ったことはないか声をかけることも大切です。
まずは、安全な環境を確保することが大切です。そして、早期に治療することのメリットについてお話しできれば、受診につながりやすくなるでしょう。
精神疾患をお持ちならシンプレへ

当ステーションの特徴
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神科に特化した訪問看護サービスを提供しています。精神科訪問看護は、社会復帰に向けて障害や病気をお持ちの方をサポートするサービスです。
さまざまな精神疾患や障害をお持ちの方の訪問看護の訪問看護を行っており、生活支援や自立支援、症状の悪化防止、服薬支援などのトータルサポートを行います。
PTSDの症状で悩まれている方に対しても、生活が少しでも安心したものになるようにひとりひとりの方の考え方や価値観を大切にして寄り添います。
対象となる精神疾患
・トラウマとなった記憶が突然よみがえる
うつ病
・気分の落ち込みや意欲の低下
・体のだるさや痛み
統合失調症
・幻覚や妄想という症状が特徴的
・生活に支障をきたしてしまう
ADHD
・不注意さ、多動性、衝動性が特徴的
その他精神疾患全般
シンプレは精神疾患に特化した訪問看護ステーションで、うつ病や摂食障害など、幅広い疾患を対象としています。
シンプレは訪問看護サービスを通して利用者の不安を受け止め、治療への頑張りを一緒に共有し、心から安心できる居場所づくりをお手伝いします。
ご利用者様が持つ病気とどう向き合っていくかを看護師が一緒に考え、患者さんらしさを失わないよう自立した生活をするためのサポートを心がけています。
病気と付き合いながら自分らしい生活ができるように、自主性を尊重した看護サービスを提供してしており、病院、行政、在宅との情報共有を行い、それぞれの専門性を活かしながら治療や社会復帰のサポートができるのも特徴です。
主治医や通っている医療機関とも密に連携をとりながら社会復帰に向けてのご支援をさせていただきます。
PTSDの症状で悩まれている方に対しても、生活が少しでも安心したものになるようにお手伝いします。
シンプレの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの訪問エリアは、上記中心に行っています。
訪問対応エリアを順次拡大しています。上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。
また、TwitterやLine、TikTokなどのSNSでも情報を発信していますので、ぜひご覧ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

PTSDについて、診断の基準や診察について解説しました。PTSDは、実は身近におこりえることです。自分自身や家族がこのような状態にある場合には、安全を確保すること、こころのケアをなるべく早く行うことが大切です。
治療が遅れることで、ほかの精神的問題もおこす可能性があり、早期に専門知識をもつ医師へ相談しましょう。
わたしたち、シンプレ訪問看護ステーションもきっとお役に立てることがあります。PTSDの症状でお悩みの方、そういった方がご家族におられる方は、是非一度シンプレへご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



