子どものPTSDとは?年齢別の特徴と大人の対応・治療法を徹底解説。
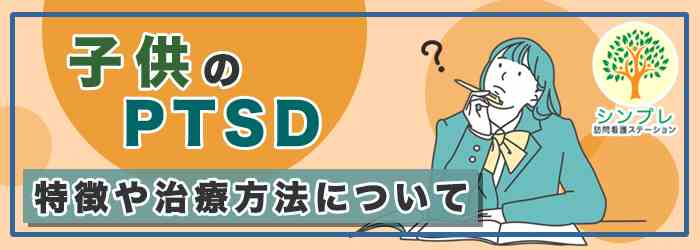
PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、大人だけでなく子どもにも発症する可能性がある精神的なストレス反応です。
特に子どもは、自分がPTSDの状態にあることを理解できず、行動や感情の変化として現れることが多い傾向があります。
そのため、周囲の大人が子どものサインに気づき、年齢に応じた適切なサポートを行うことがとても重要です。
この記事では、「子供のPTSD」というテーマのもと、特徴を年齢別に分かりやすく解説します。
あわせて、正しい知識を身につけ、子どもの心を守るためにできる支援についても紹介します。
子どものPTSDの特徴を年齢別に解説

子どものPTSDは、年齢によってそのあらわれ方が異なります。
幼児期、小学生、中・高校生と発達段階ごとに、行動や感情の変化が変わってくるため、それぞれの特徴を理解することが大切です。
ここでは、年齢別に見られる典型的な反応と、大人がどのように関わるべきかを詳しく解説していきます。
幼児期(5歳まで)の特徴
はじめに、5歳までの子ども、いわゆる幼児期の子どもに見られるPTSDの特徴について見ていきたいと思います。
- 夜中に泣き出す・目を覚ます
- 赤ちゃん返りが起こる
- 大きな音や暗闇を怖がる
- 言葉数が減る、笑顔が少なくなる
幼児期に見られる典型的な反応
幼児期の子どもは、言葉で不安をうまく表現できないため、行動や身体の反応で心の不調を示すことがあります。
特に「トイレの失敗」や「体験したことを何度も繰り返し話す」などは、PTSDのサインの一つかもしれません。
急に無口になる、大人に甘えるようになるといった変化が見られた際は、子どもの心に寄り添うことが大切です。
幼児期にPTSDを発症した際の大人の対応方法
この時期の子どもは安心感を求める傾向が強いため、スキンシップや共感的な対応がとても重要です。
子どもの話を途中で否定せずに聞き、安心できる環境を保つよう意識しましょう。
夜間は一人にしない、慕っている大人と一緒に過ごす時間を増やすなど、安心できる時間を意識的に作ることが大切です。
また、食事や睡眠などの日常生活のリズムを整え、普段通りの楽しみを継続させることで、回復をサポートできます。
小学生の特徴
次に、幼児期よりも少し大きくなった小学生がPTSDを発症した場合の反応について、見ていきましょう。
- 体験した出来事を何度も話す
- 同じようなことが起きるのではと不安がる
- 無口になる、または攻撃的な態度をとる
- 眠れない・悪夢を見るなどの睡眠障害
- 親や先生の反応に過敏になる
小学生に見られる典型的な反応
小学生になると、言語や思考力が発達するため、感情を言葉で表現できる一方で、心の負担を抱え込みやすくなります。
その結果、PTSDを発症した子どもでは、学校生活や家庭での行動にも変化が現れることがあります。
特に注意したいのが「攻撃的になる」「親の表情を過度に気にする」といった行動です。
これらは心の不安や恐怖の表れであり、叱責ではなく理解を持って受け止めることが求められます。
また、成績の低下や集中力の欠如など、学校での様子にもPTSDの影響が出る場合があります。
周囲の大人が早期に気づくことで、回復へのサポートがしやすくなるでしょう。
小学生でPTSDを発症した際の大人の対応方法
小学生の時期は自我が芽生え始めるため、「自信を取り戻す関わり」が重要です。
子どもの話に耳を傾け、努力や気持ちを認めてほめることが、安心と回復につながります。
また、一時的に赤ちゃん言葉を使ったり、一人で行動できなくなったりする「赤ちゃん返り」が見られることもあります。
そのような行動を馬鹿にしたり否定したりせず、「安心を求めているサイン」として受け止めましょう。
子どもが再び安心できる環境を整えることで、PTSDからの回復をサポートできます。
中・高校生の特徴
さらに、中・高校生がPTSDを発症した場合に見られる症状はこれまでの幼児期、小学生とどのような違いがあるのかについて見ていきたいと思います。
- 睡眠や食事など生活リズムの乱れ
- 人との関わりを避けて引きこもる
- 悲観的・無気力な状態が続く
- 行動範囲が極端に狭くなる
- 集中力や学業成績の低下
中・高校生に見られる反応
思春期に入る中・高校生は、自己意識が強くなり、感情の起伏も激しくなります。
そのため、子どものPTSDの中でも特に難しい年齢層といえます。
この時期のPTSDは、大人と似た反応を示すことが多く、睡眠障害や摂食の乱れ、対人関係の回避などが目立ちます。
また、「自分が悪い」「何もしたくない」といった自己否定的な思考に陥りやすく、孤立感を深めるケースもあります。
家庭内でのコミュニケーションが減少し、表面的には「反抗期」と見えることもありますが、実際は心のSOSであることが少なくありません。
中・高校生でPTSDを発症した際の大人の対応方法
中・高校生の場合、本人の意思やプライドを尊重しながら支援することが大切です。
「無理をさせない」「否定しない」を意識し、安心して過ごせる空間を確保しましょう。
子どもが楽しみにしている活動を続けられるようにサポートし、「できることから少しずつ始めよう」と励ます姿勢も有効です。
また、感情の浮き沈みが激しい場合や、攻撃的な行動が見られる場合には、早めに専門機関や医療機関へ相談することが必要です。
思春期のPTSDは放置すると長期化することがあるため、信頼できる専門家と協力しながら支えていきましょう。
そもそもPTSDとは?子どもが発症する割合を知ろう

ここでは、PTSDという病気の基本的な仕組みと、子どもがどのくらいの割合で発症するのかを見ていきましょう。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、強いショックや恐怖体験が心に深く刻まれ、その出来事を思い出したり、似た状況に強い不安を感じたりする状態を指します。
大人だけでなく、子供のPTSDという形で小さな子どもにも見られることがあり、発症後の生活や学習、人間関係に大きな影響を及ぼす可能性があります。
まずは、PTSDの特徴を改めて整理してみましょう。
子どものPTSDとはどんな状態か
| PTSD | 特徴 |
|---|---|
継続期間 |
1カ月以上続くストレス反応 |
発症の原因 |
交通事故・犯罪被害・虐待・DVなど |
合併症 |
うつ病・不安障害など |
子どもがPTSDを発症する背景には、事故や災害、家庭内暴力、いじめなどさまざまな要因があります。
強い恐怖やショックを経験すると、脳がその記憶を処理しきれず、トラウマとして残ることがあります。
このような体験の後、「似た音や場所を避ける」「眠れない」「過剰に驚く」といった行動が現れる場合、PTSDの可能性が考えられます。
また、子どもによっては無気力や自尊心の低下、周囲への不信感など心理的な影響が長く続くこともあります。
周囲の大人が変化に気づき、早期に専門機関へつなぐことが、回復への第一歩です。
子どもがPTSDを発症する割合について
| 状況 | 有病率 |
|---|---|
一般的な子ども |
0.5%〜10% |
自然災害を経験した子ども |
15%〜86% |
性的虐待を受けた子ども |
約56% |
虐待経験のある子ども |
約31% |
このように、子どもがPTSDを発症する割合は体験した出来事によって大きく異なります。
一般的には1割未満とされていますが、虐待や性的被害など深刻な体験をした子どもでは、そのリスクが数十倍に高まります。
また、災害や事故などで命の危険を感じた場合にも、PTSDの発症率が急上昇します。
年齢や性格、サポート環境によっても回復力には差があるため、家庭・学校・地域が一体となって子どもを支えることが重要です。
子どものPTSDを相談できる窓口一覧
| 相談先 | 保健所・保健センター |
精神保健福祉センター |
精神科・訪問看護 |
|---|---|---|---|
| 方法 | 電話・面談 | 電話・面談 | 電話・面談 |
| 対応者 | 保健師・医師など | 医師・看護師 保健師など |
訪問看護師 |
PTSDが疑われる子どもを抱えている場合は、家庭だけで悩まず、信頼できる専門機関に早めに相談しましょう。
児童相談所や保健センターでは、心理士や保健師が相談に応じてくれます。
また、自宅から出ることが難しい場合は、精神科訪問看護を利用するのも一つの方法です。
訪問看護では、専門の看護師が家庭を訪問し、心のケアや日常生活のサポートを行います。
シンプレ訪問看護ステーションでは、PTSDをはじめとした精神的な不調に寄り添い、安心して過ごせるよう支援しています。
子どものPTSDを治療する方法

子どものPTSD(心的外傷後ストレス障害)は、放置すると長期化し、学校生活や家庭での適応にも影響を及ぼす可能性があります。
しかし、専門的な治療やサポートを受けることで回復は十分に可能です。
ここでは、代表的な治療法である「EMDR(眼球運動による脱感作再処理法)」「薬物療法」「認知行動療法」について詳しく解説します。
それぞれの特徴を理解し、子どものPTSDの症状に合った方法を検討することが大切です。
トラウマ記憶に働きかけるEMDR
EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)は、眼球運動や軽いタッピングなどの刺激を用いて、トラウマ記憶を安全に処理していく心理療法です。
強いショックを伴う出来事は、脳が「危険な記憶」として固定してしまうことがあります。
EMDRでは、その記憶を刺激によって再処理し、恐怖や不安を和らげていくことを目的としています。
特に、事故や災害、いじめなどを経験した子どもに対して有効であり、感情の整理や心の安定を取り戻す効果が期待されます。
施術は専門の心理士・臨床心理士によって行われ、子どものペースに合わせて進められるのが特徴です。
不安や抑うつを和らげる薬物療法
PTSDに伴う不眠、不安、怒りのコントロールが難しい場合には、薬物療法が併用されることがあります。
薬はあくまで症状の緩和を目的とし、根本的なトラウマの解消ではなく「心を安定させるサポート」として用いられます。
子どもの発達段階に応じた慎重な処方が必要となるため、医師の指導のもとで進めていくことが大切です。
| 薬の種類 | 主な効果 |
|---|---|
セロトニン系薬剤 |
不安・抑うつ気分・強迫症状・衝動的な怒りの軽減 |
アドレナリン系薬剤 |
過剰な覚醒や睡眠障害、悪夢などの緩和 |
ドーパミン系薬剤 |
強いフラッシュバックや攻撃的行動の抑制 |
三環系抗うつ剤 |
不眠や睡眠時の悪夢の改善 |
現在、PTSDそのものに直接効果があると認可された薬は存在しませんが、症状を和らげる補助療法として有効です。
服薬中は副作用や変化をよく観察し、医師と連携しながら安全に治療を進めましょう。
思考と感情を整理する認知行動療法
認知行動療法(CBT)は、トラウマによって歪んだ思考や感情を整理し、現実的で前向きな考え方を身につけていく心理療法です。
子どもの場合、専門家が絵や言葉、ロールプレイを用いて丁寧に進めることが多く、安心感を持ちながら取り組めます。
また、恐怖の対象に少しずつ慣れていく「曝露療法(PE療法)」を併用するケースもあります。
これは、安全な環境で徐々にトラウマ記憶と向き合う練習を行い、心の負担を軽減していく治療法です。
認知行動療法は、再発防止にも効果があるとされ、PTSDからの回復だけでなく、将来的なストレス耐性を育むことにもつながります。
子どものPTSDのサポートならシンプレ訪問看護ステーションへ

PTSDを発症した子どもは、学校生活や家庭での人間関係に支障をきたすこともあります。
そんな時、専門職による訪問看護が大きな支えになることをご存じでしょうか。
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神疾患や発達障害を含む幅広い心のケアを専門に行っており、「子どものPTSD」への支援も豊富な実績があります。
ここでは、シンプレ訪問看護ステーションの特徴と対応エリアについて詳しく紹介します。
シンプレ訪問看護ステーションの特徴
| サービス内容 | 具体的な支援 |
|---|---|
生活支援・自立支援 |
子どもが安心して自分らしい生活を送れるよう、日常のリズムづくりや生活習慣の整えを支援します。 |
症状の悪化防止・服薬支援 |
医師の指示に基づき、服薬の確認や体調の変化を見守り、再発予防や安定した生活をサポートします。 |
社会復帰へのサポート |
学校や関係機関と連携しながら、外出練習や登校支援など、社会復帰に向けた段階的サポートを行います。 |
家族への支援 |
保護者の方に対しても、日常での接し方や気持ちのケア方法などをアドバイスし、家庭全体の安心を支えます。 |
シンプレ訪問看護ステーションのスタッフは、精神科の経験が豊富な看護師・准看護師・作業療法士で構成されています。
訪問時には、子どもの状態や生活状況を丁寧に観察し、主治医や支援機関と連携しながら、最適な看護プランを提案します。
また、家庭内でのサポート方法や学校との連携が必要な場合も、担当者が間に入り調整を行うため、安心して相談できます。
特に、外出が難しい子どもや、病院に通うことに不安を感じるケースでは、訪問看護が非常に有効な手段となります。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションでは、以下のエリアを中心に訪問サポートを行っています。
・東京23区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、府中市、東久留米市、埼玉県一部
上記地域外でも、状況によっては訪問可能な場合があります。
まずはお気軽にご相談ください。
訪問回数は週1〜3回(場合によっては週4回以上)まで対応しており、1回あたり30〜90分の訪問を行います。
また、祝日や土曜日の訪問も実施しているため、保護者の予定に合わせて柔軟に利用できます。
PTSDをはじめ、うつ病や発達障害など多様な疾患にも対応しており、子どもだけでなくご家族のサポートにも力を入れています。
子どものPTSDに関して「どこに相談すればいいのかわからない」「家庭でどう対応すればいいのか不安」と感じたら、ぜひシンプレ訪問看護ステーションへご相談ください。
専門職がご家庭に伺い、子どもの心に寄り添いながら一歩ずつ前進できるようサポートいたします。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ|子どものPTSDは年齢に応じた対応と専門的支援が大切

PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、大人だけでなく子どもにも発症する心の病気です。
特に、幼児期・小学生・中高生など発達段階によってその表れ方が大きく異なるため、年齢に応じた理解と支援が欠かせません。
「夜一人になるのを怖がる」「不眠や悪夢が続く」「引きこもりがちになる」など、子どもの行動や感情に変化が見られた場合、それはSOSのサインかもしれません。
保護者や周囲の大人がそのサインに気づき、早めに専門家へ相談することが、心の回復への第一歩です。
また、PTSDは一人で抱え込むと悪化してしまうことがあります。
学校や家庭でのサポートが難しい場合は、精神科訪問看護などの専門サービスを利用するのも効果的です。
特に「子どものPTSD」に対応した訪問看護では、自宅で落ち着いてケアを受けられるため、外出に不安を感じるお子さんにも適しています。
定期的な訪問を通じて、安心できる環境を保ちながら、生活リズムや気持ちの安定をサポートしてくれるのが特徴です。
シンプレ訪問看護ステーションでは、うつ病・統合失調症・発達障害・PTSDなど、幅広い精神疾患に対応しています。
看護師・准看護師・作業療法士などの専門スタッフが連携し、ご家庭に合わせたケアプランを提案します。
また、ご家族への支援にも力を入れており、子どもへの接し方や日常のサポート方法など、具体的なアドバイスを行っています。
「どう接してよいかわからない」「話を聞いてもらいたい」――そんな時こそ、専門職の力を借りることが重要です。
PTSDの治療は時間がかかることもありますが、焦らず、子どものペースに寄り添う姿勢が回復の鍵となります。
子どもが再び笑顔を取り戻し、安心して過ごせるように、家庭・学校・医療が連携して支えていきましょう。
もしご家庭でサポートが難しいと感じた場合は、シンプレ訪問看護ステーションへお気軽にご相談ください。
お子さま一人ひとりの気持ちを尊重しながら、専門のチームが丁寧に支援いたします。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (5)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



