アルコール依存症の治療薬一覧|抗酒薬・飲酒欲求を抑える薬・副作用まで徹底解説
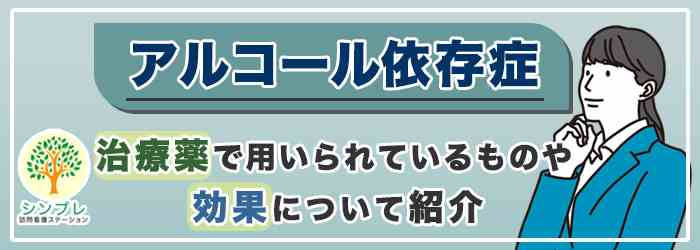
アルコール依存症の治療では、薬物療法を上手に組み合わせることで回復の道筋が見えやすくなります。長年の飲酒習慣により身体がアルコールを求める状態になると、意思の力だけで断酒を続けることは簡単ではありません。そのため、「アルコール依存症の薬」として、飲酒を避けやすくしたり、飲みたい気持ちを和らげたりする治療薬が用いられます。本記事では、治療で使われる主な薬の種類や作用、注意したい副作用、併用の考え方までをわかりやすく解説します。ご自身やご家族が安心して治療に取り組むための情報整理にお役立てください。
アルコール依存症の治療で用いられる治療薬について

①お酒をやめる手助けをする「抗酒薬」
・ジスルフィラム
・シアナミド
効き目
身体のアルコール拒否反応
(嘔吐、頭痛、動悸など)
抗酒薬は、服用中に飲酒すると血中のアセトアルデヒドが過剰にたまり、吐き気や頭痛、動悸などの不快な反応が出やすくなる薬です。これは、抗酒薬がアルコール分解に関わる「アルデヒド脱水素酵素」の働きを妨げるためで、飲酒そのものに強いブレーキがかかります。結果として、「お酒を飲むとつらい」という学習が進み、断酒の継続を後押しします。自己判断での使用は避け、必ず医師の管理下で服用量・タイミングを守ることが重要です。また、通院時には飲酒の有無や体調の変化を正直に伝えることで、安全性と効果を高められます。
②飲酒したい気持ちを和らげる薬
アカンプロサート
効き目
・脳内の神経活動を抑制
・飲酒欲求を減退
アカンプロサートは、脳内の神経伝達のアンバランスを整えることで「飲みたい衝動」を和らげ、断酒の維持に役立つ薬です。抗酒薬のように飲酒時の不快反応を引き起こすタイプではありませんが、飲酒欲求そのものを下げる働きが期待できます。継続服用によって効果が安定しやすいため、飲み忘れ防止の工夫(服薬カレンダーや家族の見守り、スマホのリマインダーなど)を取り入れると良いでしょう。心理療法やカウンセリングと組み合わせることで、ストレス対処や生活リズムの調整が進み、総合的な再発予防につながります。
気をつけたい副作用について
抗酒薬の副作用
抗酒薬では、皮疹や肝機能障害などが現れることがあります。服用前に血液検査で肝機能を確認し、服用中も体調の変化を感じたら早めに医師へ相談しましょう。重い肝硬変、心疾患・呼吸器疾患がある場合は使用が推奨されないこともあります。処方の可否や用量は必ず専門医の判断に従ってください。
飲酒欲求を抑える薬の副作用
アカンプロサートでは、下痢や軟便などの消化器症状が見られることがあります。多くは一過性ですが、長引く場合や日常生活に支障が出る場合は受診を。腎機能に重い障害がある方は使用が制限されることがあるため、事前の評価が欠かせません。副作用を恐れて自己中断すると再燃のリスクが高まるため、気になる症状は我慢せず医師・薬剤師に共有しましょう。
状況に応じて併用されることもある
抗酒薬とアカンプロサートは、症状や生活状況に応じて単独または併用で用いられます。効果を高めるカギは、服薬の継続と通院フォローです。家族や支援者と協力して服薬記録をつけたり、ピルケースで管理したりといった小さな工夫が、毎日の積み重ねを支えます。薬はあくまで「治療を進めるための支援役」。カウンセリングや自助グループなどの心理社会的支援と合わせて取り組むことで、再発予防の土台が強化されます。
アルコール依存症の治療とお薬の役割

①断酒に向けた治療と薬のサポート
アルコール依存症からの脱却
治療概要
・断酒を実行
・様子を見つつ精神療法
・投薬治療
・治療後経過観察
アルコール依存症の治療では、まず断酒を続けるための基盤づくりが重要です。入院によって身体からアルコールを抜き、離脱症状をコントロールしながら治療を進めます。アルコール依存症の薬はこの過程で欠かせないサポート役となり、抗酒薬や飲酒欲求を抑える薬が併用されることもあります。
断酒初期は不安やイライラ、手の震えなどの離脱症状が起こりやすく、再飲酒のリスクが高まります。そんな時期に薬の助けを借りることで、身体的な安定を保ちながら治療に取り組めるのです。また、治療には医療だけでなく、心理的サポートや家族の理解も不可欠です。
②減酒を目指す治療と薬の使い方
・いきなり飲酒をやめられない方向け
・依存症予防として酒量を減らしたい
・軽度のアルコール依存を改善
治療概要
・減らす酒量を設定
・酒量を観察しつつ投薬治療
・治療後経過観察
「減酒治療」は、完全な断酒が難しい場合に段階的に飲酒量を減らすアプローチです。アカンプロサートなどの飲酒欲求を抑える薬を用いながら、医師やカウンセラーのサポートのもとで進めます。無理のないペースで少しずつ減酒していくことで、依存症の再燃を防ぐ効果が期待できます。
この治療では、飲酒を完全にやめる前の準備期間として取り組むケースも多く、心理的なハードルを下げることにもつながります。個人の体調や生活リズムに合わせて治療計画を立てることが大切です。
薬で期待できる効果と限界
アルコール依存症の治療薬は、飲酒への欲求を軽減し、断酒の継続をサポートします。ただし、薬だけで依存症を完治させることはできません。薬はあくまで再発を防ぐための一助であり、患者さん自身の意識改革や生活習慣の改善と並行して進める必要があります。
また、服薬を途中でやめてしまうと、再び飲酒をしてしまうリスクが高まります。通院を続け、医師や看護師と相談しながら服薬の内容を見直すことが、長期的な回復には不可欠です。薬の効果を最大限に引き出すためには、治療チームとの信頼関係を築きながら根気強く続けることが大切です。
治療を受けずに放置した場合に起こりやすいこと
・酒を執拗に探す
・常に飲酒する
離脱症状
・手のふるえ
・イライラ
・焦燥感
・睡眠障害
心理特性
・屁理屈をいう
・周囲を過小評価する
行動異常
・暴言、暴力
・徘徊、行方不明
治療を受けずに放置してしまうと、アルコールによる臓器障害や精神的不安定が進行し、社会生活に大きな支障をきたします。飲酒をやめようとしてもコントロールできず、再飲酒の悪循環に陥ることもあります。
また、家族関係の悪化や孤立感の増大など、心理的ダメージも深刻です。こうしたリスクを防ぐためにも、早期に治療へ踏み出すことが重要です。治療の第一歩として、医療機関や訪問看護の相談窓口に話してみることから始めましょう。
アルコール依存症の治療の流れ

治療のステップとカリキュラム
アルコール依存症の治療は、身体的な回復だけでなく、心理面や社会的な立て直しを含めた長期的なサポートが必要です。治療は大きく分けて「解毒治療」「リハビリ治療」「アフターケア」という3つのステップで進められます。それぞれの段階で、医療・薬・心理支援がバランスよく行われることが大切です。
①体からアルコールを抜く「解毒治療」
最初のステップは、アルコールを体から抜く「解毒治療」です。離脱症状(手の震え・発汗・不眠・焦燥感など)を和らげるために、抗酒薬や鎮静剤などを使いながら慎重に行われます。医師や看護師による24時間体制の管理が行われることも多く、安全に離脱を進めるための重要な段階です。
この時期は、身体的な依存を断ち切るとともに、再飲酒を防ぐための心理的な準備を整える期間でもあります。無理に自己判断で断酒を試みると、重い離脱症状やけいれんなどが起こる危険があるため、必ず医療機関で専門的なケアを受けましょう。
②生活を立て直す「リハビリ治療」
解毒治療が終わると、次は心と生活を整える「リハビリ治療」に入ります。この段階では、カウンセリングやグループセラピー、社会復帰のための生活訓練などが行われます。再発しやすいアルコール依存症では、薬だけでなく、心理的な支援や社会的なつながりを取り戻すことが非常に重要です。
また、家族との関係を修復したり、就労に向けた準備を進めたりするなど、生活全体の再構築を目指します。リハビリ治療の期間は個人差がありますが、焦らず自分のペースで進めることが大切です。
③再発を防ぐための「アフターケア」
治療が完了しても、再発防止のためのケアは続きます。退院後は定期的に通院し、服薬管理や心理的サポートを受けながら生活を維持します。同じ悩みを抱える人たちと交流する自助グループ(AAなど)に参加することで、モチベーションを保ち、断酒の継続につながる安心感を得られます。
また、家族もサポートを受けることで、依存症への理解が深まり、より良い支援環境を整えることができます。地域によっては、NPO法人や行政の相談窓口なども利用可能です。
NPOや自助グループなどの特定非営利活動法人に相談してみる
アルコール依存症の治療では、NPO法人や自助グループが大きな役割を果たしています。特定非営利活動法人「ASK」などでは、依存症や再発防止をテーマにした講演・集会を開催しており、本人や家族が安心して相談できる場を提供しています。
こうした団体では、同じ経験を持つ人たちとの交流を通して、自分の状態を理解し、希望を見つけることができます。「一人で抱え込まない」ことが回復の第一歩です。家族や支援者も一緒に話を聞ける機会が設けられている場合もあり、安心して参加できます。
ご自宅で受けられる精神科訪問看護
| サービス名 |
 精神科訪問看護 |
|---|---|
| 職種 |
 ・看護師 ・准看護師 ・作業療法士 |
| 訪問日数 |
 原則週1〜3回(※体調により調整可) |
外出が難しい方や、入退院を繰り返している方には、精神科訪問看護の利用もおすすめです。医師の指示のもと、看護師や作業療法士が自宅を訪問し、服薬や生活支援、家族への助言などを行います。訪問は医療保険を使って週1〜3回、1回あたり30〜90分の範囲で実施され、安心して自宅で療養を続けられる環境を整えられます。
断酒治療や再発防止の継続支援としても活用されており、「病院には通いづらい」「家族に迷惑をかけたくない」といった方にも適した選択肢です。まずは医師や地域の相談窓口、シンプレ訪問看護ステーションへお気軽にご相談ください。
精神疾患や依存症のサポートならシンプレ訪問看護ステーションへ

シンプレ訪問看護ステーションの特徴
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神疾患や依存症をお持ちの方が自宅で安心して過ごせるよう、医療の専門チームが継続的にサポートを行っています。精神科に特化した訪問看護として、医師やご家族と連携しながら、一人ひとりの生活状況や症状に合わせたケアを提供しています。
訪問看護では、症状の観察や服薬管理、日常生活のサポートのほか、退院後の再発予防や社会復帰の支援も行っています。また、利用者ご本人だけでなく、ご家族への支援も大切にしており、相談やアドバイスを通して安心できる生活環境づくりをお手伝いしています。
病状やライフスタイルに合わせて訪問回数を調整できるのも特長です。週1〜3回を基本に、必要に応じて回数や時間を延長することも可能です。土日や祝日も対応しているため、働く世代の方やご家族の介護負担を減らしたい方にもご利用いただけます。
対応している精神疾患と依存症
・酒類(アルコール)に依存する
・アルコール中心の生活になってしまう
統合失調症
・幻覚や妄想という症状が特徴的
・生活に支障をきたしてしまう
うつ病
・気分の落ち込みや意欲の低下
・体のだるさや痛み
その他精神疾患全般
シンプレでは、アルコール依存症をはじめとする依存症や、幅広い精神疾患に対応しています。薬の服用管理や体調観察を行うことで、症状の悪化を防ぎ、安定した生活の維持をサポートします。
また、社会復帰を目指す方や、在宅療養を希望する方のサポートにも力を入れています。訪問時には、医師・保健師・ケースワーカーなど他機関とも連携し、治療の継続や就労支援など、利用者様の目的に合わせた支援を行います。
訪問可能なエリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションは、東京都を中心に広い範囲で訪問サービスを提供しています。今後も訪問エリアを拡大し、より多くの方に専門的なサポートを届けられるよう取り組んでいます。「通院が難しい」「一人では不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
こころの健康に関する問題は、一人で抱え込まずに早めの相談が大切です。電話やお問い合わせフォームからも簡単にご連絡いただけます。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ|アルコール依存症のお薬と治療を正しく理解して一歩ずつ回復へ

アルコール依存症は「意志が弱い」からではなく、脳と身体がアルコールに適応してしまった病気です。治療には時間がかかりますが、薬や心理的サポートを組み合わせることで、確実に回復を目指すことができます。
アルコール依存症の薬として用いられる抗酒薬やアカンプロサートなどは、飲酒を防いだり飲みたい気持ちを抑えたりする効果があり、断酒の継続に大きく役立ちます。これらの薬を医師の指導のもとで正しく使いながら、心理療法や家族・支援者との関わりを続けることが、長期的な回復の鍵です。
また、治療を終えても再発防止のためのケアを続けることが大切です。退院後は自助グループやNPO法人、精神科訪問看護などを利用して、孤立を防ぎ、支え合いながら前向きな生活を取り戻していきましょう。
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神疾患や依存症を持つ方の在宅支援を行っています。服薬管理や生活支援、家族へのサポートを通して、安心して自宅で療養を続けられるようお手伝いしています。訪問は東京23区を中心に、西東京市・三鷹市・府中市・調布市など幅広い地域に対応しています。
アルコール依存症は適切な治療を受ければ回復できる病気です。もし「お酒をやめたいけどやめられない」「治療について相談したい」と感じている方は、一人で悩まずに専門機関や訪問看護ステーションへ相談してください。小さな一歩が、確実な回復への第一歩になります。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (5)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



