アルコール依存症の離脱症状とは?危険性・症状・治療法を徹底解説
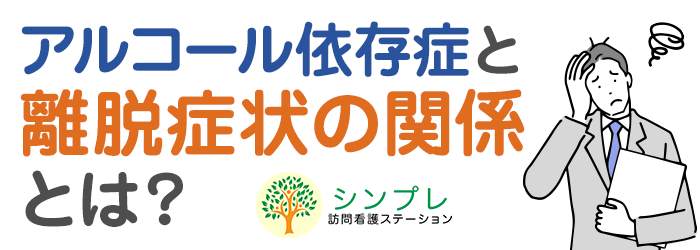

アルコール依存症において特に注意が必要なのが「離脱症状」です。飲酒をやめた直後に起こるこの症状は、単なる不快感にとどまらず、命に関わる危険を引き起こすことがあります。例えば手の震えや不眠といった軽度のものから、けいれんや幻覚、さらにはアルコールせん妄と呼ばれる重篤な状態まで多岐にわたります。アルコール依存症の離脱症状は、適切な治療を受けなければ進行しやすく、家庭や仕事への影響も深刻です。本記事では、離脱症状の仕組みや危険性、症状の流れを詳しく解説し、早期に医療介入が必要な理由をお伝えしていきます。
アルコール依存症の離脱症状はなぜ怖いのか

離脱症状とは?その仕組みと危険性
離脱症状とは、長期的にアルコールを飲み続けていた人が断酒や減酒をした際に現れる身体的・精神的な反応のことです。アルコールは中枢神経を抑制する働きがありますが、依存状態になると体はアルコールありきでバランスを保つようになります。そのため突然お酒を断つと神経が過剰に興奮し、不安・震え・発汗などが出現します。軽度で済む場合もありますが、重度になると幻覚やけいれん、意識障害といった命に関わる症状を引き起こすことがあるため、非常に危険です。
離脱症状が出るタイミング(断酒後6〜72時間がリスク大)
離脱症状は断酒後すぐに出るわけではなく、時間の経過とともに強まるのが特徴です。
離脱症状は最後の飲酒から6〜24時間後に初期症状(手の震え、発汗、不安)が出現し、12〜48時間後には幻覚が、48〜96時間後にはアルコール離脱せん妄(振戦せん妄)のリスクが最も高まります。ただし個人差が大きく、予測は困難です。
特にアルコール依存症が進んでいる人ほど症状は深刻化しやすいため、断酒の際は必ず医師や専門機関のサポートを受けることが推奨されます。
離脱症状の主な症状(震え・発汗・不眠・不安感・けいれん・幻覚)
離脱症状の代表的な症状として、手足の震え、寝汗、強い不安感、焦燥感、不眠などが挙げられます。進行すると全身のけいれんや幻覚・幻聴、さらには意識がもうろうとする状態になることもあります。こうした症状は本人にとって非常につらいだけでなく、家族にとっても大きな負担となります。特に幻覚や妄想を伴う場合、暴力や事故につながる危険性もあり、専門的な治療や管理が不可欠です。
重症化すると起こること(アルコールせん妄・死亡リスク)
離脱症状が重症化すると「アルコールせん妄」と呼ばれる状態に至ることがあります。これは幻覚や妄想、見当識障害(時間や場所が分からなくなること)などが急激に出現し、興奮や徘徊を伴う危険な症状です。アルコールせん妄は放置すると死亡につながる可能性があるため、緊急の医療介入が必要です。断酒はアルコール依存症を克服するために不可欠ですが、その過程で離脱症状が起こるリスクを正しく理解し、安全に治療を進めることが重要です。
アルコール依存症の症状と進行段階

依存症の流れ(初期 → 中期 → 末期)
アルコール依存症は、徐々に進行する病気です。最初は「少し飲みすぎかな」と思う程度でも、飲酒習慣が固定化すると次第に生活の中心がお酒になっていきます。初期には飲酒量の増加や隠れ飲酒がみられ、中期では耐性がついて以前の量では酔えなくなり、離脱症状が出現します。そして末期になると、肝硬変や膵炎などの身体疾患や、家庭・社会生活の崩壊を招くケースもあります。このように、アルコール依存症は進行性の病気であり、放置すると深刻な結果をもたらす点に注意が必要です。
初期症状(飲酒量増加・隠れ飲酒・ブラックアウト)
初期段階では、お酒を飲む量や頻度が徐々に増え、隠れて飲酒する行動が出てきます。また、飲酒後に記憶が途切れる「ブラックアウト」も見られるようになります。こうした初期症状は「単なる飲みすぎ」と見過ごされがちですが、依存症のサインである可能性が高いため、早期に気づくことが大切です。アルコール依存症の進行を食い止めるには、この段階で医療機関や専門家に相談するのが理想です。
中期症状(耐性・離脱症状の出現・飲酒中心の生活)
中期に入るとアルコールへの耐性が進み、以前と同じ量では酔えなくなります。そのため飲酒量はますます増加し、飲まないと体調が悪化する「離脱症状」が現れるようになります。震えや不安、不眠、発汗などは代表的な症状で、仕事や家庭生活にも深刻な影響を与えます。さらに飲酒が生活の中心となり、人間関係の悪化や社会的信用の喪失につながる危険もあります。この時期には断酒の必要性が高まりますが、自己判断でやめると重篤な離脱症状を引き起こすリスクがあるため、医療的サポートが欠かせません。
末期症状(肝硬変・膵炎・精神症状・家庭崩壊)
末期に入ると、身体的にも精神的にも深刻なダメージが現れます。肝硬変や膵炎といった臓器障害に加え、うつ病や幻覚・妄想などの精神症状が強くなり、日常生活を送ることが困難になります。家庭内では暴言や暴力、経済的な問題が重なり、家庭崩壊を招くことも少なくありません。アルコール依存症を放置すれば命に関わる病気に進展するため、末期に至る前に治療を開始することが何より重要です。
アルコール依存症によってリスクが高まる疾患
アルコール依存症は、心身にさまざまな合併症を引き起こします。特に以下の疾患は発症リスクが高まりやすく、健康被害を拡大させる要因となります。
肝硬変
肝硬変は、長期間の飲酒によって肝臓に慢性的な炎症が生じ、組織が硬化していく病気です。肝臓の機能が低下すると、黄疸や腹水、さらには肝がんのリスクも高まります。アルコール依存症では肝硬変の進行が早まりやすいため、特に注意が必要です。
糖尿病
アルコールはインスリンの働きを阻害し、血糖値を不安定にさせる作用があります。過剰な飲酒を続けると糖尿病を発症するリスクが高まり、合併症として失明や手足の壊死など重篤な症状を引き起こす可能性があります。
がん
アルコールの分解過程で発生する物質は発がん性を持つことが知られており、口腔がん・食道がん・肝がんなどのリスクを上昇させます。また免疫力の低下も重なり、がん全般にかかりやすくなる点も見逃せません。
アルコール依存症は治る?治療の流れを解説

断酒と節酒の違い(依存症は断酒が基本)
アルコール依存症の治療において大切なのは「断酒」であり、「節酒」では改善は難しいとされています。なぜなら、依存症の人は少量でも飲むとコントロールを失い、再び大量飲酒へと戻ってしまうからです。節酒を繰り返すうちに依存症が進行し、離脱症状も悪化していきます。したがって、アルコール依存症の根本的な治療は断酒の継続であり、本人の意思だけではなく医療機関や家族、専門的サポートの協力が欠かせません。
アルコール依存症の治療は入院が基本
アルコール依存症が進行し離脱症状が強く出ている場合は、入院治療が基本となります。入院することでアルコールを完全に断った環境を作り、まずは「解毒治療(デトックス)」を行います。解毒期には震えや不眠、発汗などの離脱症状が現れますが、医療スタッフの管理下であれば安全に乗り越えることができます。その後は「リハビリ治療」として心理療法や生活習慣の改善プログラムに取り組み、再び飲酒に戻らないよう支援していきます。自己判断で断酒すると重度の離脱症状から命に関わる危険があるため、専門施設での治療が不可欠です。
アルコール依存症に用いられる薬の種類
薬物療法はアルコール依存症の治療において重要な役割を果たします。代表的な薬には以下のようなものがあります。
飲酒欲求を抑える薬(アカンプロサート)…脳内のバランスを整え、飲酒への衝動を和らげます。
飲酒量を減らす薬(ナルメフェン)…依存症の進行を抑え、断酒につなげる効果が期待されます。
これらの薬は単独で治療を完結させるものではなく、心理療法や生活支援と組み合わせて使用されます。副作用の可能性もあるため、必ず医師の指示のもと適切に使用することが重要です。
退院後のアフターケア(再発予防プログラム・自助グループ)
入院治療を終えた後も、アルコール依存症は再発リスクが高いため継続的なケアが必要です。退院後は通院による経過観察や、薬物療法の継続が行われます。また、自助グループへの参加も効果的です。同じ経験を持つ仲間と交流することで孤立感を防ぎ、断酒継続のモチベーションを高めることができます。家族も支援を受けることで、適切な対応方法を学びながら本人の回復を支えることができます。
再発のリスクと長期的治療の重要性
アルコール依存症は慢性かつ再発性の病気であり、短期の入院や一時的な断酒で完全に治るものではありません。ストレスや人間関係の影響で再び飲酒衝動が高まり、再発につながるケースは少なくありません。そのため、治療は長期的に継続することが大切です。医師や訪問看護師、家族が連携し、断酒を支え続ける体制を整えることで、安定した生活を取り戻すことができます。アルコール依存症の治療は「継続」が最大のポイントであり、焦らず段階的に進めていくことが回復への道となります。
訪問看護でアルコール依存症の治療をサポート

アルコール依存症は1人では治せない?
アルコール依存症は「意志の弱さ」ではなく病気であり、1人での克服は非常に困難です。飲酒をやめようとしても強い欲求や離脱症状が立ちはだかり、再び飲酒に戻ってしまうケースが多いのです。そこで必要になるのが、医療機関や専門スタッフによる継続的なサポートです。特に訪問看護は、自宅にいながら専門的な支援を受けられるため、再発予防や生活の安定に大きな役割を果たします。「依存症は1人で治すものではなく支援と共に回復していくもの」という意識を持つことが重要です。
訪問看護とはどんなサービスか
訪問看護とは、看護師や作業療法士といった専門職が、医師の指示に基づき利用者の自宅を訪問して支援を行うサービスです。通院が難しい方や入院を繰り返してしまう方でも、自宅で継続的に医療ケアを受けられるのが大きな特徴です。病状の観察や生活習慣の改善指導だけでなく、家族へのサポートも行うため、安心して治療に専念できる環境を整えることができます。
訪問看護でできること
服薬指導 … 飲み忘れや過量服薬を防ぎ、正しい服薬習慣を定着させます。
生活習慣の改善サポート … 睡眠・食事・日中活動のリズムを整え、再発予防につなげます。
家族への支援 … 接し方のアドバイスや相談対応を行い、家族の不安を軽減します。
訪問看護では、アルコール依存症特有の離脱症状や再発リスクを把握しながら、本人と家族を包括的に支えることができます。特に断酒直後の不安定な時期においては、生活リズムを支え、薬の管理を徹底することで再飲酒を防ぐ効果が期待できます。「日常生活の中で支援が届くこと」こそが訪問看護の大きな魅力です。
訪問看護が向いている人(退院直後・通院困難・家族サポートが必要な方)
訪問看護は、退院直後で生活リズムが不安定な方、外出や通院が困難な方、また家族によるサポートが難しい環境にある方に特に適しています。病院での治療から在宅生活へと移行する時期は再発リスクが高く、支援が途切れると依存症が悪化しやすくなります。そのため、訪問看護を利用することで「治療の継続性」を確保し、安心して社会復帰へ向けて歩みを進めることができるのです。
アルコール依存症の治療ならシンプレ訪問看護ステーションへ

当ステーションの特徴と取り組み
シンプレ訪問看護ステーションは、精神科に特化した訪問看護サービスを提供しています。アルコール依存症は進行すると離脱症状や身体疾患を伴い、生活への影響が大きくなります。当ステーションでは、看護師や作業療法士など専門職が定期的にご自宅を訪問し、利用者様の症状や生活状況に合わせたきめ細やかなサポートを行います。再発予防・服薬支援・家族支援などを通じて、安心して治療を継続できる環境を整えています。
利用の流れ(相談 → 医師の指示書 → 契約 → 訪問開始)
ご利用の流れはシンプルで、まずはご相談いただくところから始まります。その後、主治医からの「訪問看護指示書」が発行され、契約を経て訪問がスタートします。訪問は1回あたり30分~90分、週1〜3回を基本とし、必要に応じて回数を増やすことも可能です。祝日や土曜日も訪問を行っているため、生活リズムに合わせた柔軟なサポートを受けられます。入院から在宅へ移行する過程で支援が途切れないことが、安心して断酒生活を継続できる大きなポイントです。
対応エリアのご紹介
シンプレ訪問看護ステーションでは、東京23区・西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・東久留米市および埼玉県の一部地域を中心に訪問を行っています。近隣の市区町村にお住まいの方も、対応できる場合がありますのでお気軽にご相談ください。地域に根差したサービスを展開し、必要な方に確実にサポートを届けることを大切にしています。
利用者の声や実際の事例紹介
実際にシンプレを利用された方からは「退院直後の不安な時期に寄り添ってもらえた」「服薬の管理を一緒にしてもらい再発を防げた」「家族も接し方を学べて安心した」など、多くの感謝の声をいただいています。アルコール依存症の治療は長期的な支援が必要であり、訪問看護があることで孤立感を減らし、社会復帰への道を支えられるのです。離脱症状に苦しんでいても、専門職による見守りと助言があれば一歩ずつ回復へ進むことが可能です。
まとめ|アルコール依存症の離脱症状は命に関わるため早期治療が必要
ご相談の問い合わせはこちら▼

離脱症状は早急な医療介入が不可欠
アルコール依存症を放置すると、断酒の際に離脱症状が発生します。震えや不眠、不安感などから始まり、重症化すると幻覚やけいれん、アルコールせん妄に至ることもあります。これらは時に命に関わる危険な状態です。離脱症状は「我慢すれば治る」ものではなく、医療介入が必要な緊急事態であると理解しておくことが大切です。特に断酒を決意した初期段階は危険度が高いため、必ず専門機関のサポートを受けましょう。
アルコール依存症は進行性の病気で放置は危険
アルコール依存症は進行性の疾患です。初期段階では飲酒量の増加やブラックアウトといった症状ですが、中期になると離脱症状が常態化し、飲酒を繰り返す悪循環に陥ります。そして末期には肝硬変や膵炎など深刻な臓器障害や、幻覚・妄想などの精神症状を伴い、社会生活の維持が困難になります。「気づいたときには手遅れ」にならないためにも早期発見と早期治療が不可欠です。
入院・薬物療法・心理療法・訪問看護を組み合わせた治療が効果的
アルコール依存症の治療は、単一の方法では不十分であり、入院による解毒治療、薬物療法による飲酒欲求のコントロール、心理療法による再発防止への意識づけ、さらに訪問看護による日常生活支援を組み合わせることで効果を発揮します。特に訪問看護は、自宅にいながら専門的な支援を受けられるため、退院後の再発予防や生活リズムの安定に大きな役割を果たします。アルコール依存症は長期的な治療が前提となるため、このような包括的支援が欠かせません。
シンプレ訪問
看護で安心して回復をサポートできる
シンプレ訪問看護ステーションでは、アルコール依存症の方やそのご家族に寄り添い、退院直後から在宅生活に至るまで切れ目のない支援を提供しています。服薬指導や生活習慣の改善支援、家族へのアドバイスを行い、再発防止と社会復帰をサポートしています。対応エリアは東京23区・西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・東久留米市および埼玉県の一部地域です。近隣にお住まいの場合もご相談いただければ対応可能な場合があります。アルコール依存症と向き合い、離脱症状を安全に乗り越えるために、ぜひ私たちシンプレにご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼

高座渋谷つばさクリニック
医師:武井智昭
外来としてはうつ病(うつ状態)が年間300名程度はおりこちらが得意分野です。この他に、思春期特有の対応(起立性調節障害や拒食症など)も行っています。心療内科としては10年、日本精神神経学会会員に所属
本記事へのコメント
アルコール依存症は本人の意志の弱さではなく、脳の病気です。
特に重要なのは、離脱症状への対応です。長期・大量飲酒者が急に断酒すると、手の震えから始まり、重症化すれば幻覚やけいれん、意識障害など生命に関わる状態になることがあります。ご本人が「お酒をやめる」と言い出したとき、良い決意ですが、必ず事前に医療機関に相談してください。
ご家族にお願いしたいのは、本人を責めたり説教したりせず、治療につなげることに専念していただくことです。また、お酒を隠す、問題行動の後始末をするなどの行為は、かえって依存症を長引かせます。
ご家族自身も疲弊されていることと思います。家族会への参加や専門家への相談を通じて、ご自身のケアも大切にしてください。
いつでも医療スタッフは家庭での対応などにバックアップしていきます。
監修日:2025年11月18日
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



