解離性同一性障害(DID)とは?原因・症状・治療法をわかりやすく解説
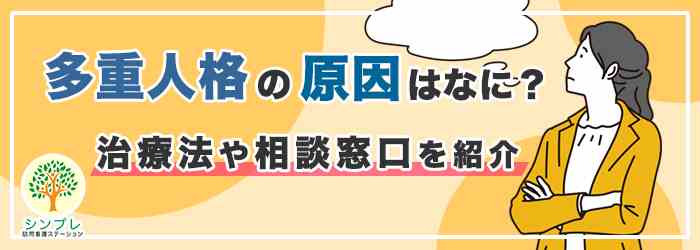

一般に「多重人格」と呼ばれ、映画や小説の中の出来事のように誤解されがちですが、正式には解離性同一性障害(DID)と呼ばれる実在の精神疾患です。
一人の人の中に複数の人格が存在し、記憶が途切れることもあるため、日常生活に大きな影響を及ぼします。その背景には、幼少期の虐待やネグレクト、強い人間関係のストレスなど、深刻な体験が関係していることが少なくありません。
この記事では、解離性同一性障害の原因を中心に、症状や治療法、相談窓口について詳しく解説します。
解離性同一性障害(多重人格)の原因

幼少期の過酷な体験(虐待・ネグレクトなど)
解離性同一性障害の原因として最も多いのは、幼少期に受けた虐待やネグレクトです。
子どもはまだ心が未発達で、耐え難い体験に直面すると、自分を守るために記憶や感情を切り離すことがあります。こうした防衛反応の積み重ねが、やがて人格の分裂を生み出すと考えられています。
「本来なら安心できるはずの家庭」で裏切られる体験は、後の人生に深刻な影響を残すのです。
人間関係でのつらい経験(いじめ・DVなど)
成長の過程で受ける強いストレスも、解離性同一性障害の原因になり得ます。
学校でのいじめや職場でのパワハラ、配偶者からのDVなどは、長期間続くことで心に大きな傷を残します。こうした状況に置かれると、本人は「別の人格」に痛みを背負わせることでバランスを取ろうとし、解離性同一性障害を発症することがあります。
死を予感するような強いトラウマ体験
交通事故や自然災害、犯罪被害など、命の危険を感じる体験もトラウマとなり、解離症状を引き起こすことがあります。
死を間近に感じるほどの恐怖は、記憶を切り離して心を守ろうとする反応を強め、それが人格の分裂につながる場合があるのです。
発症のリスク要因(遺伝・環境・性格傾向)
解離性同一性障害はトラウマ体験が主因ですが、すべての人が同じ状況で発症するわけではありません。
繊細で感受性が強い人や、家族環境が不安定な人はリスクが高いとされています。また、遺伝的な要因が関わる可能性も指摘されています。
なぜトラウマが解離性同一性障害につながるのか(発症のメカニズム)
強いトラウマを経験すると、人はその出来事を自分の一部として受け入れられず、記憶や感情を切り離して「別の人格」が体験したかのように処理してしまうことがあります。
この解離のメカニズムが繰り返されることで複数の人格が形成され、結果として解離性同一性障害へと発展していくのです。
解離性同一性障害(多重人格)の主な症状

健忘(記憶の抜け落ち)
解離性同一性障害では、特定の記憶が欠落する「解離性健忘」がよく見られます。
これは単なる物忘れとは異なり、特定の期間や出来事に関する記憶が丸ごと抜け落ちてしまうのが特徴です。
例えば、幼少期の虐待の記憶や、数週間〜数か月にわたる生活の記録が完全に消えてしまうケースがあります。本人はその記憶の欠落に気づかないことも多く、家族や友人からの指摘や日記、写真を通じて初めて気づくことも少なくありません。
複数の人格の出現
解離性同一性障害の代表的な症状が、複数の人格の出現です。
これは健忘と連動して現れることが多く、日常生活の中で突然「別の人格」が前に出てくることがあります。人格の入れ替わり方には、大きく分けて憑依型と非憑依型の2種類があります。
憑依型
憑依型では、他人から見ても人格が変わったことがはっきりわかります。
普段とは異なる口調や態度を示したり、まるで他人が乗り移ったかのような行動を取ったりするため、周囲にも強い違和感を与えます。
時には過去に亡くなった人物や宗教的存在などが人格として現れることもあります。
非憑依型
一方、非憑依型は外から見ると人格交代が目立ちにくいのが特徴です。
本人の中では「自分が自分ではない」という感覚が強く、ドラマや映画の登場人物のように、自分を客観的に眺めているかのような体験をします。外見上は自然に見えるため、気づかれにくいケースもあります。
その他の症状
解離性同一性障害では、記憶や人格の問題に加えてさまざまな症状が現れます。代表的なのは以下のようなものです。
・気づけば数時間〜数日が経過している
・予定していない場所にいることがある
身体感覚の変化
・強い頭痛や体のしびれ
・自分の身体が自分のものではない感覚
解離症状(現実感の喪失など)
・自分が現実から切り離されているように感じる
・周囲の世界が夢や映画のように見える
これらの症状は、強いストレスや過去のトラウマが引き金となって現れることが多いです。
症状の現れ方は人それぞれで、日常生活に支障をきたすほど重度になることもあります。解離性同一性障害の原因が心の防衛反応にある以上、症状は「自分を守るために無意識に行われている」という点を理解することが大切です。
また、解離性同一性障害は診断が非常に難しく、他の精神疾患(境界性パーソナリティ障害、PTSD、統合失調症など)と誤診されることもあり、専門的な評価を受けることが重要です。
解離性同一性障害(多重人格)の治療方法

解離性同一性障害の治療は長期にわたり、完全な「人格の統合」を目指すかどうかは議論があります。
近年では「人格の統合」よりも「各人格間の協調」を目標とするアプローチも重視されています。
焦らず、ご自身のペースで回復を目指すことが大切です。
心理療法(トラウマに向き合う治療)
解離性同一性障害の中心となる治療は心理療法です。
患者さんと治療者との間に信頼関係を築き、複数の人格と向き合いながら、根底にあるトラウマ体験を少しずつ処理していきます。暴力や虐待といった環境が続いている場合は、まず安全な環境を確保することが前提です。
トラウマに正面から向き合う作業には時間がかかりますが、本人の安心感を土台に少しずつ進めていくことが重要です。
リラクセーション法(不安や緊張の緩和)
治療を継続することが難しい場合でも、リラクセーション法は不安や緊張の軽減に役立ちます。
呼吸法や筋弛緩法、イメージトレーニングなどを通じて、自分の心と体を落ち着かせる練習をします。アロマや音楽を取り入れることでリラックス効果を高めることも可能です。こうした方法は、日常生活でストレスを和らげるセルフケアにもつながります。
薬物療法(不安・抑うつへの対処)
解離性同一性障害の原因そのものを取り除く薬は存在しませんが、不安やうつなどの症状を和らげるために薬物療法が用いられることがあります。
抗うつ剤や抗不安薬が処方され、症状を一時的に抑える役割を果たします。これはあくまで補助的な治療であり、根本的な改善には心理療法が欠かせません。
家族への支援と理解
患者さんの回復には家族の理解と支えも大切です。
解離性同一性障害の症状は周囲から誤解されやすいため、家族が正しい知識を持つことが必要になります。専門家による家族向けのカウンセリングやサポートを受けることで、家庭内での安心できる環境を整えることができます。
長期的な治療の必要性
解離性同一性障害は短期間で治るものではなく、長期にわたる治療が必要です。
治療の過程で症状が変化することもありますが、焦らずに取り組むことが大切です。「解離性同一性障害は原因を理解し、長い時間をかけて回復を目指す疾患」であるという意識を持つことで、治療を続けやすくなります。
解離性同一性障害の相談先は?

専門家による相談窓口
解離性同一性障害の症状が疑われる場合、まずは専門機関への相談が大切です。
解離性同一性障害の原因が過去のトラウマや人間関係のストレスにあることが多いため、専門的な治療や支援が必要となります。
地域ごとに設置されている窓口では、精神科医や看護師、精神保健福祉士などの専門職が相談を受け付けており、安心して利用できます。
精神科病院・クリニック
精神科病院やクリニックでは、医師による診察とカウンセリングを受けられます。
症状に応じて心理療法や薬物療法が行われ、継続的な治療を進めることが可能です。初めての相談先としても利用しやすい機関です。
保健所、保健センター
地域住民の健康を守る役割を担う保健所や保健センターでも、心の健康に関する相談を受け付けています。
必要に応じて専門医療機関への紹介や、グループ活動・デイケアといった地域支援サービスに繋げてもらえることがあります。
精神保健福祉センター
都道府県に設置されている精神保健福祉センターでは、精神疾患全般についての相談を行えます。
精神科医や心理士、精神保健福祉士などが在籍しており、治療や生活支援の相談に対応しています。
いのちの電話
「いのちの電話」は、悩みを抱える人が匿名で利用できる相談窓口です。
24時間365日対応しており、強い孤独感や絶望感に押しつぶされそうなときでも、専門の相談員が耳を傾けてくれます。個人情報を伝える必要がないため、安心して利用できるのも特徴です。
精神科訪問看護を利用するという選択肢もある
外出や通院が難しい方には、精神科訪問看護の利用も選択肢のひとつです。
訪問看護師や作業療法士が自宅を訪問し、服薬のサポートや生活支援を行います。「自宅で安心して療養を続けられる」というメリットがあり、ご本人だけでなくご家族の負担軽減にもつながります。解離性同一性障害の原因が過去の体験にある場合、家庭という安心できる環境でサポートを受けられることは大きな意味を持ちます。
精神疾患をお持ちならシンプレ訪問看護ステーションへ

当ステーションの特徴
解離性同一性障害(多重人格)は、原因が幼少期のトラウマや人間関係によるストレスなど複雑に絡み合っており、治療やケアには時間と専門的なサポートが必要です。
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神科に特化した訪問サービスを行い、ご自宅にいながら安心して看護を受けられる環境を提供しています。
看護師・准看護師・作業療法士といった専門スタッフが訪問し、服薬支援や生活支援、社会復帰へのサポートを行います。ご本人だけでなく、ご家族への支援も大切にしている点が特徴です。
精神疾患の一例(うつ病・統合失調症・解離性障害など)
シンプレが対応している精神疾患は幅広く、解離性同一性障害を含む解離性障害、うつ病、統合失調症、PTSD、発達障害、自閉スペクトラム症、認知症などさまざまです。
症状は人によって異なり、気分の落ち込みや幻覚、強い不安など多岐にわたります。精神疾患は「本人だけでなく家族や生活全体に影響を及ぼす疾患」であるため、医療と生活支援をつなげる訪問看護の存在が重要となります。
シンプレの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションは、東京都23区をはじめ、西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・東久留米市、さらに埼玉県の一部地域に対応しています。
近隣の市区町村でも訪問できる場合がありますので、まずはご相談ください。週1〜3回を基本とした訪問ですが、状況に応じて週4回以上の対応も可能です。祝日や土曜日の訪問にも対応しているため、柔軟に利用できます。
訪問時間は1回あたり30分〜90分で、患者さんの症状やご希望に合わせて調整します。
退院支援や服薬管理、生活支援、再発予防、家族へのケアなど、多角的なサポートを提供しています。また、胃ろうやカテーテル管理、ストーマ、褥瘡ケア、在宅酸素療法、緩和ケアなどの医療的処置にも対応可能です。
さらに、自立支援医療制度や生活保護など、利用できる制度の案内も行っており、経済的な負担を軽減しながら安心してサービスを受けられるよう支援しています。
解離性同一性障害の原因となる過去の体験やトラウマに向き合うには、長期的なサポートが欠かせません。シンプレでは専門的な視点から、利用者一人ひとりに寄り添った看護を心がけています。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

解離性同一性障害の原因は幼少期のトラウマが大きい
ここまで解離性同一性障害(多重人格)について解説してきました。解離性同一性障害の原因として最も大きいのは、幼少期に受けた虐待やネグレクトといった深刻なトラウマです。
そのほかにも、いじめやDV、事故や災害による死を予感する体験など、強いストレス体験が引き金になることがあります。こうした体験は心を守るための防衛反応を生み、それが人格の分裂へとつながっていくのです。
早期の治療と相談が回復のカギ
症状としては、健忘や人格交代、時間感覚の喪失、現実感の喪失などが現れます。これらは日常生活に大きな支障をきたすため、できるだけ早い段階で専門家に相談することが重要です。
心理療法を中心とした治療が行われ、不安や抑うつには薬物療法が補助的に用いられることもあります。回復には時間がかかりますが、適切なサポートを受けながら継続することで改善の可能性が高まります。
専門機関や支援を活用しよう
解離性同一性障害に悩んでいる場合、精神科クリニックや精神保健福祉センター、保健所などの専門機関に相談することが第一歩となります。
さらに、通院が難しい場合には精神科訪問看護の利用も有効です。専門職が自宅に訪問し、服薬支援や生活支援、再発予防に取り組んでくれるため、ご本人やご家族の負担を軽減できます。
シンプレ訪問看護ステーションでは、東京23区や西東京市、埼玉県の一部地域など幅広く対応し、患者さんの生活に寄り添った支援を行っています。
解離性同一性障害の原因は一人ひとり異なり、症状の出方もさまざまです。しかし、孤独に苦しむ必要はありません。
専門家や支援機関とつながることで、少しずつでも安心できる生活を取り戻すことができます。自分や大切な人が悩んでいると感じたら、まずは相談窓口に連絡を取り、信頼できるサポートを受けることから始めましょう。
ご相談の問い合わせはこちら▼

高座渋谷つばさクリニック
医師:武井智昭
外来としてはうつ病(うつ状態)が年間300名程度はおりこちらが得意分野です。この他に、思春期特有の対応(起立性調節障害や拒食症など)も行っています。心療内科としては10年、日本精神神経学会会員に所属
本記事へのコメント
解離性同一性障害(DID)は、幼少期の深刻なトラウマ体験から心を守るために生じた、脳の適応反応です。「意志が弱い」「演技」ではなく、れっきとした医学的疾患です。
診断には専門的な評価が必要で、他の精神疾患と見分けることも容易ではありません。治療には長い時間がかかりますが、焦らず一歩ずつ進むことが大切です。
最近では「人格の完全な統合」よりも「各人格が協調して生活できること」を目指す治療も重視されています。
家族が症状を理解することは難しいですが、ご本人は苦しみながら懸命に生きています。責めるのではなく、専門家と連携しながら見守る姿勢が回復の支えになります。
決して一人で抱え込まず、精神科専門医や訪問看護などの支援を活用してください。安心できる環境の中で、回復への道は開けていきます。
監修日:2025年11月21日
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (5)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



