産後うつの治療が重要な理由。治療法や相談できる場所について知ろう
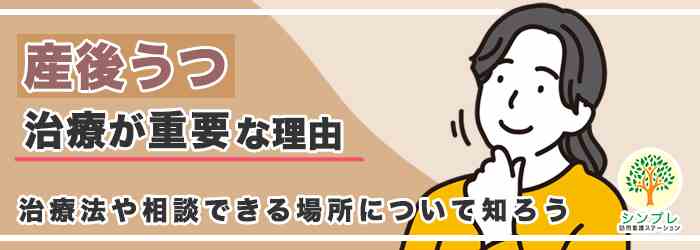
産後うつの治療方法をお探しですか?産後は急激なホルモンの変化によって精神状態が不安になりやすい傾向にあります。
産後うつを治療せずに放置してしまうと、重症化して取り返しのつかない事にため、早期に対策を打たなければいけません。
今回は、産後うつの治療方法や治療を受けるにはどこに相談すればいいのかなどを詳しく紹介します。
産後うつの治療が重要な理由

重症化や再発を繰り返しやすくなるため
産後うつ病は、出産後に発症する代表的な心の病気です。産後数週間から発症リスクが高まり、産後3~6ヵ月以内に発症することが多いと言われています。
症状は、気分が落ち込み、楽しみがなくなり、自分を責めてしまう、食欲がなくなる、眠れない、など、一般的なうつ病と共通した症状が現われます。
また、育児への興味や関心が薄れ、赤ちゃんを虐待してしまうのではないかという不安や恐怖感に襲われることもあります。
産後うつ病は、マタニティブルーズと似ていますが、マタニティブルーズは通常は1~2週間でおさまるのに対し、産後うつ病の症状は2週間以上持続します。
子どもの発達にも悪影響が出るため
産後うつ病は、母親の精神状態が悪化することで、子どもの発達や健康にさまざまな影響を与えることがあります。
具体的には、母親の抑うつ気分や意欲低下によって、育児が十分に行われず、子どもの認知や情緒の発達が遅れる可能性があります。また、睡眠不足や食欲低下によって、母乳の分泌量が減少し、子どもの栄養不足や発育不良につながることもあります。
このように、産後うつ病は母親だけでなく、子どもにとっても深刻な問題となります。早期発見・早期治療によって、症状を改善し、母子ともに健やかな生活を取り戻しましょう。
そもそも産後うつとは?

出産から3ヶ月の間に現れやすいうつ病
産後うつ病は、出産後3ヵ月以内に発症することが多いですが、1年後に産後うつが発症するというケースもあります。産後うつ病の原因はさまざまですが、一般的には、出産による体力の消耗やホルモンバランスの変化が原因と考えられています。
出産後は、体力が低下し、ホルモンバランスが乱れます。そのため、気分が落ち込みやすくなり、育児や今後の生活に対する不安が大きくなることがあります。このような状況が続くと、産後うつ病を発症するリスクが高くなります。
経産婦の内約10~15%が発症
産後うつ病は、日本では約10〜15%の女性が経験すると言われています。誰にでも起こりうる病気なので、早めに気づいて、適切な対処をしましょう。
産後うつ病になりやすい人は、完璧主義で責任感が強く、一人で抱え込もうとする人が多いと言われています。また、家族との関係がうまくいっていない人も発症リスクが高くなります。
産後うつ病を放置すると、症状が悪化し、さらに重い精神病を引き起こす可能性もあります。早期発見・早期治療が大切です。
産後うつの症状にはどんなものがある?
- 極度の悲しみ
- 頻繁に泣く
- 気分の変動
- 易怒性および怒り
産後うつ病になると、気分が落ち込みやすくなり、突然悲しい気持ちになったり、頻繁に泣いたりするようになります。
また、気分の起伏が激しくなり、焦ったり、イライラしたりすることもあります。そのため、精神状態が不安定になり、赤ちゃんとの絆を築くことが難しくなります。
産後うつ病が重症化すると、自殺願望や暴力的な思考、幻覚などの症状が現れることもあります。最悪の場合、子どもを傷つけたいと考えてしまうこともあるのです。
マタニティーブルーズとの違いは?
| 患者の状態 | 産後うつ | マタニティーブルーズ |
|---|---|---|
発症時期 |
・産後1年以内 (発症率10〜15%) |
・産後数日から 2週間程度 (発症率30〜50%) |
経過と対応 |
適切な治療や 周囲の支援が必要 |
大抵は一過性で 産後10日程度で 軽快する |
マタニティーブルーズは、約30-50%の女性が出産後に経験します。また「マタニティーブルー」とも呼ばれます。
出産後、数日から2週間程度の間に、涙が止まらなくなったり、いらいらしたり、落ち込んだりするなどの症状があらわれます。
ほかにも、眠れなくなったり、集中力が低下したり、焦ったりするなどし、情緒が不安定にもなります。
しかしマタニティーブルーズの場合は、産後うつとは違い、多くの場合で産後10日程度で症状が自然に回復します。そのため、過度に心配する必要はありません。
産後うつになってしまう原因は?

出産時のホルモンバランスの乱れ
産後うつの原因は、妊娠中に分泌されていたエストロゲンやプロゲステロンなどの女性ホルモンが、出産をきっかけに急激に減少することが挙げられます。
また、出産後は授乳のためにホルモンバランスが変化し、脳や身体がその変化に対応できずに、自律神経のバランスが崩れてしまい、不安や落ち込みなどの症状が現れやすくなります。
慢性的な睡眠不足と疲労
赤ちゃんは、生後3か月くらいまでは2~3時間ごとに授乳が必要です。また、授乳の合間にも、抱っこ、おむつ替えや沐浴、赤ちゃんのお世話で忙しく、なかなか休息がとれません。
そのため、産後のママは、睡眠時間も休息時間も十分に確保できず、肉体的に疲れ切ってしまいます。さらに、肉体的な疲労は、精神的な不調を増幅させやすく、産後うつにつながってしまうことがあります。
産後うつの予防策として、十分に睡眠や休息をとることが大切です。一人で頑張ろうとせず、パートナーや家族の協力を得て、家事や育児を分担するようにしましょう。
産後は、ママにとって大きな変化の時期です。周囲のサポートをうまく利用して、心身をリラックスさせることも大切です。
育児不安や育児ストレス
出産後は、赤ちゃんの世話や育児に不安を感じる人が多いです。赤ちゃんの泣き声や夜泣きへの対処、赤ちゃんの病気への対応など、さまざまな不安が頭をよぎります。
また、出産後は、家族や友人、職場などから、さまざまな期待や要求が寄せられることもあります。しかし、産後は体調や気持ちが不安定なため、それらをうまく受け止めることができず、ストレスを感じてしまうことがあります。
さらに、育児に対する不安など、自分が「良い母親になれるのか」というプレッシャーも、ストレスとなり、産後うつの発症につながると考えられています。
産後うつの治療方法はどんなもの?

薬物療法
・セロトニン再取り込み阻害薬
・三環系抗うつ薬
一般的に産後うつには、脳内の神経伝達物質が減少しているため「セロトニン再度取り込み阻害剤」を投与し、セロトニンの増加を促します。
もしくは、三環系抗うつ薬を投与し、脳内の神経伝達物質の1つであるノルアドレナリンを増加させます。
授乳中の場合は、母乳を通して赤ちゃんに対しての安全性を配慮が必要です。そのため、断乳指導の上で薬物療法を行う場合があります。
心理療法
・支持的カウンセリング
・対人関係療法
・認知行動療法
薬物療法のほかに、産後うつの治療に対して心理療法も効果的です。心理療法の例としては、支持的カウンセリング、対人関係療法や認知行動療法などがあります。
支持的カウンセリングとは、医師がママのつらさや苦しみについて聞き、専門的な立場からアドバイスや手助けなどをするカウンセリングです。
対人関係療法とは、対人関係に焦点をあて、感情や行動を変化させて問題を解決するカウンセリングです。認知行動療法は、ストレスや否定的な考え方にうまく対処できるように、考え方や行動を修正する心理療法です。
サポート体制の構築
産後うつになった場合、育児や家事をすることは難しくなります。
赤ちゃんへの大きな責任感や、産後うつになったことに対する罪悪感が生まれ、一人で悩んでしまうことが多いです。そのため家族や周りの人のサポートが必要となります。
早期回復には、家族全体でママと子どもをケア・フォローをして、産後うつを治療することが大事です。
産後うつに関する相談先は?

専門家による相談窓口
ここでは産後うつに対して、「こころの健康損統一ダイヤル」や「よりそいホットライン」など専門家による相談窓口についてご紹介します。
こころの健康相談統一ダイヤル
こころの健康相談統一ダイヤルは、自殺の危機に直面している方や、自殺の考えに悩まれている方に対して、お話をお聞きし、自殺を思いとどまらせ、ご家族やご友人の力になっていただくことを目的とした相談窓口です。
各都道府県の病院や保健センターなどが連携し、産後うつに悩まれている方からのご相談をお受けしています。
よりそいホットライン
「よりそいホットライン」とは、生活に苦しいかた、高齢者、外国人、DV、性暴力など社会的に悩んでいるかたに対しての支援をする団体です。
産前産後のママに対して、育児相談だけでなくどんな悩みにも対応してくれます。
いのちの電話
いのちの電話は、あなたの気持ちに寄り添い、一緒に解決策を探す相談窓口です。
さまざまな問題をかかえて孤独と不安に苦しみ、悩み、生きる力をうしないかけている方々に、専門の相談員がじっくり聞いて、あなたの状況を一緒に考え、必要な支援策について一緒に考えます。
生きる意欲を自らみいだせるように心の支えになる団体です。
精神科・心療内科
産後うつはこころの病気です。あてはまることがあれば、ひとりで抱え込むのはなく、精神科や心療内科に相談することが大切です。
医師に相談することで適切な治療やカウンセリングを受けることができます。早めに対処することが大切で、重症化を抑えることもできます。
また、産後うつなどの精神的な症状は、自分では気づきにくいことが多いです。ご家族やパートナーからみて、ママの普段との様子の違いや、気になることがあれば早めに相談したり、受診することを勧めましょう。
精神科訪問看護
| サービス名 | 精神科訪問看護 |
|---|---|
職種 |
・看護師 ・准看護師 ・作業療法士 |
訪問日数 |
原則週3日以内 (※例外もあります。) |
産後うつの方には、精神面でのフォローのほか、身の回りのケアなどが必要なことがあります。
「産後うつと診断された」または「家族が産後うつと診断されたけど、どうしたらよいかわからない」など、ご本人やご家族の困りごとや悩みに対して、自宅で看護を受けられるのが精神訪問看護です。
精神訪問看護では、症状悪化の防止、服薬指導や病気との付き合い方などを一緒に考え、社会復帰を目指したサポートなどを行い、利用者さまに合わせた看護を提供します。
精神疾患をお持ちならシンプレへ

当ステーションの特徴
産後うつへの対応やケアについては、慎重に行うことが必要であり、周囲のサポートが必要不可欠です。
シンプレ訪問看護ステーションでは、特に精神科に特化した訪問看護サービスを展開し、患者さんが自宅でも安心してケアを受けられる看護を提供しています。
患者さんはやはり、「暮らし慣れた自宅でケアを受けながら、赤ちゃんの育児をしたい、または社会復帰を目指したい」と思っています。精神訪問看護はそのような方をお手伝いするサービスです。
またシンプレ訪問看護ステーションでは、患者さんだけでなく、そのご家族の精神的なフォローにも対応し、皆で一緒に前向きに生活を改善していくことを目指しています。
精神疾患の一例
・気分の落ち込み
・何をしても楽しめない
・眠れない・食欲がない・疲れやすい
自閉スペクトラム症
・他人と目を合わせることが苦手
・相手や状況に自分の行動をあわせることが苦手
・言葉の裏の意味や抽象的な言葉の意味を理解するのが苦手
統合失調症
・幻覚や妄想という症状が特徴的
・生活に支障をきたしてしまう
双極性障害
・躁状態とうつ状態を繰り返す
PTSD
・トラウマとなった記憶が突然よみがえる
その他精神疾患全般
シンプレ訪問看護ステーションではさまざまな精神疾患が対象です。
精神疾患とは、産後うつのほかにも、うつ病、自閉スペクトラム症、総合失調症やPTSD、など、気分の落ち込みや幻覚・妄想など心身に様々な影響が出る疾患のことをいいます。
おもな原因としては、脳内の神経伝達物質のバランスが乱れることなどによって起こるとされています。
厚生労働省の調査によると精神疾患のあるかたは、平成29年度で日本国内に約420万人いるとされ、年々増えつづける傾向です。
シンプレの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応地域は主に上記が中心で、訪問活動をおこなっています。該当エリアにお住まいの方はぜひご検討ください。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。電話やメールなどで相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
また、HPのほかにもTwitterやLine、TikTokなどのSNSでも情報を発信していますので、ぜひご覧ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

産後うつの原因や治療方について解説してきました。産後うつは決して発症する可能性が低くはなく、その原因もさまざまです。
出産することは心理的にも、身体的にもつらく、産後うつを発症した場合、一人で悩んでいるかたが大勢いらっしゃいます。そのため家族や周囲のサポートが必要です。
シンプレ訪問看護ステーションでは、そんなママに対して病気のケアや社会復帰への支援を行っています。またご家族へのサポートも行うことで、産後うつに関わる人たちの生活を看護の立場から支援いたします。
産後うつでお悩みの場合には、ぜひシンプレ訪問看護ステーションにご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



