訪問看護における医療保険と介護保険の違い|対象者・費用・申請方法を解説
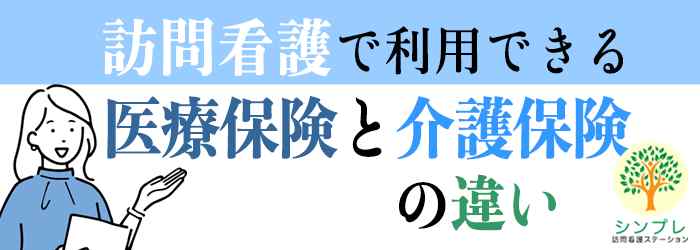

訪問看護は、医療保険や介護保険の制度を利用して受けることができます。
しかし、訪問看護の利用を検討したいと思っていても、医療保険と介護保険の違いが分かりにくく、どちらを使えばよいのか迷う方も少なくありません。
この記事では、それぞれの対象者・利用条件・自己負担額の違いを整理し、制度を上手に活用するためのポイントを解説します。
さらに、シンプレ訪問看護ステーションで利用できる保険制度についてもご紹介しますので、利用を検討中の方はぜひ参考にしてください。
訪問看護における医療保険と介護保険の違いについて
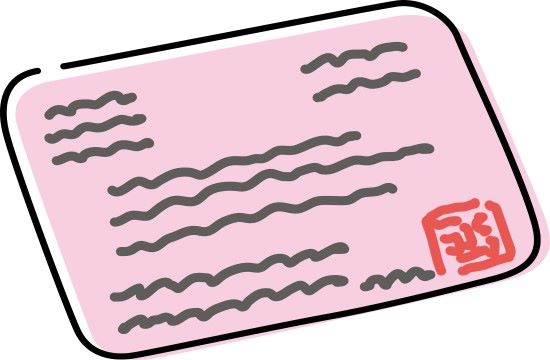
訪問看護で利用する場合の医療保険と介護保険の違い
訪問看護を利用する際には、医療保険と介護保険のどちらかが適用されます。
それぞれの制度は対象者・利用回数の上限・自己負担額が異なるため、状況に応じて正しく選択することが大切です。
以下で具体的に違いを確認していきましょう。
違い①対象者
医療保険は、40歳未満で主治医から「訪問看護指示書」が交付された方や、40歳以上で要介護認定を受けていない方が対象です。
一方、介護保険は65歳以上で要介護・要支援認定を受けている方、または40歳以上65歳未満で特定疾病によって認定を受けた方が対象となります。
違い②利用上限
医療保険では原則として週3回までの訪問が上限です。
ただし、末期がんなど重篤な病気を持つ方や「特別訪問看護指示書」がある場合には、週4回以上の利用も可能です。
一方、介護保険には利用回数の上限はなく、ケアプランに基づいて必要な回数を設定できます。
違い③自己負担額
医療保険では、70歳未満の方は3割負担、70歳から74歳は原則2割、75歳以上は1割負担です。
ただし所得に応じて3割負担となる場合もあります。
介護保険は原則1割負担ですが、一定以上の所得がある方は2〜3割負担となります。
介護予防とは?
介護予防訪問看護は、65歳以上で要支援認定を受けた方が要介護状態になるのを防ぐためのサービスです。
血圧や体温のチェック、リハビリ、医師の指示による処置などを通じて、自立した生活の維持を支援します。
医療保険と介護保険の詳細
・医師が必要と判断
・原則週3回以内
・70歳以上:1~3割
・6~69歳:原則3割
・6歳未満:2割
介護保険
・要介護、要支援認定を受けている(原則65歳以上)
・ケアプランに準じた利用回数
・原則1割(所得に応じて2~3割)
このように、訪問看護は医療保険・介護保険のどちらを利用するかで条件や費用が大きく変わります。
ご自身やご家族の状況に合わせて制度を選ぶことが重要です。
医療保険と介護保険で違いのある申請方法

医療保険と介護保険の申請方法
訪問看護を利用する際には、医療保険と介護保険で申請方法が異なります。
どちらを利用するかによって手続きの流れが変わるため、事前に確認しておくことが大切です。
ここではそれぞれの申請方法について解説します。
①医療保険
・市役所や区役所などで申請
・国民健康保険、社会保険(健康保険)のいずれかに加入
・法的に加入義務あり
医療保険は、国民健康保険と社会保険の2種類に分かれます。
会社員や公務員の場合は勤務先で申請が行われ、保険証が交付されます。
自営業やフリーランスなど職場で保険に加入していない方は、居住地の市町村役場で申請手続きを行います。
申請からおおむね1週間前後で保険証が自宅に届き、訪問看護の利用が可能となります。
②介護保険
・要介護認定や要支援認定を受けた後に申請
・市役所、区役所で手続き
・ケアマネジャーと連携してケアプランを作成
介護保険を利用するには、まず要介護認定・要支援認定を受ける必要があります。
申請は市町村役場や地域包括支援センターで行い、調査を経て約30日で認定結果が通知されます。
その後、ケアマネジャーと相談しケアプランを作成することで、訪問看護を含む介護サービスが利用できるようになります。
注意!2種類の保険の併用は出来ない
訪問看護において、医療保険と介護保険の併用は原則できません。
同一の診断名ではどちらか一方しか適用されない仕組みになっているためです。
ただし、リハビリや介護などサービス内容が異なる場合や、一定期間を空けてからであれば、もう一方の保険に切り替えることは可能です。
・医療保険の訪問看護 + 介護保険の訪問介護
・医療保険の訪問看護 + 介護保険のデイサービス
※特別訪問看護指示期間中は医療保険が全面優先されます。
誤った理解で申請を進めると利用できるサービスが制限される恐れがあるため、必ず専門機関に相談することをおすすめします。
訪問看護で医療保険を適応した場合の料金
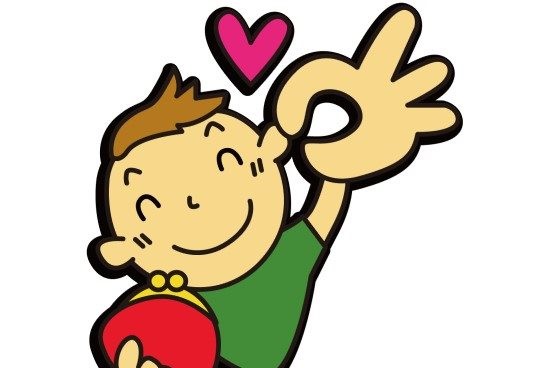
医療保険を適応した訪問看護の料金
| 負担割合 | 月の初回訪問 | 2回目以降 |
|---|---|---|
1割負担 | 1,299円/回 | 855円/回 |
2割負担 | 2,598円/回 | 1,710円/回 |
3割負担 | 3,897円/回 | 2,565円/回 |
上記は週3回までの訪問料金となります。週4回以上訪問となる場合には料金が異なります。
精神科訪問看護では、医療保険を利用することにより自己負担を軽減できるメリットがあります。
30分を一区切りに利用可能。かかった費用については、年齢や所得によって変わり、医療費の1〜3割が自己負担となります。
また早朝や深夜などの時間外に依頼する場合や、長時間の訪問を行う場合は別途料金が発生します。
また自立支援医療制度という制度を利用すると料金が1割負担になるほか、所得に応じて自己負担が0円になる場合もございます。
訪問回数や時間によって料金が変動しますが、保険適応により大幅にコストを抑えられるのが特徴です。
精神科訪問看護の料金(医療保険適応時)
精神疾患を対象とした訪問看護も医療保険の対象となり、1~3割の自己負担で利用できます。
精神科訪問看護では服薬支援や生活支援、症状の悪化防止など幅広いサポートが受けられ、在宅療養を続けやすい体制が整っています。
さらに、精神科訪問看護では公費負担制度の利用が可能で、経済的な負担をさらに減らせる点も大きなメリットです。
自立支援医療(精神通院医療)の利用で自己負担を軽減
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 生活保護 |
0円 |
| 低所得1 |
2,500円 |
| 低所得2 |
5,000円 |
| 中間所得1 |
5,000円 |
| 中間所得2 |
10,000円 |
| 一定所得以上 |
20,000円 |
表の料金は所得に応じた医療費の月額自己負担額の上限額となっております。
表の料金を超えた場合には、自己負担なしで医療が受けられます。
精神科訪問看護を利用する場合は、自立支援医療制度を併用することで自己負担額をさらに抑えられます。
この制度は精神疾患を抱える方の医療費を軽減する仕組みで、医療費が1割負担となるうえ、所得に応じて月ごとの自己負担上限額が設定されます。
上限を超えた分は公費でカバーされるため、利用者の金銭的な安心感につながります。
このように、訪問看護を医療保険で利用する場合は年齢や所得による自己負担割合に加え、
自立支援医療制度を組み合わせることで、より安心して継続的にサービスを受けられます。
経済的負担を抑えながら、自宅での療養や生活を支える強力な制度といえるでしょう。
介護保険を適応した訪問看護の料金

要支援
看護師が訪問を行う場合
| 時間 | 利用料金 (10割) | 負担額 (1割) | 負担額 (2割) |
|---|---|---|---|
30分未満 | 5,130円 | 約513円 | 約1,026円 |
| 30分以上 1時間未満  | 9,029円 | 約904円 | 約1,806円 |
| 1時間以上 1時間30分未満  | 12,392円 | 約1,240円 | 約2,479円 |
作業療法士が訪問を行う場合
| 時間 | 利用料金 (10割) | 負担額 (1割) | 負担額 (2割) |
|---|---|---|---|
20分未満 | 3,226円 | 約323円 | 約646円 |
| 20分以上 40分未満  | 6,452円 | 約645円 | 約1,291円 |
| 40分以上 1時間未満  | 9,679円 | 約969円 | 約1,937円 |
要介護
看護師が訪問を行う場合
| 時間 | 利用料金 (10割) | 負担額 (1割) | 負担額 (2割) |
|---|---|---|---|
30分未満 | 5,358円 | 約536円 | 約1,072円 |
| 30分以上 1時間未満  | 9,359円 | 約936円 | 約1,872円 |
| 1時間以上 1時間30分未満  | 12,825円 | 約1,283円 | 約2,565円 |
作業療法士が訪問を行う場合
| 時間 | 利用料金 (10割) | 負担額 (1割) | 負担額 (2割) |
|---|---|---|---|
20分未満 | 3,340円 | 約334円 | 約668円 |
| 20分以上 40分未満  | 6,680円 | 約668円 | 約1,336円 |
| 40分以上 1時間未満  | 10,021円 | 約1,003円 | 約2,005円 |
介護保険を利用する場合の訪問看護の料金は、介護保険の自己負担割合に応じて決まります。
自己負担割合は、所得応じて異なりますが、原則として1割、2割、3割の3段階に分かれています。
自己負担が軽くなる制度もあります。詳しい訪問看護の料金については、市区町村の介護保険課にお問い合わせください。
訪問回数や時間は個々の状態に応じて調整されるため、利用者にとって無理のない範囲で支援が受けられるのが特徴です。
費用面でも医療保険と比較して安定した自己負担割合で利用できるため、継続したサービス利用がしやすいといえるでしょう。
介護予防サービスとしての訪問看護
自己負担割合は、所得に応じて異なりますが、原則として1割、2割、3割の3段階に分かれています。
介護保険制度では、介護予防訪問看護も提供されています。
これは65歳以上で要支援認定を受けた方が対象で、将来的に要介護状態になるのを防ぐために行われます。
サービス内容には、バイタルチェックや服薬管理、リハビリテーション、医師の指示による処置などが含まれます。
介護予防訪問看護を利用することで、利用者ができるだけ長く自立した生活を送れるように支援します。
特に高齢者にとっては、健康状態を安定させ、生活の質(QOL)を維持する大切な役割を果たします。
このように、訪問看護における「医療保険と介護保険の違い」を理解することで、自分や家族にとって最適な制度を選択できます。
費用面や対象条件が異なるため、どちらを利用するか迷った際には、専門機関やケアマネジャーに相談してみることをおすすめします。
訪問看護を利用するなら当ステーションへご相談ください

訪問看護を利用する際に「医療保険と介護保険の違い」で迷った場合は、専門の訪問看護ステーションへ相談するのが安心です。
シンプレ訪問看護ステーションは精神疾患に特化したサービスを提供しており、医療面・生活面の両方からサポートを行っています。
医師や行政と連携しながら、利用者が自宅で安心して療養を続けられるよう支援いたします。
シンプレ訪問看護ステーションについて
シンプレはうつ病や統合失調症、発達障害など幅広い疾患に対応しています。
専門性を持つ看護師・准看護師・作業療法士がチームで訪問し、病状の安定や社会復帰をサポートします。
利用者の自主性を尊重したケアを行い、安心できる居場所づくりを目指しています。
医療保険で精神科訪問看護を1~3割で利用可能
シンプレでは自立支援医療制度を利用でき、医療保険の適応により1~3割の自己負担で精神科訪問看護を受けられます。
これにより経済的な負担を軽減しつつ、継続的な療養生活が可能になります。
制度や手続きに不安がある場合もスタッフが丁寧にサポートしますので、安心してご利用いただけます。
精神科訪問看護のサポート内容
- 生活支援(食事・睡眠・服薬管理など)
- 再発予防や症状の悪化防止
- 社会復帰や就労支援
- 家族への相談・支援
- 在宅での医療処置やリハビリ
- 地域資源との連携による支援
このように、精神科訪問看護では生活面と医療面を一体的に支援することで、利用者がより自分らしく暮らせるようお手伝いします。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
シンプレの対応エリアは以下の通りです。
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
上記以外の近隣エリアでも訪問可能な場合があります。
まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
ご相談の問い合わせはこちら▼
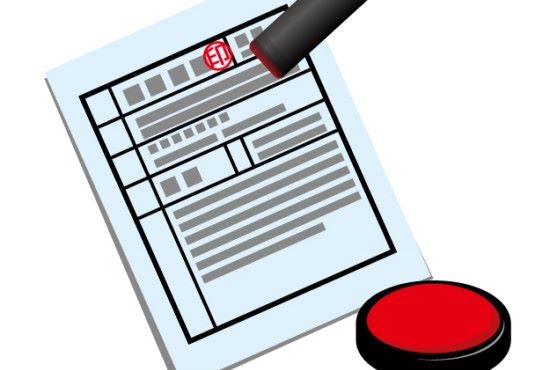
訪問看護は医療保険と介護保険の両方で利用できる
訪問看護は、医療保険と介護保険のどちらでも利用できます。
それぞれの制度には対象者・利用条件・自己負担額に違いがあり、状況に応じて選択することが重要です。
特に精神科訪問看護や介護予防訪問看護など、サービスの種類によっても適用保険が変わります。
対象者や利用条件によって適用保険が変わる
医療保険は主治医の指示がある場合に幅広い年齢層で利用でき、介護保険は要支援・要介護認定を受けた高齢者を中心に対象としています。
このように「訪問看護を利用する際の医療保険と介護保険の違い」を理解することで、費用面やサービス内容の違いを把握でき、最適な選択につながります。
迷ったらまず専門機関に相談してみよう
どちらの保険を利用すべきか迷った場合は、ケアマネジャーや訪問看護ステーションなどの専門機関に相談するのが安心です。
シンプレ訪問看護ステーションでは、利用者やご家族の状況に合わせて最適な制度の活用をサポートしています。
制度を上手に使いながら、安心できる在宅療養を実現しましょう。
ご相談の問い合わせはこちら▼

高座渋谷つばさクリニック
医師:武井智昭
外来としてはうつ病(うつ状態)が年間300名程度はおりこちらが得意分野です。この他に、思春期特有の対応(起立性調節障害や拒食症など)も行っています。心療内科としては10年、日本精神神経学会会員に所属
本記事へのコメント
訪問看護は医療保険と介護保険のどちらでも利用できますが、ご自身の年齢・病状・要介護認定の有無によって適用される制度が異なります。
精神疾患をお持ちの方は、自立支援医療制度を併用する事で医療費を1割負担に軽減でき、所得に応じてさらに月額上限が設定されます。経済的負担を心配されている方も、安心してケアを受けられる仕組みが整っています。
医療保険では原則週3回までですが、精神科訪問看護の場合は週4回以上の訪問も可能です。症状が不安定な時期でも、必要な頻度でサポートを受けられます。
制度が複雑で分かりにくいかもしれませんが、訪問看護ステーションのスタッフやケアマネジャーが丁寧に説明し、申請手続きもサポートします。まずはお気軽にご相談ください。安心して療養できる環境を、一緒に整えていきましょう。
監修日:2025年11月25日
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



