ADHDと前頭葉の関係性|症状・治療法・二次障害・相談先まで徹底解説
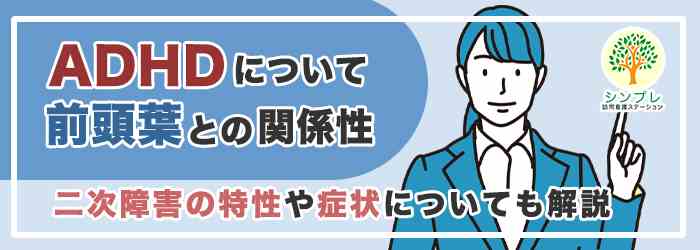
発達障害のひとつであるADHD(注意欠如・多動症)は、前頭葉の働きと深く関わっていることが近年の研究で注目されています。
「集中が続かない」「じっとしていられない」「考える前に行動してしまう」などの症状は、子どもから大人まで日常生活に大きな影響を及ぼします。
本記事では、ADHDと前頭葉の関係を中心に、特徴・症状・治療法・相談先について詳しく解説します。ADHDに関する理解を深めることで、支援や治療の第一歩につながるでしょう。
ADHDとは?
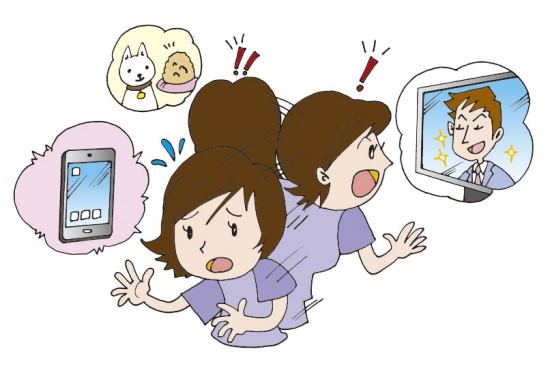
ADHDの定義と特徴
ADHDとは「注意欠如・多動症」の略称で、発達障害のひとつです。主な特徴としては、不注意(集中が続かない、忘れ物が多い)、多動性(落ち着きがなく常に動いている)、衝動性(考える前に行動する)などが挙げられます。
これらの症状は学校や仕事、家庭生活に支障をきたすことも少なくありません。しかし、ADHDにはポジティブな面も存在します。
たとえば、興味のあることには強い集中力を発揮できる、新しいことに柔軟に取り組める、行動力があるなどの長所です。特性を理解し、適切な支援を受けることで、自分らしい生活を送ることが可能になります。
子どもから大人まで影響する発達障害
ADHDは子どもの発達段階で症状が現れることが多いですが、大人になっても特性が続くケースは少なくありません。子どもの頃には「落ち着きがない」「授業に集中できない」といった形で表れ、大人になると「仕事でミスが多い」「計画を立てるのが苦手」「時間管理ができない」といった問題につながります。
近年では、大人のADHDが社会的に認知されるようになり、診断や治療を受ける方も増えています。発達障害のひとつとして理解を深めることは、本人だけでなく家族や職場など周囲のサポートも大切です。
ADHDと前頭葉の関係性
前頭葉の役割(注意・感情・行動制御)
脳の前方に位置する前頭葉は、人間らしい行動をコントロールする中枢として重要な役割を果たしています。注意力や集中力、感情のコントロール、行動の計画性や社会的判断力など、多岐にわたる機能を担っています。
特に前頭葉の一部である前頭前野は、思考・判断・コミュニケーションに深く関与しており、社会生活を円滑に送るために欠かせない領域です。
この前頭葉の機能に偏りが生じると、集中が続かない、衝動的に行動してしまう、感情をうまく抑えられないといったADHD特有の症状につながると考えられています。
ADHDと前頭葉の機能低下の関係
近年の研究では、ADHDの発症要因のひとつとして「前頭葉の機能低下」が注目されています。前頭葉の働きが十分でない場合、情報を整理する力や衝動を抑える力が弱まり、不注意・多動性・衝動性といった症状が現れやすくなります。
実際、脳画像の研究ではADHDの方の前頭葉に活動の低下が見られることが報告されており、日常生活に支障をきたす要因のひとつと考えられています。
つまり、ADHDと前頭葉の関係は切っても切れない密接なものであり、この領域の働きを理解することがADHDの理解にもつながります。
脳内の神経伝達物質(ドーパミン・ノルアドレナリン)の不足
ADHDの背景には、前頭葉の機能低下に加えて神経伝達物質の不足も関与しているといわれています。脳内で情報を伝える物質であるドーパミンやノルアドレナリンは、意欲や集中、抑制に関わっています。
ADHDの方では、これらの神経伝達物質の働きが不十分なため、気持ちの切り替えが難しかったり、集中が続かないといった症状が表れるのです。
また、ドーパミンが不足すると報酬系の働きが低下し、「やる気が続かない」「達成感を得にくい」といった課題にもつながります。こうした神経科学的な要因がADHDの特性を支えていると考えられています。
ADHDと関連する障害や二次障害

ADHDと同分類の障害(自閉スペクトラム症など)
ADHDは発達障害のひとつであり、他の発達障害と併せて診断されることも少なくありません。代表的なものとしては、自閉スペクトラム症(ASD)、学習障害(LD)、知的障害、発達性協調運動症、コミュニケーション症群などがあります。
これらはADHDと同じく神経発達の過程で起こる特性であり、しばしば複数の症状が併存します。たとえば、ADHDの「衝動性」とASDの「対人関係の難しさ」が重なると、学校や職場での人間関係に困難を抱えることがあります。
発達障害は一人ひとり症状の現れ方が異なるため、「ADHD=不注意」など単一の見方ではなく、総合的に理解する姿勢が重要です。併存障害を正しく把握することで、本人に合ったサポート方法を見つけやすくなります。
ADHDの二次障害(不安障害・うつ病など)
ADHDの方は日常生活での失敗体験や叱責を繰り返しやすく、自己肯定感が低下しやすい傾向があります。その結果として、不安障害やうつ病、パニック障害などの二次障害を発症することがあります。
特に大人のADHDでは「仕事でのミスが多い」「人間関係がうまくいかない」といった問題が長期間続くことで、強いストレスや抑うつ気分につながることが少なくありません。
また、不登校や引きこもりなど社会的な孤立を招くケースもあり、家族全体に大きな負担を与えてしまうこともあります。
こうした二次障害を予防するためには、早い段階でADHDの特性に気づき、本人の強みを伸ばせる環境を整えることが重要です。本人が成功体験を積み重ねられるよう、周囲の理解と支援が不可欠といえるでしょう。
ADHDの主な症状

不注意(集中が続かない)
ADHDの代表的な症状のひとつが「不注意」です。宿題や仕事を始めても集中力が続かず、気づけば別のことをしてしまうといった特徴があります。物をよくなくす、約束を忘れる、期限を守れないといった日常生活の困りごとにつながることも多いです。
また、整理整頓が苦手で部屋が散らかりやすい、作業を中断してしまうなども不注意の現れです。これらは本人の努力不足ではなく、前頭葉の働きと神経伝達物質の影響によるものであると理解することが大切です。
不注意の症状には工夫も有効で、チェックリストを作る、タイマーを活用するなどで集中の持続を助けることができます。
多動性(じっとしていられない)
次に多く見られるのが「多動性」です。授業中や会議中に体を動かさずにいられない、他人の話を最後まで聞けないといった行動に表れます。子どもの場合は授業で席に座っていられない、大人の場合は長時間のデスクワークが苦手など、状況に応じた困難が現れます。
多動性は「落ち着きがない」ことではなく、脳の抑制機能が十分に働かないことによる特性であると理解されつつあります。本人や周囲がそのサイクルを知り、休憩や体を動かす時間をあらかじめ設けることで生活に取り入れることが可能です。
衝動性(考える前に行動してしまう)
「衝動性」もADHDの大きな特徴のひとつです。思いついたことをすぐ口に出してしまう、順番を待てずに割り込んでしまう、衝動買いを繰り返すなどが代表的な行動です。
この衝動性は人間関係のトラブルや金銭的な問題につながることもあり、本人にとっても周囲にとっても負担になることがあります。
ただし衝動性は裏を返せば「直感力」「行動力」としてポジティブに働く面もあります。状況に応じて行動の仕方を学ぶことで、マイナス面を減らし、長所を伸ばしていける可能性があります。
子どものうちからルールを明確にしたり、大人の場合は環境を整えることが、衝動性のコントロールに役立ちます。
ADHDの治療法は?

心理士によるカウンセリングや認知行動療法
ADHDは脳の働きに関わる発達障害であるため、根本的に「完全に治す」という治療は現時点では存在しません。しかし、心理士によるカウンセリングや認知行動療法(CBT)を通じて、症状を軽減し日常生活をより送りやすくすることを目指すことができます。
カウンセリングでは、本人が自分の特性を理解しやすくなるようサポートしたり、ストレスの軽減方法を一緒に考えたりします。また、認知行動療法では「忘れ物を減らす工夫」「時間を意識する練習」など具体的な行動改善を学ぶことができます。
親子で取り組むプログラムもあり、子どもへの対応方法を保護者が学ぶことで、家庭内のコミュニケーション改善やストレス軽減にもつながります。
心理的支援はADHDの特性を理解し、長所を伸ばすための重要な治療法といえるでしょう。
薬物治療
ADHDの治療では薬物療法も大きな役割を果たします。薬は症状そのものを根本から取り除くものではなく、不注意や多動・衝動性といった症状を軽減し、生活をスムーズに送れるようにするサポートの役割を持ちます。
代表的な薬は以下のように分類されます。
中枢神経刺激薬
脳内のドーパミンやノルアドレナリンの働きを高め、集中力や注意力を改善します。学業や仕事におけるパフォーマンス向上に役立つとされます。
非刺激薬
神経伝達物質の調整を行い、不安感や衝動性を和らげる働きを持ちます。刺激薬が合わない方や副作用のリスクを避けたい方に用いられるケースがあります。
薬物療法は本人に合わせて処方が変わり、副作用として眠気や食欲不振、頭痛などが現れる場合があります。そのため、必ず医師の指導のもとで適切に服用する必要があります。
また、薬物治療と心理的支援を併用することで、生活の質を大きく改善できる可能性が高まります。薬だけに頼るのではなく、行動療法や生活習慣の工夫と組み合わせることが効果的です。
ADHDの相談先

医療機関(精神科・心療内科・発達外来)
ADHDの診断や治療を受ける場合、まずは精神科・心療内科・発達外来などの医療機関を受診するのが基本です。医師による問診や心理検査、必要に応じて脳の画像検査などを行い、総合的に診断が下されます。
医療機関では薬物療法や心理療法の提案を受けられるだけでなく、就学や就労に関する相談も可能です。早期に医療機関を訪れることで、本人の困りごとを和らげ、家族のサポート体制を整えやすくなります。
「ADHDかもしれない」と感じた段階で専門機関に相談することが第一歩です。
支援センターやカウンセリング窓口
ADHDの方やご家族は、地域の支援センターや発達障害者支援センターを活用することもできます。こうした機関では、専門の相談員が生活上の困りごとや就学・就労に関する支援を行っています。
また、学校のスクールカウンセラーや企業内の産業カウンセラーなども相談先のひとつです。医療機関とは異なり、日常生活や環境調整に寄り添った支援を受けられる点が大きな特徴です。
カウンセリングでは「時間管理の方法」「人間関係の工夫」など具体的なアドバイスを得られることもあり、本人の自己理解を深める手助けになります。
精神科訪問看護という選択肢
外出や通院が難しい方にとって、精神科訪問看護は有効な選択肢です。看護師や作業療法士が自宅に訪問し、症状の観察や服薬管理、生活のサポートを行います。
ADHDの方に対しては、薬の服用状況を確認したり、生活リズムを整えるアドバイスをしたりと、自宅で安心できる支援が受けられます。
自宅で看護を受けられる
外出が難しい場合でも、自宅で継続的なサポートを受けられることは大きな安心材料となります。
家族の負担軽減
服薬や生活支援を看護師に任せることで、家族の介護負担が減り、休息や仕事に専念する時間を確保できます。
通院負担の軽減
通院が難しい状況でも、訪問看護によって医師と連携を取りながら必要な医療サポートを受けられます。
このように、ADHDの相談先は医療機関だけでなく支援センターや訪問看護など多岐にわたります。本人と家族に合った支援を見つけることが、生活の質を高める第一歩です。
精神疾患をお持ちならシンプレへ

当ステーションの特徴
シンプレ訪問看護ステーションは、精神疾患を抱える方やご家族に向けて、専門的なサポートを行っている訪問看護サービスです。特にADHDやうつ病、統合失調症などの精神科領域に特化している点が大きな特徴です。
ご利用者さま一人ひとりが「自分らしい生活」を送れることを最優先に考え、主体性を尊重した支援を行っています。また、看護師・准看護師・作業療法士がチームで連携し、体調や状況に応じたきめ細やかなサポートを提供します。
緊急時には医療機関や行政とも素早く連携できる体制を整えており、安心してご利用いただける環境を整えています。
「心のケアと生活支援を同時に受けられる訪問看護」として、多くの方から信頼をいただいています。
対応している精神疾患の一例
シンプレが対応している精神疾患には以下のようなものがあります。
自閉スペクトラム症:対人関係の困難や強いこだわりが特徴
うつ病・双極性障害:気分の変動や抑うつ状態による生活への影響
統合失調症:幻覚や妄想、現実との区別の難しさが見られる疾患
PTSDや不安障害:強いストレス体験から心身に影響を及ぼす障害
このほかにもアルコール依存症や薬物依存症、適応障害、認知症など幅広い精神疾患に対応可能です。本人の状態や生活背景に合わせたオーダーメイドの支援を行い、再発予防や社会復帰を目指します。
シンプレの対応エリア
シンプレは東京都23区を中心に、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、府中市、東久留米市、そして埼玉県の一部地域まで対応しています。
近隣の市区町村でも訪問できる場合がありますので、詳細はお気軽にご相談ください。
訪問回数は週1〜3回が基本で、状況によっては週4回以上の訪問も可能です。1回あたりの訪問時間は30分〜90分と柔軟に対応しており、祝日や土曜日の訪問にも対応しています。
精神疾患をお持ちの方やそのご家族にとって、通院や日常生活の負担を軽減するサポートは大きな安心につながります。シンプレは「心の支え」として寄り添いながら、地域で安心して生活できるようお手伝いいたします。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

ADHDは前頭葉の働きと深く関わる発達障害
ADHD(注意欠如・多動症)は、集中力や感情のコントロール、行動の抑制などを担う前頭葉の機能と深く関連していると考えられています。前頭葉の働きが十分でないことで、不注意・多動性・衝動性といった症状が現れるのです。
さらに、神経伝達物質であるドーパミンやノルアドレナリンの不足もADHDの特徴を強める要因とされています。こうした脳科学的な背景を理解することは、本人や家族がADHDを正しく受け止めるために重要です。
ADHDは単なる性格や努力不足ではなく、脳の働きに基づく発達障害であるという認識が欠かせません。
治療は心理療法と薬物療法の組み合わせが有効
ADHDには根本的な「完治」の方法はありませんが、心理士によるカウンセリングや認知行動療法、さらに薬物療法を組み合わせることで症状を軽減し、生活の質を大きく向上させることができます。
心理的支援では特性を理解し、行動改善やストレス対処法を学ぶことが可能です。一方、薬物治療ではドーパミンやノルアドレナリンの働きを補い、集中力や衝動のコントロールを助けます。
「心理療法+薬物療法」の併用は、ADHDの治療における標準的なアプローチであり、本人や家族が安心して生活を送るための大きな支えとなります。
専門家や訪問看護を活用して生活をサポートしよう
ADHDは子どもから大人まで一生涯にわたって影響を及ぼす可能性があります。そのため、医療機関や支援センターでの相談に加え、精神科訪問看護のような在宅での支援を活用することも有効です。
訪問看護では看護師や作業療法士が自宅を訪れ、服薬管理や生活支援を行うことで、通院が難しい方でも安心して支援を受けられます。これは家族の負担軽減にもつながり、地域で自分らしく生活を続ける助けとなります。
ADHDの理解と適切なサポートを組み合わせることで、困難を和らげ、長所を伸ばして社会で活躍できる可能性が広がります。
最後に、シンプレのような専門的な訪問看護ステーションも選択肢のひとつとしてぜひ検討してください。地域での生活を支えながら、本人と家族の安心を守るパートナーとなるはずです。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (5)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



