【摂食障害】診断基準や気になる症状・治療法について詳しく解説。
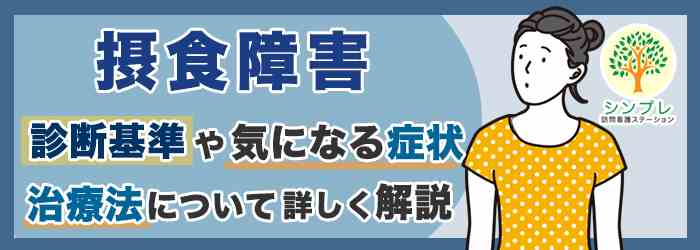
摂食障害は主に食べることを拒んでしまう「拒食症」と反対に際限なく食べ続けてしまう「過食症」の2タイプがあります。
症状的に正反対ですが、それぞれ明確な診断基準があります。
では、その診断基準とは具体的にどのようなものなのでしょうか?今回は摂食障害の診断基準を解説し、また治療方法についても紹介していきます。
摂食障害の診断と診断基準

診断の流れ
摂食障害がうたがわれる場合、クリニック(心療内科など)に予約をとり、医師の診察をうけましょう。診察前に問診票の記入がありますが、空欄があってもかまいません。
診察では、医師が患者さまのなやみや症状、心理テスト、表情などから治療方針の提案をします。また、診察前に心理士が話をきくこともあります。
質問があれば医師にきいてみると、アドバイスをしてくれるでしょう。問診票の記入、予診、心理テスト、診察の流れは、基本的にどこのクリニックでも同じようなものです。
症状によって診断基準が変わる
摂食障害には「拒食症」と「過食症」があり、それぞれ診断基準はことなります。「太ることに対する恐怖」はおなじですが、症状により診断基準はかわります。
「拒食症」の症状は、やせすぎているのに食事の量を極端にへらす、行きすぎた運動や嘔吐で体重増加をふせぐ、「自分はふとっている」というゆがんだ思いをもっているなどがあります。
「過食症」の症状には、「食べたい気持ち」をおさえられずたべすぎてしまい、体重増加を防ぐために、きびしいダイエットや自分で嘔吐、下剤などの不適切な使用があります。
DSM-5に基づく基準で診断される
摂食障害の診断基準は、米国精神医学会が刊行している「精神障害の診断・統計マニュアル第5版(DSM-5)」に記載されています。
DSM-5には、摂食障害の代表的な2つのタイプ、拒食症と過食症の診断基準が記されています。
摂食障害の診断は、専門の医師や心理士が行います。診断の際には、患者の体重や食行動の様子、精神状態などを評価します。
摂食障害は、早期発見・早期治療が重要です。摂食障害に心当たりがある場合は、早めに専門家に相談しましょう。
摂食障害の種類と特徴
・極端に痩せようとする
・食事、体重増加を毛嫌いする
過食症
・食事のコントロールができない
・頻繁に間食する
「拒食症」は男性より女性が発症しやすく、体重増加をいやがり、体重がへることに喜びをかんじ、いつも食べ物のことで頭がいっぱいです。
「過食症」は10代後半、20代前半あたりに発症する方が多いといわれています。食べたい気持ちをおさえられないため、食べおわった後に食べすぎた後悔や罪悪感をかんじやすいです。
「拒食症」「過食症」ともに、食べては吐くをくり返してしまい、精神的にも身体的にもさまざまな症状があらわれ、日常生活に支障をきたしてしまうでしょう。
①拒食症

拒食症の診断基準
- 年齢不相応の体重か
- 極端なカロリー制限をしているか
- 体重増加への恐怖心がある
- 自身に状態に対する認識の欠如しているか
拒食症の方は、体重が健康的な範囲に達していないにもかかわらず、体重を増やすことを恐れて、極端な食事制限を繰り返します。その結果、低体重になってしまいます。
年齢不相応の体重とは、健康的な生活を送るために必要な体重よりも低い体重のことです。子どもの場合は、成長段階で必要な最低体重よりも低い体重を指します。
拒食症の方は、自分の病気に気づいていないことが多いです。自分の体型に対する誤った認識から、「やせれば美しくなれる」と考え、自分の体重が深刻な状態であることを理解できないようです。
BMI等を用いた健康状態の数値化
自分の健康状態の把握するために、BMIやその他の計算方法を用いて、数値化します。拒食症の方は、BMIが17.5未満で、15未満になると最重度の低体重と診断されるようです。
また、日本方の体型(小柄)にあわせた平田法を用いて、自分の標準体重を数値化することもできます。これにより、現在の健康状態を把握することができます。
拒食症の方は、やせるにつれて、筋力低下、疲れやすさ、骨粗鬆症、さむがり、貧血、などの症状が現れます。そのため、やせ具合に応じて、身体状況と活動制限の目安が示されています。
診断からどのような病型か判断
3ヶ月間過食や食物の排出行為を繰り返していない
排出型
3ヶ月間過食や食物の排出行為を繰り返している
拒食症にはさらに「制限型」と「排出型」の2つの病型があり、過食や下剤などの乱用、浣腸、嘔吐をする行動があるかどうかで病型を判断します。
制限型は過食などの行為をくりかえしませんが、過度なダイエットや食事制限、行きすぎた運動により、体重をへらそうと考えるようです。
「制限型」の拒食症でも、「排出型」の拒食症でも、過食後に行う嘔吐や下剤、浣腸の乱用、過剰な運動などの行為は、誰にも知られないように行われることが少なくありません。
その為、家族であっても、その異常な行動のすべてを把握するのは難しいでしょう。
②過食症

過食症の診断基準
- 通常よりも食べ物を多く食べる
- 飲食の歯止めがない
- 不適切な方法で体重を減らす
- 過食と不適切な減量を繰り返す
- 過度に体系、体重を気にする
過食症の方のほとんどは標準体重であるのにもかかわらず、自分の体系や体重を気にしてたり、他方からどうみられているかを心配する傾向があります。
しかし食べたい欲求は制御できないため、だれよりも食べる量が多くなります。そして、体重増加をおそれ不適切な行動で体重をへらす、また食べ過ぎるをくり返してしまうのです。
食事中は食べることをコントロールできないという感覚があり、その過食と不適切なダイエット行為が癖になってしまうと考えられます。
不適切な減量とは
過食症における不適切な減量とは、過食をした罪悪感から摂取しすぎたカロリーをなかったことにするため、無理やり体重を落とす行為になります。
過食が原因による体重増加を防ぐため、自分で嘔吐、下剤など服用したり、絶食や過剰な運動が日常化してしまいます。過食後にこのような不適切な減量を行うことに依存するようです。
過度なカロリー制限をするとその反動からまた過食したい衝動にかられ、またなかったことにするため不適切な減量を行うをくり返してしまう悪循環になってしまいます。
摂食障害の治療方法

外来治療と入院治療の違い
摂食障害の治療は、通常は外来で行いますが、体重が著しく減少している、合併症が生じている、食事が全くとれないなどの場合には、入院での治療が必要になることがあります。
外来治療では、食事や栄養に関する指導が行われ、正しい食習慣を身につけることを目標とします。また、家族への説明や支援も行われます。
入院治療では、過度な食事制限による栄養不良の状態を改善することを第一に考えます。そのため、内科的な治療が優先されます。
主な治療内容
特定の症状に対して効果のある薬を処方
カウンセリング
根本的な原因の解決を目指す
摂食障害の治療には、カウンセリングが有効です。カウンセリングでは、摂食障害の根本的な原因を探っていき、解決することで、過食や拒食を繰り返さないようにします。
摂食障害の原因は、家庭環境や方間関係のトラウマなど、様々な要因が考えられます。カウンセリングでは、患者さんの話を丁寧に聴き、その原因を理解することが重要です。
現在のところ、摂食障害を完全に治す薬はありません。薬物療法では、抗うつ薬や抗不安薬など症状に対して効果が見込める薬を処方します。
薬物治療で用いられる薬とは
薬物療法では、SSRI(セルトラリン)やデュロキセチンなどが使用されます。しかし、上記でも記載したとおり、摂食障害を完全に治す薬はありません。
SSRI(セルトラリン)は抗うつ薬であり、摂食障害による気分の落ち込みや嘔吐を抑える効果が期待できます。2〜3ヶ月服用すると、過食の回数が減少する可能性があるとされています。
デュロキセチンは、3ヶ月服用を続けると過食が減少したという報告があります。
精神科訪問看護という手段もある
- 日常生活の維持
- 生活技能の獲得・拡大
- 対方関係の維持・構築
- 家族関係の調整
- 精神症状の悪化や増悪を防ぐ
- ケアの連携
- 社会資源の活用
- 対象者のエンパワーメント
摂食障害のように精神的な症状をお持ちの方に、日常生活に支障をきたす方を支援するために精神科訪問看護があります。看護師が利用者の自宅を訪問して、上記のようなさまざまな支援をします。
利用者の自分らしさを優先して、日常生活や対方関係のなやみへの対処法を考えます。また、薬の服用管理やバイタルチェックを行い、症状の悪化や憎悪を防ぎます。
日常生活や社会活動、治療のすすみをサポートするのが精神科訪問看護であり、困り事があれば頼れる存在になるでしょう。
精神疾患をお持ちならシンプレへ

当ステーションの特徴
シンプレは精神疾患に特化しており、看護師や作業療法士が利用者の自宅を訪問して支援を行う訪問看護ステーションです。
利用者様の気持ちを優先して、自分らしく生活できる支援を行います。緊急のさいは、医療機関や行政と素早い連携をとる体制を整えています。
就労支援センターなどと連携をとりあっており、利用者さまが自立した生活を送るための自立支援を行います。
利用者さまやご家族の心によりそった支援を提供しますので、お気軽にご相談ください。
シンプレのサービス内容
・自立した生活を営めるための支援
・生活リズムの調整
症状の悪化防止・服薬支援
・生活状況を観察
・受診や服薬を支援
社会復帰へのサポート
・主治医や関係機関と連携
・社会復帰を支援
家族の方への支援
・家族へのアドバイスや相談
・社会資源の活用などを支援
シンプレでは、薬を正確に飲めない方や通院が途絶えがちな方には、病状が悪化のおそれがあるため受診や服薬のサポートを行います。
社会復帰のサポートでは、ありのままの自分で社会にでられるよう、利用者様にあった支援を提供します。各関係機関と連携を取り合い、社会復帰を一緒に目指していきます。
また必要であれば、利用者さまのご家族への支援をすることも可能です。たとえば、ご利用者さまとの関わり方、なやみや社会資源の活用などのアドバイスを行います。
対象となる精神疾患
- 摂食障害
- うつ病
- 双極性障害
- 自閉スペクトラム症
- アルコール依存症
- 統合失調症
- ADHD
- その他精神疾患全般
シンプレは精神科に特化しているので、精神疾患全般に対応できます。上記以外にも、自閉症や解離性障害、薬物依存、パニック障害、適応障害などがあります。
精神疾患をお持ちの方は病気が原因で、日常生活や人間関係などで困難なことがでてくる場合もあるでしょう。シンプレではそういった悩みに寄りそい、解決できるようサポートを提供します。
訪問する看護師等と事務所に配置されているバックオフィスは連携をとっているので、摂食障害でお悩みでしたり、そういった方が周囲にいらっしゃる場合はお気軽に相談ください。
シンプレの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレの対応エリアは上記になっておりますが、対応エリア外でも近隣であれば訪問看護にうかがえる場合もありますので、お気軽にお問いあわせください。
シンプレでは、精神疾患をお持ちのかたなら年齢、性別問わずご利用いただけます。サービス内容やスケジュールの相談なども受けつけております。
また、TwitterやLine、TikTokなどのSNSで情報発信をしていますので、訪問看護にご興味がある方はぜひご覧ください。 ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

拒食症の診断基準は、年齢不相応な低体重になっているにもかかわらず、過度なカロリー制限、過剰な運動、おうと、下剤の使用で体重をさらにへらす行為などがあります。
過食症の診断基準は、たべたい気持ちをコントロールできないためたべる量が多くなり、過食後はおうとや下剤の使用、カロリー制限、また過食をくりかえす行為などがあります。
摂食障害の治療に有効といわれているのはカウンセリングであり、摂食障害の根本的な原因を解決して、摂食障害の改善を目指すようになります。
シンプレは精神科に特化しているので、摂食障害に悩んでいる方のお力になれるようサポートを提供します。ひとりで悩まず、ぜひお気軽にご連絡ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



