ナルコレプシーとADHDの関係性|症状・違い・治療法を解説

ADHDは注意力の欠如や多動性が特徴とされる発達障害ですが、実は睡眠障害の一つであるナルコレプシーを併発するケースが多いことが知られています。
近年の研究では、両者には遺伝的な関連があることも示されており、共通点や誤診のリスクについても注目されています。この記事では、ナルコレプシーとADHDの関係性や症状の特徴、治療法や相談先について詳しく解説します。ご自身やご家族に当てはまる部分がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
ナルコレプシーとADHDの関係は?

ナルコレプシーとADHDの合併は多い
ナルコレプシーは、時間や場所を選ばず突発的に強い眠気に襲われる睡眠障害です。一方、ADHD(注意欠陥・多動性障害)は、不注意や多動性、衝動性といった行動面の特徴を持つ発達障害です。これらは一見異なる障害に思えますが、研究では両者の合併率が高いことが示されています。
実際に、ADHDの方はそうでない方と比べて約1.9倍眠気が強く出やすいと報告されています。このことから、ADHDの診断を受けている方の中に、実はナルコレプシーを併発しているケースも少なくないと考えられます。
共通の遺伝子が関与していることが判明
2020年に発表された研究では、ナルコレプシーとADHDの間に遺伝的な関連があることが明らかになりました。具体的には、神経伝達物質に関与する遺伝子や免疫系を支えるグリア細胞に関わる遺伝子に共通点が見つかっています。
つまり、両者は単なる偶然の合併ではなく、遺伝子レベルでつながっている可能性が高いのです。これは、患者さんの治療方針を考えるうえで重要な視点となります。
症状が似て誤診されやすい点もある
ADHDの不注意症状とナルコレプシーによる日中の強い眠気は、表面的には「集中できない」「ぼーっとしている」といった似た特徴を示します。そのため、ADHDと診断された方が、実はナルコレプシーを伴っていたというケースも少なくありません。
このように、両者には深い関係があるため、正確な診断を受けることが非常に重要です。症状が重なっていると感じた場合には、発達障害と睡眠障害の両方に詳しい専門医に相談することが推奨されます。
ナルコレプシーの症状について知りたい

日中の過度の眠気
ナルコレプシーの代表的な症状は、日中に強烈な眠気が繰り返し起こることです。これは通常の「寝不足による眠気」とは異なり、状況や環境に関係なく突然発症します。授業中や仕事中、さらには会話中や食事中でも耐えられないほどの眠気に襲われ、数分から数時間眠ってしまうこともあります。
週に3回以上、3か月以上続く場合に診断されることが多く、目が覚めた後に「すっきりとした感覚になる」のが特徴です。こうした症状は、ADHDの「集中力が続かない」「気が散りやすい」といった症状と混同されることがあり、誤診につながる大きな要因ともなっています。
情動脱力発作(カタプレキシー)
ナルコレプシーのもう一つの特徴的な症状が「情動脱力発作(カタプレキシー)」です。これは、強い感情が引き金となって突然筋力が抜けてしまう現象です。例えば、驚いたときや大笑いしたときに、膝が崩れたり、頭がぐらついたりすることがあります。
発作は数秒から数分程度で治まりますが、繰り返し起こるため日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。本人は意識があるため「体が動かない」ことに不安を感じることもあります。
睡眠麻痺(金縛り)
入眠時や起床時に体が動かなくなる「睡眠麻痺(金縛り)」も、ナルコレプシーの患者さんに多く見られます。健康な方でも一時的に経験することがありますが、ナルコレプシーでは頻繁に発症するのが特徴です。
約4人に1人の割合でみられるとされ、特に初めて体験した方にとっては非常に恐怖を伴う症状です。自然に回復する場合もあれば、他人に体へ触れてもらうことで解除されるケースもあります。
入眠時幻覚などのその他の症状
さらに、入眠時にリアルな夢のような幻覚を体験する「入眠時幻覚」や、夜間に眠りが分断されてしまう「睡眠分断」なども代表的な症状です。これらは心身に大きな負担を与えるだけでなく、ADHDの注意散漫や衝動性をさらに悪化させる要因になる場合もあります。
このように、ナルコレプシーの症状は多岐にわたり、生活や学業、仕事への影響も大きいため、早期に医療機関で相談することが大切です。
ADHDの主な症状について知りたい
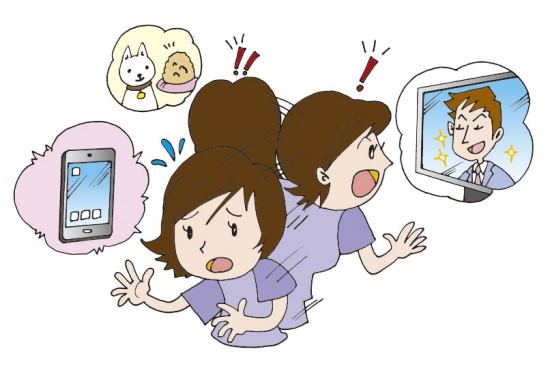
不注意
ADHD(注意欠陥・多動性障害)の代表的な症状の一つが「不注意」です。物事に集中できず、重要な用事でも締め切りを守れない、持ち物をよくなくす、忘れ物が多いなど、日常生活や仕事・学業に直接影響を与えます。
例えば宿題に取り組んでいても、テレビやスマホなど他の刺激に気を取られてしまい、気づけば全く違う行動をしてしまうことも珍しくありません。この「集中力の持続の難しさ」は、ナルコレプシーに伴う強い眠気による注意力低下と混同されやすい特徴でもあります。そのため、ADHDとナルコレプシーを誤診してしまうケースもあり、正しい診断が重要です。
多動性
ADHDのもう一つの特徴が「多動性」です。落ち着きがなく、そわそわと体を動かしたり、じっと座っていられなかったりする行動が目立ちます。授業や会議など静かにしているべき場面でも、体を動かしてしまい注意を受けることが多いでしょう。
また、興味のあることに夢中になると切り替えができず、時間を忘れて没頭してしまう傾向もあります。こうした特性は「活発でエネルギッシュ」と見える一方で、周囲と調和を保つことが難しく、学業や仕事において誤解を招くことも少なくありません。
衝動性
ADHDでは「衝動性」も大きな特徴です。思ったことをすぐに口に出してしまう、相手の話を遮ってしまう、買い物で衝動的に大きな出費をしてしまうなど、行動のコントロールが難しいのです。
また、感情のコントロールも難しく、ちょっとしたことで怒りやすい、ストレスが溜まりやすいといった傾向も見られます。その結果、家庭や職場、学校など人間関係のトラブルにつながる場合があります。
特に衝動性は、ナルコレプシーの「感情の高ぶりによる情動脱力発作」とは異なりますが、「感情に左右されやすい」という点で似ているため、症状の区別が難しいこともあります。
このように、ADHDは「不注意」「多動性」「衝動性」という3つの特徴的な症状を軸として日常生活に影響を及ぼします。ナルコレプシーとの症状の重なりを理解することは、正確な診断と治療の第一歩です。ご自身やご家族にこうした傾向がある場合には、専門の医療機関で相談してみることをおすすめします。
ナルコレプシーとADHDの共通点と違い
集中力の低下・不注意の共通点
ナルコレプシーとADHDは、いずれも「集中力が続かない」「注意が散漫になる」という共通の症状を持ちます。ADHDの場合は脳の実行機能の働きに偏りがあるために集中できないのに対し、ナルコレプシーでは日中の強烈な眠気が原因で集中力を維持できません。
どちらも学業や仕事において「だらしない」「やる気がない」と誤解されやすいのが大きな問題です。そのため、周囲の理解が不十分だと生活全般に支障が出ることが多く、本人や家族にとって大きな負担となります。
ナルコレプシー特有の睡眠関連症状
両者を区別する上で重要なのは、ナルコレプシー特有の睡眠関連症状です。代表的なものは「日中の過度の眠気」「情動脱力発作」「睡眠麻痺(金縛り)」「入眠時幻覚」などです。
これらはADHDには見られない症状であり、特に日中に突発的に眠ってしまう現象はナルコレプシーに特有のものです。このような症状を伴う場合は、ADHD単独ではなくナルコレプシーを合併している可能性が高くなります。正しい診断のためには睡眠障害の検査が欠かせません。
ADHD特有の行動面の症状
一方で、ADHDには「多動性」「衝動性」といった行動面の特徴があります。授業中や会議中でも落ち着いて座っていられなかったり、思ったことをすぐに発言してしまったりといった行動はナルコレプシーでは見られません。
また、衝動買いや感情のコントロールが難しいといった側面もADHD特有です。これらは本人の努力不足ではなく、脳の機能的な特性によるものであるため、「本人の性格」と誤解されやすい点に注意が必要です。
まとめると、ナルコレプシーとADHDは注意力の低下という共通点がある一方で、睡眠関連症状があるかどうかや行動面での特性によって区別できます。両者を正しく理解し区別することは、適切な治療やサポートを受けるための第一歩です。
ナルコレプシー・ADHDの治療方法

TMS(磁気刺激治療)
近年注目されているADHDの治療法の一つに「TMS(反復経頭蓋磁気刺激)」があります。これは脳の特定部位に磁気を当てることで活動を促し、神経ネットワークの働きを改善する方法です。副作用が少なく、一定回数の施術で集中力や衝動性の改善が見られると報告されています。
ADHDの症状が安定することで、ナルコレプシーによる眠気や注意力低下の悪化を防ぐ効果も期待できます。薬だけに頼らない治療の選択肢として注目されています。
ナルコレプシーの薬物療法
ナルコレプシーには複数の薬物療法が用いられます。症状ごとに適切な薬が選ばれるため、医師の診断を受けることが大切です。
日中の眠気に対する薬物療法
主にモダフィニルやメチルフェニデートなどの中枢神経刺激薬が処方されます。これらは日中の過度な眠気を軽減し、日常生活や仕事への支障を減らすことを目的としています。
情動脱力発作に対する薬物療法
三環系抗うつ薬(イミプラミン、クロミプラミンなど)が用いられることが多く、笑いや驚きなど感情の高まりによる発作を抑制します。数週間の服用で効果が現れるケースもあります。
夜間の睡眠分断に対する薬物療法
短時間作用型の睡眠導入剤や、鎮静作用を持つ抗精神病薬を少量使用することがあります。夜間の覚醒を減らし、睡眠の質を改善することが目的です。
ADHDの治療法(薬物療法・行動療法)
ADHDでは、メチルフェニデートやアトモキセチンなどの薬物療法に加え、行動療法や環境調整が行われます。薬によって注意力を改善しつつ、生活習慣や行動パターンを整えることで効果を高めます。
特に子どもにおいては、学校や家庭でのサポートも重要で、本人の努力不足ではなく脳の特性によるものであることを周囲が理解することが欠かせません。薬物療法と行動療法を組み合わせることが最も効果的とされています。
ナルコレプシーを伴うADHDの相談先は?

病院へ受診
ナルコレプシーかADHDの症状が疑われる場合、まずは医療機関への受診が重要です。ADHDは精神科や児童精神科、小児神経科などが専門で、発達障害の診療経験がある医師のもとで診断を受けることが望ましいです。一方、ナルコレプシーは睡眠障害に分類されるため、睡眠外来や神経内科での診断が一般的です。
注意したいのは、すべての医療機関がADHDやナルコレプシーに精通しているわけではないという点です。そのため、事前に専門外来や実績のある病院を調べて受診すると安心です。特に、ADHDとナルコレプシーの両方に関わる症状がある方は、発達障害と睡眠障害の双方を診られる医師の診断が欠かせません。正確な診断がその後の治療の質を大きく左右するため、早めの受診をおすすめします。
その他の相談先
- 発達障害者支援センター
- 発達障害教育推進センター
- 児童発達支援センター
- 各自治体の福祉担当窓口
病院以外にも、相談できる窓口は数多く存在します。たとえば、各自治体に設置されている「発達障害者支援センター」では、発達障害に関する相談や生活上の困りごとについて支援を受けることができます。また、「児童発達支援センター」では子どもの発達を促すプログラムを提供しており、学習や集団活動への適応を助けます。
さらに「発達障害教育推進センター」では、学校生活や教育面での具体的なサポートが可能です。これらの施設では、本人やご家族が抱える悩みに対して情報提供や助言を行い、必要に応じて医療機関や福祉サービスにつなげる役割を担っています。
孤立せず、相談先を複数持つことが大切であり、地域の福祉窓口に問い合わせて支援を受けるのも一つの方法です。特にADHDとナルコレプシーが併発している場合、生活リズムの乱れや学業・就労への影響が大きいため、医療と福祉の両面からのサポートが効果的です。
このように、「病院」と「地域の相談窓口」を組み合わせることで、より適切な支援体制を整えることができます。症状が似ていて誤診されやすいナルコレプシーとADHDだからこそ、早期に相談し、生活全体をサポートしてもらうことが大切です。
精神科訪問看護を利用するという手段もある

精神科訪問看護とは?
精神科訪問看護とは、精神疾患や睡眠障害などで定期的な支援が必要な方に対して、看護師や作業療法士が自宅を訪問しサポートを行うサービスです。病院に通うだけでは管理しきれない日常生活のリズムを整えたり、服薬の確認を行ったりすることで、再発予防や社会復帰を助けます。
特にナルコレプシーとADHDのように複数の症状が重なっている場合、医療機関だけでなく自宅での支援が大きな役割を果たします。自宅で安心して療養できる体制が整うことで、本人や家族の負担を軽減することができます。通院が難しい方にとって心強い選択肢です。
精神科訪問看護のサービス内容
| サービス名 | 精神科訪問看護 |
|---|---|
職種 |
・看護師 ・准看護師 ・作業療法士 |
訪問日数 |
原則週1〜3回(※例外あり) |
訪問看護では、服薬管理や体調観察だけでなく、生活リズムの改善や社会参加のサポートなど幅広い支援が行われます。例えば、朝の起床を促し生活リズムを安定させる、症状が悪化していないかを確認する、必要に応じて医師と連携を取るなどです。
また、ご家族への助言や心理的なサポートも重要な役割の一つです。本人だけでなく周囲の理解を深めることで、長期的な安定につながります。
精神科訪問看護の料金
| 負担割合 | 月の初回訪問 | 2回目以降 |
|---|---|---|
1割負担 | 1,299円/回 | 855円/回 |
2割負担 | 2,598円/回 | 1,710円/回 |
3割負担 | 3,897円/回 | 2,565円/回 |
上記は週3回までの訪問料金となります。週4回以上訪問となる場合には料金が異なります。
精神科訪問看護では、医療保険を利用することにより自己負担を軽減できるメリットがあります。
30分を一区切りに利用可能。かかった費用については、年齢や所得によって変わり、医療費の1〜3割が自己負担となります。
また早朝や深夜などの時間外に依頼する場合や、長時間の訪問を行う場合は別途料金が発生します。
また自立支援医療制度という制度を利用すると料金が1割負担になるほか、所得に応じて自己負担が0円になる場合もございます。
精神科訪問看護は医療保険が適用されるため、自己負担額は比較的少なく済みます。さらに自立支援医療制度や障害者医療費助成制度などを利用できるケースも多く、経済的な負担を軽減することが可能です。
料金は訪問回数や地域によって異なりますが、医師の指示のもとで行われるため安心して利用できます。特にナルコレプシーとADHDの両方で悩んでいる方にとっては、医療・生活の両面からサポートを受けられる有効な仕組みです。
このように、精神科訪問看護は「医療」と「生活支援」をつなぐ架け橋となり、本人が社会の中で安心して暮らしていくための大切なサポートになります。外来治療に加えて訪問看護を取り入れることで、より安定した生活を送ることができるでしょう。
精神疾患でお悩みならシンプレへ

シンプレの特徴
ナルコレプシーとADHDのように、複数の症状が絡み合うケースでは、ご本人だけでなくご家族も大きな負担を抱えやすくなります。そんなときに頼れるのが、精神科に特化した訪問看護サービスを提供する「シンプレ」です。
シンプレ訪問看護ステーションでは、利用者様が住み慣れた自宅で安心して療養できる環境を整えることを大切にしています。医師や地域の支援機関と連携し、服薬管理や生活リズムのサポート、社会復帰へのサポートを行います。「病院に通うだけでは不安」という方に寄り添うサービスです。
精神疾患の一例
シンプレでは幅広い精神疾患に対応しています。以下は訪問看護の対象となる疾患の一部です。
・幻覚や妄想が特徴で、日常生活に大きな影響を及ぼすことがあります。
ADHD
・不注意や多動性、衝動性があり、学業や仕事、対人関係に困難が生じやすい発達障害です。
うつ病
・気分の落ち込みや強い疲労感、不眠などが続き、生活全般に支障をきたします。
その他の精神疾患
・発達障害、適応障害、パニック障害など幅広いケースに対応可能です。
シンプレの訪問看護は「症状の管理」だけでなく、「その人らしい生活を取り戻すこと」を目指しています。医療的ケアはもちろん、生活習慣や社会とのつながりを支えることで、本人の安心と自立をサポートします。
また、ご家族への助言や相談対応も大切にしており、「支える側の不安」も一緒に解消していくのが特徴です。
シンプレの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
東京23区や西東京市、三鷹市、調布市など、シンプレの対応エリアにお住まいの方は、まずはお気軽にご相談ください。地域に根ざした訪問看護だからこそ、利用者様の生活に寄り添った支援を行うことが可能です。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。電話やメールなどで相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

ナルコレプシーとADHDは合併が多く誤診されやすい
これまで見てきたように、ナルコレプシーとADHDは併発するケースが多く、それぞれの症状が似ているため誤診されやすいという特徴があります。特に「集中力が続かない」「ぼんやりしている」といった症状は、ADHDの不注意ともナルコレプシーの強い眠気とも解釈できるため、区別が難しいのです。
正確な診断を受けることが、その後の治療や生活改善の第一歩となります。誤診を避けるためには、発達障害と睡眠障害の双方に詳しい医師の診察を受けることが重要です。
治療は薬物療法や行動療法を組み合わせることが重要
治療方法としては、ナルコレプシーには眠気や情動脱力発作に対する薬物療法、ADHDには中枢神経刺激薬や非刺激薬の処方に加え、行動療法や環境調整が行われます。
薬物療法と行動療法を組み合わせて進めることで、より効果的な症状のコントロールが可能です。また、近年では副作用が少ないTMS(磁気刺激治療)も注目されており、選択肢が広がっています。本人の状態やライフスタイルに合わせた治療を進めることが大切です。
不安があれば早めに専門機関へ相談を
ナルコレプシーとADHDの両方に悩まされている場合、ご本人もご家族も大きな不安を抱えることになります。その際には、医療機関だけでなく地域の相談窓口や訪問看護といった支援制度を活用することが有効です。
特に精神科訪問看護は、自宅で専門職による支援を受けられるため、通院が難しい方にとって大きな助けとなります。地域や家庭で安心して療養できる環境を整えることは、症状の安定につながり、再発予防や社会復帰を後押しします。
「もしかしたら…」と感じた時点で早めに相談することが、症状を悪化させないための最善の対応です。
ナルコレプシーとADHDは、症状が重なりやすく誤診されやすい病気ですが、正しい診断と適切な治療、そして周囲の理解と支援があれば安定した生活を送ることが可能です。もし悩みを抱えている方は、専門機関や支援サービスを活用し、一人で抱え込まず相談してみてください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (5)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



