広汎性発達障害の症状をチェック!原因や症状を持つ方への接し方も解説
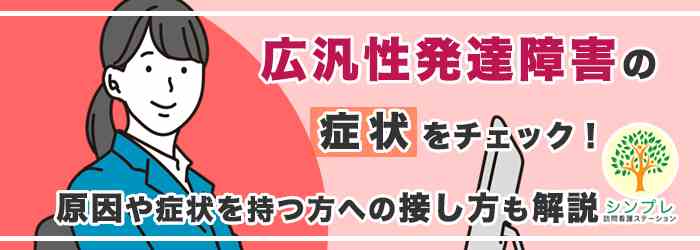
広汎性発達障害の症状には、相手の感情を感じ取ったり空気を読むことができないなどの特徴があります。
悪気なく相手の気分を害することを言ってしまい、周囲からは「気配りのできないひとだ」と受け取られてしまうことがあります。
また独自に強いこだわりがあるため、臨機応変に対応する事が難しいなど社会生活が困難になりやすいという問題があります。
広汎性発達障害の症状

対人関係やコミュニケーション困難
広汎性発達障害の症状は、まわりの人に関心を示さない、あるいは積極的に人と関わろうとするが一方的になってしまう等が挙げられます。
相手の気持ちや立場を理解することが難しいため、悪気がなく相手の気分を害してしまう等対人関係やコミュニケーションに困難を抱えることが多い傾向にあります。
そのため、学校や職場で孤立してしまうことが多いのです。
独自のこだわりによる社会適応の困難
広汎性発達障害の方は、ものごとの手順に対して強いこだわりがあったり、同じパターンの行動に固執したりする傾向があります。
そのため、イレギュラーな依頼が舞い込んだり、手順や予定が狂ったりすると、パニック状態に陥りやすいのが特徴です。
とくに社会生活においては、全てが予定通りに進むとは限らず、それがストレスや悩みにつながることも少なくありません。
また、興味や関心が極端に偏っていることから、ある特定の分野にだけ異常に没頭し、ほかにはまったく目を向けないこともあります。
その他の症状
・突然の大きな音(雷など)を異様に怖がる
・食べ物の好き嫌いが激しい
・特定の臭いや光が苦手
・季節の寒暖の変化に気づきにくい。
運動などが苦手
・縄跳びやボール遊びなどが苦手
・体の動きがぎこちなく転んだりする
・手足をドアや家具等にぶつけることが多い
・手先が不器用
広汎性発達障害の方は、聴覚、味覚、触覚などの感覚に対して、苦痛や不快感を感じる「感覚過敏」の症状を示すことが多いといわれています。
感覚過敏は、広汎性発達障害の症状のひとつですが、必ずしも広汎性発達障害の方にみられるわけではありません。
その他にも手先が不器用だったり、運動が苦手だったり、ぶつかることが多かったりと、処理能力に課題がある方もいます。
このように、広汎性発達障害の方の症状や特性は多岐にわたります。ご自身の症状や特性を理解し、症状応じた対策をとることが重要です。
自閉症スペクトラムと診断される場合も
自閉症スペクトラム(ASD)とは、以前は「広汎性発達障害」と呼ばれていた発達障害です。
広汎性発達障害には、自閉性障害、アスペルガー症候群、特定不能の広汎性発達障害などのサブカテゴリーがありましたが、2013年にアメリカ精神医学会の診断基準DSMにおいて「自閉症スペクトラム」に統一されました。
そのため近年では、医療機関によっては自閉スペクトラム症という診断名が用いられるようになってきているようです。
広汎性発達障害の原因

広汎性発達障害の発症原因は、現在のところ完全には解明されていませんが、いくつかの要因が考えられています。
具体的には、脳のネットワーク連結機能の低下、感情に関わる偏桃体の異常、前頭葉の異常、小脳の異常、脳内物質の異常などです。
また広汎性発達障害は、生まれつきの脳の特徴に基づく発達障害であり、親の育て方などの心理的な要因によって引き起こされる病気ではないことがわかっています。
親御さんがご自身を責めたり、過度に心配したりすることは避けましょう。
広汎性発達障害の方への接し方

広汎性発達障害のお子さんへの対応
広汎性発達障害をもつ子どもの中には、音や光などの感覚に過敏な子どもや、逆に鈍感な子どもが多いといわれています。また、言葉や行動、状況に対する理解の仕方や受け止め方が、一般的な子どもとは異なる場合もあります。
そのため、子どもは自分とは違う感覚や理解の仕方をしているということを意識し、理解をしていくことが重要です。
「これくらい言わなくてもわかるだろう」「この程度の音なら我慢できるはず」と思わず、子どもがどう感じているのか、何に困っているのかを考えながら接するようにしましょう。
患者さん本人が心がけること
広汎性発達障害の方は、抽象的な表現を理解するのが難しいため、以下のようなことに心がけることが大切です。
わからないことは確認したり、相手に具体的に話してほしいことを頼んでみましょう。具体的に話してもらうことにより、相手の意図を正確に理解しやすくなります。
また、わからないことを確認することで、誤解やトラブルを防ぐことができます。
家族や周囲の方が心がけること
- 感情的にならず、具体的な言葉で伝える
- 症状は持って生まれた特性と割り切る
家族や周囲の方は、広汎性発達障害の方に接する際には、上記のことを心がけましょう。
広汎性発達障害の方は、一般的な人と異なるコミュニケーションの特性があります。そのため、自分の思いが伝わらずイライラすることはありますが、感情的になると相手に伝わりにくくなります。
広汎性発達障害の方は、抽象的な表現や意図を読み取ることが苦手です。そのため、具体的に「何を」「どうやって」してもらいたいのかを伝えることが大切です。
また、症状は持って生まれた特性であり、本人も努力しているということを理解することで、より円滑にコミュニケーションが図れるでしょう。
広汎性発達障害の相談窓口

保健センター
保険センターは、年代や性別に関係なく、住民のさまざまな健康ニーズに対応し、健康をサポートすることを目的とした施設です。市区町村ごとに設置されています。
精神疾患だけでなく、母子保健、生活習慣病、高齢者保健、健康づくりなど、幅広い相談に対応できることが特徴です。
相談方法は、電話相談と面談による相談があります。施設の規模によって異なりますが、保健師、医師、精神保健福祉士などの専門職が対応しています。
発達障害者支援センター
発達障害者支援センターは、発達障害者に対する総合的な支援を行うことを目的とした専門機関です。
窓口は、都道府県や政令指定都市の自治体です。また、それらから委託された事業所でも相談を受け付けています。
基本的には社会福祉士が対応していますが、臨床心理士、言語聴覚士、医師などがいる施設もあり、それぞれの専門分野に応じたサポートを受けることができます。
まずはお住まいの地域の発達障害者支援センターがどんな支援をおこなっているのか調べてみるとよいでしょう。
精神科・心療内科
不安、抑うつ、不眠、イライラなどの症状を感じたら、精神科や心療内科に相談しましょう。精神科や心療内科では、相談だけでなく、治療法や対策を提案してくれることもあります。
初めて行くときは、自分の症状や悩みをうまく伝えられるか不安もあるかもしれません。家族に付き添ってもらったり、事前に話したいことを紙にまとめたりして、気持ちに余裕を持って受診しましょう。
広汎性発達障害の治療

- 不眠や食欲低下のが症状がある
- 落ち込みや抑うつ状態がひどい
- 不安やイライラ
- 衝動性や攻撃性が高まっている
広汎性発達障害の治療の基本は、一人ひとりの特性に合わせた療育です。療育を受けることで、生活に支障をきたす問題を減らすことができます。
ただし、上記のような二次的症状がある場合は、薬物療法を行うこともあります。
広汎性発達障害の人は、特性が周囲に理解されにくいため、二次的症状を引き起こしやすい傾向にあります。そのため、事前にご家族や周囲が本人の特性を理解することが大切です。
精神科訪問看護を利用するという選択も

精神科訪問看護とは?
・自立した生活を営めるための支援
・生活リズムの調整
症状の悪化防止・服薬支援
・生活状況を観察
・受診や服薬を支援
社会復帰へのサポート
・主治医や関係機関と連携
・社会復帰を支援
家族の方への支援
・家族へのアドバイスや相談
・社会資源の活用などを支援
精神科訪問看護とは、精神疾患を抱えている人や精神的な理由で不安を感じている人に対して、看護師などの専門職が自宅を訪れて支援するサービスです。
生活リズムの調整や受診・服薬の支援、社会復帰の支援など、さまざまな観点からサポートすることで、利用者が安心して生活できるようにすることを目指します。
また、家族への支援も実施し、利用者を取り巻く環境全体を整えていく役割も担っています。
特に、自宅から出るのが難しい場合や、日常生活での注意点などを家族にも共有したい場合は、精神科訪問看護を利用するのもよいでしょう。
精神科訪問看護のサービス内容
| サービス名 | 精神科訪問看護 |
|---|---|
職種 |
・看護師 ・准看護師 ・作業療法士 |
訪問日数 |
原則週3日以内 (※例外もあります。) |
精神科訪問看護では看護師、准看護士、作業療法士などのスタッフがご自宅に伺い、看護を行うことで健康状態の悪化防止や回復に向けたお手伝いをします。
一般的な訪問回数は週3回程度ですが、精神状態がわるく命に危険がおよぶ可能性があるかたや、家族など頼れる人がいない場合は週3回以上通うこともあります。
時間に関しては利用するかたの負担にならないよう、1回30分を目安に自宅や施設に訪問しています。精神科訪問看護はお子さまから高齢者の方まで幅広い年代のかたが利用できるというのも特徴です。
訪問看護を利用するメリット
- 自宅に居ながら専門的なケアが受けられる
- 自宅での様子を主治医に連携できる
- 家族の負担が軽減できる
訪問看護を利用するメリットは外出が難しい方や治療を中断してしまう方も、継続的に専門的な支援を自宅で受けられることです。
病状や内服状況など、医療機関やかかりつけの医師と連携し情報を共有できます。
家庭での療養状況や家族の疲労を確認し、デイサービスやショートステイ、介護サービスの導入も提案できます。
精神疾患と診断された方が、家庭や地域社会、また学校生活を安心して過ごせるよう利用できる制度なども提案します。
精神科訪問看護の料金
| 負担割合 | 月の初回訪問 | 2回目以降 |
|---|---|---|
1割負担 | 1,299円/回 | 855円/回 |
2割負担 | 2,598円/回 | 1,710円/回 |
3割負担 | 3,897円/回 | 2,565円/回 |
上記は週3回までの訪問料金となります。週4回以上訪問となる場合には料金が異なります。
精神科訪問看護では、医療保険を利用することにより自己負担を軽減できるメリットがあります。
30分を一区切りに利用可能。かかった費用については、年齢や所得によって変わり、医療費の1〜3割が自己負担となります。
また早朝や深夜などの時間外に依頼する場合や、長時間の訪問を行う場合は別途料金が発生します。
また自立支援医療制度いう制度を利用すると料金が1割負担になるほか、所得に応じて自己負担が0円になる場合もございます。
精神疾患をお持ちならシンプレへ

シンプレの特徴
シンプレ訪問看護ステーションは精神科に特化している訪問看護ステーションです。こころの健康問題を抱えて悩んでいる方やそのご家族様への継続的なサポートを通じて解決への一歩をお手伝いします。
訪問看護に入らせていただく上で、利用者様が病気と付き合いながら自分らしい生活ができるように、自主性を尊重した看護サービスを提供しています。
訪問してご本人様と面会ができない場合でも、ご希望があればご家族様からの相談を受けることも可能であったりと、それぞれの利用者様にあった看護を行っております。
利用者さんの思いをしっかりと受けとめ、少しでも安心して生活できるように支援させていただきます。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応地域はおもに上記が中心で、訪問活動をおこなっています。該当エリアにお住まいの方はぜひご検討ください。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。電話やメールなどで相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

広範性発達障害の人はコミュニケーションにおいて問題をかかえていたり、こだわりが強かったり、感覚過敏だったりとさまざまな症状が考えられます。
治療にはソーシャルスキルトレーニングや生活環境の調整を通じて、障害とうまく付き合う方法を身につけていくことが大切です。
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神科に特化した訪問看護を提供しており、広汎性発達障害の方の支援も行っております。
ご家族へのサポートも一緒に行い、周りの環境から整えるお手伝いをさせていただきますので、広汎性発達障害の症状でお悩みの方は、当ステーションにご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



