精神疾患で暴れるときの正しい対処法|予防策・家族の対応・専門機関の活用


一部の精神疾患では、感情のコントロールが難しくなり、周囲の人に対して暴言や暴力をふるってしまうケースがあります。
精神疾患の身内が暴れる(この記事での「暴れる」は、「攻撃的行動」や「興奮状態」、「衝動的行動」や「判断力低下・脱抑制による衝動的行動」のことを指します)という状況に直面したとき、家族や身近な人はどう対処すべきか迷うものです。適切な対応を知っておくことは、ご本人だけでなく周囲の安全を守るためにも欠かせません。
この記事では、精神疾患を持つ方が攻撃的な行動をとってしまったときの具体的な対処法や予防策、また利用できる専門機関や支援制度について詳しく解説します。ご家族や支援者の方にとって参考になる内容をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
精神疾患を持つ方が暴れてしまう場合の対処法

対処方法一覧
対処①疾患者から逃げる
精神疾患を持つ方が暴れてしまった場合、まずは自分や周囲の安全を最優先に考えましょう。患者さんに近づきすぎず、可能であればすぐに安全な場所へ避難することが重要です。
もし攻撃を受けそうになった場合は、手や物(雑誌やカバンなど)で顔や体を守り、掴まれないように注意しながら距離を取ります。普段から危機回避の方法を知っておくと、いざという時に落ち着いて行動できます。精神科医や看護師に相談し、必要であれば専門的な危機対応のトレーニングを受けるのも効果的です。
対処②反論・挑発などをしない
暴れている患者さんに対して反論したり、挑発するような言葉をかけたりすると、状況が悪化しやすくなります。相手の怒りを増幅させてしまうため、言い返すのではなく落ち着いた態度で対応しましょう。
言葉を交わす必要がある場合でも、できるだけ短く穏やかな声で話すことがポイントです。患者さんの行動や言動に振り回されないよう、精神疾患の特性を理解して正しい対応を心がけることが大切です。
対処③落ち着くまで放置
感情のコントロールを失った患者さんは、一定時間が経つことで自然に落ち着くケースがあります。そのため、無理に止めたり説得しようとせず、安全な距離を保って静観するのも有効です。
ただし、暴れ続けて本人や周囲に危険が及ぶ場合は、放置せず次の段階の対応が必要になります。
対処④警察や救急へ連絡すべきケース
暴れ方が激しく、自分や他人に危害を加える可能性がある場合は、ためらわず警察や救急へ連絡してください。
特に刃物など危険な物を手にしている場合や、自傷行為が見られる場合は一刻を争います。専門機関に迅速に連絡することで、被害を最小限に抑えることができます。
暴れてしまう前の予防策

生活習慣の改善(睡眠・食事・アルコール制限)
精神疾患を持つ方が暴れてしまう背景には、日常生活のリズムの乱れが大きく影響していることがあります。
特に睡眠不足は感情コントロールを難しくし、暴れるきっかけになりやすいため、規則正しい生活を心がけることが大切です。
食生活においても、栄養バランスを整えた食事をとることで心身の安定につながります。さらにアルコールの摂取は症状を悪化させる場合があるため、制限または医師の指導のもとでコントロールすることが望ましいでしょう。
ストレスをためない工夫
日々のストレスが蓄積すると、些細なきっかけで怒りや不安が爆発し、暴れる行動に発展することがあります。
趣味や軽い運動、リラックスできる時間を意識的に取り入れることは、心の安定を保つ有効な手段です。また、過度なストレス環境を避けるために、生活環境の調整や人間関係の工夫も役立ちます。
本人だけでなく家族も一緒にストレスマネジメントに取り組むことで、安心できる家庭環境を築くことが可能です。
家族ができる日常的な声かけ
患者さんが暴れる前には、不安や苛立ちなどのサインが現れることが多いです。そのため、普段から落ち着いた声かけを心がけ、安心感を与えることが予防につながります。
例えば「今日はよく眠れた?」「一緒に散歩でも行こうか」といったさりげない会話は、本人が孤立感を抱かず安心できるきっかけになります。大切なのは指示や命令のように聞こえないこと。
優しい言葉と態度で接することで、信頼関係を築きやすくなり、暴れる前に気持ちを落ち着けてもらえる可能性が高まります。
このように、日常生活の見直しやコミュニケーションの工夫によって、暴れる行動を事前に防げるケースは少なくありません。
精神疾患を持つ方への対応は一朝一夕で身につくものではありませんが、家族や支援者が協力して取り組むことで、安定した生活をサポートすることができます。
家族や周囲がとるべき対応

本人に安心感を与える接し方
精神疾患を持つ方が暴れてしまう背景には、不安感や孤独感が強く影響している場合があります。そのため、日常の中で本人が安心できる言葉や態度を示すことが大切です。
例えば、落ち着いた声のトーンで「大丈夫だよ」「一緒に考えていこう」と伝えるだけでも、安心感につながります。特に感情的にならず冷静に対応することが、家族の役割として求められます。本人が「受け入れられている」と感じられる環境を整えることが、暴れる行動の抑制に役立ちます。
安全を確保するための工夫(部屋のレイアウト、避難経路)
暴れる可能性がある場合には、家庭内の安全対策を事前に整えておくことが重要です。
例えば、部屋に壊れやすい物や刃物類を置かない、家具の配置を工夫して逃げやすい通路を確保するなどが挙げられます。
特に避難経路を家族全員で共有しておくことは、緊急時の行動をスムーズにし、被害を最小限に抑えるために役立ちます。患者さんにとっても安全な空間を意識した環境作りは、日常生活を安心して送るための基盤となります。
一人で抱え込まず専門機関に相談する
精神疾患による暴れる行動に直面したとき、家族だけで抱え込むのは非常に大きな負担です。無理をして対応を続けると、家族自身が疲弊し、共倒れのような状態に陥る危険もあります。
こうした時には、地域の精神保健福祉センターや医療機関、訪問看護などの専門機関に早めに相談することが望ましいです。専門スタッフと連携を取ることで、患者さんに必要な支援を受けやすくなり、家族の心の負担も軽減されます。
家族が安心して過ごせることは、結果的に患者さんの安定にもつながります。
このように、家族や周囲の人がとるべき対応は、安心感を与える接し方・安全な環境の整備・専門機関との連携の3つに集約されます。
すべてを完璧に行うことは難しくても、少しずつ取り入れることで患者さんとの関係性が改善され、暴れる行動を減らす効果が期待できます。
専用施設に頼ることを視野に入れてもいい

専門施設の一例を紹介
①入院
精神疾患を持つ方が暴れてしまい、本人や周囲の安全が確保できない場合は、精神科への入院を検討する必要があります。入院することで医師や看護師による管理のもと、薬物療法や心理療法などを集中的に受けることが可能です。
入院期間や必要性は精神科医の判断によって決定され、無理のない形で治療が進められます。
家庭だけで支えきれないと感じた時には、ためらわず医療機関に相談しましょう。
②保健所
保健所は地域住民の健康を守るための窓口であり、精神疾患を持つ方が暴れるといったケースについても相談可能です。
家庭での対応が難しい場合や、どこに相談していいかわからない場合は、まず保健所に問い合わせるとよいでしょう。医療機関や福祉サービスの紹介、患者本人や家族へのサポートにつなげてもらえます。地域の相談窓口を把握しておくことは、いざという時の安心材料になります。
③精神科救急情報センター
精神科救急情報センターは、急を要する精神疾患の相談に対応している機関です。都道府県によって設置状況や対応時間が異なりますが、患者さんが暴れて自傷や他害の恐れがある場合など、緊急性の高い事態では非常に心強い窓口です。
あらかじめ電話番号や利用可能時間を確認しておくと、万が一の際に迅速に連絡できます。ただし、刃物を持っているなど差し迫った危険があるときには、迷わず警察へ通報することが最優先です。
このように、入院・保健所・精神科救急情報センターといった専用施設や公的機関を頼ることで、家庭内だけでは対応しきれない「精神疾患で暴れる」ケースに備えることができます。
特に家族が一人で抱え込んでしまうと心身の負担が大きくなるため、早い段階で外部の支援を活用することが安全確保と治療の第一歩となります。
急性興奮・攻撃的行動を呈する精神疾患

自らをコントロールできなくなる疾患が多い
精神疾患にはさまざまな種類があり、その中には感情や行動を自分で抑えられなくなり、暴力的な言動に至るものもあります。
暴れる行動は本人の意思だけでなく、脳の働きや症状が大きく影響していることを理解することが大切です。以下では、代表的な疾患を取り上げ、暴れるリスクについて解説します。
疾患①統合失調症
統合失調症は幻覚や妄想といった陽性症状が特徴の精神疾患です。症状による不安や恐怖から、防御的な行動を取った結果、周囲の人を攻撃してしまうことがあります。
実際には存在しない刺激に反応して興奮し、攻撃的な行動につながるケースも少なくありません。早期に治療を受け、服薬を継続することが症状悪化を防ぐ重要なポイントです。
疾患②アルコール依存症
アルコール依存症では、大量飲酒や禁断症状によって精神が不安定になり、攻撃的な行動に出ることがあります。
飲酒によって理性のコントロールが効かなくなり、家族や周囲に暴言や暴力をふるうケースは珍しくありません。長期的には肝機能障害など身体的な悪影響も出やすく、心身両面で生活が破綻してしまう恐れがあるため、断酒支援や専門治療が不可欠です。
疾患③双極性障害(躁うつ病)
双極性障害は、気分の波が「躁(そう)」と「鬱(うつ)」の両方の状態として現れるのが特徴です。
中には感情の抑えがきかなくなって衝動的に行動してしまい、攻撃的な言動に発展する場合もあります。
双極性障害による暴れる行為は周囲にとっても衝撃的ですが、症状の一部であると理解し、医療的なサポートにつなげることが大切です。
暴れる前兆を見逃さず早期治療を進めよう
精神疾患による暴れる行動には前兆が見られることがあります。例えば落ち着きがなくなる、声を荒げる、被害妄想を語るといったサインが見えたら、早めに医師に相談しましょう。
前兆を察知できれば、暴力的な行動に至る前に対処できる可能性が高まります。特に家族や支援者は、普段の様子と比べて違和感がないかを観察し、気づいたことを医師や看護師に共有することが重要です。
早期治療の開始は本人の負担を軽減するだけでなく、家庭や社会全体の安全確保にもつながります。
治療は投薬治療が一般的
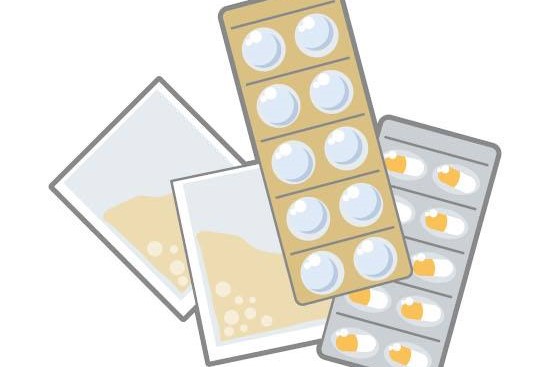
服薬によって症状が改善される場合が多い
精神疾患による「暴れる」行動は、薬物療法によって改善されることが多くあります。特に抗精神病薬は、統合失調症や双極性障害の躁状態など、興奮を伴う症状を抑えるために用いられます。
服薬を続けることで幻覚や妄想が和らぎ、感情の起伏も安定しやすくなります。副作用が出る場合もあるため、必ず医師の指示に従って継続的に管理することが重要です。
自己判断で中断すると再び暴れる可能性が高まるため注意が必要です。
興奮を抑える薬一覧
抗精神病薬にはいくつかの種類があり、患者さんの症状に合わせて使い分けられます。ここでは代表的な薬のタイプを紹介します。
治療薬①非定型抗精神病薬
非定型抗精神病薬は「新しいタイプの抗精神病薬」と呼ばれ、統合失調症の陽性症状(幻覚や妄想)だけでなく、陰性症状(無気力・引きこもり)にも効果を示します。
例としてリスペリドンやオランザピンなどがあります。比較的副作用が少なく、長期的な服用に適している点も特徴です。
治療薬②定型抗精神病薬
定型抗精神病薬は従来から使われている薬で、脳内のドーパミン神経活動を抑えることで強い興奮を沈める効果があります。
スルピリドやチアプリド塩酸塩などが代表的で、症状が急激に悪化した際に使用されることが多いです。ただし副作用として錐体外路症状(手の震えや筋肉のこわばり)が現れる場合もあるため、慎重な投薬管理が必要です。
治療薬③注射剤
抗精神病薬には飲み薬のほか、注射剤もあります。注射剤は一度の投与で2〜4週間効果が持続するため、飲み忘れによる症状悪化を防ぐのに有効です。
服薬管理が難しい患者さんにとっては、安定した治療を続けられる選択肢となります。
あくまで定期的な内服継続が前提
投薬治療は一時的に症状を抑えるものではなく、長期的に継続していくことで効果を発揮します。症状が落ち着いたからといって自己判断で服薬をやめると、再び暴れる行動や興奮状態が現れる危険があります。
そのため、医師と相談しながら定期的な服薬を続け、必要に応じて薬の種類や量を調整していくことが不可欠です。ご家族も服薬状況を見守り、サポートすることが患者さんの安定につながります。
精神科訪問看護のサポートを得ることも可能

精神科訪問看護とシンプレ訪問看護ステーション
- 日常生活の維持
- 生活技能の獲得・拡大
- 対人関係の維持・構築
- 家族関係の調整
- 精神症状の悪化や増悪を防ぐ
- ケアの連携
- 社会資源の活用
- 対象者のエンパワーメント
精神疾患を持つ方が暴れてしまう状況は、家族だけでの対応が難しいことも少なくありません。そのようなときに役立つのが精神科訪問看護です。
訪問看護では、看護師や作業療法士などの専門スタッフが自宅を訪問し、症状や生活のサポートを行います。シンプレ訪問看護ステーションでも、東京23区や西東京市、武蔵野市、埼玉県の一部地域などでサービスを提供しており、週1〜3回(場合によっては週4回以上)30〜90分の訪問が可能です。
精神疾患による不安定な状態を抱えるご本人やご家族にとって、安心して相談できる伴走者がいることは大きな支えとなります。
精神科訪問看護の内容
訪問看護で提供される支援は幅広く、症状の観察や服薬管理、再発予防のサポート、社会復帰に向けた支援などがあります。
特に「服薬を忘れてしまう」「外出が難しく通院が途切れてしまう」といった課題に対応できる点は大きなメリットです。
また、家族へのサポートも重要視されており、患者さんと接する際のアドバイスや不安の相談にも応じてもらえます。必要に応じて主治医やケースワーカーとも連携し、総合的な支援を受けられるのが訪問看護の強みです。
さらに、胃ろうや在宅酸素療法、カテーテル管理などの医療的な処置にも対応可能であるため、身体的なケアと精神的なケアを同時に受けられる点も特徴です。
利用にあたっては「自立支援医療制度」や「生活保護」などの制度を活用できる場合もあり、経済的な負担を軽減しながら継続して支援を受けられます。
精神疾患を持つ方が暴れる場面に直面したとき、家庭だけで抱え込むのは限界があります。訪問看護のサポートを取り入れることで、患者さんは安定した生活を送りやすくなり、家族も安心して日常を続けられるようになります。
信頼できる専門職とつながりを持つことが、症状の悪化防止と生活の質の向上につながるのです。
法的な支援制度や相談窓口

精神保健福祉センター
精神保健福祉センターは、精神疾患を持つ方やそのご家族が利用できる公的な相談窓口です。
暴れてしまうなどの問題がある場合でも、専門スタッフが対応方法のアドバイスをしてくれます。また、医療機関や福祉サービスとのつなぎ役として機能し、患者さんに合った支援先を紹介してくれるため、最初の相談窓口として非常に有効です。
地域で利用できる公的サービスを把握しておくことは、緊急時の安心感にもつながります。
障害者総合支援法による支援
障害者総合支援法に基づき、精神疾患を持つ方もさまざまな福祉サービスを利用することが可能です。
たとえば、日中活動の場を提供する就労支援、居宅介護サービス、短期入所サービスなどがあります。これらを活用することで、本人だけでなく家族の負担も軽減できます。制度を利用するには市区町村への申請が必要ですが、精神保健福祉センターや保健所が手続きのサポートをしてくれるので安心です。
緊急時に使える公的機関の相談先
精神疾患によって暴れる行動が激しくなり、生命や安全に危険が及ぶ場合には、ためらわず警察や救急へ連絡することが第一です。
そのうえで、精神科救急情報センターのような専門的な緊急窓口を利用することで、医療機関へのスムーズな搬送や適切な対応が可能になります。
また、地域包括支援センターや福祉課でも、家庭での困りごとについて相談を受け付けています。公的機関の電話番号や連絡先を事前に控えておくと、いざという時に迅速な対応ができます。
このように、法的な支援制度や相談窓口を活用することで、精神疾患を持つ方が「暴れる」状況に直面した際でも、家族だけで抱え込まず適切な支援につなげることができます。
身近に頼れる仕組みを知っておくことは、安心した生活を続けるための大きな力となるでしょう。
暴れることへの誤解をなくすために

精神疾患を持つ人=危険人物ではない
精神疾患を持つ方が「暴れる」場面ばかりが強調されると、あたかも全員が危険であるかのような誤解が広がってしまいます。
しかし実際には、ほとんどの患者さんは穏やかに生活しており、暴力的な行動はごく一部のケースに限られます。大切なのは、精神疾患そのものと暴力行為を切り離して理解することです。
「精神疾患=危険人物」ではなく、支援や環境次第で安定した生活を送れる方が多いという事実を、社会全体で認識していく必要があります。
正しい理解と社会的サポートの必要性
精神疾患に対する誤解や偏見は、患者さんや家族を孤立させ、治療や支援につながりにくくする原因になります。
暴れるという行動も、症状の一部として現れることがあるにすぎず、適切な治療とサポートがあれば改善や予防が可能です。そのためには、社会全体が精神疾患について正しい知識を持ち、安心して支援を受けられる環境を整えることが不可欠です。
学校や地域、職場などでの啓発活動を通じて理解を深めていくことも重要でしょう。
また、家族や支援者も「一人で抱え込まない」姿勢を持つことが大切です。
医療機関や訪問看護、福祉制度を活用することで、患者さんだけでなく支える側の負担も軽減されます。社会的なサポートを積極的に取り入れることが、長期的な安定と再発予防につながります。
精神疾患に伴う「暴れる」行動は恐怖心を与える一方で、その背景には適切な治療や支援が不足していることが多くあります。
誤解をなくし、正しく理解することで、患者さんが安心して暮らせる社会をつくることが可能です。それは患者さん本人だけでなく、家族や地域にとっても大きな安心材料となるでしょう。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

暴れてしまったときはまず身の安全を優先する
精神疾患を持つ方が暴れてしまった場合、最も大切なのはご本人を無理に制止しようとするのではなく、自分や周囲の安全を守ることです。
反論や挑発を避け、危険を感じたらすぐに安全な場所へ避難し、必要であれば警察や救急へ連絡してください。冷静に状況を判断することが、被害を最小限に抑えるポイントです。
予防・日常的な関わりが再発防止につながる
暴れる行動は突然起こるように見えても、生活習慣の乱れや強いストレスがきっかけになっている場合が多くあります。
日頃から睡眠や食事を整えること、リラックスできる時間を設けること、そして家族の声かけによって安心感を与えることが再発防止につながります。小さな積み重ねが長期的な安定を支えるのです。
専門機関や支援制度を積極的に活用する
精神疾患による「暴れる」行動を家族だけで解決するのは非常に困難です。精神科訪問看護や精神保健福祉センター、障害者総合支援法の制度など、利用できる仕組みは数多くあります。
一人で抱え込まず専門家や公的機関に相談する姿勢が、患者さんと家族双方の負担を軽減します。支援を受けることは決して弱さではなく、安定した生活を築くための大切な一歩です。
精神疾患への誤解をなくし社会全体で支えることが大切
精神疾患を持つ方に対して「危険人物」という誤解を持つのではなく、正しい理解を広げていくことが社会的な課題です。
暴れる行動も症状の一部であり、適切な治療と支援があれば改善可能です。家族や地域、医療機関が協力し、社会全体で支える環境を整えることで、患者さんは安心して生活でき、周囲も安心して寄り添うことができます。
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神疾患を持つ方やご家族をサポートするために、看護師・准看護師・作業療法士が訪問し、服薬支援や生活支援を行っています。
東京23区や西東京市、埼玉県一部地域などでサービスを展開しており、必要に応じて制度利用のご案内も可能です。暴れる行動に不安を感じた際や、日常的なサポートについて知りたいときは、どうぞお気軽にご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼

高座渋谷つばさクリニック
医師:武井智昭
外来としてはうつ病(うつ状態)が年間300名程度はおりこちらが得意分野です。この他に、思春期特有の対応(起立性調節障害や拒食症など)も行っています。心療内科としては10年、日本精神神経学会会員に所属
本記事へのコメント
興奮や攻撃的行動は家族からみて「暴れて困る」ととらえがちですが、診断名に準じた医学的な症状として捉えることが重要です。
この背景には精神疾患の合併もありますが、処方されている薬物の副作用や服薬ミスによる身体疾患が隠れている場合も比較的多いです。
「暴れる」場合で重要であることは、患者本人もそして家族も安全を確保することが最優先であり、必要があれば救急要請・入院を視野に援助をためらわず要請してください。
精神疾患の方の多くは、適切な服薬と精神的なアプローチにより安定した生活を送られており、適切な医療と周囲の理解があれば改善することが多いです。
監修日:2025年11月5日
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (5)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



