アルコール依存症と家族|正しい接し方・相談先・支援方法を徹底解説
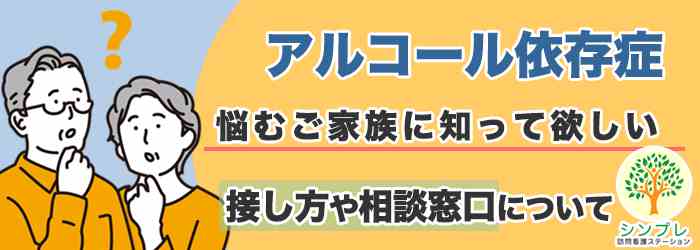

アルコール依存症は本人だけでなく、家族にも深刻な影響を与える病気です。家庭内でのトラブルや精神的負担、経済的困難など、その影響は多岐にわたります。
家族は支える立場でありながらも、孤立感や疲弊を抱えやすく、どう接すればよいのか悩むケースも少なくありません。本記事では、アルコール依存症と家族の関わり方や負担、接し方のポイントについて解説します。さらに、正しい知識を持つことで家族自身も守りながら、患者の回復を支えるための具体的な方法を紹介していきます。
アルコール依存症と家族が抱える問題

アルコール依存症と家族の関係性
アルコール依存症は単なる飲酒習慣の問題ではなく、脳や心に深刻な変化をもたらす病気です。
そのため、本人だけでなく家族も強い影響を受けます。家族は「問題を外に知られたくない」という気持ちから周囲との交流を避け、孤立してしまうこともあります。
また、子どもがいる家庭では、精神的な不安や生活環境の悪化が子どもにも及ぶリスクがあります。家族と本人が協力して治療に取り組むことで、悪循環を断ち切りやすくなります。
患者を支える家族の苦しみと負担
アルコール依存症の患者を支える家族は、日常生活や経済面でも大きな負担を抱えます。
たとえば、酔った際の暴力や物損、社会的なトラブルの後始末を家族が背負わされることもあります。さらに、経済的困窮から家族が長時間労働を強いられるケースも少なくありません。
このような状況は、患者と家族の関係性を悪化させ、精神的な疲弊をもたらします。家族自身の心身を守りながら、適切な支援を得ることが重要です。
アルコール依存症の方への接し方のポイント
- アルコール依存症は病気であると正しく理解する
- 専門機関に相談し、適切なサポートを受ける
- 家族自身の健康を優先し、無理をしすぎない
- 患者の回復を信じて支える姿勢を持つ
- 同じ悩みを共有できる人やグループを見つける
アルコール依存症は「意志が弱いから飲んでしまう」という誤解を持たれがちですが、実際には医学的に治療が必要な病気です。
家族が正しい知識を持ち、専門機関と連携することで、本人の治療効果も高まりやすくなります。治療は長期に及ぶこともありますが、家族が支え続けることで回復の道は開かれます。
アルコール依存症の経過と症状を知ろう

依存症の進行と経過
- 常習的な飲酒により耐性がつき、量が増える
- 以前と同じ効果を得るためさらに飲酒量が増える
- 飲酒していないと不快な離脱症状が出る
- 飲酒のコントロールが困難になる
- 身体・精神・社会的な問題が頻発する
アルコール依存症は、誰にでも起こり得る病気です。飲酒を繰り返すうちに気づかないうちに依存が強まり、飲酒をやめられなくなります。本人だけでなく家族が問題に巻き込まれることも多く、病気の進行に早く気づくことが重要です。
初期の段階では「ただお酒が好きなだけ」と周囲が見過ごしやすいですが、次第に飲酒が習慣化し、飲んでいないと落ち着かない、体調が悪いといった状態になります。
さらに進むと仕事や家庭生活に深刻な悪影響を及ぼし、日常生活が成り立たなくなることもあります。
見逃してはいけないアルコール依存症のサイン
- 寝酒をしないと眠れず、夜中に目が覚める
- 朝起きると気分が落ち込み、体がだるい
- 飲酒をやめると震えや不安などの離脱症状が出る
アルコール依存症の初期サインを家族が見逃さないことが大切です。本人は「ストレス解消」や「リラックスのため」と飲酒を正当化することが多いため、周囲が病気の兆候に気づくのが遅れる場合があります。こうした小さな変化を早期に発見し、専門機関に相談することが、回復への第一歩となります。
健康診断などで指摘されやすい合併症
- 肝障害(肝炎・肝硬変など)
- 胃腸障害(胃炎・胃潰瘍・下痢など)
- 膵炎や糖尿病
- がん(食道がん・胃がんなど)
- 睡眠障害
- うつ病や認知症
アルコール依存症は精神的な問題だけでなく、身体の病気を伴うことが多いのが特徴です。
特に肝臓へのダメージは深刻で、肝硬変や肝がんにつながることもあります。また、消化器系や心臓・脳への影響もあり、健康診断で異常を指摘されるケースが少なくありません。
家族がこうしたリスクを理解しておくことで、早期に医療機関へつなぐことができます。
家族がやるべきことと相談先

家族がやるべき対応の一覧
- 依存症を直視し、問題から目をそらさない
- 話し合うならお酒を飲んでいないタイミングを選ぶ
- 責めるのではなく、「治療が必要な病気」として精神科の医療機関への受診を勧める
- 本人の責任まで肩代わりせず、自立を支える姿勢を保つ
- トラブルの後始末を家族が背負わない
- 回復の兆しを積極的に認めて伝える
- 冷静さを失わず、自分の生活も大切にする
- 必ず外部の相談先を活用する
アルコール依存症の患者を支える家族の対応次第で回復の道が変わることもあります。過度に世話をしてしまうと本人が病気と向き合えず、逆に放置しすぎても症状が悪化するリスクがあります。
バランスを意識した関わり方が必要です。また、家族自身も心身の健康を守ることがとても重要です。
外部の相談窓口について
- 精神保健福祉センター
- 地域の保健所
- 精神科病院やクリニック
- 訪問看護サービス
- 自助グループ(断酒会・AAなど)
アルコール依存症は本人と家族だけで解決するのは困難です。専門の相談窓口を活用することで、家族の負担が軽減され、治療の選択肢も広がります。
たとえば、精神保健福祉センターでは専門家による助言が受けられ、保健所でも地域に応じたサポートが提供されます。医療機関や訪問看護は、治療や生活支援を通して長期的な回復をサポートしてくれます。
自助グループの活用方法
同じ悩みを持つ人たちとつながることは、家族にとって大きな支えになります。自助グループでは経験を共有し合い、孤立感を減らす効果も期待できます。
断酒会の取り組み
断酒会は日本で広く活動している自助グループで、飲酒をやめて健康な生活を取り戻すことを目的に活動しています。
本人だけでなく、家族も準会員として参加できるのが特徴で、家族の視点からの支援も大切にされています。定例会や酒害相談など、実際に役立つ活動が展開されています。
AA(アルコホーリクス・アノニマス)の支援
AAはアメリカ発祥の自助グループで、匿名性を守りながら平等な立場で回復を目指します。「12ステッププログラム」に基づき、定期的なミーティングを通じて仲間と支え合いながら断酒を継続します。
日本国内でも多くの地域で活動しており、安心して参加できる環境が整っています。
アルコール依存症を持つ家族が気をつけたいこと

家族が注意すべき行動や心構え
- 問題を家族内だけで抱え込まない
- 飲酒を助長する行動を避ける
- 依存を「本人の意思の弱さ」と決めつけない
アルコール依存症の問題は、家族だけで解決しようとすると負担が大きすぎます。
問題を隠してしまうと、家庭内で孤立し、状況が悪化することもあります。家族自身の心身を守るためにも冷静な判断と外部のサポートが必要です。
また、依存症は意思の問題ではなく病気であるため、責めたり説得で変えようとすることは逆効果になりがちです。
さらに、飲酒を我慢させようと極端な監視をしたり、本人の失敗をカバーし続けると、結果的に依存を長引かせることになります。家族が正しい心構えを持つことは、患者だけでなく家庭全体の回復にとっても大切です。
イネイブリングとは?支援と依存を助長する行為の違い
「イネイブリング」とは、依存症の人の行動を無意識に助長してしまう行為のことです。たとえば、酔って起こしたトラブルの後始末を代わりに行ったり、飲酒代を立て替えたりする行動が当てはまります。
一見すると支援のように見える行為でも、本人が責任を回避できる環境を作ってしまうため、依存を強める原因になります。
イネイブリングを避けるためには、家族が「本人の問題は本人に返す」という姿勢を持つことが大切です。もちろん見放すのではなく、適切な相談先につなげる、治療を勧めるなど、回復に向けた支援をすることが望まれます。
支援と依存を助長する行為の違いを理解し、家族も健全な距離感を保ちながら接することが重要です。
断酒後に家族が気を付けたいこと

依存症回復期に起こり得る問題
- 過去の飲酒トラブルに対する嫌悪感や不信感
- 償いを過度に求めてしまい関係が悪化する
- 過去へのこだわりから前向きになれない
- 子どもに飲酒問題の影響が残る
断酒が始まったからといって、すぐに家族関係や生活が元に戻るわけではありません。回復期には心理的な葛藤や関係性の再構築が必要です。
本人は罪悪感や再飲酒への不安に苦しみ、家族も「また同じことが起きるのでは」と緊張しがちです。こうした時期にどう対応するかが、再発予防と回復の大きなポイントになります。
家族全員で回復を目指す取り組み
アルコール依存症は本人だけの問題ではなく、家族全体の問題でもあります。家族が協力し合い、正しい知識を学びながら対応することが回復への近道です。
家族会や相談機関を活用することで、同じ立場の人と悩みを共有し、より適切な支援方法を学ぶことができます。孤立せず支援の輪に入ることは、家族にとっても精神的な支えになります。
また、本人への接し方だけでなく、家族自身が心身の健康を守ることも欠かせません。無理をせず休養を取ること、専門家の意見を取り入れることが、長期的な支援を続ける鍵となります。
精神科訪問看護を利用するメリット
断酒後の生活を安定させるためには、医療や福祉のサポートを取り入れることが効果的です。
精神科訪問看護は、アルコール依存症の患者やその家族を支えるサービスであり、自宅で安心して療養を続けられる体制を整えます。ここでは具体的なサービス内容と利用料金について紹介します。
精神科訪問看護で受けられるサービス内容
- 日常生活のサポート(服薬・健康管理など)
- 生活技能の習得や社会復帰の支援
- 家族関係や対人関係の調整
- 症状の悪化を防ぎ、再発予防につなげる支援
- 地域資源や制度の活用サポート
訪問看護では、患者本人だけでなく家族からの相談も受け付けているため、家庭全体を支える仕組みになっています。自宅で療養できる安心感と、定期的に専門職が訪問することによる心の支えは、再飲酒防止にもつながります。
精神科訪問看護の利用料金
| 負担割合 | 月の初回訪問 | 2回目以降 |
|---|---|---|
1割負担 | 1,299円/回 | 855円/回 |
2割負担 | 2,598円/回 | 1,710円/回 |
3割負担 | 3,897円/回 | 2,565円/回 |
上記は週3回までの訪問料金となります。週4回以上訪問となる場合には料金が異なります。
精神科訪問看護では、医療保険を利用することにより自己負担を軽減できるメリットがあります。
30分を一区切りに利用可能。かかった費用については、年齢や所得によって変わり、医療費の1〜3割が自己負担となります。
また早朝や深夜などの時間外に依頼する場合や、長時間の訪問を行う場合は別途料金が発生します。
また自立支援医療制度という制度を利用すると料金が1割負担になるほか、所得に応じて自己負担が0円になる場合もございます。
費用は医療保険の適用があり、各種助成制度も利用できます。生活保護や自立支援医療制度をはじめ、状況に応じた制度を活用することで、経済的負担を軽減しながら継続的に利用可能です。
精神疾患や依存症の支援ならシンプレ訪問看護ステーションへ

シンプレ訪問看護ステーションの特徴
シンプレ訪問看護ステーションは、精神科に特化した訪問看護サービスを提供しています。
アルコール依存症を含む精神疾患に幅広く対応し、患者本人と家族が安心できる生活をサポートします。訪問看護の強みは、自宅という安心できる環境で療養できる点にあります。
定期的に専門職が訪問することで孤立を防ぎ、再発のリスクを下げる効果も期待できます。
また、治療には時間がかかることが多いため、焦らずじっくりと回復を目指せるよう支援を行います。患者本人の状態だけでなく、家族へのケアも重視しているのが特徴です。「支える側の負担を減らす」ことを大切にし、長期的な回復を一緒に目指していきます。
対応可能な精神疾患・依存症
- アルコール依存症
- うつ病・双極性障害
- 統合失調症
- 発達障害(ADHD・自閉スペクトラム症など)
- 不安障害・パニック障害
- PTSD・適応障害・強迫性障害
- 認知症 など
シンプレ訪問看護ステーションでは、アルコール依存症だけでなく幅広い精神疾患に対応しています。
医師や地域の関係機関と連携しながら、利用者一人ひとりに合ったサポートを行うため、安心して利用できます。特にアルコール依存症の家族にとっては、専門のスタッフが寄り添い、患者だけでなく家庭全体を支えることができる点が大きな強みです。
対応エリアは東京23区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、府中市、東久留米市、さらに埼玉県の一部地域です。
近隣市区町村についても、訪問可能な場合がありますのでご相談ください。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応地域はおもに上記が中心で、訪問活動をおこなっています。該当エリアにお住まいの方はぜひご検討ください。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。電話やメールなどで相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ|アルコール依存症の家族に必要なのは「正しい知識」と「相談先」

アルコール依存症は本人だけの問題ではなく、家族全体に影響を与える病気です。家庭内でのトラブルや精神的負担、経済的な困難を抱え込むことで、家族も疲弊してしまいます。そのため、正しい知識を身につけ、孤立せずに支援を受けることが不可欠です。
とくに大切なのは、家族だけで抱え込まず相談先を活用することです。
精神保健福祉センターや保健所、医療機関、自助グループ、そして精神科訪問看護など、さまざまなサポートがあります。外部の力を借りることで、家族自身の心身を守りつつ、患者の回復を支えていくことができます。
また、治療は長期にわたることが多いため、家族が無理をせず、持続的に支えられる体制を整えることも重要です。アルコール依存症と向き合うご家族の方は、ぜひ一人で悩まず、専門機関やシンプレ訪問看護ステーションへご相談ください。きっと回復への道を一緒に歩んでいけるはずです。
ご相談の問い合わせはこちら▼

高座渋谷つばさクリニック
医師:武井智昭
外来としてはうつ病(うつ状態)が年間300名程度はおりこちらが得意分野です。この他に、思春期特有の対応(起立性調節障害や拒食症など)も行っています。心療内科としては10年、日本精神神経学会会員に所属
本記事へのコメント
アルコール依存症のご家族を支えておられる皆様へ。日々、大きな不安や疲れを抱えながら過ごされていることと思います。
まず、お伝えしたいのは「あなたは一人ではない」ということです。
アルコール依存症は、意志の弱さではなく、医学的な治療が必要な脳・精神の病気です。
専門機関や医療者、同じ経験を持つ仲間たちが、必ずあなたの力になることができます。支える側であるご家族自身の心と体を守ることも、とても大切です。無理をせず、ご自身の健康も優先し、孤立せずに相談してください。
回復には時間がかかりますが、適切な支援のもとで、ご本人もご家族も穏やかな日常を取り戻すことは可能となります。
私たちは、身体・精神・社会的な側面から、あなたとご家族を支え続けます。一緒に、希望の道を歩んでいきましょう。
監修日:2025年11月26日
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (5)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



