【不安障害】症状を詳しく解説。思い当たる人はひとりで悩まず相談を。
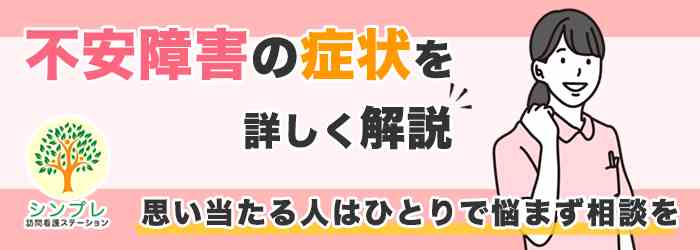
不安障害の症状は、恐怖や不安を異常に強く感じる状態のことをいいます。
不安を感じることはだれにでもあるものですが、不安障害では毎日のように恐怖や不安が続いたり発汗や動悸などのような身体的な症状が現れることもあります。
こういった症状が日常の生活にも影響を及ぼしてしまう事もあるので症状が現れている場合は、早期に治療することが大切です。
不安障害の症状について解説

精神的な症状
- 不安を感じやすく、取り越し苦労が多い
- 些細なことが気になり、イライラする
- 取り越し苦労になることが多い
- 集中力がおちた感じ
- 常に緊張していて、疲れやすい
不安障害の精神的な症状は、不安を感じやすく、些細なことが気になり、集中力が落ち、常に緊張しているなど、精神的な症状が特徴です。
また、心配や不安が大きくなると、コントロールできなくなり、日常生活や社会生活に支障をきたすことがあります。
具体的には、多くの事で取り越し苦労になることがある、緊張していてリラックスできないなどの症状もみられます。
身体的な症状
- めまい、動悸がある
- 脈拍がはやくなる
- 筋肉のこわばりや痛みがある
- 便秘や下痢など胃腸の不調がある
- 吐き気、のどの詰まる感がある
- 頭痛や頭のゆれを感じる
不安障害の身体的な症状としては、めまい、動悸、筋肉の緊張や頭の圧迫感などがあり、上記のように症状はさまざまです。
強すぎる不安や心配などから感情を上手にコントロールできず、こころとからだのバランスを崩してしまい、心身に大きな症状が生じてしまいます。
また患者さんの中には、身体的な症状を強く訴えこころの病気であることに気付かない場合もあります。
不安障害の種類を紹介

全般性不安障害
全般性不安障害とは、日常のあらゆることに対して不安を感じてしまう病気です。
例えば、自分が病気にかかったり、家族が事故に遭ったりすることを必要以上に心配してしまいます。
このような不安な考えが頭から離れず、常に不安を感じてしまいます。そのため、疲れやすさやだるさ、頭痛や肩こりなどの身体的な症状を引き起こします。
恐怖症
恐怖症の場合は、特定の事象に対して感じる症状です。例えば血、雷、高い場所、飛行機や尖ったものなど、ハッキリと目に見えるものにたいして症状がでます。
また人ごみ、行列、バスや電車の中、橋の上などといった場所やシチュエーションで恐怖を感じることもあります。
社会不安障害
社会不安障害とは、人前で何かをすることに対して強い不安を感じ、恥ずかしい思いをしたり、自分のことを品定めされているのではないかと考えてしまうことです。
人前で汗が出たり、手が震えたりなどの身体的な症状も伴い、対人関係の場面でさまざまな症状が現れます。
社会不安障害の人は、会話などでも極度の不安と緊張を感じ、人前で仕事をしたり、字を書いたりといった日常のありふれた状況でも、強い不安を感じます。
不安障害の原因と治療法を紹介

原因
不安障害の原因は、脳内の神経伝達物質であるセロトニンなどの低下やバランスの崩れが原因で発症すると考えられています。
また性格、環境面でのストレスや遺伝的な因子なども影響し、不安障害を引き起こすのではないかと考えられています。
他にも、うつ病やパニック障害などの精神疾患と併存するケースがあり、その他の精神疾患が原因で引き起こされる場合があります。
そのため上記の原因が複雑に影響され不安障害が引き起こされ、全般性不安障害、恐怖症や社会不安障害などといったさまざまな症状が生じます。
治療法
不安障害の治療には大きく分けて、精神療法と薬物療法の2つがあります。
精神療法と薬物療法は、根本的な不安障害を解消するよりは日常に感じている苦痛を和らげることをまずは目的としています。
その中で徐々に、日常の中で普通に生活が送れるように環境面など整えていきます。
生活習慣の改善
コーヒーやチョコレートなどのカフェインを含む食品を過剰に摂取すると、パニック発作の引き金になる可能性があると言われています。
治療中は、カフェインを含む食品を避け、麦茶やルイボスティーなどのカフェインを含まない食品に置き換えることをおすすめします。
ただし、個人差があり、カフェインが精神的に不安感を高めて症状を悪化させることもあるので注意が必要です。まずは日常の食生活を見直し、体調管理を整えることから治療が始まります。
マインドフルネス
マインドフルネスとは、仏教の瞑想法と西洋医学の心理療法を組み合わせた手法です。
自分の心と体の感覚に意識を向け、今起きていることをありのままに受け入れる瞑想方法です。
認知行動療法
認知行動療法は、ストレスを感じた出来事に対して、頭の中に浮かぶ考えや感情、身体の反応、行動を分析する心理療法です。
自分の考えや行動を見つめ直し、ストレスの原因となる考えを修正することで、考え方を変えていきます。
一般的には、医師や専門のカウンセラーと面談しながら、何度もカウンセリングを行います。また、薬物療法と併用することで、より効果的に治療を進めることができます。
薬物療法
不安障害は、脳内の神経伝達物質であるセロトニンが低下しています。そのため脳内の改善をはかるためにSSRIや三環系抗うつ薬などの抗うつ薬を用います。
しかし、抗うつ薬には即効性がなく効果が実感するまでに2週間程度必要だと言われています。そのため併用して、即効性のある抗不安薬を処方されることが少なくありません。
服用には、医師の診断の元、服用方法を必ず守るようにしましょう。
ただの心配症だと思い気づかない事も

不安障害の初期症状は、本人でも「気にしすぎているかも」と感じることもあり、気づきにくいことがあります。
不安障害は、単なる心配性とは異なり、眠れなくなったり、電車に乗れなくなったり、仕事に集中できなくなったりして、日常生活に支障をきたす症状があります。
しかし、周囲から「気のせい」「考えすぎ」と扱われることがあり、相談をためらったり、我慢したりして、医療機関を受診が遅れることがあります。
不安障害の初期段階においても、早期発見・早期治療が重要です。不安を感じたら、自分だけで悩まず、医療機関に相談しましょう。
症状に心当たりある方へ相談窓口紹介

- 精神科・心療内科
- 保健所・精神保健福祉センター
- 電話
- SNS相談窓口
不安障害の症状に心当たりのある方は、さまざまな専門機関や窓口に相談することができます。
医療機関では、精神科や心療内科を受診することができます。また、地域には必ず保健所または精神保健福祉センターがあります。
保健所や精神保健福祉センターでは、心の問題や病気で困っているご本人やご家族からの相談を受け付けています。各センターの規模によって異なりますが、医師、精神保健福祉士、臨床心理士などの専門家が在籍しています。
「自殺対策支援センターライフリンク」「こころのほっとチャット」などがあり、電話、Skype、LINE、Twitter、Facebookやメールでも相談が可能です。
精神科訪問看護という手段もある

精神科訪問看護とは
| サービス名 | 精神科訪問看護 |
|---|---|
ケア内容 |
・日常生活の維持 ・生活技能の獲得・拡大 ・対人関係の維持・構築 ・家族関係の調整 ・精神症状の悪化や増悪を防ぐ ・身体症状の発症や進行を防ぐ ・ケアの連携 ・社会資源の活用 ・対象者のエンパワーメント |
精神科訪問看護では、「健康状態の観察」「病状悪化の防止・回復」「社会復帰の支援」など、症状の改善に向けてさまざまなポートを受けることができます。
訪問してご本人様と面会ができない場合でも、ご希望があればご家族様からの相談を受けることも可能であったりと、それぞれの利用者様にあった看護を行っております。
また住み慣れた自宅で療養できるので、安心感が得られることや訪問看護の職員が定期的に自宅に訪問することによって孤立や孤独感が軽減され、心の支えを得られるというメリットもあります。
そのほかにも必要に応じて、医師や保健師、ケースワーカーなどの関係機関と連携し、病状の悪化の防止や早期回復につながるようサポートを行います。
精神科訪問看護の内容
| サービス名 | 精神科訪問看護 |
|---|---|
職種 |
・看護師 ・准看護師 ・作業療法士 |
訪問日数 |
原則週3日以内 (※例外もあります。) |
精神科訪問看護は、原則週1日〜3日、看護師や作業療法士などの資格を持つスタッフがお伺いします。
訪問看護は主治医が必要と判断すれば利用することが可能であり、年齢などの制限はなく、医師の判断で利用の有無が決定します。
また訪問看護の中でも精神疾患に特化したサービスができるのが、精神科訪問看護となります。
不安障害をお持ちならシンプレへ

シンプレの特徴
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神科に特化した訪問看護サービスを展開しており、患者さんが自宅でも安心してケアを受けられる看護を提供しています。
病気と付き合いながら自分らしい生活ができるように、自主性を尊重した看護サービスを提供しています。
また、病院、行政、在宅との情報共有を行い、それぞれの専門性を活かしながら治療や社会復帰のサポートができるのも特徴です。
シンプレは訪問看護サービスを通して利用者の不安を受け止め、治療への頑張りを一緒に共有し、心から安心できる居場所づくりをお手伝いします。
シンプレの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応地域は主に上記が中心で、訪問活動を行っています。該当エリアにお住まいの方はぜひご検討ください。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
サービス内容をくわしく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。電話やメールなどで相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
また、HPのほかにもTwitterやLine、TikTokなどのSNSでも情報を発信していますので、ぜひご覧ください。
対象となる精神疾患
・些細なことに不安や恐怖を感じ日常生活に支障がでる
・イライラや恐怖で夜よく眠れない
うつ病
・気分の落ち込みや意欲の低下
・体のだるさや痛み
統合失調症
・幻覚や妄想という症状が特徴的
・生活に支障をきたしてしまう
ADHD
・不注意さ、多動性、衝動性が特徴的
シンプレは精神疾患に特化した訪問看護ステーションで、不安障害の他にもうつ病や統合失調症など、幅広い疾患を対象としています。
治療においては、家族のサポートや安心できる環境作りが重要なため、精神科訪問看護では安心して自宅療養できる環境を整え、再発を予防していきます。
シンプレは精神疾患に特化した訪問看護サービスで、家族とともに本人に寄り添い、本人らしく生きていけるようサポートします。
ご利用をご検討の際はお気軽にご連絡ください。 ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

これまで、不安障害の症状や種類について解説してきました。不安障害の原因は、非常に特徴的なものがあります。
そのため、患者さまは強い不安感に襲われ、日常生活を送ることが困難になっているのです。治療には、心理療法や薬物療法が用いられますが、日常生活からのケアも重要です。
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神科に特化した訪問看護を行っています。症状悪化の防止や病気との付き合い方、外出などの日常生活のお手伝い、ご家族へのサポートなど、幅広いケアを提供いたします。
不安障害でお悩みの場合には、ぜひシンプレ訪問看護ステーションにご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



