【強迫性障害】恐怖・不安・こだわりなどの症状について解説!
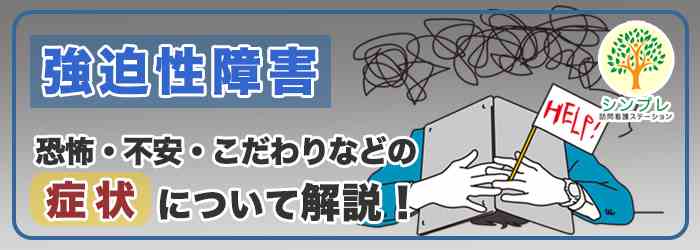
強迫性障害の症状は玄関の鍵やガス栓を閉めたかどうかが気になるあまり家に何度も戻ってしまったり、汚れなどの恐怖から消毒などを過剰にくり返すなどがあります。
キレイ好きや少し神経質なだけだと深刻にとらえず進行し、うつ病など他の疾患を患ってしまう事も珍しくありません。
自分ではひどくない症状だと感じている方も心当たりのある場合は早めに医療機関を受診するようにしましょう。
強迫性障害の主な症状

不潔恐怖と洗浄
不潔恐怖、洗浄行動とは、不潔だと感じるものに触れなくなったり、手やモノが汚れているのではと感じてしまうことから何度も繰り返し手を洗ったりすることをさします。
手を洗いすぎるあまり、ひどい手荒れを起こしてボロボロになっている方を見かけることも少なくありません。
こうした行為は次第に手順が込みいっていき、何時間もかかる儀式になるなど、日常生活に大きな支障をきたすことが多いといわれています。
加害恐怖
加害恐怖とは、自分の不注意などで他人に危害を与えてしまったのではないかと不安になり、その考えが頭から離れない症状です。
刃物や車などの危険なものを見ると、誰かに危害を加える自分を想像してしまったり、誰かをひいたかもしれない、誰かを殺してしまったかもしれないと不安にるような症状が見られ、自分が加害者になるのではないかと、日常生活で不安を感じています。
確認行為
確認行為とは、カギ、戸締り、ガス栓、電気のスイッチなどを何度も確認したり、じっと見たり、指差しで確認したり、手で触って確認したりすることを指します。
何度も戻ってきては確認しなければ気が済まないため、外出できなくなってしまったり、遅刻や欠席をするなど、生活上の支障をきたす場合が多いです。
また、こういった確認行為を本人だけでなく、家族にも強要してしまうケースも少なくありません。
自分でも気にしすぎていることがわかっていても、気になって仕方なく、気づけば何十回も確認してしまうのが、確認行為の特徴です。
その他の症状
- 儀式行為
- 数字へのこだわり
- 物の配置、対称性などへのこだわり
そのほかの症状として、いつどんな時でも同じ手順で行動しようとする「儀式行為」や不吉と感じる数字や幸運とされる数字に過剰なこだわりを見せる「数字へのこだわり」などがあります。
儀式行為は途中で手順を間違えるとはじめからやり直そうとし、1つのものごとを終えるまでに時間がかかるというのが特徴です。
また数字へのこだわりを持っている方はテレビ、時計、カレンダーなどさまざまなものから数字を拾い、不吉な数字を見つけるとそれを打ち消すために別の数字を思い描いたりします。
これら以外にも、物の配置や対称性に一定のこだわりを持ち、必ずその通りになっていないと不安を感じるといった方もいたりと強迫性障害の症状はさまざまです。
強迫性障害の原因

強迫性障害の原因はいまだに完全にはわかっていませんが、気質要因、環境要因、遺伝要因、生理学的要因などが発症に影響を与えていると考えられています。
神経質な性格や完璧主義な性格などの気質や、物事に対してネガティブな感情を持ちやすい方や、回避してしまう行動パターンをとってしまう方なども、強迫性障害を発症しやすいと考えられています。
また、物事に対してネガティブな感情を抱きやすく、回避してしまう行動パターンをとってしまう場合も、強迫性障害を発症しやすいと考えられます。
強迫性障害と併発しやすい疾患

- うつ病
- 不安障害
- 強迫性パーソナリティー障害
強迫性障害の人は、うつ病、不安障害、強迫性パーソナリティー障害、チック症、摂食障害など、他の精神疾患を合併するリスクが高いと言われています。
特にうつ病に関しては、強迫性障害の人が一生のうちにうつ病を発症するリスクが65%近くあると考えられています。
また、強迫性障害は以前は、不安を主症状とする「不安障害」の一種とされていました。
しかし、不安や恐怖よりも嫌悪感や道徳心と結びついている症状が多いことから、現在では不安障害から独立した思考や行動の病気に分類されています。
強迫性障害かもしれないと感じたら

専門家に頼る
- 戸締り確認で家に戻り約束の時間に遅刻する
- 日々の不安から心身ともに疲れている
- 強迫観念に周囲の人を巻き込んでいると感じる
強迫性障害は、誰もが生活の中で普通にすること(戸締りの確認や手洗いなど)の延長線上にあるものです。
「もしかしたらちょっとやりすぎか」なのか「自分は少し神経質なだけ」という判断は難しいところです。
例えば、戸締りの確認や手洗いに時間を取られたり、火の元を確認しに家に何度も戻ったり、家族にも確認を強要し、困っている様子がうかがえる場合などが、強迫性障害の症状として考えられます。
このような症状が見られる場合には、医療機関への相談を考えてみましょう。
強迫性障害の方への接し方
強迫観念や強迫行為は、本人もやりたくないのに、どうしてもやめられなくなってしまうものです。
強迫行為は、不安を解消するための手段です。そのため、無理やりやめさせようとするのではなく、見守ってあげることが大切です。
また、少しでも強迫行為が減った場合は、それを評価したり褒めたりすることで、本人の自信につながります。
強迫性障害の人は、周囲の人から理解されず、苦しんでいることが多いです。まずは、病気であることを理解してあげることが大切です。
強迫性障害の治療

心理療法
強迫性障害の場合、認知面からのアプローチが難しいため、行動面からのアプローチである「曝露反応妨害法」を行うことがあります。
この治療は、本人が恐れている状況に自ら曝露し、症状が出ても我慢することで、不安に慣れて認知の変化を促すというものです。
例えば、汚いと思うものを触って、手を洗わずに我慢する、留守にした自宅が鍵をかけて外出したか心配でも、施錠を確認するために戻らないで我慢するなどです。
しかし、こういった心理療法はエネルギーを使うことが多いため、精神的に落ち着いたときに行うことが大切です。
心理療法は地道な積み重ねが必要になりますが、少しずつ改善していくことで、行動範囲やできることが広がっていきます。
薬物療法
強迫性障害の治療には、薬物療法と認知行動療法の併用が一般的です。
薬物療法では、セロトニンの働きを強める抗うつ薬であるSSRIが用いられます。SSRIを服用することで、不安や恐怖などの症状が緩和し、認知行動療法の導入がしやすくなります。
相談窓口

・よりそいホットライン
・こころの健康相談ダイヤル
電話・窓口
・保健センター
・精神保健福祉センター
強迫性障害でお悩みの方の問い合わせ窓口として、上記のようなものがあります。
「よりそいホットライン」は、24時間電話相談の受付をしています。相談内容に応じて、対面相談に切り替えたり、公的機関につなげたりしてくれます。
保健センターや精神保健福祉センターには、施設の規模間によっても異なりますが、医師や精神保健福祉士、臨床心理士などの専門家が在籍しています。
今すぐに誰かに話を聞いてほしい、1人で抱え込んで辛い、周りに相談できる人がいないという場合には、ぜひこれらの相談窓口に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
精神科訪問看護という選択肢も

精神科訪問看護とは?
・精神科・心療内科に通院中の方
・精神疾患の診断を受けた方
・診断がなくとも医師が必要と判断した方
訪問する人
・看護の専門職
・リハビリテーションの専門職
訪問時間
・医療保険
(30分から90分程度)
精神訪問看護とは、精神科勤務経験や研修を受け資格を持っている看護師や作業療法士等が精神疾患をもつ方の自宅に直接訪問して、在宅医療を提供するサービスです。
訪問時間については医療保険の場合は30分から1時間半程度となっています。ご利用者様の体調に合わせて時間を調整いたします。
また訪問回数は基本的に週に3回まで利用することはできます。ただし条件によっては週に4回以上利用することも可能です。
精神科訪問看護のメリット
- 自宅に居ながら専門的なケアが受けられる
- 自宅での様子を主治医に連携できる
- 対人関係や日常生活の支援を受けられる
精神科訪問看護のメリットは、自宅にいながら専門的なケアを受けられる、自宅での様子を主治医に連携できる等が挙げられます。
退院後も自宅でのケアに移行できるのも訪問看護のメリットの1つです。住み慣れた自宅にいながら医療サポートを受けられるため、より生活に根差した支援を受けることが出来ます。
また必要時には家族への助言を行い、社会資源の活用をサポートすることで、療養環境を整え治療に集中できるよう支援します。
精神科訪問看護の料金
| 負担割合 | 月の初回訪問 | 2回目以降 |
|---|---|---|
1割負担 | 1,299円/回 | 855円/回 |
2割負担 | 2,598円/回 | 1,710円/回 |
3割負担 | 3,897円/回 | 2,565円/回 |
上記は週3回までの訪問料金となります。週4回以上訪問となる場合には料金が異なります。
精神科訪問看護では、医療保険を利用することにより自己負担を軽減できるメリットがあります。
30分を一区切りに利用可能。かかった費用については、年齢や所得によって変わり、医療費の1〜3割が自己負担となります。
また早朝や深夜などの時間外に依頼する場合や、長時間の訪問を行う場合は別途料金が発生します。
また自立支援医療制度いう制度を利用すると料金が1割負担になるほか、所得に応じて自己負担が0円になる場合もございます。
自立支援医療制度(精神通院)
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 生活保護 |
0円 |
| 低所得1 |
2,500円 |
| 低所得2 |
5,000円 |
| 中間所得1 |
5,000円 |
| 中間所得2 |
10,000円 |
| 一定所得以上 |
20,000円 |
表の料金は所得に応じた医療費の月額自己負担額の上限額となっております。
表の料金を超えた場合には、自己負担なしで医療が受けられます。
自立支援医療(精神通院医療)制度は、精神に障害のある方の、障害の軽減などのために医療の自己負担費が補助されます。
助成の内容としては精神科にかかわる医療費が1割負担になることと、所得に応じて月の自己負担上限額が設定され上限額を超えた分に関しては自己負担がなしとなります。
ただし、すべての医療機関で1割負担になるわけではありません。登録を行った病院・薬局・精神科訪問看護などの医療機関で対象となります。
精神疾患をお持ちならシンプレへ

シンプレの特徴
シンプレ訪問看護ステーションは、精神疾患をお持ちのかたの看護に特化しており、さまざまな精神疾患に対応が可能です。
各医療機関や行政と常に連携をとり、多方面から利用者さまをサポートできるよう心がけております。
また訪問看護に入らせて頂くうえで、地域で暮らす精神疾患のあるかたの自主性を尊重しているのもシンプレ訪問看護ステーションの特徴です。
強迫性障害の症状に該当するのかわからない、病気なのかどうかの判断ができないといった場合でもぜひ一度お気軽にご相談ください。
シンプレで対象となる精神疾患
・不安とりつかれて、なかなか離れない
・何度も確認しないと気が済まない
不安障害
・些細なことに不安や恐怖を感じ日常生活に支障がでる
・イライラや恐怖で夜よく眠れない
うつ病
・気分の落ち込みや意欲の低下
・体のだるさや痛み
シンプレ訪問看護ステーションでは精神科に特化した訪問看護サービスを提供しており、強迫性障害、不安障害、うつ病などさまざまな精神疾患に対応しています。
精神疾患を抱えている方の中には、日常生活が困難になったり、人とのコミュニケーションがうまくとれなくなったりすることもあるでしょう。
シンプレ訪問看護ステーションでは、そういったお悩み、不安点についてご相談に乗り、症状や病気の回復にむけてサポートさせていただいております。
どんな小さなお悩みやご相談でも受付けしておりますので、お気軽にご相談ください。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応地域はおもに上記が中心で、訪問活動をおこなっています。該当エリアにお住まいの方はぜひご検討ください。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。電話やメールなどで相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

強迫性障害の症状には、不潔洗浄、加害恐怖、確認行為のような多様な症状があることを解説しました。
また、原因は性格、生育歴、ストレス、感染症など多様な要因が関係していると考えられていますが、はっきりとはわかっていません。
しかし、ストレスをうまく対処したり、無理のない生活を送ったりすることで、症状の悪化や再発を防ぐことができます。
わたしたち、シンプレ訪問看護ステーションもきっとお役に立てることがあります。
強迫性障害の症状ででお困りの方や、ご家族に強迫性障害の方がいて、相談ごとがある場合には、シンプレ訪問看護ステーションへご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



