過食症は病院で治療すべき?特徴・症状・原因・治療法を徹底解説
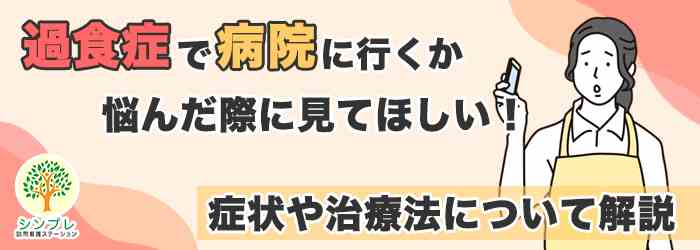

「過食症かもしれないけれど、病院に行くべきなのか…」と悩む方は少なくありません。過食症は自分の意思だけで克服するのが難しい病気であり、放置すると身体的・精神的な健康に深刻な影響を与えます。特に病院という選択は、回復への大きな一歩となります。
この記事では、病院で治療するべき過食症の特徴や症状、原因、受診のタイミングや検査・治療法について詳しく解説します。さらに、シンプレ訪問看護ステーションによるサポートについてもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
病院で治療するべき過食症の特徴

過食症にはいくつかのタイプがありますが、特に病院での治療が必要とされる代表例が「神経性過食症」と「過食性障害」です。それぞれの特徴を理解することで、受診の必要性を判断しやすくなります。
神経性過食症(むちゃ食い症)
神経性過食症は摂食障害の一つです。
自分の意思ではコントロールできない強迫的な過食を繰り返し、体重増加を防ぐために嘔吐や下剤の乱用といった代償行為を行うのが特徴です。自己評価が体型や体重に大きく依存しているため、太ることへの恐怖が常に付きまといます。
自分ではコントロールできない
過食が生活に悪影響を及ぼしていると理解していてもやめられず、強い苦痛を伴います。
大食いとの違いは「本人の意思で止められない」という点にあり、病的な性質を持っています。
20代女性に多い
統計的に、神経性過食症は20代女性に多く見られます。
大学生や社会人、主婦層など幅広い年代に及びますが、特に若年層に多い傾向があり、社会的プレッシャーや体型へのこだわりが背景にあると考えられています。
過食性障害
神経性過食症と似た症状を持つのが「過食性障害」です。短期間に大量の食事を摂り、自己嫌悪や強い罪悪感に苦しむ点が特徴です。
ただし、神経性過食症と異なり、嘔吐や下剤の使用といった代償行為は見られません。
神経性過食症と似た症状
どちらもコントロールできない過食を繰り返しますが、過食性障害では「埋め合わせ行動」がなく、過食後にダイエットを試みる傾向があります。
神経性過食症よりも寛解しやすい
研究によれば、過食性障害は神経性過食症に比べて回復(寛解)しやすいとされています。
ただし、放置すれば慢性化する恐れがあるため、病院での早期治療が重要です。
このように、過食症にはタイプによって異なる特徴がありますが、いずれも自力での改善は難しい病気です。次の章では、過食症が心身にどのような症状をもたらすのかを解説します。
過食症の症状

過食症では、身体面と精神面の両方に影響が現れるのが特徴です。
また、他の精神疾患や問題行動と併存することも多く、病院での治療が欠かせません。ここでは「身体・心の症状」と「併存しやすい精神疾患や問題行動」に分けて詳しく見ていきます。
身体・心の症状(肥満・胃腸障害・うつ症状など)
・肥満や体重増加
・胃もたれ、胃痛、消化不良
・虫歯、唾液腺の腫れ、のどの痛み
・低カリウム血症や不整脈
・栄養障害、慢性的な疲労感
心の症状
・強い自己嫌悪や無力感
・「太ること」への強い恐怖
・気分の落ち込みやうつ症状
・不安やイライラ
・こだわりの強さ、強迫的な思考
過食症は、単に「食べ過ぎる」だけの問題ではなく、身体の機能や心の健康に大きな負担をかけます。消化器系の不調や肥満に加え、低栄養や不整脈など命に関わるリスクもあります。
また、精神面では「食べてしまった自分を責める」思考が強く、うつ病や不安障害の発症につながるケースも少なくありません。
これらは本人の意志の弱さではなく、病気による症状であることを理解することが大切です。
併存しやすい精神疾患や問題行動(うつ病・依存症・自傷行為など)
・うつ病、気分障害
・不安障害
・アルコール依存症などの依存症
・パーソナリティ障害
問題行動
・自己誘発性嘔吐
・下剤や利尿薬の乱用
・窃盗や浪費などの衝動的行動
過食症の患者さんは、他の精神疾患を併存していることが多く見られます。
特にうつ病や不安障害は高頻度で併発し、症状を悪化させる要因になります。また、強い罪悪感やストレスから衝動的な行動に出ることもあり、生活全体に深刻な影響を及ぼします。
例えば「過食のためのお金を得る目的での窃盗」や「嘔吐や下剤乱用による身体リスク」などが典型的です。こうした背景からも、専門医や心理士など複数の専門家が連携して治療にあたる必要があります。
過食症の症状は多岐にわたり、身体と心の両面に深刻な影響を及ぼすため、早期の病院受診が重要です。次の章では、過食症がなぜ発症するのか、その原因について解説します。
過食症の原因

過食症は単純に「食べ過ぎてしまう性格」や「意思の弱さ」が原因ではありません。実際にはさまざまな要因が複雑に絡み合い発症する病気です。ここでは代表的な原因を整理して解説していきます。
さまざまな要因が絡み合って起こる
過食症の背景には、心理的要因・環境的要因・生物学的要因などが複数重なり合っています。
例えば、完璧主義や自己肯定感の低さといった性格傾向、家庭環境でのストレスや人間関係の不安定さ、さらに現代社会における「痩せていることが美しい」という価値観が強いプレッシャーとなり、過食に結びつくことがあります。
また、神経伝達物質のバランス異常など、脳の働きそのものが関与しているとも考えられています。
遺伝子的要因も考えられる
過食症には遺伝的な要素が関与している可能性も報告されています。特定の遺伝子が原因と断定されているわけではありませんが、第10染色体上の領域に関連があることが確認されています。
親や兄弟姉妹に摂食障害を持つ人がいる場合、発症リスクが高まるという研究もあり、遺伝と環境が相互に影響し合って発症につながると考えられています。家族歴がある場合は注意が必要です。
過食症になりやすい人の特徴
・若い女性に多い
性格傾向
・完璧主義で努力家
・他人からの評価を気にしやすい
・自己評価が低い
・ストレス解消が苦手
過食症は誰にでも起こりうる病気ですが、特に上記のような特徴を持つ人に多い傾向があります。たとえば「頑張りすぎてしまう完璧主義」や「他人に認められたい思いが強い」タイプは、日常のストレスを抱え込みやすく、食行動に依存してしまうことがあります。
また、自己評価が低い人は「自分を罰する手段」として過食に走ることもあり、精神的負担が症状をさらに悪化させることがあります。
もちろん、これらの特徴を持つ全ての人が過食症になるわけではありません。しかし、発症リスクを高める要因として理解しておくことは重要です。次の章では、実際に過食症になったときにどの病院を受診すべきかを解説していきます。
過食症になってしまった時の病院の受診
過食症は自分だけで克服することが難しい病気です。放置すると身体的・精神的な健康を損ない、慢性化や再発のリスクも高まります。そのため病院での受診は非常に重要です。ここでは「受診先の選び方」「受診のタイミング」「初診時に伝えるべき内容」について解説します。
受診先の選び方(精神科・心療内科・摂食障害専門外来)
過食症の診療科は主に精神科や心療内科です。特に「摂食障害専門外来」がある病院では、過食症の治療経験が豊富な医師や心理士が在籍しているため安心です。
身体合併症(栄養障害・不整脈・胃腸障害など)がある場合には、内科と連携して診療を行うケースもあります。精神面と身体面の両方から治療を進められる病院を選ぶことが望ましいでしょう。
受診のタイミング(症状が長引く・生活に支障がある時)
「自分でなんとかなるかもしれない」と思って受診を遅らせてしまう方は少なくありません。しかし、症状が続くほど改善は難しくなります。以下のような場合は受診を検討しましょう。
- 過食や嘔吐、下剤・利尿薬の乱用が続いている
- 体重が大きく増減している
- 月経が止まっている、または不規則になっている
- 吐きダコやむくみなどの身体症状がある
- 気分の落ち込みや不安などの精神症状が強い
これらの症状が見られる場合、自己判断で放置せず、早めに専門医へ相談することが大切です。早期に病院を受診することで回復の可能性は高まるため、迷っている方もまずは一歩踏み出しましょう。
初診時に伝えるべき内容(食行動・体重変化・気分の状態)
初診では、現在の症状や生活習慣について詳しく医師に伝えることが大切です。具体的には以下の情報を整理しておくと診察がスムーズになります。
・過食の頻度や食べる量
・嘔吐や下剤使用など代償行為の有無
・体重の変化やBMI
・気分の状態(不安・落ち込み・イライラなど)
・生活への影響(学校・仕事・家庭での支障)
・併存している精神疾患や服薬の有無
医師はこうした情報をもとに診断や治療方針を決定します。正確に伝えることが、より適切な治療を受けるための第一歩です。特に「恥ずかしいから」と隠してしまうと正確な診断が難しくなるため、なるべくありのままを伝えることが大切です。
過食症の受診は勇気がいる行動ですが、「病院に行くこと自体が治療のスタート」です。次の章では、過食症の検査や治療法について詳しく解説していきます。
過食症の検査・治療

過食症の診断と治療には、身体的な検査と心理的な評価の両面が必要です。単に「食べすぎの問題」として扱うのではなく、心と身体の両面を診る病院での治療が不可欠です。
ここでは検査方法、治療法、予後について解説します。
過食症の検査(血液検査・心理検査など)
・血液検査(栄養状態・電解質異常の確認)
・心電図(不整脈の有無)
・歯科検査(虫歯・歯の損傷)
・内視鏡検査(胃や食道の損傷確認)
・心理検査(摂食行動や精神状態の評価)
過食症では、食行動の問題だけでなく、身体に深刻なダメージが及んでいることが多いため、血液検査や心電図などで合併症を確認します。
また、心理検査を通して「過食の背景にある心理的要因」を把握することも重要です。心身両面からの総合評価が診断の鍵となります。
過食症の治療
過食症の治療は、精神療法・薬物療法・生活指導を組み合わせるのが一般的です。
患者の状態に合わせて、病院で複合的にアプローチしていきます。
精神療法(認知行動療法・対人関係療法)
認知行動療法では「過食につながる思考パターン」を修正し、対人関係療法では人間関係のストレス要因にアプローチします。
これらは過食をやめられない心理的背景に直接働きかける治療です。
薬物療法(抗うつ薬など)
抗うつ薬や抗不安薬が処方されることがあります。特に気分の落ち込みや強い不安を伴う患者には有効で、過食行動の抑制や併存症状の改善に役立ちます。
ただし、薬物療法は単独ではなく精神療法と組み合わせて行うのが基本です。
栄養指導・生活改善
管理栄養士による栄養指導も欠かせません。偏った食事や不規則な生活を見直し、バランスの取れた食習慣を身につけることで、心身の安定を促します。
また、規則正しい生活リズムを整えることが再発防止にもつながります。
過食症の予後(回復の見通しと再発防止)
過食症は一度の治療で完治する病気ではなく、改善と再発を繰り返すことが多いのが特徴です。しかし、継続的に治療を受け、家族や専門家のサポートを得ながら生活を整えることで、寛解に至る可能性は十分にあります。
再発防止のためには、精神療法や薬物療法の継続に加え、生活の中でストレスを適切に解消する方法を学ぶことが重要です。周囲の理解と支援も、回復の大きな力となります。
このように、過食症の治療は単に「食べ方を改善する」だけではなく、心理的要因・身体的要因・生活習慣の三方面からのアプローチが必要です。次の章では、精神疾患をお持ちの方に向けたシンプレ訪問看護ステーションの取り組みをご紹介します。
精神疾患をお持ちならシンプレへ

シンプレの特徴
- 精神疾患に特化した訪問看護
- 摂食障害(過食症・拒食症)を含む幅広い疾患に対応
- 自主性を尊重し、一人ひとりに寄り添った看護
- 病院・行政・地域との連携による安心サポート
シンプレは、過食症のような摂食障害を含む精神疾患に特化した訪問看護ステーションです。
利用者さまが病気と向き合いながらも「自分らしい生活」を送れるよう、自主性を尊重した支援を行っています。
また、医療機関や行政との情報共有を行い、在宅での生活支援・服薬サポート・再発予防・社会復帰支援など、多角的なサポートが可能です。
「病院に通うのが難しい」「一人では治療を続けられるか不安」という方に、訪問型のサービスは大きな助けになります。
過食症をはじめとする精神疾患は、本人だけでなくご家族も支えが必要です。シンプレはその両方に寄り添い、安心できる生活環境を一緒に整えていきます。
対応エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリアは以下の通りです。
- 東京23区
- 西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・東久留米市
- 埼玉県一部地域
上記以外の近隣市区町村でも訪問可能な場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
週1〜3回、1回あたり30〜90分を目安に訪問を行っており、土日や祝日も対応可能です。
過食症や精神疾患で「病院に通い続けるのが難しい」「在宅でのサポートがほしい」と感じている方は、ぜひ一度シンプレへご相談ください。 ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

過食症は「神経性過食症」と「過食性障害」に分けられる
過食症は大きく分けて神経性過食症と過食性障害の2種類があります。
いずれも「自分ではコントロールできない過食」が特徴ですが、代償行為の有無など違いがあります。神経性過食症では嘔吐や下剤の乱用が伴うことが多く、心身への負担が非常に大きいのが特徴です。
一方、過食性障害では代償行為はなく、比較的寛解しやすいとされていますが、放置すれば慢性化する恐れもあります。
症状が続く場合は早めに病院を受診することが大切
過食症は放置して自然に治るものではなく、慢性化・重症化しやすい病気です。
肥満や胃腸障害などの身体症状に加え、うつ症状や依存症、自傷行為などの精神的リスクを伴います。そのため、症状が続くときは病院での受診が必要です。
精神科や心療内科、摂食障害専門外来での早期治療により、回復の可能性は大きく高まります。迷っている間にも症状は進行してしまうため、できるだけ早めの受診が推奨されます。
治療は精神療法・薬物療法・栄養指導を組み合わせるのが基本
過食症の治療は、精神療法・薬物療法・栄養指導を組み合わせるのが基本です。
精神療法では認知行動療法や対人関係療法が行われ、過食を引き起こす心理的背景にアプローチします。
薬物療法では抗うつ薬や抗不安薬が症状改善に用いられます。さらに、管理栄養士による栄養指導や生活改善も重要で、心身のバランスを整える支援が行われます。
訪問看護など支援を活用すれば回復につなげやすい
病院での治療に加え、訪問看護など外部の支援を活用することで、より安定した回復を目指すことができます。
訪問看護では服薬管理や体調チェック、生活リズムの調整、家族へのサポートなど幅広い支援を受けられます。患者さんだけでなくご家族にとっても大きな安心につながるため、再発防止や社会復帰に向けた重要なサポート体制となります。
過食症は深刻な病気ですが、正しい知識と早期の病院受診によって回復の道は開かれます。
一人で抱え込まず、専門家や支援サービスを活用しながら、健康的な生活を取り戻していきましょう。
ご相談の問い合わせはこちら▼

菅原クリニック東京脳ドック
医師:伊藤たえ
脳神経外科医20年、頭痛患者さんでうつや不安障害をお持ちの方も多く対応しております。所属:日本脳神経外科学会、日本脳卒中学会、日本脳ドック学会、日本認知症学会
監修日:2025年11月5日
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (5)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



