精神作用物質による依存症の症状って?当てはまらないかチェックしよう
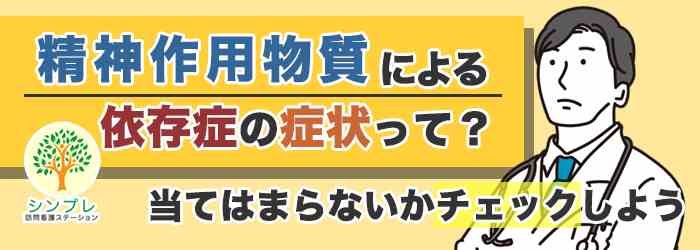
精神作用物質の依存症とは、アルコールやタバコ、薬物などの精神作用物質を「やめたいのにやめられない」状態が続き、日常生活よりもその摂取を優先してしまう状態を指します。
これは単なる「好きでやっている」段階とは異なり、本人の意思だけではコントロールが難しくなるレベルの強い欲求や渇望があることがポイントです。
精神作用物質が効かなくなると、また使いたいという衝動が強まり、その衝動に従うことでさらに依存が進みます。
こうした症状が見られる場合、放置すると心身の不調や人間関係・仕事への支障につながるおそれがあるため、早めのケアや治療につなげることが大切です。
また、依存症は特別な人だけがなる病気ではなく、誰にでも起こり得る医療的な問題としてとらえることが必要です。
精神作用物質の依存症にみられる主な症状

精神作用物質をくり返し使用していると、身体がその物質に慣れていき「耐性」ができ、次第に量が増えていきます。
思ったような効果を感じにくくなると、もっと強く、もっと早く摂取したいという気持ちが高まり、
精神作用物質を手に入れることや使うことを最優先にしてしまうことがあります。
これは単なるクセではなく、依存症の代表的なサインです。
依存が進むと、「今すぐ使いたい」という欲求が頭から離れなくなり、仕事・家事・学業など本来やるべきことが手につかなくなります。
休んでいても、移動していても、次にいつ摂取できるかばかりを考えてしまい、他の予定や約束より摂取を優先する、といった行動の変化が起こります。
これは本人の性格の問題ではなく、精神作用物質が脳や神経に影響し、自己コントロールが難しくなる状態が背景にあります。
さらに、使用量を減らしたり我慢したりすると、いらいらしやすくなる・怒りっぽくなる・暴言が出る・落ち込むといった精神面の不安定さが強くあらわれることがあります。
これらはいわゆる「離脱症状」の一部で、精神的なつらさだけでなく、発汗、手のふるえ、震え、けいれん発作(てんかんのような症状)、幻覚・幻視・幻聴など身体や感覚にも異常が出る場合があります。
こうした状態になると、家族や友人との人間関係が乱れやすくなり、周囲と衝突する、嘘をついてまで使用を続ける、隠れて摂取する、といった行動が増えることも少なくありません。
また、日常生活の乱れ(睡眠リズムの崩れ・食事の偏り・通院の中断・仕事の欠勤や遅刻など)につながることもあります。
結果的に、依存症の症状そのものが、健康面・生活面・社会面すべてに影響してしまうのです。
このような依存症は、一人で何とかしようとしても悪循環になりがちです。
「やめたい」気持ちと「どうしても使いたい」衝動の間で揺れ続け、悪化すると常に摂取のことを考えてしまい、生活の中心が精神作用物質になっていきます。
自分でブレーキをかけにくい状態が続いているなら、早い段階で医療・支援につなぐことが、回復への入口になります。
精神作用物質とは?わかりやすく解説

- アルコール(お酒)
- たばこ(ニコチン)
- 鎮痛薬・睡眠薬・抗不安薬などの医薬品
- 風邪薬・栄養ドリンクなどの市販薬
- 大麻・覚せい剤などの違法薬物
「精神作用物質」とは、脳や神経に働きかけて気分・思考・行動などに影響を及ぼす物質のことをいいます。
アルコールやタバコ、睡眠薬、鎮痛剤、大麻、覚せい剤などが代表的なものです。
これらの物質は摂取することで一時的にリラックスしたり高揚感を感じたりしますが、長期間使用を続けると依存が生じやすくなります。
つまり「気持ちを落ち着けたい」「もう少し楽になりたい」という心理がくり返されるうちに、脳がその感覚を記憶してしまうのです。
精神作用物質にはこのように、合法・違法を問わず私たちの身の回りに多く存在しています。
中には医師の指示に基づいて使えば安全なものもありますが、自己判断で量を増やしたり、頻度を上げたりすると依存症へと進行するおそれがあります。
特に、薬が効きにくくなったからといって勝手に服用量を増やすのは非常に危険です。
また、カフェインやエナジードリンクのような身近な商品でも、摂りすぎることで依存的な傾向を示す場合があります。
はじめは「少しだけリフレッシュしたい」という気持ちでも、知らず知らずのうちに「摂らないと落ち着かない」「頭が働かない」と感じるようになったら注意が必要です。
このような状態が続くと、精神作用物質を摂取しないと不安を感じる「心理的依存」、身体が物質に慣れてしまう「身体的依存」の両方が進行していきます。
精神作用物質の特徴は、心身に一時的な快感をもたらす一方で、脳内の神経伝達物質(ドーパミンなど)の働きを乱す点にあります。
そのため、気分の変化や集中力の低下、不眠、イライラなどが現れやすく、生活全体に悪影響を及ぼします。
特に長期間の乱用は、うつ症状や幻覚、記憶力の低下などの深刻な症状につながることもあります。
このように、精神作用物質は本来医療的に役立つ側面を持ちながらも、使い方を誤ると依存症という重大なリスクを伴います。
大切なのは「正しい知識を持ち、自分の状態を客観的に見ること」です。
少しでも気になる症状がある場合は、早めに医療機関や専門家に相談することをおすすめします。
精神作用物質の依存症の原因と診断基準

精神作用物質依存の4つの主な原因
精神作用物質の依存症は、単に「意思が弱いから」起こるものではなく、心理・行動・遺伝・脳の働きなど複数の要因が複雑に関係しています。
ここでは、依存の背景にある4つの主な原因について説明します。
①精神力動的要素
過度なストレスや孤独感、心の葛藤などを抱えている人は、精神作用物質を使うことで一時的に心を落ち着かせようとする傾向があります。
特にうつ状態や不安が強いと、薬やアルコールによって気分を調整しようとする「自己治療仮説」があてはまるケースもあります。
しかし、一時的な安心感のために使用をくり返すと、次第に精神作用物質が心の支えとなり、依存が形成されていくのです。
②行動理論的要素
精神作用物質を摂取したときに感じる快感や安心感は、脳に「報酬」として記憶されます。
そのため、ストレスや不安を感じたときに再びその物質を求める行動がくり返されます。
これを「強化」と呼びます。
たとえば、「嫌なことがあったら飲む」「眠れないときに薬を増やす」などの習慣がつくと、本人の意識とは無関係に使用行動が自動化され、依存が固定化されるリスクが高まります。
③遺伝的要素
研究によると、アルコールや薬物などの依存症はある程度の遺伝的傾向をもつことがわかっています。
親や近い親族に依存症をもつ人がいる場合、脳内の報酬系の反応が強く出やすいなどの特徴があり、依存に発展するリスクが高いとされています。
ただし、遺伝は「なりやすさ」を示すものであって、必ず発症するわけではありません。
生活環境や心理的サポートが整えば、予防や回復は十分に可能です。
④神経科学的要素
精神作用物質を摂取すると、脳内で快感物質ドーパミンが大量に放出されます。
これがくり返されると、脳が「ドーパミンが出る状態」を求めるように変化します。
その結果、自然な喜びや楽しみを感じにくくなり、精神作用物質がないと心が満たされないという状態になります。
これは脳の構造的な変化を伴うため、意思の力だけで止めるのは難しく、専門的な治療が必要になります。
ICD-10に基づく診断基準
- 物質を摂取したいという強い欲求がある
- 使用のコントロールができない(量や回数など)
- 離脱症状がみられる
- 耐性(同じ効果を得るために量が増える)がある
- 生活の中心が物質の使用になっている
- 使用によって問題が起きてもやめられない
世界保健機関(WHO)の国際疾病分類(ICD-10)では、精神作用物質依存症の診断基準として上記の項目が定められています。
過去1年間にこのうち3つ以上が該当する場合、依存症と診断されます。
これらの基準は、依存が単なる「嗜好」ではなく、れっきとした医療的に治療が必要な状態であることを示しています。
自己判断で放置してしまうと、心身への影響が悪化するだけでなく、社会生活にも深刻な支障をきたす恐れがあります。
DSM-5に基づく診断基準
- 意図したより多く、長期間使用している
- やめたいと思ってもやめられない
- 入手・使用・回復に多くの時間を費やす
- 強い渇望(使用への欲求)がある
- 責任を果たせなくなる(仕事・学校・家庭など)
- 人間関係に悪影響が出ても使用を続ける
- 社会活動や趣味をやめてしまう
- 危険な状況での使用(運転中など)
- 身体的・精神的問題を悪化させている
- 耐性ができて使用量が増える
- 使用をやめると離脱症状が出る
アメリカ精神医学会が定めるDSM-5では、依存症を「物質使用障害(Substance Use Disorder)」と呼び、上記の11項目のうち該当する数によって軽症・中等度・重症に分類されます。
DSM-5では、該当項目が2〜3個で軽症、4〜5個で中等度、6個以上で重症と診断されます。
これにより、早期の段階から依存傾向を把握し、治療や支援につなげることが可能です。
依存症は、放置すると重症化することも多いため、違和感を覚えた時点で専門機関への相談を検討しましょう。
精神作用物質の依存症に対する治療方法

症状が軽い場合の短期的なケア
精神作用物質の依存症は、急に治るものではなく、少しずつ回復していく過程が必要です。
依存の度合いが比較的軽い場合には、短期的なケアや生活習慣の見直しだけでも改善が期待できるケースがあります。
たとえば、ニコチン依存やカフェイン依存などでは、「使用を控える」「使用環境を変える」などの小さなステップを積み重ねることが大切です。
また、精神作用物質を断つ際には、一時的に不安・いらだち・不眠などの離脱症状が出ることがあります。
こうした症状は「回復のサイン」でもあるため、焦らず医師や専門家に相談しながら少しずつ減らしていくことが推奨されます。
離脱症状の強さや持続期間には個人差があり、環境のサポートや家族の理解があると乗り越えやすくなります。
また、軽症の段階では「動機づけ面接」や「個人精神療法」などの心理的アプローチも効果的です。
これらの方法では、依存してしまう背景や感情を整理し、再発を防ぐための考え方を身につけていきます。
症状が軽いからといって放置せず、早期に取り組むことで重症化を防げる可能性が高まります。
症状が重い場合に必要な治療
依存が進行し、自己コントロールが難しい段階になると、専門的な治療が必要です。
ここでは、代表的な治療法として「認知行動療法」「薬物療法」「自助グループやピアサポート」の3つのアプローチを紹介します。
①認知行動療法によるアプローチ
認知行動療法(CBT)は、精神作用物質を使ってしまう原因となる「考え方」や「行動のクセ」を見直す治療法です。
たとえば、「ストレスがあるから飲む」「眠れないから薬を多めに使う」といった行動パターンを分析し、より健康的な対処方法に置きかえていきます。
依存の根本には、感情のコントロールや人間関係のストレスが関係していることが多く、考え方を変えることが再発防止につながります。
また、CBTでは「トリガー(使用のきっかけ)」を特定し、回避するための行動計画を立てます。
心理士や医師のサポートのもと、数か月から半年程度かけて継続的に行うことが一般的です。
グループセッションを取り入れることで、同じ悩みを持つ人たちとの共感が生まれ、治療効果が高まりやすくなります。
②薬物療法によるサポート
精神作用物質の依存症では、離脱症状のつらさや精神的な不安を軽減するために薬物療法を併用することがあります。
抗不安薬や抗精神病薬、抗うつ薬などを用いて、イライラや不眠、幻覚、興奮状態を抑える治療が行われます。
薬物療法の目的は「精神を安定させる」ことであり、依存を置き換えるものではありません。
特に重度の依存状態では、自殺念慮や幻覚などの症状が現れる場合もあり、その際は一時的な入院治療が必要となることもあります。
医師の指示のもとで安全に治療を進め、徐々に薬の量を調整しながら自然な生活リズムを取り戻すことを目指します。
③自助グループやピアサポートの活用
依存症の回復において非常に効果的なのが、自助グループ(AA、NAなど)やピアサポートです。
同じ悩みを経験している仲間と話すことで、「自分だけではない」という安心感を得ることができます。
自助グループでは、依存症から回復したメンバーが新しい参加者を支え、励まし合う循環ができているのが特徴です。
また、精神科訪問看護などの地域支援を併用することで、継続的なフォローアップが可能になります。
治療は「やめること」ではなく、「やめた後の生活を整えること」が目的であり、本人のペースに合わせた長期的支援が重要です。
精神科訪問看護という選択肢もある

精神科訪問看護とは?
| サービス名 | 精神科訪問看護 |
|---|---|
職種 |
・看護師 ・准看護師 ・作業療法士 |
訪問日数 |
週1〜3回 (※必要に応じて週4回以上も可) |
| 訪問時間 | 1回あたり30〜90分 |
精神作用物質の依存症に悩む方の中には、「通院がつらい」「自宅で安心してサポートを受けたい」と感じている方も少なくありません。
そんな方におすすめなのが、精神科訪問看護という仕組みです。
精神科訪問看護とは、看護師や作業療法士などがご自宅に訪問し、医師の指示のもとで心身のケアや生活支援を行うサービスです。
病院やクリニックに行くことが難しい方でも、自宅で継続的な支援を受けられるのが特徴です。
訪問では、服薬のサポートや体調チェック、生活リズムの調整、再発防止のための相談などを行います。
特に依存症の回復過程では、気分の波や孤独感が出やすく、「専門職がそばにいてくれる」という安心感が大きな支えになります。
精神作用物質の依存症に対して、医療と生活の両面から支援できる点が精神科訪問看護の強みです。
訪問看護を利用するメリット
精神科訪問看護を利用することで、依存症の回復だけでなく、生活の安定や再発予防にもつながります。
たとえば、以下のようなメリットがあります。
- 専門的な支援を受けながら自宅で療養できる
- 通院の負担を減らせる
- 服薬や体調管理のサポートが受けられる
- 家族の精神的負担が軽くなる
- 孤立を防ぎ、社会とのつながりを保てる
精神作用物質の依存症は、症状の波があるため一人で立ち直るのは難しい場合があります。
訪問看護では、看護師が利用者さまの体調や気持ちを丁寧に観察し、必要に応じて主治医や関係機関と連携をとりながら支援を続けます。
依存によって生活が乱れてしまった場合でも、少しずつ規則正しいリズムを取り戻せるようサポートします。
また、訪問看護はご本人だけでなく、ご家族への支援も重視しています。
ご家族の相談を受けたり、依存症への理解を深めてもらったりすることで、家庭内でのサポート体制を強化します。
依存症の回復には、本人だけでなく「支える家族の心のケア」も欠かせません。
「依存症を治したいけど、どう動けばいいのかわからない」「通院する元気がない」という方は、精神科訪問看護の利用を検討してみましょう。
訪問看護師があなたの生活に寄り添いながら、安心できる回復環境を一緒につくっていきます。
精神作用物質の依存症の方はシンプレへ

シンプレ訪問看護ステーションの特徴
シンプレ訪問看護ステーションは、精神科に特化した専門的な訪問看護サービスを提供しています。
精神作用物質の依存症をはじめ、うつ病・統合失調症・発達障害・PTSDなど、幅広い精神疾患を持つ方のサポートを行っています。
特徴は、医療だけでなく「その人らしい生活の再構築」に重点を置いている点です。
利用者さま一人ひとりの状態を丁寧に見つめ、「やりたいことを少しずつ取り戻す」ことを目標に支援しています。
医療機関や行政とも連携しながら、社会復帰・就労支援・家族支援まで一貫して行うため、長期的な回復を目指す方にも安心してご利用いただけます。
また、訪問スタッフには看護師・准看護師・作業療法士が在籍しており、専門的な視点から心身両面をサポートできる体制を整えています。
精神作用物質の依存症に苦しむ方でも、「一人で頑張らない」ための居場所として、シンプレは支えとなる存在を目指しています。
シンプレのサービス内容
・自立した生活を営めるための支援
・生活リズムの調整
症状の悪化防止・服薬支援
・生活状況を観察
・受診や服薬を支援
社会復帰へのサポート
・主治医や関係機関と連携
・社会復帰を支援
家族の方への支援
・家族へのアドバイスや相談
・社会資源の活用などを支援
使用できる制度
・自立支援医療制度(精神通院)
・心身障害者医療費助成制度
・子ども医療費助成制度
・生活保護制度
シンプレ訪問看護ステーションでは、看護師・作業療法士などの専門職が利用者さまの心と体に寄り添います。
服薬支援や生活支援、家族への相談対応など、回復までの道のりを共に歩む体制が整っています。
祝日・土曜日も訪問可能で、1回あたり30分〜90分、週1〜3回の訪問を基本としています。
必要に応じて週4回以上の訪問にも柔軟に対応しており、利用者さまの生活リズムに合わせた支援を実現します。
依存症の方の中には、医療費や通院費用の負担を心配される方もいますが、上記のような公的制度を活用することで経済的負担を軽減できます。
シンプレでは、こうした制度の申請サポートや利用方法のご案内も行っています。
訪問可能なエリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションでは、東京都23区を中心に幅広いエリアに対応しています。
エリア外でも近隣であれば訪問看護にうかがえる場合もありますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ|精神作用物質の依存症の症状を理解し、早めに相談を

精神作用物質の依存症は、アルコール・タバコ・薬物・睡眠薬・覚せい剤など、脳に作用して気分や思考を変化させる物質を継続的に摂取してしまうことで生じる病気です。
症状が進行すると、「やめたいのにやめられない」という強い渇望が生まれ、心身・生活・人間関係のすべてに悪影響を及ぼします。
放置してしまうと、離脱症状(不眠・いらだち・幻覚・震えなど)が強まり、生活の立て直しが難しくなります。
しかし、依存症は適切な支援によって回復が可能です。
早期に治療を開始すれば、生活リズムや社会参加を取り戻すことも十分にできます。
治療方法には、認知行動療法や薬物療法、自助グループなどがありますが、症状が重く通院が難しい場合は
精神科訪問看護を活用するのも有効です。
訪問看護では、自宅で安心して治療や生活支援を受けられるため、再発防止や社会復帰へのサポートとして利用する方が増えています。
依存症は「弱さ」ではなく、「治療が必要な病気」です。
一人で抱え込まず、まずは相談からはじめてみましょう。
あなたの「精神作用物質の依存症を少しでも克服したい」、「変わりたい」という気持ちは、回復への第一歩です。
シンプレ訪問看護ステーションは、あなたのペースで回復に向かうための伴走者となります。
お気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (5)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



