こんな症状は注意欠陥多動性障害(ADHD)かも?こども・おとな別に解説
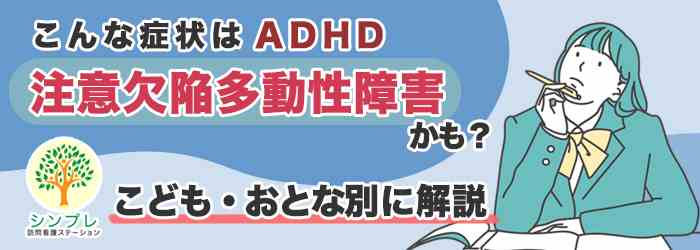
注意欠陥多動性障害(ADHD)の症状は子供の場合、授業中にじっとしていられず歩き回ってしまうなどの症状があります。
大人の場合には約束を忘れたり締め切りを守れない、思ったことをすぐに口にしてしまうなどがあり、周囲の方に誤解されたりトラブルに発展してしまうなどがあるので注意が必要です。
心当たりのある方や、周囲の方の症状で悩んでいる方は参考にしてみて下さいね。
注意欠陥多動性障害(ADHD)の症状とは

注意欠陥多動性障害の主な3つの症状
「不注意」「衝動性」「多動性」ついてそれぞれ説明していきます。
不注意
集中できない、忘れやすい、モノをなくしやすいなどの症状があらわれます。
不注意の症状を抱えている人は、周囲から「集中力がないから」「不真面目だから」などと誤解されやすいため、ストレスや孤独感を感じてしまうこともあります。
衝動性
衝動性とは、外部からの刺激や思いついたことに対して、衝動的に行動や反応をしてしまう症状のことです。
具体的には「思ったことをすぐ言ってしまう」「自分の思った通りにならないとイライラする、衝動的に買い物をしてしまうなどがあ挙げられます。
多動性
多動性とはじっとしていることが難しいなどの状態を指し、男性に多いのが特徴です。
手遊びが止まらないことや、学校の授業中に立ち歩いてしまう、貧乏ゆすりがとまらないなども多動性の症状に該当します。
こどもの症状
- 落ち着きがなく座っていることがむずかしい
- 授業などにじっと参加することができない
- 順番をまつことができない
- 怒りをコントロールできない
- ルールに従うことがむずかしい
注意欠陥多動性障害(ADHD)の子どもは、上記のような症状が現れがちです。
これらの症状から、日常生活や学業、仕事において、さまざまな困難や問題を引き起こす可能性があり、家や学校でしかられ続け、自尊心が低下しやすいといわれています。
日常生活や学業、仕事において、さまざまな困難や問題を引き起こす可能性があります。そうならない為にも症状や「本人の気持ち」「悩み」に早めに気づき、二次障害を防ぐことが大切です。
おとなの症状
- 忘れ物やなくし物が多い
- 時間の管理が苦手
- 順序だてて仕事や作業を行うことが苦手
- 約束や用事を忘れてしまう
ADHDの症状は、成長とともに緩和していくものもありますが、多くの場合、大人になっても引き続き症状がみられます。
これを「大人のADHD」と呼びますが、実際は大人になってもADHDに気づかない人が多いといわれています。
大人になると、仕事や家事、人間関係など、さまざまな場面で上記のような「用事や約束を忘れてしまう」「忘れ物が多い」「時間の管理が苦手」といった特徴が顕著になります。
注意欠陥多動性障害(ADHD)の原因
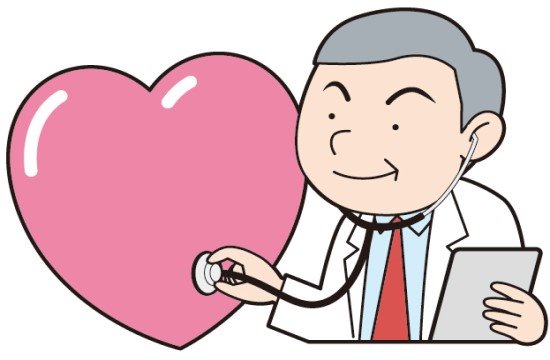
注意欠陥多動性障害(ADHD)の原因ははっきりわかっていませんが、脳機能の低下や遺伝との関係があると考えられています。
ADHDの原因は、脳機能の低下と神経伝達物質の不足の2つが考えられています。
脳機能の低下としては、スムーズな行動を行うための「尾状核」や、集中力の維持や行動の計画などの働きをするための「前頭前野」の働きの低下が挙げられます。
神経伝達物質の不足としては、ノルアドレナリンやドーパミンなどの不足が考えられます。
特にドーパミンは、ワーキングメモリーを働かせたり、目的のある行動を促したりする役割があります。この働きが低下すると、不注意や多動性・衝動性などの特性が現れやすくなります。
注意欠陥多動性障害(ADHD)の向き合い方と接し方

こども
注意欠陥多動性障害(ADHD)の子どもと接するときは毎日の習慣や些細なことなど、一般的に当たり前とされることを褒めてあげることが大切です。
褒めてあげることで次も褒められたいという意欲が湧いたり、自信がついたり、自己肯定感が向上したりするからです。
また注意欠陥多動性障害(ADHD)の子どもは自分が失敗した場合、叱られなくても自信を失うことや、自己嫌悪におちいることが多いといわれています。
そのため失敗した場合でも叱ったりせず、「次はがんばろうね」などと励ましてあげることも大切です。
おとな
ADHDの方は、仕事や家事、人間関係などにおいて、さまざまな困難や問題を抱えることがあります。
こうした困難を乗り越えるために、約束や締め切りの前には声をかけたり、一度に複数のことを頼まないなど周囲からのサポートが重要です。
周囲からのサポートを受けることで、ADHDの人は、仕事や生活がしやすくなり関係もスムーズになっていくでしょう。
注意欠陥多動性障害(ADHD)の診断基準と二次障害

注意欠陥多動性障害の診断基準
注意欠陥多動性障害(ADHD)の診断基準には、アメリカの精神医学会が定めたDSM-5が使われます。
また必要に応じてアンケート形式のチェックリストを用いたり、心理テストや知能検査を行ったりする場合もあります。
ADHDの診断を受けるには、精神科や神経科、心療内科などの医師の診察を受けることが一般的です。
なりやすい二次障害の疾患
- うつ病
- 不安障害
- アルコールや薬物などの依存症
- ひきこもりや不登校
注意欠陥多動性障害の方がなりやすい二次障害として上記のような疾患が挙げられます。
これらの二次障害は周囲との関係性の中で、日々否定的な感情が積み重なり、生きづらさを感じることで発症するといわれています。
二次障害が起こると、もともと持っていた困難さにくわえて状況が悪化し、家族も本人もそのつらい状況から脱するのに、相当な労力と時間が必要になるでしょう。
そのためできるだけ早い段階から、周囲の人間が注意欠陥多動性障害をもつ本人の特性に気づいて理解することや、本人が生きやすい環境を作っていくことが大切です。
注意欠陥多動性障害(ADHD)の治療方法

カウンセリング・心理行動療法
注意欠陥多動性障害(ADHD)の治療にカウンセリングや心理行動療法があり、これは薬に頼ることなく感情や行動をコントロールできるようになるための治療法です。
具体的には注意欠陥多動性障害(ADHD)の困りごとが、自分の努力不足によるものではないことを理解する「心理教育」や規則正しい生活リズムになるよう見直す「環境調整」などがあります。
自身の特性を理解し、自分に合った生活環境に調節することで忘れ物が少なくなったり、気が散りにくくなったりといった効果が期待されます。
また考え方や行動のかたよりを把握し、自分の認知や行動パターンを整えることで生活や仕事上のストレスを減らしていく「認知行動療法」も有効な治療法の1つです。
ソーシャルスキル・トレーニング(SST)
ソーシャルスキルトレーニングは他の人との関係を良好に維持するためのスキルを身につけ、ストレスへの対処や問題解決ができるようになることを目的としています。
トレーニング方法はお手本となるような他の人のふるまいを見せる「モデリング」や実際に会話の練習をする「ロールプレイング」などさまざまです。
また就労移行支援では実際に職場で困ることを想定して、「質問の仕方」「断り方」「質問されたときの回答の仕方」などのトレーニングが行われます。
ソーシャルスキルトレーニングは現在、精神科など医療領域だけでなく、教育や就労支援、など幅広い領域で受けられますので、気になる場合は問い合わせてみるとよいでしょう。
薬物療法
注意欠陥多動性障害(ADHD)に処方される代表的なお薬に、不注意に効果のある「コンサータ」注意欠陥多動性障害(ADHD)の特性全体に効果のある「ストラテラ」多動・衝動性に効果のある「インチュニブ」があります。
これらのお薬を使うことで、脳内のドーパミンやノルアドレナリンの量を適量に調整し、結果として症状の緩和につながるとされています。
しかしあくまでも薬の効果は一時的で、障害自体を治すものではないため注意が必要です。
また長く飲み続けることで依存症になるリスクや、薬の効果が出にくくなることもあるので医師と相談し、納得した上で薬物治療を行いましょう。
注意欠陥多動性障害(ADHD)の方の支援・相談窓口

発達障害者支援センター
発達障害者支援センターは、発達障害者への支援を総合的に行うことを目的とした専門機関です。
窓口は政令指定都市や各都道府県の自治体となっていますが、それらから委託された事業所でも相談をうけつけています。
基本的には社会福祉士がいますが、施設によっては、臨床心理士、言語聴覚士、医師などがいるところもあり、それぞれの専門に沿ったサポートをうけられるのが特徴です。
まずはお住まいの地域の発達障害者支援センターが、どんな支援をおこなっているのか調べてみることをおすすめします。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は精神疾患により、「生活に支障をきたす人」が取得できる手帳です。
この手帳には1級~3級までの障害等級という分類があり「どれくらい生活ができないか」「どのような症状がでているか」を基準に振り分けられます。
また取得することで、障害者雇用枠へ応募できたり、料金の割引や助成が受けられたり、といったさまざまな支援を受けられるのが特徴です。
精神障害者保健福祉手帳を持つことで受けられる支援は、治療を続けていくうえでの負担軽減にもつながりますのでぜひ申請してみてはいかがでしょうか。
自立支援医療制度
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
生活保護 |
0円 |
低所得1 |
2,500円 |
低所得2 |
5,000円 |
中間所得1 |
5,000円 |
中間所得2 |
10,000円 |
一定所得以上 |
20,000円 |
表の料金は所得に応じた医療費の月額自己負担額の上限額となっております。
表の料金を超えた場合には、自己負担なしで医療が受けられます。
自立支援医療(精神通院医療)制度はすべての精神疾患を対象に通院による継続的な治療が必要な人が申請・利用できる制度です。
この制度は指定の薬局・医療機関のみ利用可能で、3割負担の医療費が1割負担まで軽減されます。
また状況にもよりますが上の表のように、月間の自己負担額に上限が定められるので、原則として上限を超える分の医療費は負担しなくてもよいことも特徴の1つです。
このように自立支援医療制度は精神疾患の治療でかさみがちな医療費負担を軽くし、治療に専念できるようにしてくれます。
精神科訪問看護という選択も

精神科訪問看護って?
・自立した生活を営めるための支援
・生活リズムの調整
症状の悪化防止・服薬支援
・生活状況を観察
・受診や服薬を支援
社会復帰へのサポート
・主治医や関係機関と連携
・社会復帰を支援
家族の方への支援
・家族へのアドバイスや相談
・社会資源の活用などを支援
精神科訪問看護とは、精神疾患を抱えるかたや精神的な理由で不安があるかたに対して、看護師などの専門職がご自宅におうかがいし、支援するサービスです。
「生活リズムの調整」「受診や服薬の支援」「社会復帰の支援」などさまざまな観点からサポートすることで、利用者さまが安心して生活できる環境づくりを目指します。
同時に家族への支援も実施し、利用者さまを取りまく環境全体を整えていく役割を担っているのも精神科訪問看護の特徴です。
とくにご自宅からでるのが難しい場合や、日常生活での注意点などを家族にも共有したい場合は、精神科訪問看護の利用をおすすめします。
訪問看護のメリット
- 自宅に居ながら専門的なケアが受けられる
- 自宅での様子を主治医に連携できる
- 家族の負担が軽減できる
訪問看護のメリットは、医療の知識や経験が豊富な専門家から、病院と同等のケアを、住み慣れた自宅でうけられることです。
これまでは医療サービスを受ける際に病院に行くのが基本でしたが、医療サービス需要の増加にともない、訪問看護サービスが増えていきました。
病気が治るまでずっと病院で治療をうける必要がなく、退院後すぐに自宅でのケアに移行できるのも訪問看護のメリットの1つです。
また自宅に訪問してもらえることで、ご家族の精神的負担や肉体的負担を軽減することにもつながるでしょう。
精神疾患をお持ちならシンプレへ

シンプレの特徴
シンプレ訪問看護ステーションは、精神疾患をお持ちのかたの看護に特化しており、さまざまな精神疾患に対応が可能です。
利用者さんの想いをしっかりと受けとめ、安心して生活ができるようサポートさせていただきます。
また訪問看護に入らせていただくうえで、地域で暮らす精神疾患のあるかたの自主性を尊重しているのもシンプレ訪問看護ステーションの特徴です。
注意欠陥多動性障害(ADHD)でお悩みの方はぜひ一度シンプレ訪問看護ステーションへご相談ください。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応地域はおもに上記が中心で、訪問活動をおこなっています。該当エリアにお住まいの方はぜひご検討ください。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。電話やメールなどで相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

注意欠陥多動性障害(ADHD)は不注意と多動性・衝動性といった症状がありますが、生まれ持った脳機能の障害のため完全に治癒することはありません。
しかし「心理社会的治癒」や「薬物療法」によって、症状の緩和や注意欠陥多動性障害(ADHD)の症状による困りごとを軽減できるでしょう。
また早期の治療や、周囲の人がしっかりサポートしていくことで、困りごとによる自尊心の低下や意欲の低下など、二次的問題の防止にもつながります。
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神科に特化した専門的なスタッフがさまざまな観点注意欠陥多動性障害(ADHD)を支援いたします。
ご家族へのサポートも一緒に行い、周りの環境から整えるお手伝いをさせていただきますので、注意欠陥多動性障害(ADHD)でお悩みの場合には、ぜひシンプレ訪問看護ステーションにご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



