PTSDとパニック障害の関係性|共通点・違い・治療法と相談窓口を解説


PTSDとパニック障害はいずれも不安障害に分類され、発作や強い不安といった共通の特徴を持つため、混同されやすい疾患です。
しかし実際には、PTSDとパニック障害の関係性には似ている部分と異なる部分があり、それぞれに応じた治療や支援が必要となります。
本記事では、PTSDとパニック障害の共通点や違い、治療法、相談窓口について解説します。
症状に悩まれている方や、ご家族・ご友人がサポートを必要としている方はぜひ参考にしてください。
PTSDとパニック障害の共通点は?
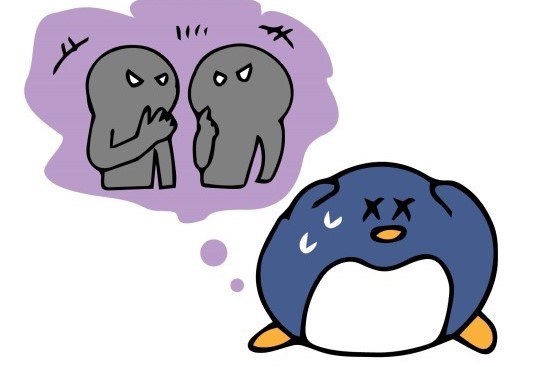
PTSDとパニック障害は一見すると異なる疾患に思われますが、実は精神的・身体的な症状に共通点が多く存在します。
両方の疾患は突然の発作や強い不安感を伴い、日常生活に大きな支障を与える点で似ています。ここでは、代表的な3つの共通点を紹介します。
初回発作を思い出すことで苦痛に襲われる
PTSDは過去のトラウマ体験(虐待・暴力・事故・災害・戦争など)を思い出した際に、当時の恐怖がよみがえり強い苦痛を感じます。
パニック障害では、理由もなく突然「パニック発作」が起こり、動悸やめまい、発汗、窒息感などの身体症状とともに強い恐怖感が押し寄せます。
いずれの場合も、突然の苦痛が心身を襲うことが特徴であり、この点が両疾患の大きな共通要素といえるでしょう。
発作が起こる不安から回避行動をとる
両疾患とも「また発作が起こるのではないか」という不安を抱きやすく、自然と回避行動を取る傾向があります。
PTSDの場合、トラウマを想起させる状況や場所を避けるようになり、症状が悪化すると外出が困難になることもあります。
パニック障害では、電車や飛行機、エレベーターなど「すぐに逃げられない場所」を避けるケースが多く、これが生活の制限につながります。
予期不安から鬱症状や神経質な状態が続く
PTSD・パニック障害どちらの場合も、予期不安によってうつ病や神経症的な状態を併発しやすくなります。
PTSDではアルコール依存症や薬物依存症を伴うことも多く、パニック障害では「パニック性不安うつ病」と呼ばれる症状に発展することがあります。
このように、発作そのものだけでなく「先の不安」によって心の状態が不安定になりやすい点も共通しています。
PTSDとパニック障害の違いは?

前の章ではPTSDとパニック障害の共通点を解説しましたが、両者は発症のきっかけや症状の特徴に明確な違いがあります。
ここでは、原因・症状・発症のきっかけという3つの視点から両疾患を比較し、それぞれの特徴を整理していきましょう。
両方の疾患が混同されやすいのは事実ですが、違いを理解することが適切な治療への第一歩となります。
原因の違い
PTSDは過去の出来事や体験が原因
PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、その名の通り過去のトラウマ体験が主な原因となります。
戦争、犯罪被害、自然災害、交通事故、性的暴行など、命や安全が脅かされる体験が強い恐怖記憶として残り、心に深い傷を残します。
これらの出来事をきっかけに「再体験」や「過覚醒」といった症状が引き起こされ、日常生活に大きな影響を及ぼします。
つまりPTSDは外的出来事に起因する疾患であることが特徴です。
パニック障害は遺伝・環境的要因が複雑に絡み合い発症
一方でパニック障害は、遺伝的要因と環境的要因が複雑に関係して発症すると考えられています。
脳内の神経伝達物質のバランス異常に加え、仕事や人間関係のストレス、生活環境の変化などが重なることで発作が生じやすくなります。
また、過去に強いストレスやトラウマ体験があった場合、その経験が発症リスクを高めるとも言われています。
このようにPTSDが「明確な出来事」に起因するのに対し、パニック障害は遺伝的素因と日常的なストレスの相互作用による発症が多いのが違いです。
症状の違い
PTSDの症状(再体験・回避・過覚醒など)
PTSDの代表的な症状は「再体験」「回避」「過覚醒」の3つです。
突然つらい記憶がよみがえり、まるで体験を繰り返しているかのような錯覚に襲われるのが特徴です。
また、その記憶を避けようとする行動や、常に神経が張りつめて落ち着かない状態が続くこともあります。
このため、PTSDではトラウマ記憶に関連した症状が中心になります。
パニック障害の症状(動悸・息苦しさ・発作など)
パニック障害の中心症状は「予期できないパニック発作」です。
突然、強い不安や死の恐怖に襲われ、動悸・息苦しさ・めまい・発汗といった身体的な反応が伴います。
加えて「また発作が起きるのでは」という予期不安や、発作が起きた場所を避ける「広場恐怖」も特徴です。
PTSDと異なり、パニック障害は身体症状が前面に出やすい疾患と言えるでしょう。
発症のきっかけの違い
PTSDは命の危険を感じるような過去の出来事が引き金となる一方、パニック障害は必ずしも明確な出来事がなくても発症します。
強いストレスや環境の変化などがきっかけとなりやすく、突然の発作として現れることが多いのが特徴です。
このように、発症の背景や症状の現れ方を比較すると、PTSDとパニック障害の関係性には明確な相違点が見えてきます。
PTSDの治療方法にはどんなものがある?

PTSD(心的外傷後ストレス障害)は放置してしまうと症状が慢性化しやすいため、専門的な治療を早期に受けることが重要です。
治療には大きく分けて「心理療法」と「薬物療法」があり、患者さんの症状や状態に合わせて組み合わせて行われます。ここでは代表的な治療法を紹介します。
心理療法
持続エクスポージャー療法
持続エクスポージャー療法(PE療法)は、トラウマ体験を安全な環境で繰り返し想起させ、恐怖反応を徐々に弱めていく方法です。
最初はつらく感じることも多いですが、専門家のサポートを受けながら少しずつ記憶に慣れていくことで、再体験症状が軽減し、日常生活への適応力が高まります。
効果が期待できる治療法ですが、実施できる専門機関や医師が限られているため、希望する場合は事前に確認が必要です。
眼球運動脱感作療法(EMDR)
EMDR(眼球運動脱感作療法)は、トラウマ体験を思い出しながら目を左右に動かすことで、脳内での記憶処理を促進する心理療法です。
この方法により、トラウマを「過去の出来事」として整理しやすくなり、恐怖感や不安が和らいでいきます。
海外の研究でも有効性が認められており、世界的にも標準的なPTSD治療法のひとつとされています。
薬物療法
心理療法と並んで行われるのが薬物療法です。
PTSDの薬物療法では、主に抗うつ薬や抗不安薬が用いられます。特にSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)やSNRIがよく処方され、脳内の神経伝達物質の働きを整えることで症状の改善が期待できます。
抗うつ薬は気分の落ち込みを軽減し、不安や過覚醒の症状を和らげる効果があります。
また、睡眠障害が強い場合には睡眠薬が併用されることもあります。薬の選択や投与量は医師が症状に応じて調整するため、自己判断で中断や変更をせず、必ず指示に従うことが大切です。
このようにPTSDの治療は、心理療法と薬物療法をうまく組み合わせることで効果が高まります。
症状に悩んでいる場合は一人で抱え込まず、精神科や心療内科など専門医に相談することをおすすめします。
パニック障害の治療方法にはどんなものがある?

パニック障害は適切な治療で改善が期待できる疾患です。
発作や予期不安によって生活に支障をきたすこともありますが、治療を受けることで日常生活を取り戻すことが可能です。
治療の基本は「心理療法」と「薬物療法」であり、患者さんの状態に応じて単独または組み合わせて行われます。ここでは代表的な治療法を紹介します。
心理療法(認知行動療法など)
パニック障害の治療においては、認知行動療法(CBT)が広く用いられています。
CBTでは「発作が起きるのでは」という誤った認知を修正し、不安に対する考え方を変えていくことが目的です。
曝露(ばくろ)療法も効果的で、実際に不安を感じる場面に少しずつ直面することで、恐怖や回避行動を克服できるようになります。
また、日本では「森田療法」と呼ばれる心理療法も用いられ、不安を排除しようとせず「あるがままに受け入れる」姿勢を学ぶことで症状を軽減します。
このような心理療法は、再発を防ぎ根本的な改善につなげる重要な治療法です。
薬物療法(抗うつ薬・抗不安薬など)
心理療法と並行して行われることが多いのが薬物療法です。
代表的なのはSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)で、脳内の神経伝達物質セロトニンの働きを整えることで、パニック発作や予期不安を抑える効果があります。
また、必要に応じて抗不安薬や三環系抗うつ薬が処方されることもあり、症状の強さや体質に合わせて調整されます。
薬物療法は即効性がある場合もありますが、副作用のリスクや依存性の問題もあるため、必ず医師の指導のもとで継続することが大切です。
薬だけに頼るのではなく、心理療法と組み合わせて治療を行うことでより高い効果が期待できます。
また、生活習慣の改善やストレス対策も重要で、規則正しい睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動などを取り入れることで治療の効果が高まります。
このように、パニック障害の治療は多角的に取り組むことで、発作や不安をコントロールしながら回復を目指していきます。
PTSD・パニック障害の相談窓口は?

PTSDやパニック障害の症状に悩んでいる場合、一人で抱え込まずに専門機関へ相談することが重要です。
両疾患は発作や不安が生活に大きな支障を与える点で共通しており、早めの相談が回復の第一歩になります。
ここでは、代表的な相談窓口を紹介します。
精神科・心療内科
最も基本的な相談先は精神科や心療内科です。
専門医による診断を受けることで、PTSDかパニック障害かを見極め、適切な治療方針を立ててもらえます。
心理療法や薬物療法といった専門的治療を受けられるため、症状が続く場合はまず医療機関の受診を検討しましょう。
保健所・精神保健福祉センター
各自治体にある保健所や精神保健福祉センターも心強い窓口です。
ここでは医療や福祉に関する相談ができ、必要に応じて病院や地域の支援機関を紹介してもらえます。
電話や面談による相談が可能で、費用がかからない場合も多く、初めての相談先として利用しやすいのが特徴です。
自助グループ・支援団体
同じようにPTSDやパニック障害を抱える人々が集まり、体験を共有しながら支え合う自助グループもあります。
孤独感を和らげ、症状と向き合う勇気を持てることが多く、特に長期的な支援として役立ちます。
支援団体によるオンライン相談や交流の場も増えており、参加しやすい環境が整ってきています。
精神科訪問看護を利用するという選択肢
外出が難しい方や、定期的なサポートが必要な方には精神科訪問看護という選択肢があります。
看護師や作業療法士が自宅を訪問し、服薬支援・生活支援・再発予防などを行うため、治療を継続しやすくなるのが利点です。
PTSDとパニック障害の関係性においては、どちらも「予期不安」が強いため、自宅で安心できる環境で支援を受けられる訪問看護は大きな助けとなります。
このように、PTSDやパニック障害で困ったときに頼れる窓口は複数あります。
自分に合った方法を見つけ、できるだけ早めに支援を受けることが、回復への近道となるでしょう。
PTSD・パニック障害のケアを行う精神科訪問看護とは?

| サービス名 | 精神科訪問看護 |
|---|---|
| ケア内容 | ・日常生活の維持 ・生活技能の獲得 ・対人関係の維持など |
| 訪問日数 | 原則 週3日以内 |
PTSDやパニック障害の症状がある方の中には、外出が難しい、病院に継続して通うのがつらい、といった悩みを抱える方も少なくありません。
そのような場合に有効なのが、精神科訪問看護です。
看護師や作業療法士など専門職が自宅を訪問し、医療的ケアと生活支援を行うことで、安心して療養を続けられる環境を整えます。
精神科訪問看護では、服薬管理や症状の観察、生活リズムの安定支援、再発防止のアドバイスなどが受けられます。
特にPTSDやパニック障害は「予期不安」や「再体験」といった症状が強く、日常生活における安心感の確保が欠かせません。
自宅で看護師のサポートを受けられることで、症状の悪化を防ぎ、徐々に社会復帰へとつなげていくことが可能です。
また、訪問看護はご本人だけでなく、ご家族への支援にも力を入れています。
家族がどのように接すればよいか、症状が出たときの対応方法などをアドバイスしてくれるため、支える側の不安も軽減されます。
病院・行政・在宅サービスと連携し、必要に応じて制度の利用や地域資源の紹介も行うため、包括的な支援が受けられるのも大きなメリットです。
訪問時間は1回あたり30分~90分程度、回数は週1~3回が基本ですが、症状によっては週4回以上の対応が可能な場合もあります。
精神科訪問看護は医療保険の対象となり、自立支援医療制度や障害者医療費助成制度を利用できるケースも多いため、費用面の負担も軽減されます。
このように精神科訪問看護は、PTSDやパニック障害で外来通院が難しい方や、日常生活で不安を抱えやすい方にとって、継続的に安心を得られる支援方法です。
「病院に行きにくいけれど専門的なケアを受けたい」と感じている方は、一度利用を検討してみると良いでしょう。
PTSD・パニック障害のサポートなら当ステーションへ!

PTSDやパニック障害の症状に悩む方にとって、継続的な支援を受けられる環境はとても大切です。
当シンプレ訪問看護ステーションでは、精神疾患に特化したサービスを提供し、ご利用者さまが安心して生活を送れるよう全力でサポートしています。
「病院に通うのが難しい」「自宅での支援が必要」といった方にも柔軟に対応できるのが特徴です。
シンプレ訪問看護ステーションの看護内容
当ステーションでは、PTSDやパニック障害を含む精神疾患全般に対応しています。
主な看護内容は以下の通りです。
・日常生活の支援(生活リズムの調整、衛生管理など)
・服薬支援(お薬の管理や服薬のサポート)
・再発予防のためのアドバイス
・社会復帰に向けたサポート
・ご家族への相談支援
特にPTSDとパニック障害は「予期不安」や「再体験症状」が強く出やすいため、不安を和らげ安心できる環境づくりに力を入れています。
また、病院や行政機関とも連携を取り、地域全体で回復を支える体制を整えています。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
当ステーションは東京都23区を中心に、西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・東久留米市、さらに埼玉県の一部地域まで幅広く訪問しています。
上記以外の地域にお住まいの方でも、訪問が可能な場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
訪問は週1〜3回を基本とし、1回あたり30分〜90分のサポートを提供しています。状況によっては週4回以上の訪問も対応可能です。
訪問スタッフには看護師・准看護師・作業療法士が在籍しており、医療的なケアから生活支援まで幅広く対応できます。
また、胃ろうや自己導尿、在宅酸素療法といった医療処置にも対応可能で、必要に応じて緩和ケアまでご相談いただけます。
このように、精神面だけでなく身体面のサポートも含めた包括的なケアが受けられるのが当ステーションの強みです。
PTSDやパニック障害は「自分だけではどうにもできない」と感じやすい疾患ですが、専門的な訪問看護を利用することで大きな安心につながります。
シンプレはご利用者さまの不安に寄り添い、回復への道のりを一緒に歩むパートナーであり続けます。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

PTSDとパニック障害は共通点も多いが原因と症状は異なる
PTSDとパニック障害はいずれも不安障害に分類され、発作や予期不安といった共通点があります。
しかし、PTSDは過去のトラウマ体験が原因であるのに対し、パニック障害は遺伝的要因やストレスなど複数の要因が関わる点で異なります。
また症状も、PTSDでは「再体験」「回避」「過覚醒」が中心であるのに対し、パニック障害では「動悸」「息苦しさ」「発作」など身体的症状が前面に出るという違いがあります。
このように、両疾患は混同されやすい一方で、その背景や症状には明確な差異が存在します。
治療は心理療法と薬物療法の組み合わせが有効
どちらの疾患も早期の治療が重要であり、心理療法と薬物療法の併用が効果的とされています。
PTSDでは持続エクスポージャー療法やEMDRといった専門的な心理療法が有効で、必要に応じて抗うつ薬や抗不安薬が処方されます。
パニック障害では認知行動療法や曝露療法に加え、SSRIなどの薬物療法が用いられます。
生活習慣の改善やストレスマネジメントも重要で、総合的にアプローチしていくことが重要です。
ご相談の問い合わせはこちら▼

高座渋谷つばさクリニック
医師:武井智昭
外来としてはうつ病(うつ状態)が年間300名程度はおりこちらが得意分野です。この他に、思春期特有の対応(起立性調節障害や拒食症など)も行っています。心療内科としては10年、日本精神神経学会会員に所属
本記事へのコメント
PTSDとパニック障害は、強い不安や発作という共通の苦しみを伴う疾患です。
しかし、どちらも継続的な適切な治療と支援によって、つらい症状の改善が期待できます。
あなたが感じている「また発作が起きるのではないか、発作がおきてしまったどうしよう」という予期不安や、「頭から離れないつらい記憶を思い出すと体がつらくなる」という症状は、決して甘えや気のせいではありません。これは、心が傷ついてしまい、身体が懸命にあなたを守ろうとしている、大事なサインです。
一人で抱え込まず、私たち専門家にご相談ください。薬物療法や認知行動療法などを通して、あなたらしい穏やかな日常を取り戻すサポートをいたします。
早期の相談が、回復への第一歩となります。
監修日:2025年11月21日
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



