精神科訪問看護の料金はいくら?費用相場・保険適用・自立支援医療での負担軽減を徹底解説|シンプレ訪問看護ステーション
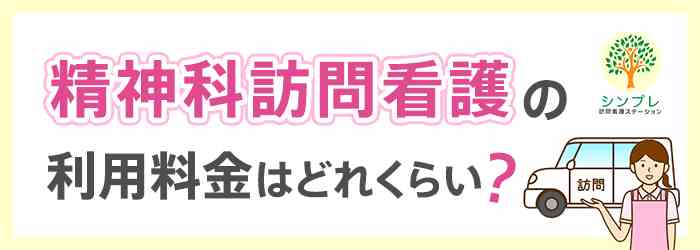
「精神科訪問看護 料金はどれくらい?」――はじめて利用を検討すると、費用や保険の仕組みが特に気になりますよね。この記事では、元の内容を踏まえつつ、精神科訪問看護の費用構成や自己負担の考え方をわかりやすく整理します。医療保険や介護保険の適用があるため、実際の支払いは負担割合に応じて抑えられます。また自立支援医療を活用すれば月々の上限管理も可能。まずは全体像をつかみ、あなたの条件での目安を理解していきましょう。
精神科訪問看護の料金はいくらかかる?

| 負担割合 | 月の初回訪問 | 2回目以降 |
|---|---|---|
利用料金 |
12,990円 | 8,550円 |
3割負担 |
3,897円 | 2,565円 |
2割負担 |
2,598円 | 1,710円 |
1割負担 |
1,299円 | 855円 |
上記は医療保険を適用した場合の料金になります。
正看護師または作業療法士が訪問した場合の料金です。週3回までの訪問料金となります。
週4回以上の訪問では料金が異なる場合があります。
精神科訪問看護の料金は、「基本料金 × 負担割合」で考えると理解しやすいです。月の初回は加算があるため高く見えますが、2回目以降は抑えられます。負担割合は原則1~3割で、収入や年齢、保険の種類によって決まります。たとえば3割負担なら、初回3,897円・2回目以降2,565円が目安です。訪問回数や時間帯(早朝・深夜など)、24時間連絡体制の有無によっても金額が前後する点を押さえておきましょう。
訪問時間は30分単位で調整可能で、1回30~90分が一般的です。週1~3回の利用なら無理なく続けやすく、通院の負担を減らしながら病状観察・服薬支援・生活リズムの調整を自宅で受けられます。通院による移動や待ち時間のストレスを減らせることも、精神科訪問看護の大きなメリット。症状が不安定な時期でも、在宅での支援により再発予防や安定した生活につながります。
また、精神科訪問看護はお子さまから高齢者まで幅広く対象です。家族への助言や連携支援も含まれるため、安心して相談できます。費用が心配な方は、次章で紹介する自立支援医療制度を利用すれば、自己負担額の上限管理が可能です。制度を使うことで、薬剤費や通院費の出費も見通しやすくなります。
時間外対応や緊急時の連絡体制などは事業所ごとに異なるため、契約前に確認しておくと安心です。料金や加算のルールは制度改定で変更される場合があるため、最新の情報を確認し、助成制度の併用可否もチェックしておきましょう。準備を整えておけば、必要な支援を我慢せずに最適な頻度・時間で利用できます。
自立支援医療を利用したときの費用負担は?
自立支援医療制度の仕組み
精神科訪問看護では、自立支援医療制度(精神通院医療)が適用できる場合があります。この制度は、長期的な通院や訪問看護などを継続的に受ける方の経済的負担を軽減する目的で設けられています。自己負担割合を通常の3割から1割に軽減できるのが最大の特徴で、利用にはお住まいの自治体への申請が必要です。
対象となるのは、うつ病・統合失調症・発達障害・不安障害・PTSD・双極性障害など、継続的な医療支援が必要な精神疾患を持つ方です。精神科訪問看護を含め、通院治療や服薬管理などが制度の対象になります。申請には主治医の意見書、保険証の写し、所得を証明する書類などが必要で、審査を経て1年間有効な「自立支援医療受給者証」が交付されます。
制度を利用することで、精神科訪問看護の費用も1割負担に軽減されるため、継続的な支援を受けやすくなります。特に週2回以上の訪問を希望する場合や、長期で利用する場合には大きな経済的メリットがあります。更新手続きは毎年必要ですが、書類をそろえれば比較的スムーズに進められるため、早めの申請をおすすめします。
負担限度額の具体例
自立支援医療には所得区分に応じた「月ごとの自己負担上限額」が設定されています。たとえば低所得世帯であれば月額2,500円〜5,000円、高所得層でも20,000円〜30,000円が上限となります。つまり、1か月に精神科訪問看護を何度利用しても、上限を超える支払いは発生しません。
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 生活保護 |
0円 |
| 低所得1 |
2,500円 |
| 低所得2 |
5,000円 |
| 中間所得1 |
5,000円 |
| 中間所得2 |
10,000円 |
| 一定所得以上 |
20,000円 |
表の料金は所得に応じた医療費の月額自己負担額の上限額となっております。
表の料金を超えた場合には、自己負担なしで医療が受けられます。
この上限管理制度によって、精神科訪問看護の継続利用が現実的になります。たとえば週2回訪問を受けたとしても、月間費用が上限内に収まるため、経済的な負担が大幅に軽減されます。高齢の方や障害年金を受給している方も対象となる場合が多く、制度を活用することで安心して在宅支援を受けられるようになります。
医療費軽減のための手続き方法
自立支援医療の申請手続きは、お住まいの市区町村の福祉課・障害福祉担当窓口で行います。申請には以下の書類が必要です。
- 主治医が記入した「自立支援医療(精神通院)診断書」
- 健康保険証の写し
- 世帯の所得証明書または課税証明書
- 印鑑(署名可の場合もあり)
申請後、通常1〜2か月で受給者証が届きます。発行後は医療機関や訪問看護ステーションに提示することで、1割負担が適用されます。更新手続きは1年ごとに必要となるため、有効期限が切れる前に早めに申請しておきましょう。
また、東京都や埼玉県など一部自治体では、心身障害者医療費助成制度や子ども医療費助成制度などと併用できる場合もあります。これらを組み合わせることで、自己負担が実質無料になるケースも。シンプレ訪問看護ステーションでは、制度利用に関するアドバイスや申請書類の準備サポートも行っていますので、気軽にご相談ください。
精神科訪問看護を利用するメリット

自宅でリラックスして看護を受けられる
精神科訪問看護の大きな魅力の一つは、「慣れた自宅で看護を受けられること」です。病院のような緊張感がなく、安心できる環境で支援を受けることで、心身の安定につながりやすくなります。特にうつ病や不安障害、統合失調症の方にとって、自宅という安心感は治療の継続に大きな意味を持ちます。在宅でリラックスした状態で看護師の支援を受けることで、通院への負担を減らし、回復をサポートします。
また、訪問看護では体調や気分に合わせて訪問時間や頻度を柔軟に調整できるため、無理なく継続できます。体調の波がある方でも、状態に合わせて短時間の訪問に切り替えるなどの対応が可能です。病状の変化があればその場で記録・共有され、主治医や関係機関とスムーズに連携が取れる点も大きなメリットです。
看護師との対話で病状を細かく把握できる
精神科訪問看護では、看護師が定期的に訪問し、利用者本人との会話を通して体調や感情の変化を丁寧に観察します。日々の小さな変化を見逃さないことが、再発防止や早期対応につながります。会話の中で不安や悩みを話すことでストレスの軽減にもつながり、医療的なサポートだけでなく「心のケア」も受けられるのが特徴です。
服薬管理や生活習慣の調整、睡眠リズムの改善など、具体的な支援を行うことも多く、体調やメンタルの安定をサポートします。また、家族への情報共有や介護負担の軽減にもつながり、本人だけでなく周囲の生活環境全体を整える効果があります。こうした定期的な関わりが、信頼関係を築きながら安心できる生活を支える基盤となります。
保健・福祉・介護・生活支援・就労支援等のサービスが受けやすい
精神科訪問看護は、単に医療的なケアを行うだけではありません。保健・福祉・介護・就労支援など、さまざまな社会資源とのつながりをサポートします。たとえば、福祉サービスの申請や生活保護制度、障害年金、就労移行支援事業所との連携なども看護師が一緒に確認・助言を行います。
また、退院直後で生活に不安がある方や、社会復帰を目指す方に対しても、生活支援・社会参加支援・就労支援を一体的にサポート。自宅での生活が安定すると、外出や趣味活動などにも意欲的に取り組めるようになります。「医療」と「生活」をつなぐ役割を担うのが、精神科訪問看護の大きな特徴です。
シンプレ訪問看護ステーションでは、看護師や作業療法士がチームで連携し、利用者一人ひとりの生活スタイルに合わせた支援を行っています。東京23区・西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市など、幅広い地域に対応しているため、地域に根ざした支援を受けたい方にも安心です。
訪問看護の内容をチェック

訪問看護全般の内容
訪問看護は、病気や障がいを持つ方が住み慣れた自宅で安心して生活できるように、医療と生活の両面からサポートを行うサービスです。看護師や作業療法士がご自宅を訪問し、健康状態の確認、服薬管理、生活支援、家族への助言などを行います。病院と同等の医療ケアを在宅で受けられることが大きな特徴です。
具体的には、バイタルサイン(血圧・脈拍・体温など)のチェック、服薬の確認や指導、体調の変化への対応、入浴・清拭などの清潔支援、創傷や褥瘡(床ずれ)の処置などを行います。また、在宅酸素療法や胃ろう、カテーテル管理、ストーマ(人工肛門)のケアなど、医療的なサポートも可能です。
さらに、退院後の生活の立て直しや再発予防の支援、家族の方への介護負担軽減のための助言も行っています。訪問看護は医療保険・介護保険のどちらでも利用可能で、状況に応じて制度を選択できます。生活の質を維持しながら治療を継続できるという点で、在宅医療の中核を担うサービスと言えます。
精神科訪問看護ならではのサポート
精神科訪問看護では、一般的な看護業務に加えて、心のケアと生活支援を重視した支援を行います。うつ病や統合失調症、不安障害などの方が、日常生活の中で症状と上手に付き合いながら過ごせるよう、メンタル面の安定をサポートすることが中心です。
看護師や作業療法士が定期的に訪問し、体調や睡眠の状態、服薬状況、日常生活のリズムなどを確認します。気持ちの変化を丁寧にヒアリングしながら、必要に応じて主治医と連携し、治療方針の調整にもつなげます。「話を聞いてもらえる安心感」が、再発防止や社会復帰への第一歩になることも多いです。
また、引きこもりや社会的孤立状態にある方への訪問支援も行っています。外出のきっかけ作りや日中活動の支援、地域とのつながりを持つためのサポートなど、生活全体の改善を目指したケアが特徴です。訪問を通じて信頼関係を築き、本人のペースに合わせながら少しずつ行動範囲を広げていきます。
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神疾患に特化した専門スタッフが在籍し、医療面・生活面の両方から支援を行っています。週1〜3回(必要に応じて週4回以上も可能)の訪問を通して、服薬支援・再発予防・社会復帰サポートなどを実施。ご家族への相談対応や制度利用のアドバイスも行っており、安心して在宅療養を続けられる環境づくりをサポートしています。
主な疾患をチェック
精神科訪問看護では、さまざまな精神疾患や心の不調に対応しています。医療と生活をつなぐ支援を目的としており、疾患の種類に合わせた専門的なケアを行うのが特徴です。うつ病や統合失調症だけでなく、発達障害・PTSD・双極性障害・不安障害・認知症など、幅広い症状に対応可能です。症状の安定や社会復帰を支える継続的な支援を受けることで、再発予防や生活の質の向上が期待できます。
統合失調症
幻聴・妄想・意欲の低下などが見られる統合失調症では、服薬管理や生活リズムの調整が特に重要です。訪問看護では、体調観察と服薬支援を中心に、再発の兆候を早期に察知し、医師への報告・連携を行います。安定した生活の継続を目指しながら、外出や社会活動のサポートも実施します。
うつ病
うつ病の方に対しては、気分や睡眠状態、食欲、服薬の継続状況を確認し、日常生活のリズムを整える支援を行います。「無理をしない生活ペース」を大切にしながら、体調に合わせて休息と活動のバランスを調整。気分の落ち込みが強い時期には、傾聴や心理的サポートを重視し、安心感を得られるよう寄り添います。
アルコール依存症
アルコール依存症の場合は、断酒の維持や再飲酒の防止を目的とした支援を行います。飲酒欲求をコントロールするための助言や、通院・服薬の継続をサポート。ご家族への支援も含め、生活リズムの改善や社会的孤立の防止を目指します。本人と家族の両面から支えることで、再発を防ぎながら回復をサポートします。
ほかにも様々な疾患に対応
精神科訪問看護では、上記以外にも以下のような疾患に対応しています。
- 発達障害(自閉スペクトラム症、ADHDなど)
- 双極性障害
- 不安障害・パニック障害
- 強迫性障害(OCD)
- PTSD(心的外傷後ストレス障害)
- 知的障害
- 認知症
- ひきこもり・適応障害 など
これらの疾患は、長期的なサポートが必要になるケースが多いため、精神科訪問看護を活用することで安定した生活を維持しやすくなります。特に、服薬の継続が難しい方や通院が負担になっている方には、自宅で医療的支援を受けられる訪問看護が有効です。
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神科の経験を持つ看護師や作業療法士がチームで支援を行い、病気と向き合いながら「その人らしい生活」を取り戻すお手伝いをしています。病状やライフスタイルに合わせて柔軟に対応いたしますので、まずはご相談ください。
精神科訪問看護が可能な疾患は?

主な疾患をチェック
妄想・幻覚・認知障害など
うつ病
抑うつ状態・集中力低下絶望感など
アルコール依存症
アルコール幻覚症・振戦せん妄・自律神経不安定
精神科訪問看護で対象の主な疾患には統合失調症・うつ病・アルコール依存症などがあります。
統合失調症は100人に1人弱がかかると言われている患者数が増えてきている精神疾患です。
うつ病は、抑うつ状態の時は命に関わることもあるので継続的な治療が必要になります。
アルコール依存症も現在は精神疾患として広く認知されており、どのようにアルコールと付き合っていくかを考える必要があります。
各疾患について、下記で詳しく解説していきます。
統合失調症
統合失調症の症状は、幻覚や妄想のほか、自分の考えがまとまらくなったり、喜怒哀楽が乏しくなり物事に感動したりできなくなるのが特徴です。
早期発見・早期治療が大切であり、薬物療法の他にもご家族や周りの人からの協力が重要です。
統合失調症は発症の原因が明らかではないため、症状悪化・再発防止のために治療の継続が必要になります。
うつ病
うつ病とは、気分が落ち込み、やる気がなくなる、興味や喜びがなくなるなどの症状が続く精神疾患です。
以前は楽しんでいたことに対して興味を持てなくなったり、疲労感や睡眠障害が現れることもあります。
また食欲減退や、頭痛やめまいなどの身体症状が現れたりします。自分自身や周囲の人がうつ病の症状に気づいた場合は、早めに医療の専門家に相談することが大切です。
アルコール依存症
アルコール依存症は飲酒量のコントロールができない、断酒ができないといった状態の中で日常生活に支障をきたす状態を指します。
離脱症状(手の震えや幻覚)が出たり正常な判断ができなくなったりなど、生活や人間関係に影響を及ぼします。
患者さんの状態次第では外来での治療も可能ですが、症状が重い場合など入院で治療も多いのが特徴です。
アルコール依存症を克服するためには個人の頑張りだけではなく、専門的な機関の協力や周りの人からの協力が必要不可欠となります。
ほかにも様々な疾患に対応
精神科訪問看護では、上記3つの疾患の他にも様々な精神疾患に対応しているのが特徴です。
精神疾患は子供や大人などの年齢や性格に関わらず様々な人がかかる可能性のあるものです。
家族の中や、一人で抱え込まず助けを求めること、他者の精神疾患も理解することが大切になります。
精神訪問看護ならシンプレ訪問看護ステーションにお任せください!

シンプレ訪問看護ステーションの特徴
シンプレ訪問看護ステーションは、精神科訪問看護を専門とした事業所として、利用者一人ひとりに合わせたきめ細やかなサポートを行っています。うつ病・統合失調症・発達障害・PTSD・不安障害など、多様な疾患に対応。看護師・准看護師・作業療法士などの専門スタッフが連携し、医療面・生活面の両方から支援を行っています。
専門性の高い看護
精神科領域の経験を持つスタッフが在籍しており、専門知識に基づいた丁寧な支援を提供します。症状の観察や服薬支援、再発予防のためのアドバイスを通じて、利用者の安定した生活をサポート。「その人らしい生活」を取り戻すことを大切にしています。また、主治医や関係機関と密に連携し、医療と地域支援をつなぐ役割も担っています。
利用者の自主性を尊重
シンプレでは、利用者の意思やペースを尊重した支援を行っています。無理に行動を促すのではなく、安心できる関係づくりを大切にしながら、本人が少しずつ前向きになれるようサポート。日常生活の中で「できた」という小さな成功体験を積み重ねることで、自信の回復と社会参加への意欲を育みます。
迅速な対応と行動力
体調の変化や急なご相談にも柔軟に対応できる体制を整えています。週1〜3回の訪問を基本としつつ、必要に応じて週4回以上の訪問も可能。土日・祝日も訪問対応しているため、仕事や家庭の都合に合わせた利用がしやすいのも特徴です。状況に応じて主治医との連携や緊急時のサポートも行い、安心して在宅療養を続けられる環境を提供しています。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションは、東京都23区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、府中市、東久留米市などを中心に訪問を行っています。また、埼玉県の一部地域への訪問も可能です。近隣市区町村にお住まいの方も、対応可能な場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
訪問スタッフには、看護師・准看護師・作業療法士が在籍し、それぞれの専門分野を活かして連携しています。訪問時間は1回あたり30分〜90分程度、週1〜3回を基本とし、ご本人とご家族の希望に合わせて柔軟に対応しています。祝日や土曜日も訪問が可能なため、生活リズムを崩さずに支援を受けることができます。
また、利用できる制度として「自立支援医療制度」「心身障害者医療費助成制度」「子ども医療費助成制度」「生活保護」などがあり、医療保険を利用して経済的な負担を軽減できます。シンプレでは、制度利用に関する相談や申請サポートも行っています。費用面や支援内容に不安がある方も、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ|精神科訪問看護の料金と費用を正しく理解して利用しよう

精神科訪問看護の料金は、訪問時間・回数・保険の種類などによって異なりますが、多くの場合は医療保険や自立支援医療制度を利用することで、自己負担を抑えて継続的に支援を受けることが可能です。初めて利用する際には、「基本料金」「保険の適用範囲」「自己負担額」「制度による助成」の4点を押さえておくと安心です。
特に、自立支援医療制度を活用することで、自己負担が1割に軽減されるうえに、月額の上限額も設定されます。そのため、週2〜3回の利用でも経済的な負担を最小限に抑えることができます。制度の利用には申請が必要ですが、自治体の福祉課で手続きを行うことでスムーズに申請できます。
また、精神科訪問看護を継続することで、病状の悪化や再発を防ぎ、安定した生活を続けやすくなります。通院が難しい方や、外出に不安を感じる方にとって、自宅で専門スタッフによる支援を受けられることは大きな安心材料です。「医療」「生活」「心の安定」を総合的に支えるのが精神科訪問看護の役割といえるでしょう。
シンプレ訪問看護ステーションでは、経験豊富な看護師・准看護師・作業療法士が在籍し、一人ひとりの生活リズムや症状に合わせたケアを行っています。東京23区を中心に、西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・東久留米市など幅広い地域で対応可能。訪問回数や時間も柔軟に調整できるため、初めて利用する方でも安心です。
料金面の不安や制度利用に関する疑問がある方は、まずは無料相談を活用してみてください。制度の仕組みや費用の目安を丁寧に説明し、最適なプランをご提案いたします。あなたの「安心して暮らせる毎日」を、シンプレ訪問看護ステーションがしっかりとサポートします。
精神科訪問看護は、「通院が難しい」「一人での生活に不安がある」という方にとって、心強い在宅支援の仕組みです。正しい料金の理解と制度の活用が、安心して長く続けられる第一歩。ぜひシンプレ訪問看護ステーションへご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (5)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



