うつ病で吐き気が続く原因と対処法|身体症状とセルフケアを徹底解説
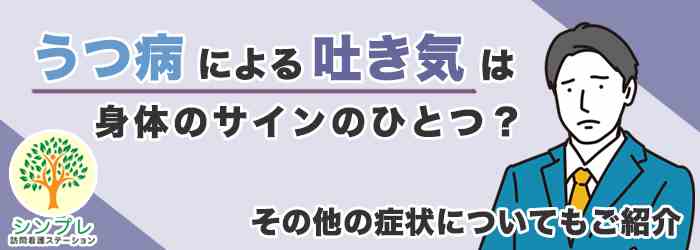

うつ病はこころの病気として知られていますが、実は身体の不調として現れることも少なくありません。
その中でも「吐き気」は、日常生活に大きな支障を与える症状のひとつです。
うつ病で吐き気を感じる方は珍しくなく、食欲不振や体調不良につながることもあります。
本記事では、「うつ病と吐き気」というテーマに注目し、原因や特徴、日常生活への影響について詳しく解説していきます。
体調と心の不調がどのように結びついているのかを理解することで、より適切な対処法が見えてくるでしょう。
うつ病で吐き気が起きる?

うつ病で吐き気が起きる原因
うつ病に伴う吐き気は、単なる消化器系の不調ではなく、心と体のバランスが崩れた結果として現れることが多いです。
脳内の神経伝達物質(セロトニンやノルアドレナリンなど)の働きが乱れることで、自律神経に影響を与え、胃腸の動きが低下することがあります。
その結果、消化不良や胃の不快感、吐き気といった症状が現れるのです。
さらに、精神的な緊張や不安感が強まると、自律神経が過敏になり、胃酸の分泌過多や胃のけいれんを引き起こす場合もあります。
つまり「うつ病と吐き気」は密接に関係しているといえるでしょう。
うつ病の特徴とは
・一人で多くのことを抱え込んでしまう
・几帳面で完璧でないと気が済まない
・自分を過度に責めてしまう
特徴
・夜眠れず生活が不規則になる
・外に出るのが辛くなる
・人と話すことができなくなる
うつ病の特徴は「気分の落ち込み」だけではありません。
身体的な不調として、吐き気や頭痛、めまい、慢性的な倦怠感などが現れることも多く、風邪や胃腸炎と間違われるケースも少なくありません。
これらの症状が長引くと、仕事や学業、家庭生活に大きな影響を及ぼします。
また、うつ病は一人ひとりの症状が異なるため、必ずしも典型的な精神症状だけが出るわけではない点も特徴です。
身体症状に気づかず放置してしまうと、病気の悪化を招く恐れがあるため、早めに医療機関へ相談することが大切です。
うつ病で吐き気が続くとどうなる?

日常生活への影響
うつ病で吐き気が続くと、仕事や家庭生活に深刻な影響を及ぼすことがあります。
例えば、朝起きた時点で吐き気を感じると通勤や通学が困難になり、欠勤や欠席が増えることもあります。
また、日中も胃の不快感やむかつきが続くと集中力が低下し、仕事のパフォーマンスに影響が出やすくなります。
吐き気が慢性的に続くと体調不良から外出を避けるようになり、孤立感を深める原因にもつながるのです。
その結果、社会とのつながりが希薄になり、さらに抑うつ状態を悪化させる悪循環に陥る可能性があります。
こうした日常生活への影響を軽視せず、早めに対応することが重要です。
食欲不振・体重減少との関係
吐き気が続くと「食べたいのに食べられない」という状況に陥りやすくなります。
特にうつ病では食欲の低下がよくみられるため、吐き気と相まって十分な食事が取れなくなるのです。
その結果、体重減少や栄養不足を引き起こし、体力の低下や免疫力の低下につながります。
さらに、栄養状態の悪化は心身の回復を妨げ、うつ症状を長引かせる要因ともなります。
「うつ病の吐き気」と「食欲不振」は互いに悪影響を及ぼし合い、心身を弱らせてしまうという点を理解しておきましょう。
食事が取れないほどの吐き気が続く場合は、我慢せず医療機関に相談することが大切です。
うつ病のからだとこころの症状

うつ病の身体症状
- 睡眠障害
- 吐き気
- 食欲減退
- 疲労、倦怠感
うつ病は「こころの病気」と思われがちですが、実際には身体にさまざまな不調を引き起こすことがあります。
代表的なのは吐き気・睡眠障害・頭痛・めまい・倦怠感などです。
特にうつ病の吐き気は胃腸の働きや自律神経の乱れに深く関わっており、消化不良や胸やけと同時に現れることもあります。
また、日によって症状が強まったり弱まったりするのも特徴で、体調の波に悩まされる方も少なくありません。
吐き気
ストレスや不安が強まると、自律神経が過敏に反応し、脳にある嘔吐中枢が刺激されます。
その結果、胃酸が過剰に分泌され、胃のムカつきや吐き気が生じるのです。
長く続くと食欲不振や体重減少を招き、さらなる体調悪化を引き起こします。
「うつ病の吐き気」は心身両面のSOSサインとして現れている可能性があるため、無視せずに受け止めることが大切です。
睡眠障害
| 睡眠障害の種類 | 症状 |
|---|---|
入眠障害 |
なかなか寝付けない |
中途覚醒 |
夜中に何度も目が覚めてしまう |
熟眠障害 |
眠りが浅くなる |
うつ病の方の多くが経験するのが睡眠障害です。
夜に眠れない「入眠障害」、途中で何度も目が覚める「中途覚醒」、ぐっすり眠れない「熟眠障害」、逆に長時間寝ても眠気が取れない「過眠」など、症状はさまざまです。
睡眠の質が低下すると疲労感が抜けず、吐き気や頭痛などの身体症状がさらに悪化する悪循環に陥ることがあります。
頭痛・めまい・倦怠感
うつ病では慢性的な頭痛やめまい、強い倦怠感を訴える方も多くいます。
これらの症状は脳内の神経伝達物質のバランスが崩れることで引き起こされると考えられています。
体を動かすエネルギーが不足し、少しの活動でも強い疲労を感じやすくなるのが特徴です。
結果として日常生活の質が下がり、気持ちの落ち込みがさらに深まる原因になります。
こころの症状
- 意欲の低下
- 抑うつ気分(何をしても気分が晴れない)
うつ病は「気分が落ち込む」だけではなく、意欲の低下や不安感、興味・関心の喪失など多面的な症状を伴います。
以前楽しめていた趣味や人との交流に喜びを感じられなくなることもあり、孤独感が増す要因となります。
また、焦燥感や自己否定的な思考が強まり、心身ともに追い詰められるケースも少なくありません。
その他の症状
・不安・焦燥感(不安な気持ちが頭から離れない)
・注意・集中力の低下
・無価値感・罪業感(自分は役に立たない人間だと感じる)
・希死念慮(死にたくなる、死や自殺について考える)
そのほかにも、注意力の低下、集中力の欠如、強い不安、無価値感や罪悪感などが現れることがあります。
さらに深刻な場合には「消えてしまいたい」といった希死念慮が出てくることもあるため、放置せず早めの対応が必要です。
うつ病は身体と心の両面に症状が出るため、「体の不調は心からのサイン」と理解し、医療機関や支援サービスに相談することが回復への第一歩となります。
ストレスと自律神経の関係

自律神経と胃腸などの消化器官の関係
私たちは緊張や不安を感じると、お腹が痛くなったり、便秘や下痢を起こしたりすることがあります。
これは、自律神経が胃腸の働きをコントロールしているためです。
自律神経は交感神経と副交感神経から成り立ち、活動時や緊張時には交感神経が優位に、休息時には副交感神経が優位になります。
ストレスが強くかかると交感神経が過剰に働き、胃腸の動きが抑制されてしまうため、胃もたれや胸やけ、さらには吐き気につながります。
うつ病で吐き気が起きやすいのも、この自律神経と胃腸の関係が大きく影響しているのです。
胃腸の働き
| 働き | 胃腸への影響 |
|---|---|
交感神経 |
胃酸の分泌を抑制 胃・腸の動きを鈍らせる |
副交感神経 |
胃酸の分泌を促進 胃・腸の動きを活発にする |
本来であれば交感神経と副交感神経がバランスを取りながら働きますが、ストレスが長期間続くと交感神経が優位な状態が続きます。
その結果、食欲不振や吐き気、便秘や下痢などの不快な症状が出やすくなります。
特に「うつ病の吐き気」の背景には、この自律神経の乱れが深く関与していると考えられます。
ストレスで自律神経が乱れるメカニズム
強いストレスを受けると脳は危険を回避するために交感神経を活発に働かせます。
これは一時的には体を守る反応ですが、慢性的に続くと心身に悪影響を及ぼします。
心拍数や血圧の上昇、呼吸の乱れに加え、胃腸の働きが低下することで吐き気や胃痛が現れやすくなります。
うつ病の方は心身ともにストレスに敏感になっているため、自律神経のバランスが崩れやすく、吐き気が繰り返し出ることも珍しくありません。
このように、ストレスと自律神経は切っても切れない関係にあり、セルフケアや医療機関でのサポートを受けながら整えていくことが重要です。
うつ病と自律神経失調症との違い

症状の共通点
うつ病と自律神経失調症は、いずれもストレスが大きな原因となる点で共通しています。
どちらの病気も、吐き気やめまい、頭痛、倦怠感といった身体症状が現れることがあり、一見すると区別がつきにくい場合があります。
特に「うつ病の吐き気」は、自律神経失調症の症状としても起こりやすく、両者を混同してしまう方も少なくありません。
また、気分の落ち込みや不安感といった心の不調が身体症状と同時に現れるケースも多いため、正しい診断を受けることが非常に重要です。
症状の違い
一方で、うつ病と自律神経失調症には明確な違いもあります。
自律神経失調症は「病名」というよりも、交感神経と副交感神経のバランスが崩れた状態を表すもので、症状が一時的に改善することもあります。
それに対して、うつ病は脳内の神経伝達物質の働きが低下することによって起こる精神疾患のひとつであり、長期間にわたって気分の落ち込みや意欲の低下が続きます。
加えて、うつ病では「何をしても楽しめない」「気力が出ない」といった精神症状が強く出るのが特徴です。
つまり、うつ病は自律神経失調症よりも心の症状が深刻で長期化しやすいといえます。
このように、両者は似た症状を持ちながらも原因や特徴が異なります。
特に吐き気のような身体症状だけを見て自己判断してしまうと、適切な治療を受けられない恐れがあります。
うつ病の場合はカウンセリングや薬物療法を組み合わせた治療が必要となることが多いため、気になる症状が長引く場合は早めに精神科や心療内科を受診することが大切です。
自己判断せず、医師の診断を受けることで正しいアプローチにつながり、回復への近道となります。
うつ病のきっかけとなりやすいライフイベント

・パワハラ・セクハラ
・仕事のトラブル
・夫婦の不和
・近隣トラブル
・育児ストレス
喪失体験
・近親者との死別
・失恋
・離婚
・子どもの独立
職場や人間関係のストレス
うつ病の大きなきっかけのひとつが人間関係や職場でのストレスです。
パワハラやセクハラ、同僚との不和、過重労働などが続くと心身に大きな負担がかかり、抑うつ状態に陥りやすくなります。
特に責任感が強く、真面目な性格の方ほど「自分が頑張らなければ」と無理を重ねてしまい、気づかないうちに症状が悪化する傾向があります。
こうしたストレスは、自律神経を乱し胃腸の働きに影響するため、吐き気や胃の不快感といった症状にもつながります。
大きな環境の変化(引っ越し・転職など)
進学・就職・転職・引っ越しといった大きな環境の変化も、うつ病のきっかけになりやすい要因です。
新しい生活に適応するためにはエネルギーが必要であり、緊張や不安が続くと心身のバランスを崩しやすくなります。
環境の変化は「期待」と同時に「負担」にもなりやすく、吐き気や不眠といった身体症状を伴うことも少なくありません。
このような変化の時期には、無理をせず十分な休養を取り、必要であれば周囲のサポートを受けることが重要です。
喪失体験(離婚・死別など)
家族や大切な人との死別、離婚、失恋などの喪失体験も、心に大きな影響を与えます。
強い悲しみや孤独感は長期間続くことがあり、気分の落ち込みや不安感を引き起こします。
これらのストレスは身体にも表れ、食欲不振や吐き気といった消化器症状が出やすくなるのです。
喪失体験による「うつ病の吐き気」は心の痛みが身体に現れているサインとも言えるでしょう。
悲しみをひとりで抱え込むのではなく、信頼できる人や医療機関に相談することが大切です。
このように、うつ病は日常生活の中で起こるさまざまな出来事がきっかけとなって発症することがあります。
自分では「乗り越えられる」と思っていても、心身は確実に負担を受けています。
ストレスや喪失体験によって吐き気や体調不良が長く続く場合、それは心からのSOSかもしれません。
無理をせず、早めに専門家へ相談することが回復への第一歩です。
うつ病の吐き気への対処法(セルフケア)

規則正しい生活習慣を整える
うつ病に伴う吐き気を和らげるためには、まず生活リズムを整えることが重要です。
毎日同じ時間に起き、食事や就寝のリズムを一定にすることで、自律神経の乱れが改善されやすくなります。
特に睡眠は心身の回復に欠かせないため、できるだけ質の良い睡眠を意識することが大切です。
朝日を浴びる、軽い運動を取り入れる、寝る前のスマホ使用を控えるといった工夫が、自律神経を整え、吐き気の軽減にもつながります。
食事で気をつけたいこと
吐き気があると食欲が落ちやすいですが、栄養不足は心身の回復を妨げてしまいます。
消化の良い食事を心がけ、無理のない範囲でバランスよく栄養をとることがポイントです。
例えば、おかゆやスープなど体に優しい食べ物を取り入れると、胃腸への負担を軽減できます。
水分補給も忘れずに行うことが大切です。
「うつ病の吐き気」と向き合うとき、食事は治療と同じくらい重要なセルフケアの一つと考えておきましょう。
体力や免疫力を維持することで、回復への道を支えることができます。
リラクゼーションやストレス解消法
うつ病の吐き気はストレスと密接に関係しているため、リラックスできる時間を意識的に取り入れることが効果的です。
深呼吸やストレッチ、アロマテラピーや音楽を聴くなど、自分に合ったリラクゼーション方法を見つけましょう。
軽い運動や散歩も気分転換になり、心身のリズムを整える助けになります。
また、趣味や好きなことに少しずつ取り組むことも、ストレスを軽減する有効な手段です。
日常の中で「安心できる時間」を作ることで、自律神経が安定し、吐き気の症状も和らぎやすくなります。
ただし、セルフケアには限界があるため、症状が長く続いたり悪化する場合は早めに医療機関に相談することが大切です。
自己判断で無理をするのではなく、専門家のアドバイスを受けながらケアを続けることで、より安心して回復を目指せます。
うつ病かもしれないと思ったら?
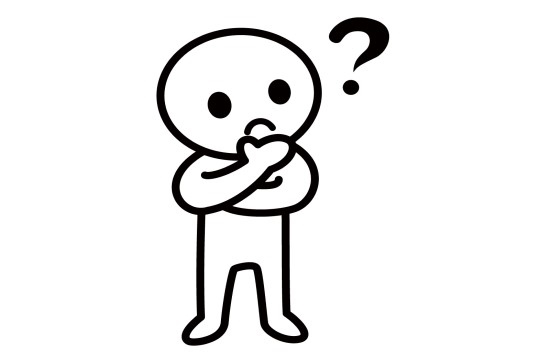
医療機関への相談
「気分が落ち込む日が続いている」「体調不良や吐き気が長引いている」と感じたら、まずは医療機関への相談を検討しましょう。
精神科や心療内科、総合病院の専門外来などでは、うつ病に関する正しい診断と治療を受けられます。
うつ病の吐き気といった身体症状は心の不調から来ていることが多いため、消化器内科だけでなく心のケアが必要なケースが少なくありません。
早めに専門家へ相談することで、治療の選択肢が広がり、回復までの時間も短縮できる可能性があります。
電話相談
「病院に行くのは不安」「誰かに話を聞いてもらいたいけれど、どうすればいいかわからない」という方には、電話相談の利用がおすすめです。
最近では、うつ病や心の悩みに関する無料相談窓口が全国に設けられており、匿名で相談できるところも多くあります。専門の相談員や心理士が対応してくれるため、気持ちを言葉にするだけでも心が少し軽くなる場合があります。
吐き気のような身体症状が続くと外出がつらくなることもあるため、まずは自宅から気軽に電話相談を利用するのも有効な第一歩です。
主な電話相談窓口としては、各自治体の「こころの健康相談統一ダイヤル(0570-064-556)」や「よりそいホットライン(0120-279-338)」、NPO法人などのメンタルヘルス支援団体があります。これらは24時間対応している場合も多く、急な不安や体調不良を感じたときにも頼れる存在です。
また、「死にたい」「誰かを傷つけたい」といった考えや発言があったり、具体的な自殺・他害の計画を立てている場合は精神科救急ダイアルなどの連絡が必要です。
一人にせず、必ず誰かが付き添うことが重要です。
周囲のサポート
うつ病の回復には、医療機関での治療だけでなく、家族や友人といった周囲のサポートが欠かせません。
ご本人の話を否定せずに傾聴すること、安心して休養できる環境を整えることがとても大切です。
特別なことをしなくても「そばにいて見守る」だけで大きな支えになります。
孤独感が強まると症状が悪化しやすいため、信頼できる人とのつながりを保つことが重要です。
一人で抱え込まず、周囲に頼ることは回復への大切な一歩であると意識しましょう。
精神訪問看護という手段もある
・病気との付き合い方を一緒に考え、生活をサポート
・症状悪化の防止や服薬指導
・社会復帰のサポート
ご家族
・家族へのアドバイスや相談
・社会資源活用方法の指導
外出が難しい、あるいは通院に強い負担を感じる場合には、精神訪問看護を利用するという方法もあります。
精神訪問看護では、看護師や作業療法士などの専門職がご自宅を訪問し、服薬管理や生活支援、再発予防、社会復帰のサポートを行います。ご本人だけでなくご家族への助言や支援も含まれるため、安心して治療を続けやすい環境を整えることができます。
特に、吐き気や倦怠感で通院が難しい方にとって、在宅でサポートを受けられることは大きなメリットです。
「自分はうつ病かもしれない」「家族の様子が気になる」と思った時点で、相談を始めることが何よりも重要です。
医療機関や訪問看護など、利用できる制度やサービスを積極的に取り入れることで、心身の負担を減らしながら回復へと進むことができます。
うつ病でお悩みでしたらシンプレ訪問看護ステーションへご相談ください

シンプレの特徴
うつ病は誰にでも起こり得る病気であり、特に吐き気や食欲不振などの身体症状が長引くことで、日常生活が大きく制限されることがあります。
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神科に特化した訪問看護サービスを提供し、患者様が慣れ親しんだご自宅で安心して療養を続けられるようサポートしています。
通院が難しい方でも自宅で専門的な看護を受けられるのが大きな特徴で、服薬支援、生活リズムの調整、社会復帰に向けた支援など幅広く対応しています。
また、シンプレではご本人だけでなくご家族の不安や悩みにも寄り添い、安心して療養を支えられるようにアドバイスや相談を行っています。
うつ病は長期的なサポートが必要となることが多いため、外来診療だけでなく、在宅で継続的に支援が受けられることが強みです。
「うつ病の吐き気」で日常生活に支障が出ている方にも、在宅で無理なく支援を受けられる訪問看護は有効な選択肢となるでしょう。
シンプレの対応エリア
シンプレ訪問看護ステーションは、東京23区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、府中市、東久留米市、埼玉県一部を中心に対応しています。
近隣の市区町村にお住まいの方でも、訪問可能な場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
訪問は週1〜3回、場合によっては週4回以上も対応可能で、1回あたり30分〜90分のサポートを行っています。
祝日や土曜日も対応しているため、生活リズムに合わせた看護が受けられます。
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
うつ病の症状は一人ひとり異なり、特に吐き気や倦怠感といった身体症状が強い場合には、外出そのものが大きな負担になることもあります。
シンプレでは、看護師・准看護師・作業療法士など専門職がチームで支援し、退院後の生活支援や再発予防、服薬管理、家族支援まで幅広く対応しています。まずはお電話やメールでお気軽にお問い合わせください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

うつ病で吐き気が起きることは珍しくない
うつ病はこころの病気というイメージが強いですが、実際には吐き気・頭痛・倦怠感などの身体症状が現れることも珍しくありません。
特に「うつ病の吐き気」はストレスや自律神経の乱れが原因で生じることが多く、食欲不振や体重減少など生活全般に影響を与える可能性があります。
体調不良が続く場合には、消化器系の病気だけでなく心の病気も視野に入れて対応することが大切です。
早めの受診とセルフケアが大切
うつ病の症状は放置すると悪化しやすく、回復に時間がかかることがあります。
吐き気や不眠などの不調が続く場合は、早めに精神科や心療内科を受診し、正しい診断と治療を受けることが大切です。
同時に、規則正しい生活やバランスの取れた食事、リラクゼーションなどのセルフケアを取り入れることで、心身の回復を助けることができます。
「うつ病の吐き気」は心からのSOSサインであると理解し、適切な対処を心がけましょう。
一人で抱え込まず相談することから始めよう
うつ病は誰にでも起こり得る病気であり、一人で抱え込む必要はありません。医療機関への相談だけでなく、家族や友人に気持ちを話すこと、場合によっては訪問看護などのサポートを利用することも大切です。
特に外出が難しい場合には、自宅で専門的な支援を受けられる精神訪問看護が有効な選択肢となります。
吐き気などの身体症状で通院が困難な方にとっても、安心して療養を続けられる環境が整います。
「体調が悪いのは気のせいかもしれない」と思わずに、まずは誰かに相談することから始めましょう。
専門家や支援サービスを活用することで、うつ病と向き合いながら回復へと進む道が開けます。
ご相談の問い合わせはこちら▼

高座渋谷つばさクリニック
医師:武井智昭
外来としてはうつ病(うつ状態)が年間300名程度はおりこちらが得意分野です。この他に、思春期特有の対応(起立性調節障害や拒食症など)も行っています。心療内科としては10年、日本精神神経学会会員に所属
本記事へのコメント
心の不調は「気の持ちよう」ではありません。風邪をひけば内科を受診するように、心の症状も医学的な治療が必要な状態であります。
うつ状態などの精神疾患も、身体の病気と同様であり早期発見・早期治療により重症化を防ぐことは可能であります。症状を我慢し続けることは基本的には心のみならず身体の症状にも表れていきます。
眠れない、食欲がない、意欲が出ない——こうした変化が2週間以上続くときは、がまんせず早めにご相談ください。特に「死にたい」といった考えが浮かんだ時は、必ず誰かに助けを求めてください。
「つらい」という訴えは立派な精神科を受診する理由です。あなた・あなたの家族の健康を守るため、一人で悩まないでください。
監修日:2025年11月5日
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (5)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



