精神疾患を抱える子供の特徴とサイン|家庭での接し方と支援方法を解説
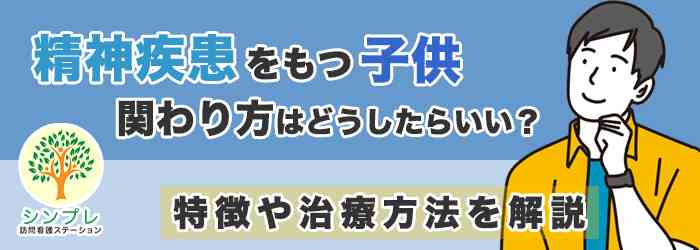

精神疾患は大人だけでなく、子供にも発症する可能性があります。実際に、幼少期から思春期にかけて精神疾患を抱える子供は少なくなく、本人も気づかないまま症状が進行してしまうこともあります。そのため、周囲の大人が子供の変化に敏感に気づき、早期に適切な支援につなげることがとても重要です。精神疾患 子供というテーマは、ご家庭や学校現場で大きな課題となっており、理解を深めることが欠かせません。
この記事では、子供にみられる精神疾患の種類や特徴、そして親や周囲の大人がどのように向き合うべきかを解説します。
子供にみられる精神疾患の例

① 先天的な精神疾患とは?
子供に多い先天的な精神疾患一覧
・集中が続かない、不注意が多い
・衝動的な言動が出やすい
・落ち着いてじっとしていられない
自閉スペクトラム症
・相手との会話ややり取りが苦手
・強いこだわりや同じ行動を繰り返す
・対人関係で困難を抱えやすい
ADHDは「気が散りやすく落ち着きがない」などの特徴があり、同年代の子供と比べて学習面や生活面に困難を生じやすい傾向があります。一方、自閉スペクトラム症は遺伝的要因や脳機能の特性が関係しており、コミュニケーションの難しさや特定のこだわり行動がみられます。これらの先天的な精神疾患は成長過程に大きく影響を及ぼすため、早期に適切な支援を受けることが重要です。
二次障害として現れやすい問題
② 後天的に発症する精神疾患
・気分が落ち込みやすい
・夜眠れない、食欲が落ちる
統合失調症
・幻覚や妄想がみられる
PTSD(心的外傷後ストレス障害)
・過去のトラウマ体験を何度も思い出す
・強い不安や緊張が続く
・頭痛やめまい、睡眠障害を伴うこともある
後天的な精神疾患は、事故や虐待、強いストレス体験などをきっかけに発症することがあります。うつ病やPTSDは日常生活に大きな支障をきたすため、周囲が早く気づき、専門機関への相談や治療につなげることが大切です。適切な治療を受けることで、症状の改善や再発予防が期待できます。
子供が発する精神疾患のサインを見逃さないために

・現実にはない声が聞こえる、根拠のない思い込みを強く持つ
落ち着きのなさ
・授業中や家庭でじっと座っていられない
感情のコントロールが困難
・突然泣き出したり怒ったりする
・理由もなく恐怖にとらわれる
極端な不安や気分の落ち込み
・常に不安を抱える
・憂うつな気持ちが続く
子供が示す行動や態度の中には、精神疾患のサインが隠れていることがあります。例えば、これまで元気に過ごしていた子供が突然「じっとできない」「理由もなく恐怖を訴える」などの変化を見せた場合、単なる性格の問題ではなく精神的な苦しみの表れかもしれません。特に「精神疾患 子供」のケースでは、本人が自覚できないことも多いため、周囲の大人が小さな変化を見逃さないことが大切です。
また、低年齢の子供は自分の気持ちを言葉で説明することが難しいため、行動として現れることが少なくありません。例えば、突然怒り出したり泣き出したりするのは、心の中にある不安や混乱をうまく言葉にできず、行動として噴き出している可能性があります。こうしたサインを「わがまま」「反抗的」と決めつけてしまうと、症状を悪化させてしまう恐れがあるのです。
子供の精神疾患は早期発見・早期治療がとても重要です。気になる行動が繰り返されるようであれば、まず家庭内で子供の様子を丁寧に観察しましょう。そして必要に応じて学校や医療機関、カウンセラーなどに相談することで、子供が安心して過ごせる環境を整えていくことができます。適切な支援を受けることで、子供自身が持つ回復力を引き出し、健やかな成長へとつなげていくことが可能です。
子供の行動から読み取れる精神疾患の兆候

子供の行動の中には、精神疾患の兆候が隠されていることがあります。特に低学年の子供は、自分の気持ちを正確に言葉で伝えることが難しく、不安や苦しみを行動で示すことが少なくありません。例えば、突然泣き出す、怒る、あるいは極端に無気力になるといった変化は、心がSOSを発している可能性があります。「精神疾患 子供」というテーマにおいては、こうしたサインをいち早く読み取ることが重要です。
一方で、大人は子供の行動を「わがまま」や「怠け」と誤解してしまうこともあります。例えば、宿題をしない、学校に行きたがらないといった行動を単なる反抗と決めつけてしまうと、本当に必要なサポートが遅れてしまうかもしれません。注意すべき行動の変化は、子供が精神的に追い込まれているサインである場合が多く、背景にある理由を探ることが大切です。
また、友人関係や学校生活の中での小さな違和感も見逃せません。急に友達と遊ばなくなる、食欲がなくなる、夜眠れなくなるといった生活習慣の変化も、心の不調を示すシグナルです。親や教師など身近な大人が子供の様子を日常的に観察し、小さな違和感を積み重ねて理解することが、早期発見につながります。
さらに、子供の精神疾患は複数の症状が重なって現れることも多くあります。そのため、一つの行動だけで判断せず、時間をかけて全体像を把握することが欠かせません。家庭内だけでなく、学校や地域の支援者とも情報を共有しながら子供を支えることで、安心できる環境を整えることができます。
精神疾患を抱える子供は、自分の気持ちを伝えることが苦手な場合が多いため、大人が「行動に隠れたサイン」を読み取ってあげることが必要です。早い段階で異変に気づき、専門機関や相談先につなげることで、子供の心の健康を守ることができるのです。
精神疾患を抱える子供に起こりやすい二次被害
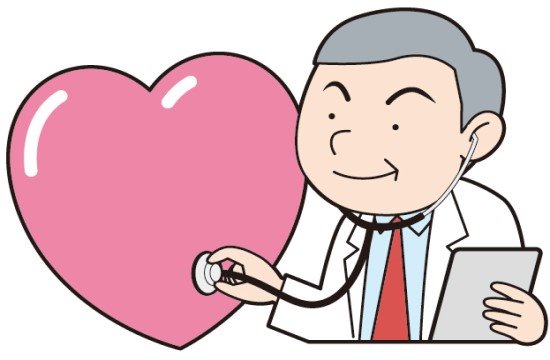
① 学校でのいじめや不登校
精神疾患を抱える子供は、対人関係においてつまずきやすく、その結果として学校でいじめの対象になったり、不登校になることがあります。時には、逆にいじめをしてしまう立場になるケースもあり、いずれも子供にとって深刻な二次被害をもたらします。いじめられる側になれば、強い恐怖や不安からPTSDや対人恐怖症を発症することがあり、最悪の場合は自傷行為や自殺につながるリスクもあります。逆にいじめる側となった場合には、非行や反社会的な行動を取るきっかけとなり、精神疾患が悪化する恐れがあります。
② コミュニケーションの拒否や孤立
「精神疾患 子供」のケースでは、コミュニケーションそのものを拒否し、引きこもってしまう傾向がみられることがあります。友達や家族との交流を避けることで、さらに孤立が深まり、学校や地域社会から遠ざかってしまうのです。このような孤立は長期化すると社会復帰が難しくなり、学習機会や人間関係の喪失といった大きな影響を残すことになります。孤立の連鎖を断ち切るためには、家庭や学校が協力して、安心できる居場所を提供することが必要です。
③ 自己否定や自信の喪失
精神疾患を抱える子供は、周囲との比較から自己肯定感を失い、「自分には価値がない」といった否定的な考えを強く抱くことがあります。この自己否定は学習意欲や人間関係にも影響し、さらに精神疾患の症状を悪化させる悪循環を生み出します。自信を失った子供は、支援者に相談することもためらうようになり、ますます支援の機会を逃してしまう可能性があるのです。
このように、精神疾患そのものだけでなく、そこから派生する二次被害は子供の人生に大きな影響を与えます。だからこそ、早い段階で子供の変化に気づき、いじめや孤立といった問題を未然に防ぐ支援が不可欠です。学校や家庭が連携し、専門機関と協力してサポート体制を整えることで、子供が安心して成長できる環境を築くことができます。
子供の精神疾患に直面する親の苦悩

子供の発症による心理的負担
子供が精神疾患を発症すると、家庭全体に大きな影響を及ぼします。親は保護者としての責任を強く感じ、「自分の育て方が悪かったのではないか」と自責の念に駆られることも少なくありません。精神疾患 子供という現実に直面したとき、親は将来への不安や孤独感に押しつぶされそうになることがあります。また、子供の症状が日常生活に影響を与えるため、仕事や家庭のバランスを取るのが難しくなり、心身ともに疲弊してしまうケースも多くみられます。
・子供の将来への強い不安
・家庭内での責任感や孤独感
・サポート体制が見つからないことによるストレス
・飲酒などで気を紛らわそうとし、アルコール依存症になる危険
このような心理的負担が続くと、親自身がうつ病や不安障害を発症してしまう可能性もあります。実際に「子供の精神疾患に対応しているうちに、親が体調を崩してしまった」という事例は珍しくありません。家族全体が疲弊する前に、第三者の支援を受けることが大切です。
親自身が苦しまないためにできること
子供を支える立場である親が、心身の健康を損なってしまうと、結果的に子供のサポートも難しくなってしまいます。そのため、まずは「親自身も支援を受けてよい」という認識を持つことが重要です。専門機関に相談することで、気持ちを共有できるだけでなく、具体的な対応方法や支援制度についてのアドバイスも得られます。
また、悩みを抱え込まず、信頼できる家族や支援者とつながることも有効です。相談を重ねることで親の不安が軽減され、子供への接し方にも余裕が生まれます。親が健やかに過ごせることは、子供にとっても安心感につながるのです。
精神疾患を抱える子供を育てることは容易ではありませんが、決して一人で抱え込む必要はありません。支援者や専門家と協力しながら、家庭全体で無理のない支援体制を整えることが、子供の回復に向けた大切な第一歩となります。
子供を支えるための方法とは?
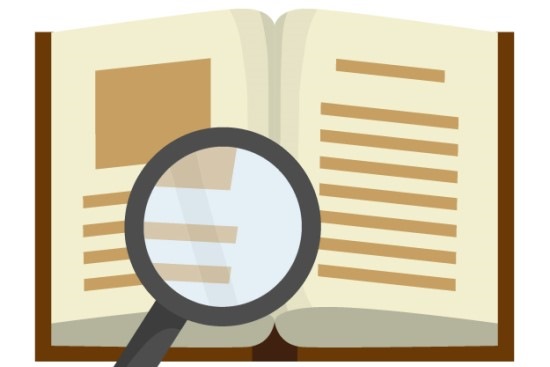
家庭での育て方と安心できる環境づくり
精神疾患を抱える子供にとって、家庭はもっとも安心できる場所であることが望まれます。家庭内の関わり方次第で、子供の安心感や症状の安定度は大きく変わります。親が子供の行動を過度に否定したり、叱責ばかりすると、子供はさらにストレスを抱え込み、不安や症状が強まることもあります。逆に、理解的で落ち着いた対応を心がけることで、子供は安心して生活することができ、症状の悪化を防ぐことにつながります。
「精神疾患 子供」という課題は親だけの責任ではありません。発達や精神面に影響を与える要因には、遺伝的背景や学校・地域環境も含まれます。親御さんは「一人で背負い込まなくていい」という意識を持つことが大切です。医療機関や教育センター、支援機関を活用して、子供に合った接し方を学ぶことで、家庭全体が安心できる環境を整えられます。
相談・対処できる施設や支援先を探す
子供の精神疾患に直面したとき、家庭だけで解決しようとすると親子関係が悪化する危険性があります。そのため、早い段階で相談機関や医療機関につなげることが重要です。適切な支援を受けることで、子供自身の回復力を引き出し、親の精神的負担も軽減できます。
① 病院・診療所での診断と治療
精神疾患を抱える子供は、児童精神科や心療内科で専門的な検査や診断を受けることができます。必要に応じて投薬治療や心理療法を受けられるほか、心理士によるカウンセリングや集団療法を取り入れる場合もあります。専門医による早期の診断は、治療の方向性を決めるうえで大変重要です。
② 地域の保健所や保健センターの利用
地域の保健所や保健センターでは、子供と家庭の状況を丁寧に聞き取り、必要なアドバイスや支援を提供してくれます。場合によっては、医療機関や支援団体とつないでくれることもあり、家庭にとって心強い窓口となります。
③ 学校カウンセラーに相談する
学校には、子供の心の悩みやストレスに対応するために、スクールカウンセラー(学校カウンセラー)が配置されています。
カウンセラーは、子供の話を丁寧に聞き取り、心理的なサポートを行うほか、必要に応じて保護者や教職員と連携して支援の体制を整えます。学校での人間関係や学業の悩み、家庭での困りごとなど、どんな小さなことでも相談できる身近な専門家です。
早めに相談することで、子供の不安を軽減し、安心して学校生活を送る手助けとなります。
④ 訪問看護サービスを利用する
外出や通院が難しい子供の場合、自宅で看護を受けられる訪問看護サービスが有効です。看護師や作業療法士が家庭を訪問し、症状の観察や服薬支援、家族への助言などを行います。とくに精神科訪問看護は、子供と家族が地域で安心して生活を続けるための強い支えとなります。
このように、子供を支える方法は家庭内だけにとどまらず、地域や医療のサポートを組み合わせていくことが重要です。親が一人で抱え込まず、周囲と協力して子供を見守ることが、健やかな成長への第一歩となります。
精神科訪問看護とは?子供や家庭を支えるサポート

自宅で受けられる精神科ケアの特徴
・精神科・心療内科に通院中のお子様
・精神疾患の診断を受けている子供
・診断がなくても医師が必要と判断したケース
訪問するスタッフ
・看護師や准看護師
・作業療法士などリハビリ専門職
訪問時間・回数
・1回30分〜90分
・週1〜3回(必要に応じて週4回以上も可)
・土曜や祝日の訪問も可能
精神科訪問看護とは、看護師や作業療法士などの医療スタッフが家庭を訪問し、子供や家族をサポートする仕組みです。外出や通院が難しい子供にとって、自宅で安心してケアを受けられることは大きな安心につながります。精神疾患 子供のケースでは、病状観察や服薬支援だけでなく、生活習慣の改善や家族への助言も含めて総合的に支援を行います。
訪問看護のメリットは「住み慣れた環境でケアを受けられること」です。子供が安心できる自宅で支援を受けることで、症状の安定や回復が期待でき、学校や社会生活への復帰もスムーズになります。また、親御さんにとっても負担が軽減され、家庭全体が安心できる暮らしを維持しやすくなります。
精神科訪問看護でできるサポート内容
・規則正しい生活リズムの定着
・日常生活の自立を促す支援
症状の悪化防止・服薬支援
・病状や行動の観察
・服薬や受診のサポート
社会復帰サポート
・主治医や学校との連携
・社会生活へ戻るための支援
家族へのサポート
・相談やアドバイス
・利用できる制度や資源の紹介
精神疾患を持つ子供のケアは、本人だけでなく家族へのサポートも重要です。訪問看護では、子供の状態を把握しつつ、家族に対しても適切なアドバイスを行うことで、親御さんが安心して子育てを続けられるように支えます。家庭に寄り添った継続的な支援があることで、子供の回復と家族の安定が両立できるのです。
このように精神科訪問看護は、医療・生活・社会復帰のすべてをつなぐ役割を担っています。専門職によるサポートを受けながら、家庭が孤立せずに子供を支えていけることが、最大の特徴といえるでしょう。
子供の精神疾患でお悩みならシンプレ訪問看護ステーションへ

シンプレ訪問看護ステーションの特徴
シンプレ訪問看護ステーションは、精神疾患に特化した訪問看護サービスを提供しています。私たちは利用者様とご家族の安心を第一に考え、精神疾患 子供への支援にも力を入れています。単なる医療的サポートにとどまらず、生活や社会とのつながりを大切にした包括的な支援を実施しているのが特徴です。主治医をはじめ、地域の支援者や行政機関と連携しながら、お子様とご家族がよりよい生活を送れるように伴走します。
対応している疾患の一例
・気分の落ち込みや意欲の低下
・睡眠障害や食欲不振
統合失調症
・幻覚や妄想などの症状
・思考や行動の混乱
不安障害
・強い不安感や緊張
・日常生活への影響が大きい
発達障害・二次障害
・ADHDや自閉スペクトラム症
・そこから派生するうつ病や不登校など
シンプレでは、うつ病や統合失調症、不安障害といった代表的な疾患はもちろん、発達障害やそこから派生する二次障害にも対応しています。特に「精神疾患 子供」のケースは、成長や学校生活に密接に関わるため、早期からの継続的な支援が欠かせません。私たちはお子様一人ひとりの状態に合わせたケアプランを作成し、家庭と社会の両面から支援を行います。
訪問看護の対応エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリアは以下の通りです。東京23区を中心に、西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・東久留米市、そして埼玉県の一部地域に対応しています。
近隣の市区町村にお住まいの方でも訪問可能な場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
私たちの訪問看護は、年齢を問わず利用が可能です。精神疾患を抱える子供やご家族が安心して生活を続けられるよう、専門的な知識と経験を持ったスタッフが全力でサポートいたします。ご不安や疑問がある場合は、まずはご相談いただければ、制度の利用方法や訪問スケジュールについても丁寧にご案内いたします。
まとめ|子供の精神疾患は早期発見と支援が大切

精神疾患は大人だけのものではなく、子供にも起こり得る重大な問題です。うつ病や不安障害、発達障害など、子供が抱える精神的な課題は多岐にわたり、日常生活や学校生活に深刻な影響を与えることがあります。精神疾患 子供という現実に直面したとき、家族にとっても大きな負担となり、適切な理解と支援が不可欠です。
重要なのは「早期発見と早期支援」です。子供の小さなサインや行動の変化に大人が気づき、専門機関へ相談することが症状の悪化を防ぐ第一歩になります。また、子供の精神疾患は本人だけでなく家族全体に影響を及ぼすため、親やきょうだいも一緒に支援を受けられる体制を整えることが望ましいでしょう。
地域の医療機関、保健センター、訪問看護など、多様なサポート先を組み合わせて利用することで、家庭だけでは支えきれない部分を補うことが可能です。特に精神科訪問看護は、自宅で専門的なケアを受けられるため、外出や通院が難しい子供にとって心強い支えとなります。親御さんにとっても、訪問看護の存在は精神的な安心材料となり、子供との生活に余裕をもたらすでしょう。
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神疾患を抱える子供とそのご家族に寄り添い、病状の観察から生活支援、社会復帰まで幅広いサポートを行っています。子供の将来を守るためには、家庭だけで抱え込まず、専門家とつながることが何よりも大切です。少しでも不安を感じたら、早めに相談することで、子供が健やかに成長できる環境を整えることができます。
精神疾患を抱える子供たちが安心して生活できるように、周囲の大人が理解と支援の手を差し伸べましょう。そして、家族だけで頑張りすぎず、地域や専門機関と協力しながら前向きに取り組むことが、子供と家庭の未来を明るくする大切な一歩となります。
ご相談の問い合わせはこちら▼

高座渋谷つばさクリニック
医師:武井智昭
外来としてはうつ病(うつ状態)が年間300名程度はおりこちらが得意分野です。この他に、思春期特有の対応(起立性調節障害や拒食症など)も行っています。心療内科としては10年、日本精神神経学会会員に所属
本記事へのコメント
お子様の精神疾患は決して他人事ではありません。記事にあるように、ADHDや自閉スペクトラム症といった発達の特性だけでなく、強いストレスをきっかけにうつ状態などを発症することもあります。
周囲の大人が子供の発言の変化、「落ち着きがない」「急に学校に行きたがらない」「こもりがちになった」といった行動に気づくことが重要であり、これらは精神的な苦しみのSOSかもしれません。
自己否定・孤立による「二次障害」を防ぐためにも、早期発見・早期支援が重要です。保護者様自身もご自分を責めず、医療機関(児童精神科など)やカウンセラー、訪問看護を積極的に頼ってください。
適切な治療と支援があれば、お子様は安心して成長し、その子らしい力を伸ばしていけます。
監修日:2025年11月5日
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (5)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



