ナルコレプシーになりやすい人の特徴|発症年齢・遺伝・生活習慣との関係を解説
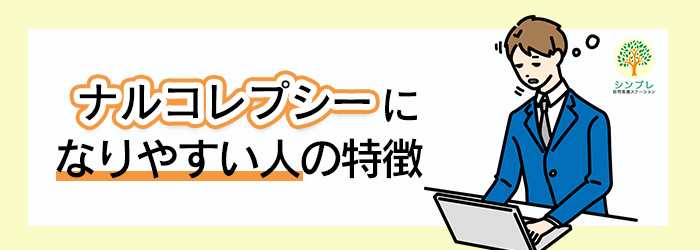

ナルコレプシーは、日中に突然強い眠気に襲われたり、脱力発作などが起こる睡眠障害の一つです。
誰にでも「眠気」はありますが、ナルコレプシーの場合は日常生活や学業・仕事に深刻な影響を与えるほど強い眠気が繰り返されます。
発症しやすい年代や体質には一定の傾向があり、「ナルコレプシーになりやすい人」として研究や臨床報告からわかってきた要素も少なくありません。
本記事では、ナルコレプシーになりやすい人の特徴や背景、さらにその症状や検査、相談先について詳しく解説していきます。
ナルコレプシーになりやすい人はどんな人?

発症は10代から20代前半に集中
ナルコレプシーは、思春期から青年期にかけて発症しやすいことが知られています。
特に14〜16歳頃にピークがあり、10代後半から20代前半に多く見られます。
この時期は学業や進路、就職など生活環境の変化も大きいため、単なる「疲れ」や「夜更かしの影響」と誤解されやすいのも特徴です。
本人も周囲も「病気」と認識せず放置されてしまうケースもあるため、強い眠気や突然の居眠りが続く場合は注意が必要です。
「ただの眠気」と思わず、専門医に相談することが早期発見につながります。
遺伝的要因
ナルコレプシーは、遺伝的要素が大きく関与していると考えられています。
家族にナルコレプシーの方がいる場合、発症リスクが高まると報告されています。
特に一卵性双生児では発症率が高いことからも、遺伝との関連性が示唆されています。
ただし、遺伝だけでなく環境要因や生活習慣との組み合わせによって発症に至ると考えられており、「遺伝があるから必ず発症する」というわけではありません。
日本人の有病率
ナルコレプシーは世界中で発症しますが、日本人の有病率は世界的にも高いとされています。
報告によると、日本人の有病率は人口1万人あたり16〜18人、つまり約600人に1人の割合で発症すると言われています。
この数値は欧米諸国と比べても高く、日本においては特に注意が必要な疾患といえるでしょう。
学校や職場で「居眠りが多い人」と誤解されるケースも少なくなく、社会的な理解の促進が望まれます。
性別との関係
ナルコレプシーは性別による大きな発症差はないとされます。
男女問わず発症しますが、症状の現れ方や生活への影響は人によって異なります。
男性では職場での評価に影響しやすく、女性では生活リズムの乱れが体調不良と重なることも多く報告されています。
性別に関係なく、症状を正しく理解して早めに対応することが大切です。
ストレスや生活習慣の影響
強い精神的ストレスや不規則な生活習慣も、ナルコレプシー発症に関与していると考えられています。
夜更かしや過度の疲労、精神的な緊張状態が続くと、睡眠リズムが乱れやすくなります。
特に思春期は勉強や部活動などで生活が不規則になりがちで、それが発症を促す要因となることもあります。
規則正しい生活を心がけることが症状悪化の予防につながります。
自己免疫との関係という説も
近年では、ナルコレプシーの原因のひとつに自己免疫の関与があるという説も注目されています。
免疫システムの異常が、脳内で覚醒に関わる神経細胞を攻撃してしまうことで、睡眠と覚醒のバランスが崩れる可能性があるとされています。
まだ完全には解明されていませんが、遺伝的要素と環境要因に加えて自己免疫の関与を考慮することで、より包括的な理解が進んでいます。
ナルコレプシーの症状は?
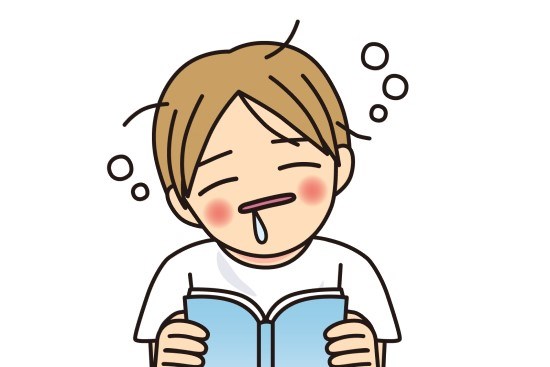
日中の強い眠気と睡眠発作
副症状
・情動脱力発作
・入眠時幻覚
・睡眠麻痺
その他
・自動症
・夜間の熟睡困難
・頭痛
・複視
日中の過度の眠気
ナルコレプシーの最も代表的な症状が、日中に繰り返し強い眠気に襲われることです。
通常の眠気と異なり、状況や場所に関わらず突然眠り込んでしまいます。
授業中や会議中、運転中など、社会生活に大きな支障をきたす危険性があるため注意が必要です。
こうした症状は「睡眠発作」とも呼ばれ、本人の意思ではコントロールが難しいのが特徴です。
情動脱力発作(カタプレキシー)
ナルコレプシー特有の症状のひとつに、強い感情をきっかけに体の力が抜ける「情動脱力発作(カタプレキシー)」があります。
喜びや怒り、驚きといった感情によって突然、顔や首、手足の筋肉の力が抜け、倒れてしまうこともあります。
発作は数秒から数分続くことがあり、日常生活での危険につながるケースも少なくありません。
睡眠麻痺(いわゆる金縛り)
入眠直後や覚醒時に、意識はあるのに体を動かせなくなる「睡眠麻痺」もよく見られる症状です。
俗に「金縛り」と呼ばれる現象で、多くの人が一度は経験しますが、ナルコレプシーの患者さんでは繰り返し起こることが特徴です。
この症状により、強い不安や恐怖感を覚える人も少なくありません。
入眠時幻覚
ナルコレプシーの人は、入眠時にリアルな幻覚を体験することがあります。
映像が鮮明で現実と区別がつきにくく、恐ろしい幻覚に苦しむ場合もあります。
これに睡眠麻痺が重なると「体が動かないのに恐怖の幻覚を体験する」という強烈な不安状態に陥りやすく、精神的な負担も大きくなります。
その他の症状
日中の過度な眠気や発作以外にも、ナルコレプシーにはさまざまな症状が伴います。
例えば、単調な動作を続けている最中に意識が飛び、無意識に行動を続けてしまう「自動症」や、夜間の熟睡困難、頭痛、複視などです。
これらの症状が重なることで、生活の質が大きく低下してしまいます。
周囲からは怠けているように誤解されがちですが、れっきとした病気の症状であることを理解することが大切です。
ナルコレプシーが起こるメカニズムは?

覚醒と睡眠リズムの乱れ
ナルコレプシーは、眠気そのものが通常と異なるのではなく、睡眠と覚醒のリズムが乱れることで症状が出ると考えられています。
夜にしっかり睡眠をとっても、昼間に強い眠気が襲ってくるのが特徴です。
さらに夜間の眠りも浅くなりがちで、疲労が十分に回復できず悪循環に陥ります。
つまり「夜眠れないのに昼は強烈に眠くなる」という状態が繰り返され、日常生活に深刻な影響を与えます。
レム睡眠とノンレム睡眠のリズムの乱れ
通常の睡眠は、筋肉の緊張が保たれる「ノンレム睡眠」から始まり、その後「レム睡眠」と交互に移行します。
1サイクルは約90分とされますが、ナルコレプシーではこのリズムが崩れてしまいます。
健康な人ではまずノンレム睡眠に入るのに対し、ナルコレプシーの人はいきなりレム睡眠に突入することがあります。
そのため、入眠時幻覚や情動脱力発作、睡眠麻痺などが起こりやすくなるのです。
この「レム睡眠への異常な移行」が、代表的な症状の背景にあると考えられています。
睡眠リズムの中枢に障害があるという説も
ナルコレプシーの原因は完全には解明されていませんが、脳内の睡眠リズムをコントロールする中枢に障害があるのではないかという説も有力です。
具体的には、覚醒を維持する役割をもつ神経伝達物質「オレキシン(ヒポクレチン)」の欠乏や機能低下が関与していると考えられています。
オレキシンは眠気を抑え、覚醒を促す働きを持ちますが、ナルコレプシーの患者さんではこの物質が極端に少ないことが確認されています。
そのため「眠気を制御するブレーキ」が効かず、突然強い眠気に襲われるのです。
このような睡眠の特徴は、赤ん坊の睡眠パターンに少し似ているともいわれます。
赤ん坊は浅い眠りと深い眠りを短い周期で繰り返しますが、ナルコレプシーの患者も睡眠が断片的で浅くなりやすく、夜間に熟睡することが難しい傾向があります。
こうした特徴からも、単なる「寝不足」ではなく、脳の機能そのものが関わる疾患であることがわかります。
ナルコレプシーの問題点

怠け者だと思われてしまう
ナルコレプシーの症状である日中の強い眠気や睡眠発作は、本人の意思に関係なく突然訪れます。
しかし周囲からは「居眠りが多い」「やる気がない」と誤解されやすく、「怠けているのでは?」と見なされてしまうことが少なくありません。
この誤解は患者本人の自己評価を下げ、さらにストレスを増加させる悪循環につながります。
本人も病気であることを自覚しにくい
ナルコレプシーは、本人ですら「ただ眠いだけ」と考えてしまい、病気だと気づきにくい傾向があります。
特に思春期や青年期に発症した場合、眠気を「年齢的なもの」や「生活リズムの乱れ」と誤解してしまうことも多いです。
結果として、医療機関を受診するのが遅れ、症状が進行するケースもあります。
「病気である」という認識を持つことが治療や支援を受ける第一歩になります。
学業や仕事に支障をきたす
強い眠気や突然の発作は、学業や仕事に大きな影響を与えます。
授業中に眠り込んでしまう、試験中に集中力が途切れる、会議や商談で意識が飛んでしまうなど、本人の努力では防ぎきれない場面が多くあります。
その結果、成績の低下や評価の誤解を招き、周囲との関係性に影響することも少なくありません。
就労場面では「信頼できない人材」と見られてしまうリスクもあり、本人にとって大きなハンデとなります。
退職や離職を余儀なくされることも
症状が重い場合、職場や学校での適応が難しくなり、最終的には退職や離職に追い込まれることもあります。
繰り返される居眠りや集中力低下は、業務の遂行に支障をきたし、上司や同僚からの理解が得られないことも多いためです。
また、公共の場で発作が起こると事故や怪我につながる危険もあり、本人の社会参加を妨げる大きな要因となります。
社会的な理解が十分に進んでいない現状では、患者は不利な立場に置かれやすいのです。
こうした問題点は、病気そのものの辛さに加えて、誤解や偏見、環境面での不利が重なっていることにあります。
ナルコレプシーは「怠け」や「根性不足」ではなく、医学的に解明が進んでいる睡眠障害です。
正しい理解と周囲のサポートが、患者の生活の質を大きく改善するカギとなります。
ナルコレプシーかどうかを検査する方法は?

睡眠ポリグラフ検査(PSG)
・脳波
・眼球運動
・心電図
・筋電図
・呼吸曲線
・いびき
・動脈血酸素飽和度など
ナルコレプシーの診断に欠かせないのが、睡眠中の脳や体の状態を測定する「睡眠ポリグラフ検査(PSG)」です。
脳波・眼球運動・心電図・筋電図・呼吸曲線・いびき・血中酸素飽和度などを一晩かけて記録し、睡眠の質や異常を詳しく調べます。
この検査により「どのタイミングで眠りが浅くなるか」「レム睡眠に入るか」などを客観的に把握できるため、ナルコレプシーの診断の第一歩となります。
反復睡眠潜時検査(MSLT)
2時間おきに睡眠潜時を
計5回検査して眠気の程度を
評価する
MSLTは、日中にどれくらいの早さで眠りに入るかを調べる検査です。
通常はPSGを前夜に実施したうえで、翌日に2時間おきに5回、横になって眠気を測定します。
健常者に比べて短時間で眠りに落ちたり、入眠直後からレム睡眠に移行する場合、ナルコレプシーの可能性が高いと判断されます。
日中の過度な眠気を客観的に数値化できることから、診断精度を高める役割があります。
覚醒維持検査
・脳波を記録しながら行う
・睡眠潜時(眠りに落ちるまでの時間)を測定
所要時間
20分または40分の検査を
起床時刻から1.5~3時間後より
2時間間隔で4回
検査費用
保険適応外のため、問い合わせ
覚醒維持検査は、暗い部屋で座ったままどの程度起きていられるかを測定する方法です。
20〜40分間の検査を数回繰り返し、眠気に耐える力を評価します。
特に運転や機械操作といった危険を伴う仕事に従事している人にとって、この検査は安全性を確認する上で重要です。
結果は眠気の強さを反映し、適切な生活指導や治療方針の決定につながります。
診断の流れと注意点
ナルコレプシーの診断では、これら複数の検査を組み合わせることが一般的です。
問診や睡眠日誌の記録も行い、生活習慣や睡眠リズムを総合的に評価します。
ただし、「眠気が強い=ナルコレプシー」とは限らず、睡眠時無呼吸症候群やうつ病など他の疾患でも同様の症状が現れるため、専門医の正確な鑑別診断が不可欠です。
これらの検査を経てナルコレプシーと診断されれば、薬物療法や生活改善など適切な治療を進めることができます。
診断に時間がかかるケースもありますが、早期に受診し検査を受けることが、生活の質を守る第一歩です。
ナルコレプシーに関する相談はどこにすればいい?

睡眠障害全般を扱う睡眠外来
「もしかしてナルコレプシーかもしれない」と思ったら、まずは睡眠障害全般を専門に扱う睡眠外来の受診を検討しましょう。
一般的に睡眠外来では、睡眠ポリグラフ検査や反復睡眠潜時検査などを行い、日中の眠気や夜間の睡眠状態を客観的に評価してくれます。
眠気の強さや睡眠リズムの異常を医学的に数値化できる点が大きな特徴で、他の病気との鑑別診断にもつながります。
眠気が1か月以上続く場合はもちろん、社会生活に支障をきたしているなら早めに相談することが大切です。
精神科・精神神経科・神経内科
ナルコレプシーは睡眠障害であると同時に、精神的・神経的な側面とも深く関わる病気です。
そのため、精神科や精神神経科、神経内科でも相談が可能です。
特にうつ病や不安障害などの精神疾患と併発しているケースも多く、総合的に診てもらえる診療科の受診が望まれます。
また、病院によっては他の医療機関と連携し、検査や治療を組み合わせて進める体制をとっているところもあります。
「どこに行けばよいのかわからない」と迷うときは、まずかかりつけ医に相談し、専門外来への紹介状を依頼する方法も有効です。
相談のタイミング
ナルコレプシーは本人が「ただ眠いだけ」と思ってしまいがちな病気ですが、放置すると学業や仕事、社会生活に大きな影響を与えます。
症状が進んでからでは改善までに時間がかかるため、できるだけ早期に医療機関へ相談することが重要です。
また、ご家族が異変に気づいた場合も、本人に受診を促してあげるとよいでしょう。
周囲の理解と協力が、治療の第一歩となります。
医療機関を探す際のポイント
地域によっては専門外来が少なく、受診できる医療機関が限られている場合もあります。
そのようなときは、大学病院や大規模な総合病院の睡眠外来を探すのが一つの方法です。
また、精神科や神経内科であっても睡眠障害に詳しい医師が在籍している場合がありますので、事前にホームページなどで診療内容を確認するとよいでしょう。
受診時には症状を詳しく説明できるよう、睡眠日誌を記録して持参すると診断に役立ちます。
他の精神疾患と併発なら精神科訪問看護という選択肢

精神科訪問看護とは?
| サービス名 | 精神科訪問看護 |
|---|---|
| ケア内容 | ・日常生活の維持 ・生活技能の獲得 対人関係の維持など |
| 訪問日数 | 原則 週3日以内 |
精神科訪問看護とは、精神疾患をもつ方の自宅へ看護師や作業療法士などが直接訪問し、在宅での生活を支援するサービスです。
ナルコレプシーは単独でも生活に支障をきたす病気ですが、うつ病や不安障害など他の精神疾患と併発するケースも少なくありません。
そのため外来受診だけでは対応が難しい場合、自宅にいながら専門職による支援を受けられる精神科訪問看護は大きな助けとなります。
訪問時間は1回30分~90分程度で、体調に合わせた柔軟な対応が可能です。
精神科訪問看護のサポート内容
- 症状のコントロールや治療の相談
- 日常生活の援助
- 対人面の相談
- 気分転換の援助・健康管理
- 服薬管理状況確認、援助
- 家族の悩みや不安の解消
- 社会資源の活用援助
精神科訪問看護では、症状の安定を図るだけでなく、生活全般のサポートも行います。
例えば以下のような内容があります。
- 服薬の確認や副作用のチェック
- 生活リズムの調整や睡眠衛生の指導
- ストレス対処法や気分転換の支援
- 家族への相談・サポート
- 社会資源の活用支援(福祉サービスや制度利用の助言)
特にナルコレプシーの方は、服薬管理や睡眠リズムの安定が重要です。
訪問看護では、医師の指示のもと定期的に状態を観察し、必要に応じて関係機関と連携をとりながら支援を進めます。
「孤立を防ぎ、安心して生活できる環境をつくる」ことが精神科訪問看護の大きな役割です。
併発時のメリット
ナルコレプシーと精神疾患を併発している場合、本人や家族が抱える負担は大きくなります。
外来診療だけでは日常生活の細かい困りごとに対応しきれないことも多いため、訪問看護が加わることで安心感が増します。
また、自宅で療養できることで、病院に通うストレスを減らせる点もメリットです。
さらに訪問スタッフは、患者本人だけでなく家族の不安や悩みを聞き取り、共に支える存在として機能します。
精神科訪問看護は、病気の治療だけでなく「生活そのものを支える仕組み」です。
ナルコレプシーにより学校や職場に適応できず苦しんでいる方や、家族のサポートに限界を感じている方にとって、有効な選択肢となるでしょう。
精神科訪問看護ならシンプレ看護ステーションへ!

シンプレ訪問看護ステーションとは?
シンプレ訪問看護ステーションは、精神科に特化した訪問看護サービスを提供しています。
看護師・准看護師・作業療法士といった専門職員がご自宅を訪問し、主治医や地域の関係機関と連携しながら、安心して日常生活を送れるようサポートを行っています。「こころの病気に寄り添い、自宅で療養を続けながら社会復帰を目指す」ことをモットーに、患者さまやご家族の不安を軽減することを大切にしています。
対応できる内容は幅広く、服薬支援・再発予防・生活リズムの安定・家族へのサポートなど、利用者一人ひとりの状況に合わせた支援を提供しています。
ナルコレプシーの方にとっても、日常生活での困りごとや不安を解消する心強いサポートとなるでしょう。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレでは東京23区を中心に、西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・東久留米市、さらに埼玉県の一部地域まで幅広く対応しています。
記載エリア以外でも訪問できる場合があるため、まずはご相談ください。
祝日や土曜日も訪問可能で、週1回から最大で週3回まで、状況によっては週4回以上の訪問も行っています。
1回あたり30分~90分と柔軟に対応できるため、利用者の体調や生活リズムに合わせて支援を受けられます。
シンプレが選ばれる理由
シンプレ訪問看護ステーションが多くの方に選ばれる理由は、精神科に特化した専門性と柔軟な対応力にあります。
対象となる疾患はうつ病・統合失調症・発達障害・PTSD・双極性障害・不安障害・薬物依存症・アルコール依存症・パニック障害・ひきこもり・適応障害・強迫性障害・自閉スペクトラム症・認知症など幅広く、「こころの病気で困っている方が安心して相談できる拠点」となっています。
また、胃ろう・カテーテル交換・在宅酸素療法・緩和ケアといった医療的処置にも対応でき、医療保険や自立支援医療制度・心身障害者医療費助成制度・生活保護などの制度利用もサポートします。
地域に根ざした安心の支援体制を整えているのが大きな特徴です。
シンプレ訪問看護ステーションは「自宅での療養を支え、安心できる居場所を提供する存在」であり、ナルコレプシーに悩む方やご家族にとって強い味方となります。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

ナルコレプシーは10代~20代前半に多い
ナルコレプシーは思春期から青年期にかけて発症しやすく、特に10代後半から20代前半で多く見られます。
この時期は勉強や仕事、進路の選択など生活環境が大きく変化する時期であり、強い眠気を「ただの疲れ」と誤解してしまうことも少なくありません。
症状を早期に気づき、医療機関を受診することが生活の質を守る第一歩となります。
遺伝や生活習慣などが発症リスクに関与する
ナルコレプシーは遺伝的要因や自己免疫の関与、さらにストレスや生活習慣の乱れが重なり発症すると考えられています。
特に日本人は有病率が高いとされ、600人に1人程度の割合で発症するとの報告もあります。
家族に患者がいる場合は発症リスクが高まるため、日中の眠気や突然の居眠りが見られる場合は注意が必要です。
「眠気が強い=怠け」ではなく、医学的に解明されつつある病気であることを正しく理解することが重要です。
早期の受診と正しい理解が大切
ナルコレプシーは、放置すると学業や仕事に支障をきたし、退職や離職を余儀なくされることもあります。
検査には睡眠ポリグラフ検査や反復睡眠潜時検査などが用いられ、客観的に診断することが可能です。
眠気の症状が長く続く場合や社会生活に影響を与えている場合は、できるだけ早めに専門医に相談しましょう。
また、他の精神疾患を併発している場合には、精神科訪問看護という在宅でのサポートも有効です。
シンプレ訪問看護ステーションでは、専門職員が定期的に訪問し、服薬支援や生活支援を通じて患者と家族をサポートしています。
地域に根ざした支援体制により、自宅で安心して療養できる環境が整っています。
ナルコレプシーは本人も周囲も気づきにくい病気ですが、適切な理解と支援があれば日常生活を大きく改善できます。
症状に悩んでいる方は一人で抱え込まず、医療機関や専門のサポートに相談してみてください。
ご相談の問い合わせはこちら▼

菅原クリニック東京脳ドック
医師:伊藤たえ
脳神経外科医20年、頭痛患者さんでうつや不安障害をお持ちの方も多く対応しております。所属:日本脳神経外科学会、日本脳卒中学会、日本脳ドック学会、日本認知症学会
監修日:2025年11月5日
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (2)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



