PTSDのカウンセリングとは?効果的な心理療法と回復のステップを徹底解説|シンプレ訪問看護
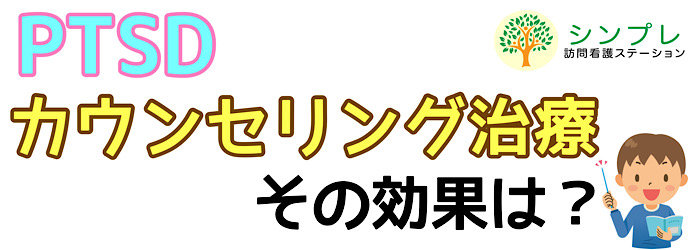
PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、過去のつらい体験やトラウマがきっかけとなって心身に影響が続く状態です。回復に向けては、専門的なptsdのカウンセリングを受け、段階的に安全の確保・感情の整理・日常の再構築を進めていくことが重要です。この記事では、ptsdのカウンセリングの進め方や代表的な心理療法、受診や相談の窓口についてわかりやすく解説します。「いまのつらさはケアできる」——その一歩を一緒に整理していきましょう。
PTSDで行われるカウンセリングの3つの段階

身体的・心理的な安全をまず確保する
PTSDのカウンセリングでは、何よりも先に「安全」を整えることが土台になります。安全が十分でない状況で過去の出来事に触れると、症状が強まって逆効果となるおそれがあるためです。身体的安全とは、面接を行う場所が落ち着いて話せる環境であることや、外的な危険から守られていること。心理的安全とは、評価や批判の心配なく、感じていることをそのまま言葉にできる関係性が保たれていることを指します。初期段階では、呼吸法やグラウンディングなどのセルフケアを学び、睡眠・食事・生活リズムを整えながら、「いま・ここ」で安心を感じられる時間を少しずつ増やしていきます。こうした準備ができると、ptsdのカウンセリングの次のステップに進みやすくなります。
責任の所在を変革し罪悪感を軽減する
多くの当事者は、「自分のせいだったのではないか」と過度に自責しがちです。第二段階では出来事の因果と責任の所在を丁寧に整理し、根拠のない罪悪感や恥の感情を軽くしていきます。起きた出来事の背景(環境・加害要因・不可抗力など)を一緒に検討し、一方的な認知に気づくことが目的です。「あの時の自分にできる最善は尽くしていた」「責任は本来どこにあるのか」という視点を取り戻すことは、自己攻撃を弱め、回復へのエネルギーを確保するうえで重要です。カウンセリングでは言語化に加え、身体感覚に注目したワークを用いて、罪悪感や無力感との距離をとる練習も行います。
自分の力で危険を回避できるという自信の回復
第三段階では、「私は危険を見分け、援助を求め、必要なときに距離を取れる」という実感(対処可能感)を回復させます。トラウマの影響で「自分には何もできない」という感覚が強まっていると、日常の場面でも過度に警戒したり、逆に感覚が麻痺してしまうことがあります。ここでは、境界線の引き方、SOSの出し方、トリガーへの対処(例:段階的な暴露やマインドフル呼吸)などを具体的に身につけ、成功体験を積み重ねます。小さな達成が重なるほど自己効力感は育ち、フラッシュバックや悪夢が起きても「対処できる」という見通しが持てるようになります。こうして安全・自責の修正・対処可能感の三つがそろうことで、生活の再構築が現実味を帯びてきます。
PTSDに効果的な心理療法の技法
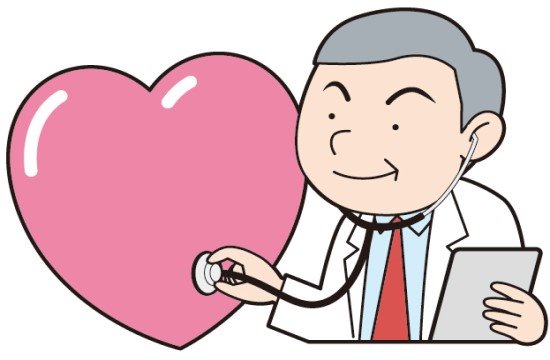
EMDR(眼球運動による脱感作と再処理法)
EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)は、トラウマ記憶に関連する苦痛を軽減するための心理療法で、ptsdのカウンセリングの中でも効果が科学的に認められている方法です。セラピストの指の動きを目で追う「両側性刺激」によって、脳内で過去の記憶が再処理され、感情の強度が和らぎます。通常の会話療法だけでは届きにくい身体的反応や無意識的な恐怖にも作用する点が特徴です。EMDRは、体験の再現ではなく「安全な環境下での再体験」を通して、心がもつ自然な治癒力を引き出すプロセス。記憶そのものを消すのではなく、「思い出しても動揺しない状態」に近づけることを目的としています。トラウマを心の中で整理する力を取り戻すことが、回復への第一歩になります。
PE(持続的エクスポージャー療法)
PE(Prolonged Exposure Therapy)は、「恐怖や回避への慣れ」を目的とした行動療法の一つです。トラウマ体験を避け続けることで恐怖が強化されてしまうという悪循環を断ち切り、安全な場で少しずつ記憶に触れながら感情を処理していきます。セラピストと一緒に、当時の出来事や関連する状況を丁寧に思い出し、それに伴う身体反応や思考を観察することで、「思い出しても現実の危険はない」と脳に再学習させることが目的です。PEを行う際には、リラクゼーション法や段階的な暴露計画を併用し、無理のないペースで進めます。こうした治療過程を通じて、恐怖の感覚が薄れ、自分自身で感情をコントロールできるようになるのです。怖くても向き合える自分を再発見することが、ptsdのカウンセリングの大きな成果のひとつといえるでしょう。
PTSDとはどんな疾患?

PTSDを発症しやすい原因とは
・生命に関わるような重大事故
・同乗者が死亡した場合 など
犯罪被害
・性暴力
・ストーカー被害 など
虐待被害
・身体外傷
・性的虐待 など
大規模災害の被災者
大規模震災など
対人援助職
職責に伴う罪責感 など
PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、生命や尊厳が脅かされるような強いショック体験をきっかけに生じる心の反応です。交通事故・災害・暴力・いじめ・性被害・突然の喪失など、体験の種類は多様です。「自分の身に起きたことが信じられない」「あの瞬間の映像が頭から離れない」などの反応は自然な防御反応ですが、時間が経っても苦痛が続く場合にPTSDとして診断されます。発症しやすさには、トラウマの強度だけでなく、その後のサポート体制や本人の気質・環境も関係します。早期の支援と安全なカウンセリング環境が、症状を悪化させずに回復へつなげる鍵となります。
代表的なPTSDの症状
突然つらい記憶がよみがえる
回避・精神麻痺症状
・記憶を呼び起こす状況や場面を避ける
・感覚が麻痺する
過覚醒症状
・常に神経が張りつめている
・睡眠障害 など
PTSDの症状は大きく「再体験」「回避」「過覚醒」「否定的認知・気分の変化」の4つに分けられます。「再体験症状」とは、フラッシュバックや悪夢のように、過去の記憶が突然よみがえる状態。回避は、トラウマを思い出す人・場所・話題を無意識に避ける行動を指します。過覚醒は、眠れない・音に敏感・常に緊張しているなど、神経が張りつめた状態が続くこと。そして否定的認知では、「自分が悪い」「世界は危険だ」といった極端な考え方に陥りがちです。これらが長期化すると、仕事や人間関係にも支障が出ることがあります。ptsdのカウンセリングでは、これらの症状を「心の反応」として理解し、自己否定ではなくケアの対象として扱うことが重視されます。
PTSDと合併しやすい精神疾患
PTSDは単独で現れることもありますが、うつ病・不安障害・パニック障害・依存症などを併発するケースも多く見られます。トラウマによる孤立感や無力感が強まることで、抑うつ症状や意欲低下が生じることがあるためです。また、睡眠障害や慢性的な身体のこわばり、頭痛などの身体症状が出る人も少なくありません。これらが重なり合うと「心も体も休まらない」状態に陥りやすく、回復を難しくします。そのため、ptsdのカウンセリングだけでなく、薬物療法や訪問支援などを組み合わせた総合的なケアが有効です。精神科訪問看護などの専門職による支援を受けることで、症状の安定化や生活リズムの再構築が進みやすくなります。
PTSDの診断基準をチェック

外傷的出来事の体験があること
PTSDの診断では、まず「外傷的出来事(トラウマ体験)」を実際に体験した、もしくは目撃したことが前提となります。ここで言うトラウマとは、生命の危険や重大な暴力・事故・災害など、極度の恐怖や無力感を伴う出来事を指します。体験の衝撃があまりに強いと、脳がその記憶を通常の方法で処理できず、断片的に保存されることがあります。その結果、フラッシュバックや夢の中で何度も再現されるなどの反応が現れるのです。ptsdのカウンセリングでは、過去の出来事を無理に思い出すことを目的とせず、「いまの心身にどんな影響が残っているか」を安全に確認しながら進めていきます。
PTSDに関連する症状が出現していること
次に、再体験・回避・過覚醒・否定的思考など、PTSD特有の症状が出現しているかどうかが診断の基準となります。これらの症状は日常生活の中で突然現れ、本人がコントロールできない形で苦痛をもたらします。例えば「何もないのにドキドキする」「音に過敏に反応する」「特定の場所を避けてしまう」などが典型的です。診断の際には、症状の持続期間や強さを丁寧に確認することが求められます。信頼できる医療機関やカウンセラーに相談することで、正しい評価と適切な治療計画が立てられます。
症状が1カ月以上続き日常生活に支障があること
最後の基準は、これらの症状が少なくとも1カ月以上続いており、仕事・学業・家庭生活などに支障をきたしているかどうかです。短期間の強いストレス反応は「急性ストレス障害(ASD)」と呼ばれ、自然に回復する場合もありますが、1カ月を過ぎても苦痛が続く場合はPTSDの可能性が高まります。診断は自己判断では難しく、医師の面談や心理検査によって総合的に評価されます。ptsdのカウンセリングでは、診断を受けた後も「症状と上手につきあう方法」や「再発予防のセルフケア」を身につけていく支援が行われます。早期に正しい診断を受けることが、回復への第一歩となるのです。
PTSDについて相談できる窓口一覧

・保健センター
・精神保健福祉センター
電話専門窓口
・よりそいホットライン
・こころの健康相談統一ダイヤル
SNS相談窓口
・こころのほっとチャット
・生きづらびっと
医療機関(精神科・心療内科)
PTSDの症状が続く場合、まず相談すべきは精神科や心療内科などの医療機関です。専門の医師が診察を行い、症状の種類や強さに応じて治療方針を立ててくれます。薬物療法と並行して、ptsdのカウンセリングや心理療法を受けることも可能です。初診時には、眠れない・思い出すと動悸がする・人混みを避けてしまうなど、自覚している症状をメモして持参するとスムーズです。また、女性専用外来やトラウマ専門外来を設けている医療機関も増えており、性被害・虐待などの体験をより安心して相談できます。診察に不安がある場合は、まず地域の精神保健センターに相談して紹介を受けるのもよいでしょう。
地域の相談窓口や支援センター
各自治体には、PTSDを含むメンタルヘルスに関する相談を受け付ける窓口があります。たとえば、保健センター・精神保健福祉センター・女性相談センターなどです。これらの機関では、カウンセラーや保健師が無料で相談に応じ、必要に応じて医療機関や福祉サービスへとつないでくれます。特にトラウマ体験後は「どこに助けを求めればいいかわからない」と感じることが多いため、最初の一歩としてこうした公的窓口を利用するのが安心です。一人で抱え込まず、信頼できる支援につながることが回復の第一歩です。窓口では匿名で相談できるケースも多く、誰にも知られずに話をすることも可能です。
専門の電話・SNS相談
最近では、電話やSNSを使ったPTSD専用の相談サービスも整備されています。緊張して面談が難しい人や、外出がつらい人でも自宅から気軽に利用できます。全国の「いのちの電話」や「こころの健康相談統一ダイヤル」では、専門の相談員が24時間体制で対応しており、急な不安やフラッシュバックに悩んだときにも支えとなります。SNS相談ではLINEなどのチャット形式でやりとりができ、言葉にしづらい思いもゆっくり整理できます。こうしたオンライン支援は、話すことが怖い人にとって大切な架け橋となる存在です。ptsdのカウンセリングを受ける前段階としても、安心して心の準備ができるサポートといえるでしょう。
PTSDのケアを行う精神科訪問看護とは?

精神科訪問看護
職種
・看護師
・准看護師
・作業療法士
訪問日数
原則週3日以内
精神科訪問看護の内容と役割
PTSDの治療や回復をサポートする手段のひとつに、精神科訪問看護があります。これは看護師などの医療専門職が自宅を訪問し、心身の状態を観察・支援するサービスです。ptsdのカウンセリングを病院やクリニックで受けている方にとって、訪問看護は「日常生活での安定を保つための支え」となります。たとえば、服薬のサポート・睡眠や食事リズムの確認・不安や緊張が高まったときの呼吸法練習などが含まれます。訪問看護の目的は「症状のコントロールと生活の再構築」であり、通院だけではカバーしきれない部分を補う役割を果たします。訪問中は、対話を通じて孤独感をやわらげ、再発防止や社会復帰を見据えた支援も行います。
カウンセリングと併用できるサポート
精神科訪問看護は、カウンセリングと並行して行うことでより高い効果が期待できます。たとえば、カウンセリングで学んだストレス対処法やセルフケアの練習を、訪問看護師が自宅で一緒に振り返り、実生活に落とし込むことができます。また、外出や人との接触に不安がある場合、訪問看護が「安心して練習できる環境」をつくるサポートにもなります。トラウマ体験によって引きこもりがちになっている方や、再発への不安を抱える方にとっては、定期的に専門職が関わることで「誰かが見守ってくれている」という安心感が生まれます。さらに、家族への説明や相談にも対応し、再発防止のための支援体制を一緒に整えることが可能です。ptsdのカウンセリングを受けている方が、安定した日常生活を取り戻すうえで、訪問看護は心強い伴走者となるでしょう。
PTSDの治療サポートなら当ステーションへおまかせ!

シンプレ訪問看護ステーションとは?
シンプレ訪問看護ステーションは、PTSDやうつ病、統合失調症、発達障害など、幅広い精神疾患を対象とした訪問看護サービスを行っています。当ステーションには看護師・准看護師・作業療法士が在籍し、一人ひとりの心と生活に寄り添った支援を提供しています。PTSDの方には、医療機関でのptsdのカウンセリングや心理療法と並行して、安心できる在宅環境を整えるお手伝いをします。訪問は週1〜3回(必要に応じて週4回以上も可)、1回あたり30〜90分と柔軟に対応。病院だけでは支えきれない時間を、あなたの生活の中で支えることを大切にしています。祝日や土曜日も訪問を行っているため、ライフスタイルに合わせて無理なく利用できます。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
当ステーションの対応エリアは、東京23区を中心に、西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・東久留米市、さらに埼玉県の一部地域にも訪問可能です。近隣の市区町村にお住まいの方も、訪問が可能な場合がありますのでお気軽にご相談ください。「自宅でも安心して心のケアを受けたい」という方に、最適なサポート体制を整えています。
また、PTSDをはじめとする精神疾患の方は、自立支援医療制度(精神通院)や心身障害者医療費助成制度、生活保護など、各種医療制度を利用して訪問看護を受けることができます。介護保険をお持ちの方でも、精神科訪問看護は医療保険が適用となるため、安心してご利用いただけます。ptsdのカウンセリングで心の整理を進めつつ、訪問看護で生活を安定させることで、より持続的な回復が期待できます。シンプレは「退院後の支援」「再発予防」「服薬管理」「家族支援」など、トータルな支援を通して、心の回復をチームで支えます。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ|PTSDのカウンセリングで心の回復を目指そう

PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、過去の強いストレス体験が心に深い影響を残す疾患ですが、早期に適切な支援を受けることで回復が十分に可能です。ptsdのカウンセリングでは、安全の確保・感情の整理・再発防止という3段階を通して、心のバランスを少しずつ取り戻していきます。心理療法の技法であるEMDRやPE(持続的エクスポージャー療法)は、トラウマに直接働きかける科学的根拠のある方法で、専門家のサポートのもとで行うことで効果を発揮します。
また、PTSDは単なる「心の問題」ではなく、身体的な反応や生活への影響も大きいため、カウンセリングだけでなく生活支援も欠かせません。精神科訪問看護などの地域支援を併用することで、安心して回復を続ける環境が整います。訪問看護師が定期的に関わることで、薬の管理や生活リズムの調整、再発予防など、日常に寄り添った支援が可能になります。
さらに、PTSDの方は孤立しやすく、「誰にも話せない」「助けを求めにくい」という思いを抱えることが多いものです。そんなときは医療機関や地域の相談窓口、SNS相談などを積極的に活用し、ひとりで抱え込まないことが大切です。「助けを求めることは弱さではなく、回復への勇気」です。あなたの体験はあなたのせいではありません。今感じている苦しみは、適切な支援の中で少しずつ和らいでいきます。
シンプレ訪問看護ステーションでは、PTSDやうつ病などの精神疾患に対して、訪問によるきめ細やかなサポートを行っています。ご自宅での療養や社会復帰を目指す方の力になれるよう、医療・心理・生活の面から総合的に支援しています。ptsdのカウンセリングを受けながら、日常生活の安定を取り戻したい方は、どうぞお気軽にご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (5)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



