ADHDの治療にはどんなものがある?検査方法や診断基準についても解説。
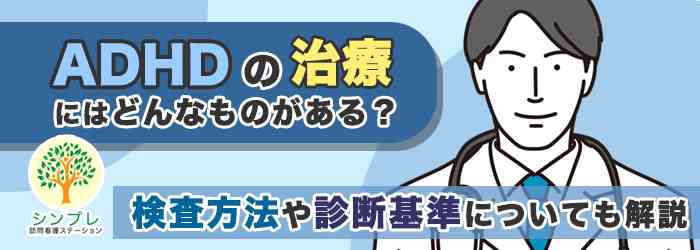
ADHDは先天的な疾患です。脳に何らかの障害があると考えられ、風邪のように完治することはありません。生涯を共にし上手く付き合わなければなりません。
そんなADHDですが、一体どのような治療方法があるのでしょうか。また疾患者の両親や知人は治療を手助けすることはできないのでしょうか。
今回はADHDの治療方法と、周囲の方々ができることについて紹介します。
ADHDの治療方法について

そもそもADHDとは何か
ADHDとは、発達障害のひとつです。ADHDは、注意欠陥多動性障害の略称で、注意の持続が難しいことや動きを抑えることが難しいのが特徴です。
生活では、落ち着きがなく、行動せずにいることが難しく、衝動的な行動をとることがあります。また、忘れ物が多く、待てなかったりすることもあります。
忘れ物が多かったり待てなかったりすることもあるようです。こういった特徴的な症状から、日常生活や学校生活でなんらかの問題が生じている場合に診断されます。
12歳以前からこれらの症状が続いていて、学校や家庭などで困る場所が複数になっている場合に診断されます。
ADHDの治療方法
- 心理社会的治療
- 薬物療法
ADHDの治療は、心理社会的治療と薬物療法が二つの柱になります。心理社会的治療には患者さん自身に対するものと、両親などの養育者に対するものがあります。
とくに小さな子どもさんが患者の場合には、子どもの生活環境を整えるために両親が勉強をすることがあります。これを、ペアレント・トレーニングといいます。
患者さんが大人の場合には、感情のコントロールの仕方や日常生活上の困りごとなどの相談にのるかたちで心理社会的治療がおこなわれることもあります。
心理社会的治療を受けたうえでも、日常生活での困難が多い場合には、薬物療法があわせて行われます。
治療方法の詳細
以下、具体的に治療方法の詳細について整理します。
①心理社会的治療
患者にとって過ごしやすい環境を作る
行動療法
・行動対応を改善
・行動のフィードバック
ソーシャルスキル・トレーニング(SST)
社会生活の過ごし方を学ぶ
心理社会的治療は、ADHDの患者さんにとって、大切な治療になります。ADHDの治療で、一番はじめにこころみられる治療です。
上記のような、生活上の関わりのポイントを取得することを、心理社会的治療で行います。集中できる環境を整えたり、患者さん自身の行動や考え方の特徴を学んだりします。
②投薬治療
ADHDの不注意や多動性を改善する薬
②アトモキセチン
ADHDの不注意、多動性、衝動性の改善が期待できる
③グアンファシン
交感神経の過剰な興奮を抑える
ADHDの症状を改善するためには、薬物療法も有効です。生活に困難がある場合は、医師と相談して薬物療法を検討しましょう。
薬剤は複数種類あり、効果の強さや持続時間が異なります。主治医と相談しながら、自分に合った薬剤を選ぶようにしましょう。
検査・診察で治療方法を決定する

問診表をもとに医師の診察
診察では、問診表の記入内容が参考にされます。クリニックによっては、発達障害専用の問診表があるでしょう。
現在困っていることを記入することや子ども時代などのことについての質問のある基本的な問診表の記入が参考にされます。
さらに、さまざまな種類のチェックリストがあり、その中の数種類を問診として記入することが多いです。
大人のADHDの問診では、「成人期のADHDの自己記入式チェックリスト」が使われる場合もあります。
評価基準はDSM-5
ADHDは、DSM-5という診断基準に当てはめて診断します。
注意力や集中力が続かない、気が散りやすい、順序だてて活動に取り組めないなどの不注意型の症状が現れているかや、じっとしていられない、静かに遊べない、待つことが苦手で他人のじゃまをしてしまうなどの多動性・衝動性の症状を確認します。
そのほかにも不注意型と多動性・衝動性型の両方の症状が現れているかを確認し、診断していきます。
医師の診察や心理検査などによって行われ、DSM-5の診断基準を満たした場合に下されます。ご自身やご家族がADHDの症状に当てはまるようでしたら、専門機関に相談することをおすすめします。
そのほかの検査方法
脳波が独特かどうかを診断
知能検査
知的障害特有のIQの低下があるかを診断
血液検査
甲状線機能亢進症などの病気かどうかを診断
頭部画像検査
MRIを用い脳の状態を診断
ADHDや他の精神疾患は、身体的な原因や他の疾患ではないか確認する必要があります。そのため、脳波や採血、頭部MRIなどの検査が行われます。
他の疾患の可能性がないかどうかの確認に、てんかんや甲状腺機能の異常がないかや、てんかんは、脳波やMRIの検査によって脳の組織や構造に異常がないか検査します。
甲状腺機能は、採血検査が行われます。また、発達障害の他の障害や知的障害がないか、IQ検査が行われることもあります。
両親・知人の方々も治療を助けられる

お子さんの治療の場合には、養育者である両親も心理社会的治療の指導をうけることができます。
まずADHDをポジティブに考える
ADHDの特徴は、周囲の人から理解を得にくい行動な場合が多いです。しかし、ポジティブにとらえなおすことで患者さんの長所として理解することができます。
例えば、「おしゃべりが多く、さわがしい」という特徴が、「積極的にコミュニケーションがとれる」という長所につながります。
こうした長所をいかして生活していくことが、患者さんの生活をよりよくする事が考えられます。
こういったとらえなおしを患者さん自身も実感できるように関わることが大切です。結果的に、自己肯定感や安心感につながります。
両親・知人の方ができること
周りの方はどのように接したらよいか悩んでしまうこともあるでしょう。ADHDのお子さんへの接し方について紹介します。
ADHDを理解する
ADHDの障害のせいで、小さな子どものころから、周囲から注意されたりすることが多い特徴があります。患者さんと第三者の関係が悪い状態になりやすいといえます。
このために、ADHDの障害があると、自己肯定感が育ちにくい傾向があるようです。障害の特徴を理解することでこういった悪循環におちいらずにすみます。
疾患者が過ごしやすい環境を作る
ADHDの障害があっても、集中するための工夫をすることができます。目標をスモールステップで設定することも有効です。
スモールステップな目標を達成することで自信をつけることもできます。学習においても、達成できるレベルでの内容や量を工夫することも有効です。
疾患者は何ができるかを考える
ADHDの障害を持っていても、得意なことや長所をいかす方法を中心に考えることが大切です。できることに目を向けていくという事です。
強みをいかして生活したり、活動したりすることで、患者さん自身の自己肯定感や自信獲得につながります。
支援を受けられるサービス(お子さんの場合)

児童発達支援センター
地域で暮らす、障害を持つ子どもやその保護者に対する支援を行う地域の中核的な療育施設です。ここで言う支援とは、実際的な援助や助言のようなことになります。
障害をもつ子どもや療育者への支援を行います。また、中核施設として、一般の事業所施設への助言なども行っています。
対象となる障害は、知的障害、身体障害、発達障害の3つの障害です。児童発達支援センターで対応が難しい場合には、他施設とも連携していくことになります。
児童発達支援事業
- 児童発達支援
- 放課後デイサービス
児童発達支援事業には、さまざまなサービスがあります。児童発達支援を行う療育や放課後デイサービスなどです。
児童発達支援は、就学前の子どもを対象としたサービスです。子どもが自立して生活できるように、必要なスキルを身につけることを目的としています。
放課後デイサービスは、就学中の子どもを対象としたサービスです。学校が終わった放課後や、夏休みなどの長期休暇の期間中、通所で療育などの支援を受けることができます。
運動療法に特化していたり、人間関係の練習に力をいれていたり、それぞれの事業所に特徴があります。
支援を受けられるサービス(大人の場合)

就労支援サービス
就労支援サービスとは、障害のある人が働き続けられるように支援するサービスです。
一般的な職場で働くのが難しい場合、就労継続支援を受けることができます。
就労継続支援には、雇用契約を結ぶ「就労継続支援A型」と、雇用契約を結ばない「就労継続支援B型」があります。
どちらのサービスも、就職や職場定着に向けたサポートを受けることができます。
グループホーム
精神疾患をお持ちの方社会生活を支える支援の一つとして、グループホームの活用がされています。
グループホームとは、障害のある人が共同生活をしながら、自立した生活を送れるように支援する施設です。
グループホームには、さまざまな種類があり、入居者の状況や希望に合わせて選ぶことができます。
施設によっては、ある程度自立した生活ができて長く住むことを希望する場合は、そのまま住み続けることもできます。
精神科訪問看護を利用するという選択肢も

精神科訪問看護のサービス内容
- 日常生活の維持
- 生活技能の獲得・拡大
- 対人関係の維持・構築
- 家族関係の調整
- 精神症状の悪化や増悪を防ぐ
- ケアの連携
- 社会資源の活用
- 対象者のエンパワーメント
精神科訪問看護は、精神科疾患のある患者さんのお宅に看護師などが訪問して、支援するサービスです。
主治医が、訪問看護が必要と判断した場合に、介護保険や医療保険で行われます。薬の内服の確認や管理のお手伝いができます。
また、体の調子についても、バイタルサイン測定をすることで、異常がないか確認することができます。
精神科の疾患があっても、日常生活を安心して過ごせるように看護師などが精神的支援も行います。日常生活のなかでの、リハビリテーションを行うこともできます。
精神科訪問看護の料金
| 負担割合 | 月の初回訪問 | 2回目以降 |
|---|---|---|
1割負担 | 1,299円/回 | 855円/回 |
2割負担 | 2,598円/回 | 1,710円/回 |
3割負担 | 3,897円/回 | 2,565円/回 |
上記は週3回までの訪問料金となります。週4回以上訪問となる場合には料金が異なります。
精神科訪問看護では、医療保険を利用することにより自己負担を軽減できるメリットがあります。
30分を一区切りに利用可能。かかった費用については、年齢や所得によって変わり、医療費の1〜3割が自己負担となります。
また早朝や深夜などの時間外に依頼する場合や、長時間の訪問を行う場合は別途料金が発生します。
また自立支援医療制度いう制度を利用すると料金が1割負担になるほか、所得に応じて自己負担が0円になる場合もございます。
自立支援医療制度(精神通院)
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 生活保護 |
0円 |
| 低所得1 |
2,500円 |
| 低所得2 |
5,000円 |
| 中間所得1 |
5,000円 |
| 中間所得2 |
10,000円 |
| 一定所得以上 |
20,000円 |
表の料金は所得に応じた医療費の月額自己負担額の上限額となっております。
表の料金を超えた場合には、自己負担なしで医療が受けられます。
自立支援医療制度は、障害があっても自立した生活が送れるように治療にかかる費用を一部国が負担する制度です。
精神障害も自立支援医療制度の対象になっています。定期的に精神科病院やクリニックに通院している場合には、通院費が自立支援医療の対象になります。
そのほか、薬代や訪問看護にかかる費用、デイサービスの費用も同様に自立支援医療の対象になります。
収入により、医療費の補助額がかわります。
ADHDの治療でお悩みならシンプレへご相談を

当ステーションの特徴
ADHDの治療中で、精神科病院への通院をされている方には、主治医の指示のもと精神科訪問看護を行っています。
シンプレ訪問看護ステーションは、精神科疾患の看護に特化した訪問看護ステーションです。
シンプレ訪問看護ステーションは、利用者さんの自主性を大切に、看護師や作業療法士が在宅生活を支援します。
主治医や通院先のソーシャルワーカーなどの支援者とも連携して、患者さんの在宅生活がよりよいかたちで継続できるように支援します。
対象となる精神疾患
- ADHD
- 自閉症スペクトラム症
- アルコール依存症
- うつ病
- パーソナリティー障害
- 統合失調症
- その他精神疾患全般
精神科訪問看護では、さまざまな精神疾患に対応しています。ADHDの障害のある方の対応も可能です。
また、うつ病などでADHDの二次障害に苦しんでいる方、自閉スペクトラム症などの発達障害を併せ持っている方についても対応可能です。
患者さん本人の支援はもちろんのこと、他の支援者との連絡調整などの連携についても患者さんが地域で暮らしやすいように協力することがあります。
ADHDの障害以外でも、精神疾患全般の患者さんの支援を行っています。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応地域はおもに上記が中心で、訪問活動をおこなっています。該当エリアにお住まいの方はぜひご検討ください。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。電話やメールなどで相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

今回は、ADHDの治療について、生活上の注意すべきポイントなどをまとめました。ADHDの治療で心理社会的治療を行うことが大切ということについてもふれました。
シンプレ訪問看護ステーションでも、ADHDの治療を行っている患者さんの対応が可能です。在宅生活のなかで、精神的な支援を行っています。
ADHDの治療中でお困りの方、大切なお身内がADHDの治療中で支援を必要としている場合など、ぜひシンプレ訪問看護ステーションにも、ご相談ください。
主治医や地域の支援者と連携し、利用者さんの主体性を大切に支援します。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



