【摂食障害の症状】過食・拒食の原因やなりやすい人について解説
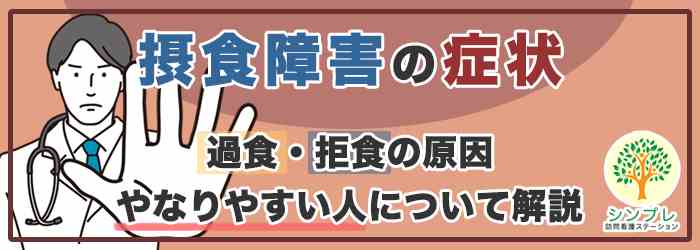
摂食障害の主な症状は際限なく食べ続けてしまう「過食症」と食べることを拒む「拒食症」の二つがあります。
今回この記事では、症状の解説や、原因やサイン、かかりやすい人の特徴についてまとめました。
心当たりのある方、症状に苦しんでいる方はひとりで抱え込まず、まずは相談をしてみることが大切です。
摂食障害の症状は大きく二つに分けられる

神経性無食欲症(拒食症)の症状
まずは、拒食症の症状についてご紹介します。
身体的
- 体重減少
- 無月経
- 血液検査で異常が見られる
拒食症は、体重が増えることを恐れ、極端な食事制限や過度な運動などによって、低体重を維持しようとする病気です。
拒食症には、上記の身体的な症状があります。脳内・卵巣などのホルモンバランスが乱れ、無月経や血液の異常がみられます。
精神的
摂食障害の人は、痩せたいという強い願望があり、太ることに対して恐怖を感じています。また、自分の体型が太っているように見えて、実際の体型と認識にズレがあります。さらに、自分が病気だと自覚していないことも多く、過度な活動をしたり、食事へのこだわりを持ったりすることがあります。
神経性大食症(過食症)の症状
続いて、過食症の症状についてご紹介します。
身体的
- 吐きダコ
- 虫歯
- 無月経
過食症の症状は、自分の体型に強いこだわりがあり、太ることを恐れて、大量の食物を短時間で食べてしまうことがあります。このことを「むちゃ食い」と呼びます。
むちゃ食いは、意志の力で止められるはずだと思われがちですが、自分では止めることができず、コントロールできない感覚が強い場合がほとんどです。また、むちゃ食いをした後には、吐く、下剤を使うなど、体重を増やさないための行動が見られることもあります。
精神的
過食症の人は、自分の体型などによるこだわりがから、太ることを恐れています。
そのため、体重が増えると、自分を価値のない人間だと思ったり、自信を失ったりしてしまいます。また、完璧主義な傾向があり、少しでも体重が増えると、自分を責めてしまうことがあります。
そのほか特定不能の摂食障害
摂食障害とは、食事や体重に対する異常な考えや行動によって、健康を害する病気です。排出障害は、摂食障害の一種で、食事を吐き出すことによって体重を減らすことを目的とする病気です。
排出障害には、食事を噛み砕いた後に吐き出す「噛み吐き」という行為があります。噛み吐きをする人は、食事を吐き出すことで体重を減らすことを目的としています。
こんな人が摂食障害になりやすい

摂食障害は、とくに若い女性がなりやすいのが特徴です。
摂食障害は、周囲からの強い期待やプレッシャー、家庭や学校での人間関係のトラブルなどによって引き起こされることが多いです。
また、摂食障害の方は、自分を責めたり、周囲に相談するのが苦手だったりする傾向があります。そのため、症状が悪化するまで受診をためらうことが多いです。
摂食障害は、早期に発見して適切な治療を受けることで、回復する可能性が高い病気です。しかし、無理に我慢してしまうこともあるため、長期的な治療が必要なケースもあります。
摂食障害は、病気だと自覚していない人も少なくありません。もし、摂食障害の疑いがある場合は、一人で悩まずに専門医に相談するようにしましょう。
摂食障害の原因と患者数

原因
上記でもご紹介したように、摂食障害の主な原因は環境・人間関係からくる強いストレスがあります。
また、ご本人の性格から「自分が甘えているから?」「なかなか人に相談できない」「ただの大食い?」などと考え、すぐに受診しないのも特徴のひとつであり、症状が悪化してから受診するのがほとんどです。
摂食障害は早期の治療が大切ですが、上記のように無理に我慢してしまうことがあるため、長期的な治療が必要なケースが多くあります。
周囲の方から見た摂食障害の前兆サイン
体重が急激に減少したり、体重の増減が激しかったり、食事や体型に過度なこだわりがある場合は、摂食障害の前兆サインです。
また、トイレに行く回数が増えたり、トイレや風呂で嘔吐物の臭いがしたりする場合も要注意です。
摂食障害は、本人が自覚していないことも多く、周囲の人が気づいたときにはすでに重症化している場合もあります。そのため、身体的に明らかに重症と思われる場合は、本人に病院を受診するよう働きかける必要があります。
本人が受診を拒否することも考えられますが、そういった場合は家族の中だけや、一人で悩まずに専門医や専門機関に相談するようにしましょう。
摂食障害の患者数
摂食障害、いわゆる拒食症・過食症は、多くは若い女性がかかる病気であり、国内の患者数は約22万人と推定されています。
とくに14歳から18歳に起きやすい症状で、女性の発症率は男性の約10〜20倍にものぼります。
また死亡率が約5%と報告されており、精神疾患の中ではとくに高い数値であり、摂食障害の対する専門性の高い病院・施設がかぎられていることが背景にあります。
摂食障害の方がかかりやすい二次障害

不安障害
- 些細なことに不安や恐怖を感じ日常生活に支障がでる
- イライラや恐怖で夜よく眠れない
摂食障害の方は、他の精神疾患を併発することがあり、を併発しやすい病気のひとつに不安障害が挙げられます。
不安障害は、人前で極度の緊張や恐怖などを感じる病気であり、緊張などを和らげるためにアルコールへの依存が高くなる症状があります。
摂食障害の方が併発して、アルコール乱用・依存症があると治療が非常に難しくなり、「摂食障害にアルコール依存が関係すると、治療が一番難しい」という医師もいるほどです。
うつ病
- 気分の落ち込みや意欲の低下
- 体のだるさや痛み
摂食障害は、食行動の異常を特徴とする精神疾患です。その背景には、自分に自信が持てず自己否定が強い傾向があり、うつ病を併発することが多いのです。
摂食障害の症状には、抑うつ状態、意欲の低下、気分の落ち込み、食欲の低下、体重減少などが含まれます。
併発して重症化してしまう前に、専門の医療機関に受診し対処する必要があります。
低アルブミン血症
- むくみが起こりやすくなル
- 体の調整機能や免疫の低下
神経性無食欲症の方は、極端な食事制限や過度な運動などにより、体重が著しく減少します。その結果、血液中のタンパク質であるアルブミンの量が低下し、低アルブミン血症と呼ばれる状態になります。
アルブミンは、血液中の水分を保持する役割を担っています。そのため、低アルブミン血症になると、血液中の水分が組織に流れ込み、むくみを引き起こします。
むくみは、主に顔、手足、脚などに現れます。また、低アルブミン血症は、ホルモンバランスの乱れを引き起こし、無月経や月経不順などの症状を引き起こすこともあります。
症状に悩んでいる方は無理せず相談を

- 精神科・心療内科
- 電話相談「相談ほっとライン」
- 精神保健福祉センター
- 摂食障害支援拠点病院
摂食障害でお悩みの方の問い合わせ窓口として、精神科・診療内科の他にも、電話相談ができる「よりそいホットライン」や幅広い相談に対応している「精神保健福祉センター」などがあります。
「よりそいホットライン」は24時間電話相談の受付をしており、相談内容に応じて、対面相談に切り替えてくれたり、公的機関につなげたりしてくれるのが特徴です。
また「精神保健福祉センター」は各センターの規模にもよりますが、医師や精神保健福祉士、臨床心理士などの専門家が在籍しています。
「摂食障害支援拠点病院」は摂食障害に特化した病院であり、患者やその家族に対して適切な治療や行政機関からの支援をサポートしています。
摂食障害の治療法

複数の治療法を組み合わせる
摂食障害の治療には、下記の複数の治療方法を組み合わせることが多いです。
環境調整
環境調整とは、学校や職場などでストレスを軽減出来るように、環境を調整してもらうことです。
摂食障害の治療には、焦らずに休養をとることが必要であり、ストレスをかけず過ごせる環境を作ることが回復への早道です。
対人関係療法
対人関係療法とは、家族や友人などの身近な人との関係に焦点を当て、そこでの感情や行動、関係性を変化させながら、問題を解決する治療方法です。
拒食症・過食症の方は、自分の体や食事に対する過剰なこだわりが原因となっていることが多い傾向にあります。対人関係療法では、その過剰なこだわりを改善するために、身近な人との関係を改善していくことで、問題解決を目指します。
行動認知療法
摂食障害の認知行動療法とは、食事や体重に関する考え方を変えることで、摂食障害の症状を改善する治療方法です。
認知行動療法では、考え方を変えることで、ストレスを軽減することができます。例えば、「太ったら嫌われる」という考え方を変えることで、「太っても、嫌われない」という考え方に変えることで、食事制限や過食などの行動を減らすことができます。
認知の考え方を変えることにより、ストレスを軽減させる治療方法です。
薬物療法を補助的に行う事もある
摂食障害には、直接的に症状を改善する薬はありません。そのため、上記の他にカウンセリングや栄養指導などの心理療法が中心となります。
摂食障害の症の中でも精神的に不安定な状態が続いたり、うつ状態になったりするケースでは、症状をおさえるため抗うつ薬・抗精神病薬などを処方することがあります。
精神科訪問看護を利用する選択肢も

精神科訪問看護とは?
・自立した生活を営めるための支援
・生活リズムの調整
症状の悪化防止・服薬支援
・生活状況を観察
・受診や服薬を支援
社会復帰へのサポート
・主治医や関係機関と連携
・社会復帰を支援
家族の方への支援
・家族へのアドバイスや相談
・社会資源の活用などを支援
精神科訪問看護とは、精神疾患を抱える方や精神的な理由で不安がある方へ、看護師などの専門職がご自宅で支援するサービスです。
看護師や作業療法士などの医療スタッフが医師の指示のもと自宅へ訪問し、病状観察や日常生活指導、また家族支援などのサポートを行います。
精神科訪問看護は精神科や心療内科に通院され精神疾患と診断されている方、診断はなくとも睡眠障害などで医師が訪問看護が必要と判断された方が対象です。
精神科訪問看護の1回の訪問時間は30分〜90分が一般的で、料金については医療保険が適用されるのが特徴です。
精神科訪問看護のメリット
- 自宅に居ながら専門的なケアが受けられる
- 自宅での様子を主治医に連携できる
- 対人関係や日常生活の支援を受けられる
訪問看護は、外出が困難な方や治療を中断してしまう方も、自宅で継続的に専門的な支援を受けられるサービスです。
医療機関やかかりつけの医師と病状や内服状況を連携し、病状や内服状況などの情報を共有できます。
家庭での療養状況を確認し、デイサービスやショートステイ、介護サービスの導入も提案できます。
精神疾患の患者さんが、家庭や地域社会、また学校生活を安心しておくることが出来るように、利用できる制度などを提案します。
精神科訪問看護の料金
| 負担割合 | 月の初回訪問 | 2回目以降 |
|---|---|---|
1割負担 | 1,299円/回 | 855円/回 |
2割負担 | 2,598円/回 | 1,710円/回 |
3割負担 | 3,897円/回 | 2,565円/回 |
上記は週3回までの訪問料金となります。週4回以上訪問となる場合には料金が異なります。
精神科訪問看護では、医療保険を利用することにより自己負担を軽減できるメリットがあります。
30分を一区切りに利用可能。かかった費用については、年齢や所得によって変わり、医療費の1〜3割が自己負担となります。
また早朝や深夜などの時間外に依頼する場合や、長時間の訪問を行う場合は別途料金が発生します。
また自立支援医療制度いう制度を利用すると料金が1割負担になるほか、所得に応じて自己負担が0円になる場合もございます。
精神疾患をお持ちならシンプレへ

シンプレの特徴
精神科に特化したシンプレ訪問看護ステーションは、摂食障害や依存症などのこころの病気で悩んでいる方やそのご家族への継続的なサポートを通じて解決への一歩をお手伝いします。
シンプレ訪問看護ステーションには、精神疾患の専門知識や看護経験が豊富なスタッフが多数在籍。
地域に密着した訪問を行い、医療関係や公共機関と連携を取り合いながら、地域全体としてサポートできる体制をととのえていきます。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応地域はおもに上記が中心で、訪問活動をおこなっています。該当エリアにお住まいの方はぜひご検討ください。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。電話やメールなどで相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

摂食障害の症状は、食べる事を拒む「拒食症」と食べ過ぎてしまう「過食症」があり、自分自身ではコントロールが難しい精神疾患です。
その症状の原因は、職場のストレスや人間関係などさまざまであり、精神療法などで症状の改善ができますが、完全な治療には長い時間がかかることがあります。
シンプレ看護ステーションでは、精神科に特化した専門スタッフがその人らしい生活をおくれるようサポートさせていただきます。
摂食障害でお悩みで訪問看護のご利用検討されたい、一度話を聞いてみたい等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



