拒食症の症状を徹底解説|身体・精神のサインと原因・治療法・支援方法まで

拒食症は「食べること」への強い不安や恐怖から食事を制限してしまう疾患で、
身体的・精神的な症状の両面に影響を与えます。
特に体重減少や低体温、無月経といった身体的変化に加え、強い不安感や自己否定感などの精神的な問題も現れることが特徴です。
症状を放置すると心身に深刻な影響を及ぼすため、早期に症状へ気づき、適切な支援を受けることが非常に重要です。
この記事では「拒食症の症状」を中心に、原因やなりやすい人の特徴、周囲ができるサポート方法、治療法について詳しく解説します。
在宅で受けられる支援として精神科訪問看護についても紹介しますので、ご自身やご家族が拒食症に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
- 拒食症の症状をチェックしてみましょう
- 拒食症の原因とは?
- 拒食症になりやすい人の特徴とは?
- 拒食症のある方に周囲の人ができるサポート
- 拒食症かな?と思った時の相談先一覧
- 拒食症の治療法について
- 在宅で支援できる精神科訪問看護という選択肢
- 精神疾患のサポートならシンプレ訪問看護ステーションへ
- まとめ|拒食症の症状は早期発見と適切な支援が重要
拒食症の症状をチェックしてみましょう

身体的な症状(体重減少・低体温・無月経など)
- 貧血
- 体重減少
- 体重減少に伴う無月経
- 腹部の膨満感
- 便秘
拒食症ではまず目に見える身体的変化があらわれます。
代表的なのが急激な体重減少で、BMI値が17.5以下の状態が続くと深刻な低体重と判断されます。
これに伴い、女性では無月経が起こり、不妊の原因となることもあります。
低体温や貧血、脱水症状、さらに嘔吐や下剤乱用による電解質異常など、命に関わるリスクもあるため注意が必要です。
消化管の機能が低下するために腹部の膨満感や便秘がみられ、成長期の子どもや思春期の方では身長の伸びが止まるケースもあります。
また、低栄養状態が続くと脳萎縮や記憶力の低下といった深刻な影響が出ることもあります。
精神的な症状(強い不安・自己否定感など)
- 瘦せたいという願望が非常に強い
- 肥満や体重増加への恐怖
- 抑うつ症状
拒食症の大きな特徴は「痩せたい」という強い願望と、太ることへの恐怖です。
たとえ周囲から「痩せすぎ」と指摘されても、本人は「自分はまだ太っている」と感じてしまいます。
こうした認識の歪みは自己否定感や強い不安を伴い、抑うつ状態につながることも少なくありません。
食事の時間になると緊張や不安が高まり、徹底した運動やカロリー制限など強迫的な行動が見られるのも特徴です。
拒食症の初期症状に早く気づくことが大切
- 好き嫌いが急に増えた
- 体重や食べ物の話をするようになる
- 野菜を好むようになる
- 甘いものは悪だと思っている
- ダイエットに良いという薬を持つ
- 食卓になかなかつこうとしない
- 食事中よくトイレに行くようになる
- 食べ物を隠す・捨てる
初期段階では「急に食べ物の好き嫌いが増える」「甘いものを極端に避ける」「食卓になかなか座らない」といった行動が現れることがあります。
また、食事を隠す・捨てるなど、家族が気づきにくい行動をとるケースも多いです。
これらは拒食症のサインであり、放置すると症状が悪化してしまうため、早期に気づいて専門機関へ相談することが重要です。
拒食症の原因とは?

誰でも発症しうる可能性がある病気
- 無理なダイエット
- 対人関係のトラブル
- 職場や学校のストレス
- 家庭環境
拒食症は特定の人だけがかかるものではなく、誰にでも起こりうる病気です。
一般的には思春期から20代前半の女性に多いとされていますが、男性や小児、高齢者にも発症するケースがあり、性別や年齢に関係なく注意が必要です。
日本では思春期の女子生徒の0.5〜1%が拒食症といわれており、決して珍しい病気ではありません。
拒食症の背景には、痩せていることを理想とする社会的な価値観や、家庭・学校・職場での人間関係ストレスなどが複雑に絡み合っています。
特に「痩せたい」という気持ちが強く、体重増加への恐怖が常に心の中にあると、日常生活に支障をきたすほどの制限行動が始まります。
こうした行動は一見ダイエットや健康志向に見えるため、周囲が気づきにくいことも特徴です。
生命にも関わる深刻な病気である理由
拒食症は単なる食事制限の問題ではなく、心身に重大な影響を与える疾患です。
体重が著しく減少すると、電解質異常による不整脈や感染症にかかりやすくなるなど、
命に直結する合併症が発生するリスクが高まります。
また、低栄養状態から貧血や肝機能障害を引き起こしたり、治療で高カロリー食を摂取した際に「リフィーディング症候群」と呼ばれる多臓器不全を起こすこともあります。
さらに、拒食症の方はうつ病や不安障害、人格障害といった精神疾患を合併しやすく、薬物依存やアルコール依存に進行する例も報告されています。
死亡率は7%前後とされ、他の精神疾患に比べても非常に高い数値です。
自殺による死亡率も高く、拒食症が「精神疾患の中でもっとも危険な病気のひとつ」とされる理由はここにあります。
拒食症の症状を早期に理解し、原因に目を向けながら治療に取り組むことは、本人の回復だけでなく命を守るためにも欠かせません。
周囲の人が病気の深刻さを正しく理解し、早めに医療機関や専門家へつなげることが重要です。
拒食症になりやすい人の特徴とは?

拒食症は誰にでも発症の可能性がありますが、特に性格傾向やストレス耐性の弱さなどが関わっているといわれています。
ここでは、拒食症になりやすい人の特徴について整理します。
なお、これらはあくまで傾向であり、すべての人に当てはまるわけではありません。
- 完璧主義で自分に厳しい方
- こだわりや思い込みが強い方
- 他人と比較して自分を低く評価しがちな方
- ストレス対処が苦手な方
- 「◯◯しなければならない」という思考が強い方
完璧主義的な性格を持つ人は、体重や食事管理においても極端にストイックになりやすく、それが拒食症の症状へとつながることがあります。
また、日常の中で「人より劣っている」と感じやすい人は、自己否定感を強める中で食事制限をエスカレートさせてしまう傾向があります。
さらに、ストレスを受けやすく発散することが苦手な人も要注意です。
学校や職場での人間関係、家庭環境などのプレッシャーに対し、自分を追い込むように食事制限を強めるケースが少なくありません。
「〜しなければならない」という強い思考があると、柔軟な対応ができず、心身に負担が積み重なりやすいのです。
拒食症の発症は決して本人の甘えではなく、環境や心理的な要因が複雑に絡み合って起こるものです。
そのため、本人が自分を責める必要はありません。
むしろ周囲が特徴や症状に気づき、早めに声をかけたり専門機関へつなげたりすることが大切です。
拒食症になりやすい人の特徴を知っておくことは、発症の予防だけでなく、再発を防ぐうえでも重要です。
「最近食事の量が極端に減っている」「体重やカロリーの話ばかりしている」といった小さな変化も、見逃さずに気づいてあげるようにしましょう。
拒食症のある方に周囲の人ができるサポート

- 安心できる環境を整える
- 本人を責めない
- 周囲の人と比べない
- できたことに注目してほめる
拒食症は、本人だけでなく家族や周囲の人にとっても大きな試練となります。
拒食症の症状が見られると「早く食べさせなければ」と焦ってしまいがちですが、強制的に食事をすすめたり叱責したりすることは逆効果です。
本人が安心できる環境をつくり、否定せずに見守ることが回復への第一歩になります。
また、周囲と比較して「なぜ普通に食べられないの?」と問い詰めるのも避けるべきです。
拒食症は意志の弱さや甘えから生じるものではなく、心理的・社会的背景が複雑に絡み合って起こる病気です。
そのため、本人を責めるのではなく、「できたこと」に注目し、小さな変化でも認めてあげる姿勢が重要です。
さらに、拒食症のある方は自己否定感が強く、失敗体験を繰り返すことで自信を失いやすい傾向にあります。
例えば「今日は一口でも食べられたね」といった肯定的な声かけは、本人に安心感を与え、治療への前向きな姿勢につながります。
小さな進歩を積み重ねていくことが大切なのです。
サポートする側も長期間にわたるケアに疲れてしまうことがあります。
そのため、家族だけで抱え込まず、医療機関や訪問看護、カウンセラーなど外部の専門家と連携して支援体制を整えることが望ましいでしょう。
拒食症の回復には「周囲の理解と支え」が欠かせません。
本人と一緒に取り組む姿勢を持つことが、治療を継続する大きな力となります。
拒食症の症状を抱える方を支えるには、忍耐強く温かい関わりが必要です。
「無理をさせない」「本人のペースを尊重する」ことを心がけながら、少しずつ安心できる環境を整えていきましょう。
拒食症かな?と思った時の相談先一覧

・専門医による診察と治療
・定期的な通院による経過観察
電話相談窓口
・よりそいホットライン(24時間対応)
・こころの健康相談統一ダイヤル
SNS相談窓口
・こころのほっとチャット(LINE/Twitterで相談可能)
・生きづらびっと(匿名で相談可能)
「もしかして拒食症かもしれない」と感じたとき、できるだけ早期に相談することが大切です。
拒食症の症状は本人が「自分は大丈夫」と思い込んでしまうことも多く、病気の深刻さを認識できないケースがあります。
そのため、気づいた段階で専門の医療機関や相談窓口にアクセスすることが回復への第一歩になります。
①精神科や診療内科
精神科や診療内科では、体調や心理状態を踏まえたうえで適切な診断と治療方針が立てられます。
初めて受診する際には不安が伴うかもしれませんが、早めに受診することで症状の悪化を防ぎやすくなります。
また、拒食症の診療経験が豊富な医師に相談することで、本人や家族の不安も軽減されます。
②電話相談窓口
電話相談窓口の「よりそいホットライン」は24時間対応しており、匿名でも利用できるため、緊急時の支えになります。
こころの健康相談統一ダイヤルでは各地域の公的機関とつながり、必要に応じて医療機関への案内も受けられます。
一人で抱え込まず、まずは声を出すことが大切です。
③SNS相談窓口
近年はSNSでの相談も広がっており、チャット形式で専門カウンセラーとやり取りが可能です。
「こころのほっとチャット」や「生きづらびっと」は、特に若い世代でも利用しやすいサービスです。
匿名性が高く気軽に利用できるため、「病院に行くのはまだ抵抗がある」という方にもおすすめです。
拒食症の症状が進むと、体重減少や精神的な不安だけでなく命に関わる危険もあります。
自分自身や家族の健康を守るためにも、少しでも不安を感じたら、電話・SNS・医療機関など複数の相談先を活用してみてください。
拒食症の治療法について
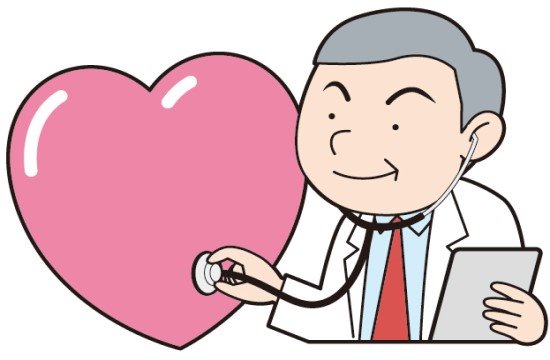
生活環境を整える「環境調整」
拒食症の治療においてまず重要なのは、安心して過ごせる環境を整えることです。
学校や職場での人間関係、家庭でのストレスなどが症状悪化の引き金になることが多く、こうした要因を軽減・除去することで改善が期待できます。
例えば、過度なプレッシャーを与える状況から一時的に距離を置いたり、休養をしっかり取ることも有効です。
安心できる生活環境は回復への土台となるため、家族や周囲の協力が欠かせません。
人間関係の改善を目指す「対人関係療法」
拒食症の症状には、人間関係のストレスや不安が影響していることが少なくありません。
そこで有効とされているのが「対人関係療法」です。
これは患者の生活における重要な人間関係に焦点を当て、葛藤や不安を整理し、より健全な関係を築けるように支援する心理療法です。
カウンセリングを通じて自己肯定感を育て、自己否定感の改善を図ることが目的です。
必要に応じて行われる「薬物療法」
拒食症の治療において、薬物は補助的に用いられることがあります。
例えば、うつ状態が強い場合には抗うつ薬、不安が強い場合には抗不安薬を使用することがあります。
また、感情の揺れや衝動的な行動が目立つ場合には抗精神病薬が処方されることもあります。
ただし、薬だけで拒食症が完治するわけではありません。
心理療法や環境調整と併せて取り組むことで効果が発揮されます。
拒食症は「心」と「体」の両面から治療を行う必要がある病気です。
生活環境の調整、心理的アプローチ、そして必要に応じた薬物療法を組み合わせることで、少しずつ改善へと向かうことが期待されます。
また、治療には時間がかかることが多いため、焦らず長期的な視点を持って取り組むことが大切です。
拒食症の症状を軽視せず、専門医やカウンセラーと協力しながら治療を続けていくことで、本人が本来の生活を取り戻せる可能性が高まります。
家族や周囲も一緒に支える姿勢を持ち、長い目で見守っていくことが回復の大きな支えとなるでしょう。
在宅で支援できる精神科訪問看護という選択肢

精神科訪問看護とは?
・精神科・心療内科に通院中の方
・精神疾患の診断を受けた方
・診断がなくても医師が必要と判断した方
訪問する人
・看護師や准看護師
・作業療法士などの専門職
訪問時間
・1回30〜90分程度
・週1〜3回(症状により調整可能)
精神科訪問看護とは、精神疾患をもつ方の自宅へ看護師や作業療法士が訪問し、日常生活や治療をサポートするサービスです。
拒食症の症状がある方は外出が難しかったり、通院を続けるのが困難になるケースも多いため、自宅で支援を受けられる訪問看護は大きな助けになります。
医師の指示のもと、病状の観察や服薬管理、家族への助言などを行い、安心して療養生活を送れるよう支援します。
拒食症の方に提供される具体的な看護内容
・自立した生活を営めるための支援
・生活リズムの調整
症状の悪化防止・服薬支援
・生活状況を観察
・受診や服薬を支援
社会復帰へのサポート
・主治医や関係機関と連携
・社会復帰を支援
家族の方への支援
・家族へのアドバイスや相談
・社会資源の活用などを支援
拒食症の方への訪問看護では、まず体重や食事の状況を観察し、症状が悪化していないかをチェックします。
さらに、食事をめぐる不安や自己否定感に寄り添い、本人が安心できるよう継続的なケアを行います。
家族に対しても「どのように声をかければよいか」「支援の負担をどう軽くするか」といった具体的なアドバイスを提供します。
精神科訪問看護を利用するメリット
- 自宅にいながら専門的なケアを受けられる
- 通院の負担を軽減できる
- 主治医と連携しながら症状を管理できる
- 家族のサポート体制も強化できる
訪問看護は「本人」と「家族」の両方を支える仕組みであり、拒食症の長期的な回復において大きな役割を果たします。
安心できる生活環境を整えるだけでなく、再発防止にもつながる点が大きなメリットです。
精神科訪問看護の料金と自己負担額
| 負担割合 | 月の初回訪問 | 2回目以降 |
|---|---|---|
1割負担 |
1,299円/回 | 855円/回 |
2割負担 |
2,598円/回 | 1,710円/回 |
3割負担 |
3,897円/回 | 2,565円/回 |
上記は正看護師or作業療法士が訪問した料金となります。
上記は週3回までの訪問料金となります。週4回以上訪問となる場合には料金が異なります。
精神科訪問看護では、医療保険を利用することにより自己負担を軽減できるメリットがあります。
30分を一区切りに利用が可能で、かかった費用については、年齢や所得によって変わり、医療費の1〜3割が自己負担となります。
また早朝や深夜などの時間外に依頼する場合や、長時間の訪問を行う場合は別途料金が発生します。
また自立支援医療制度いう制度を利用すると料金が1割負担になるほか、所得に応じて自己負担が0円になる場合もございます。
自立支援医療(精神通院医療)を活用できる場合
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 生活保護 |
0円 |
| 低所得1 |
2,500円 |
| 低所得2 |
5,000円 |
| 中間所得1 |
5,000円 |
| 中間所得2 |
10,000円 |
| 一定所得以上 |
20,000円 |
表の料金は所得に応じた医療費の月額自己負担額の上限額となっております。
表の料金を超えた場合には、自己負担なしで医療が受けられます。
自立支援医療(精神通院医療)は、継続的に通院治療が必要な人が利用できる制度で、すべての精神疾患が対象です。
入院しないで行われる医療が対象で、外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護などの通院が適用となります。
精神疾患は治療が長くなることが多いため、その間の医療費負担を軽くし、精神的にも経済的にも、安心して治療に集中できるようにする制度です。
この制度を利用すると医療保険で3割負担していたのが1割の負担となります。
また、所得に応じて負担額の月の上限額が設定されます。
上記の表の料金が所得区分別の上限額金額となりますので、ぜひ参考にしてください。
精神疾患のサポートならシンプレ訪問看護ステーションへ

シンプレ訪問看護ステーションの特徴
シンプレ訪問看護ステーションは、東京都内を中心に精神疾患をもつ方へ専門的な訪問看護を行っています。
拒食症の症状でお悩みの方をはじめ、うつ病・統合失調症・双極性障害・PTSD・不安障害・適応障害・発達障害など多岐にわたり、医療的処置が必要な場合には、胃ろう・自己導尿・在宅酸素療法・褥瘡ケアなどの対応も可能です。
訪問スタッフは看護師・准看護師・作業療法士といった医療の専門職で構成されており、症状の観察や服薬管理だけでなく、生活リズムの調整や再発防止の支援も行っています。
また、ご家族に対しても看護方法や声かけの工夫をお伝えし、家庭全体で療養を支えられる体制を整え、ご自宅で安心して療養できるよう支援しています。
訪問時間は1回あたり30〜90分で、週1〜3回の訪問が基本ですが、症状や生活状況に応じて柔軟に調整可能です。
祝日や土曜日の訪問も行っているため、日常生活のリズムに合わせた利用がしやすいのも特徴です。
「本人と家族が安心できる環境を整える」ことを大切にしているシンプレでは、病状の改善や社会復帰を見据えた支援を行っています。
医療機関や行政とも連携しながら、地域全体で支える体制を構築しているため、長期的な療養にも対応できます。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応地域はおもに上記が中心で、訪問活動をおこなっています。該当エリアにお住まいの方はぜひご検討ください。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。電話やメールなどで相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
ご本人の気持ちに寄り添いながら、最適な支援を一緒に考えていきます。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ|拒食症の症状は早期発見と適切な支援が重要

拒食症は年齢や性別に関わらず誰にでも起こり得る病気であり、食事制限や極端なダイエットがきっかけとなることも少なくありません。
体重減少や無月経、低体温といった身体的な変化だけでなく、自己否定感や強い不安など精神的な症状も伴うため、「心」と「体」の両面に影響を与える病気です。
拒食症の症状を軽視すると、命に関わる合併症や他の精神疾患を併発するリスクが高まります。
しかし、早期に気づいて適切な治療を受ければ、回復を目指すことが可能です。
環境調整や対人関係療法、薬物療法といった治療法を組み合わせ、焦らず継続することが大切です。
周囲のサポートも欠かせません。
本人を責めたり無理に食べさせたりするのではなく、小さな進歩を認め、安心できる環境を整えることが求められます。
家族だけで抱え込むのではなく、医療機関や相談窓口、精神科訪問看護などの専門サービスを活用することで、より効果的な支援が可能になります。
シンプレ訪問看護ステーションでは拒食症を含む精神疾患に幅広く対応し、本人と家族が安心できる生活を支えることを目指しています。
訪問看護を利用することで、病状の安定や再発予防、社会復帰へのステップを踏み出しやすくなります。
拒食症の症状に早く気づくこと、そして本人が安心して治療に向き合えるよう支援することが、回復への第一歩です。
「もしかして」と思ったら一人で抱え込まず、早めに相談窓口や医療機関へつなげていきましょう。
そして、必要に応じて訪問看護などの支援を取り入れることで、本人と家族の負担を減らしながら、前向きな回復を目指すことができます。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



