てんかんと精神疾患の関係を解説|併発しやすい症状・原因・治療法・相談先まとめ
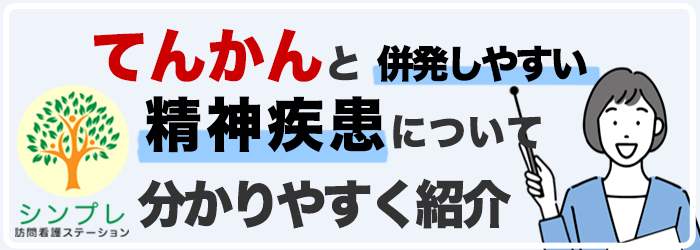

てんかんとは、脳の神経活動が一時的に異常な興奮を起こすことで、けいれんや意識障害などの発作を繰り返す病気です。
発作自体の影響だけでなく、てんかん患者さんの中には精神疾患的な症状を併発する方も多く、日常生活や社会生活に大きな支障をきたすことがあります。
特に「うつ病」「不安障害」「幻覚妄想状態」などは代表的な症状であり、適切な理解と早期対応が求められます。
この記事では、てんかんと併発しやすい精神疾患的な症状や、その背景にある要因、治療方法や利用できる公的制度、さらには相談先までを詳しく解説します。
てんかんと精神疾患の関わりを正しく理解し、本人だけでなくご家族の方も安心して支援できるような情報をお届けします。
てんかんと併発しやすい精神疾患的な症状

うつ状態(気分の落ち込み・意欲低下)
てんかんを抱える患者さんでは、うつ状態伴うケースが多く見られます。気分の落ち込みや悲観的な思考が続き、日常生活に対する意欲が低下することも少なくありません。
特に長期間にわたり無気力な状態が続くと、社会参加や家庭生活に支障をきたす可能性があります。原因としては、てんかんそのものの影響に加えて、抗てんかん薬の副作用が関係していることもあり、その場合は薬の調整や変更が行われます。
適切な診断と治療により、症状の改善が期待できます。
幻覚妄想状態(現実との区別がつきにくい症状)
てんかんに伴い、現実には存在しない声が聞こえる「幻聴」や、実際には見えないものが見える「幻覚」、事実ではないことを強く信じ込む「妄想」が現れることがあります。
これらは幻覚妄想状態と呼ばれ、患者本人にとっては非常にリアルであるため、生活や対人関係に深刻な影響を及ぼします。治療には薬物調整やストレスの軽減が用いられ、抗てんかん薬の副作用が関与している場合は処方内容の見直しが重要です。
心因性発作(解離症状との関係)
見た目にはてんかん発作に似ているものの、実際には心因性発作と呼ばれるストレス由来の発作が生じる場合があります。
これは解離症状とも関連しており、精神的負担や生活上のストレスが大きな引き金となります。治療では、ストレス要因を特定・軽減し、患者がストレスに対応できる力を高めることが目標となります。
場合によっては薬物療法が併用されますが、抗うつ薬などが必ずしも有効とは限らず、個別の対応が必要です。
また、心因性非てんかん発作(PNES)は、てんかんではなく心理的ストレスによって起こる発作の症状です。
てんかん患者の一部(10〜20%)で併発することがあり、鑑別が重要です。
脳波検査でてんかん性の変化がないことが特徴で、治療は心理療法が中心となります
不安障害やパニック症状
てんかん患者さんは、発作がいつ起こるかわからない不安から、不安障害やパニック発作を引き起こすことがあります。
動悸や呼吸困難感、強い恐怖感が突然現れることもあり、日常生活への影響は大きいです。不安症状が強い場合には薬物療法や心理療法が組み合わせて行われ、安心して生活できるようサポートされます。
認知機能障害(記憶力や集中力の低下)
てんかんと精神疾患的症状の併発の一つとして、認知機能の低下が挙げられます。具体的には記憶力の低下、注意力や集中力の持続が難しくなるといった症状です。
これにより学業や仕事に支障が出ることがあり、本人や家族にとって大きな負担となります。発作や薬の影響、脳の器質的要因が関与しており、リハビリテーションや環境調整など多面的なアプローチが必要です。
てんかん性精神病
長期間てんかんを患っている方の一部(約5〜10%)に、統合失調症に似た精神病症状が現れることがあります。
これを『てんかん性精神病』と呼びます。幻聴や被害妄想などが特徴ですが、統合失調症とは異なる特性を持ち、治療アプローチも異なります。
てんかんに伴う精神疾患的症状の要因

てんかんそのものの病態による要因
てんかんは脳の神経細胞が突発的に過剰な電気的興奮を起こす病気であり、その影響で精神疾患的な症状が現れることがあります。
例えば、発作を繰り返すことによる脳機能の異常が、うつ状態や幻覚妄想といった症状を引き起こす場合があります。つまり、てんかんそのものの病態が直接的に精神症状を誘発するケースです。
この場合は、てんかんの発作がコントロールされれば、併発する精神症状も軽減する傾向があります。しかし根本的にてんかんが完治しない限り、症状の再発リスクは残ります。
遺伝的要因・脳器質性の影響
一部の患者さんでは、遺伝的な背景や脳の器質的な障害が、てんかんと精神疾患の併発リスクを高める要因となります。
例えば、脳の発達過程での異常や外傷、脳腫瘍などが原因でてんかんを発症し、その結果、>認知機能の低下や精神疾患的症状を併発することがあります。
また、家族に精神疾患を持つ方がいる場合、遺伝的な影響でうつ病や不安障害が出やすくなることも報告されています。てんかんと精神疾患の併発には複合的な要因が関わっていると考えられます。
心理社会的要因(ストレス・人間関係など)
てんかん患者さんは、発作がいつ起こるかわからないという不安や、周囲の理解不足による孤独感、職場や学校での制約といった心理社会的ストレスを抱えやすい傾向があります。
こうした背景はうつ病や不安障害といった精神疾患的症状を悪化させる大きな要因となります。特にストレスに敏感な性格傾向を持つ方は、より症状が強く出やすいとされています。治療の際には、薬物療法だけでなく、カウンセリングや家族支援などの心理社会的アプローチも重要になります。
薬の副作用など医原性の要因
てんかん治療の中心となる抗てんかん薬は、多くの場合有効ですが、その副作用として精神症状が現れることがあります。
例えば、不眠や気分変動、うつ状態、さらには幻覚妄想といった症状が副作用として出るケースです。このような医原性の要因が関与している場合、投薬量の調整や副作用の少ない薬への変更で改善することがあります。
ただし、てんかんと精神疾患の症状が複合的に絡み合って現れる場合もあるため、医師の診断のもとで最適な治療方針を選ぶことが欠かせません。副作用を軽視せず、適切な対応を行うことが重要です。
てんかんに対する治療方法

薬物療法
てんかん治療の基本は抗てんかん薬による薬物療法です。
発作の種類や患者さんの体質に応じて薬が選ばれ、脳内の神経伝達のバランスを整えることで発作を抑えます。抗てんかん薬は発作の再発を防ぎ、生活の質を大きく向上させる重要な治療法です。
しかし一方で、副作用によって精神疾患的な症状(うつ状態、不安感、幻覚妄想など)が出現する場合もあるため、医師による慎重な投薬管理が必要となります。
また、てんかんの症状と精神病の症状が併発しており抗精神病薬を用いる場合は、抗精神病薬の中にはけいれん閾値を下げて発作を誘発しやすくするものがあるため、薬剤選択は慎重に行われます。
薬の効果からみた抗てんかん薬の種類
てんかん発作は神経細胞が過剰に興奮することで起こります。
そのため、抗てんかん薬には「興奮を抑える薬」と「抑制を強める薬」、さらに両者のバランスを整える薬があります。例えばカルバマゼピンやフェニトインは興奮を抑える作用を持ち、ジアゼパムやクロナゼパムは抑制を強める薬として使用されます。
また近年では「レベチラセタム」のように新しい作用機序を持つ薬も登場し、より幅広い患者さんに対応できるようになっています。最新の薬剤選択が治療効果を左右するため、医師との相談が欠かせません。
発作(ほっさ)型に応じた抗てんかん薬の選択
てんかんは「部分発作」と「全般発作」に大きく分けられ、さらに欠神発作、強直間代発作、ミオクロニー発作などに分類されます。発作の種類ごとに効果的な薬が異なるため、正確な診断に基づいた薬の選択が必要です。
例えば部分発作にはカルバマゼピン、欠神発作にはエトスクシミド、強直間代発作にはバルプロ酸などが用いられます。発作型を見極め、適切な薬を選択することは、精神疾患的症状の悪化を防ぐうえでも重要です。
外科治療の可能性
薬物療法で十分な効果が得られない「難治性てんかん」では、外科治療が検討されることがあります。
外科治療には、発作の原因部位を切除して根治を目指す「根治手術」と、発作の頻度や重症度を軽減する「緩和手術」があります。
特に部分発作で、発作の焦点が特定できる場合には外科治療の適応となりやすいです。ただし外科治療は脳の機能への影響もあるため、専門医による十分な検査と判断が必要です。
食事療法(ケトン食など)
薬でのコントロールが難しい場合、ケトン食療法などの食事療法が行われることもあります。
糖質を制限し脂肪を多く摂取することで、体内の代謝を変化させ、発作の抑制に効果を示すことが確認されています。特に小児のてんかんにおいて有効性が高いとされ、2年程度継続するケースもあります。
ただし副作用として低血糖や消化器症状が出る可能性があるため、医師の指導のもと慎重に実施されます。
心理社会的アプローチ(カウンセリング・精神療法)
てんかんと精神疾患は相互に影響し合うため、心理社会的アプローチも重要です。
カウンセリングや精神療法を取り入れることで、不安や抑うつといった症状を和らげ、患者さんがより安心して生活できる環境を整えることが可能です。
特に家族や職場など周囲の理解が不十分な場合、心理社会的サポートが大きな支えとなります。薬物療法や外科治療と組み合わせることで、より包括的な治療が実現します。
てんかん患者が利用できる公的制度

障害者手帳(療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
てんかんを持つ方の中には、日常生活や社会生活に大きな支障をきたす場合があります。
そのようなケースでは、精神障害者保健福祉手帳や療育手帳を取得することで、就労支援や税制上の優遇、公共料金の割引といった支援を受けられます。
特に精神障害者保健福祉手帳は、てんかんによって精神疾患的な症状が生じている場合に有効で、社会参加を後押しする制度です。自分がどの手帳の対象になるのかは、主治医の診断や自治体の窓口で確認する必要があります。
障害年金の受給条件と内容
てんかんは慢性的な病気であり、重度の発作や精神疾患的症状によって日常生活が制限される場合には、障害年金の対象となることがあります。
障害年金は国の制度であり、発作の頻度や生活への影響度に応じて等級が決定されます。支給される金額は等級や加入している年金制度によって異なりますが、生活費の補助となり患者さんやご家族の経済的負担を軽減します。
てんかんと精神疾患の併発によって働くことが困難な場合には、積極的に申請を検討するべき制度です。
自立支援医療制度の活用方法
てんかん治療は長期にわたることが多く、薬代や通院費用が家計を圧迫することも少なくありません。
そうした際に活用できるのが「自立支援医療制度(精神通院医療)」です。この制度を利用すると、通院や薬にかかる自己負担額が原則1割に軽減されます。
特に抗てんかん薬の継続投与が必要な方にとっては、大きな経済的支えとなります。利用には医師の診断書と市区町村への申請が必要ですが、長期治療を継続する上で非常に有効な制度といえるでしょう。
また、てんかんを持つ方でも加入できる医療保険商品(例:ぜんちのあんしん保険)も存在し、制度とあわせて活用することで安心感が高まります。
これらの制度を適切に利用することで、治療の継続が容易になり、精神疾患的な症状があっても生活の質を維持しやすくなります。
てんかんの相談先について

神経内科・精神科などの医療機関
てんかんは発作そのものだけでなく、精神疾患的な症状を伴う場合があるため、医療機関での相談が非常に重要です。
診断や治療の中心となるのは神経内科や精神科であり、特に「てんかん診療拠点病院」には専門医が在籍しているため、最新の医療を受けることができます。
大学病院や赤十字病院なども拠点病院に指定されており、発作のコントロールだけでなく、うつ状態や不安障害などの精神症状に対する相談も可能です。早期に受診することで、症状の悪化を防ぎ、生活の質を維持しやすくなります。
患者会・家族会(日本てんかん協会など)
医療機関だけでなく、患者会や家族会に参加することも有効です。日本てんかん協会をはじめとする団体では、同じ病気を持つ人々や家族が集まり、情報交換や心理的サポートを行っています。
孤独感の軽減や、日常生活での工夫を共有できる点が大きなメリットです。また、行政や福祉サービスの情報も得られるため、制度の活用にもつながります。
てんかんと精神疾患を併発している方やそのご家族にとって、心の支えとなる場になるでしょう。
精神科訪問看護を利用するという選択肢
外来通院だけでは十分なサポートが得られない場合、精神科訪問看護を利用することも選択肢の一つです。
精神科訪問看護では、看護師や作業療法士が自宅を訪問し、服薬管理、生活支援、再発予防といった支援を行います。
一般の訪問看護と異なり、精神疾患に特化しているため、てんかんによる精神症状(不安・うつ・幻覚妄想など)にも柔軟に対応可能です。地域社会で安心して生活を続けられるよう支援してくれるため、患者さんだけでなく家族にとっても大きな安心材料となります。在宅での治療継続を支える有効なサービスとして注目されています。
さらに、保健所や精神保健福祉センターでも相談が可能で、必要に応じて保健師が家庭を訪問するケースもあります。
こうした多様な相談窓口を組み合わせることで、てんかんと精神疾患の両面に対応したより包括的な支援を受けることができます。
精神科訪問看護ならシンプレ訪問看護ステーションへ!

訪問看護で受けられる支援内容(服薬管理・生活支援・再発予防)
てんかんを抱える方の中には、発作そのものに加えて精神疾患的な症状を併発するケースも少なくありません。
そうした状況では、服薬をきちんと継続することや生活リズムを整えることが非常に大切です。精神科訪問看護では、専門の看護師や作業療法士がご自宅を訪問し、服薬管理、生活支援、発作や精神症状の再発予防をサポートします。
また、ご家族への相談対応も行うため、安心して在宅療養を続けることができます。医療と生活の両面を支えるサービスとして大きな役割を果たしています。
シンプレ訪問看護ステーションとは?
シンプレ訪問看護ステーションは、精神科に特化した訪問看護サービスを提供しています。
看護師・准看護師・作業療法士といったスタッフがチームを組み、主治医や関係機関と連携しながら、ご利用者さまが自宅や地域社会で安心して暮らせるようサポートを行います。
特にてんかんと精神疾患を併発している患者さんにとって、服薬支援や日常生活支援は欠かせない要素です。精神科訪問看護の専門性を活かし、患者さんらしい生活を取り戻すための支援を心がけています。
利用の流れ(相談 → 指示書 → 契約 → 訪問開始)
シンプレ訪問看護ステーションを利用する流れはシンプルです。
まずお問い合わせいただくと、担当スタッフが相談に応じます。その後、主治医から「訪問看護指示書」が発行され、契約を経て訪問が開始されます。訪問時間は1回30分~90分、訪問回数は週1~3回が基本ですが、必要に応じて週4回以上の訪問も可能です。祝日や土曜日も対応しているため、柔軟にサービスを受けることができます。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリアは、東京都23区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、府中市、東久留米市、さらに埼玉県の一部地域です。近隣の市区町村であっても訪問可能な場合があるため、まずはお気軽にご相談ください。
地域密着型の訪問看護を強みとしており、利用者さまの生活環境に寄り添ったサポートを行っています。
シンプレ訪問看護ステーションは、てんかんや精神疾患に関する豊富な知識と経験を持つスタッフが多数在籍しており、服薬支援・生活支援・再発予防など幅広いケアを提供しています。
自宅療養を続けたい方やご家族にとって、安心できるパートナーとなるでしょう。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ|てんかんと精神疾患の併発には早期対応と継続支援が重要

てんかんは発作による直接的な影響だけでなく、うつ状態、不安障害、幻覚妄想といった精神疾患的な症状を併発することが少なくありません。
これらの症状は日常生活や社会生活に大きな支障をきたす可能性があるため、早期に気づき、適切な医療機関や支援機関へ相談することが大切です。
特にてんかん診療拠点病院や精神保健福祉センターでは、発作治療と精神症状の両面からの支援が受けられます。
また、患者さん本人だけでなく、ご家族が安心して生活を続けられるよう、相談窓口や患者会を活用することも有効です。
孤独感の軽減や情報交換の場として活用できるだけでなく、制度の利用に関する情報を得ることもできます。てんかんと精神疾患の併発は複合的な問題を抱えるため、医療・福祉・地域支援を組み合わせた包括的な対応が不可欠です。
さらに、在宅での生活を支える選択肢として精神科訪問看護があります。
訪問看護では服薬支援、生活支援、再発予防などを通じて、患者さんの生活の質を高めることができます。シンプレ訪問看護ステーションのように精神科に特化したサービスを利用すれば、てんかんに伴う精神症状についても専門的なケアが受けられ、家族にとっても安心できる環境が整います。
継続的な支援を受けながら生活を続けることが、再発予防や安定につながるのです。
てんかんと精神疾患の併発は、一人で抱え込むと症状が悪化しやすくなります。
しかし、適切な医療機関への受診や制度の活用、訪問看護を含めた支援サービスを利用することで、安定した生活を送ることが可能です。早期対応と継続的な支援を意識し、安心して暮らせる環境づくりを進めていきましょう。
ご相談の問い合わせはこちら▼

高座渋谷つばさクリニック
医師:武井智昭
外来としてはうつ病(うつ状態)が年間300名程度はおりこちらが得意分野です。この他に、思春期特有の対応(起立性調節障害や拒食症など)も行っています。心療内科としては10年、日本精神神経学会会員に所属
本記事へのコメント
てんかんのある方の約30〜50%が、うつ病や不安障害などの精神症状を経験されます。
これは脳の病態や薬の影響、心理的ストレスなど複数の要因が関わっています。こうした精神症状も「治療可能」だということです。気分の落ち込みや不安が続く場合は、遠慮なく主治医に相談してください。抗てんかん薬の調整や、必要に応じた精神科的治療により改善できます。
特に注意していただきたいのは、お薬を自己判断で中断しないことです。急な中断は発作を引き起こし、生命に関わる危険があります。
副作用や精神症状が気になる場合も、必ず相談してから調整しましょう。てんかんがあっても、適切な治療により多くの方が希望する生活を送っています。発作のコントロールと精神症状のケアの両面から、あなたらしい、住み慣れた地域での生活が可能です。
監修日:2025年11月8日
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (5)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



