精神疾患の薬で眠いのはなぜ?副作用の原因と対策を徹底解説

「精神疾患の薬を飲むと眠くて困る…」と感じている方は少なくありません。症状を抑えるために薬は欠かせませんが、副作用で強い眠気が出てしまうと、仕事や学業、日常生活に支障をきたすことがあります。薬を服用することで得られる効果と、副作用としての眠気は表裏一体であるため、正しい知識を持ち、適切に対応していくことが大切です。
本記事では、精神疾患に用いられる薬と眠気の関係、眠くなりやすい薬の特徴、さらに薬以外の要因で眠気が起こるケースについて解説します。また、眠気への対処法や薬物療法以外の治療法、訪問看護を活用した支援の可能性についても詳しく紹介します。精神疾患と薬の副作用について理解を深め、安心して治療に取り組むための参考にしてください。
精神疾患の薬を飲むと眠いのはなぜ?

覚醒物質を抑制する作用がある
精神疾患の薬を服用したときに眠気が出る大きな理由のひとつは、薬の成分が脳内の覚醒物質を抑制するためです。覚醒物質とはセロトニンやノルアドレナリン、ヒスタミンなどで、これらが抑えられると自然と眠気を感じるようになります。特にヒスタミンをブロックする作用をもつ薬は、強い眠気が出やすいとされています。抗うつ薬の中にはセロトニンを活性化させるものもありますが、副作用として逆に眠気を引き起こすケースもあります。
夜間の睡眠が浅くなってしまう
抗うつ薬などの精神疾患治療薬は、脳内物質の分泌バランスを調整する働きがあります。しかし分泌が過剰になると、夜間の眠りが浅くなってしまい、結果的に日中に強い眠気が出てしまうことがあります。薬による眠気は、薬の種類や服用量によって大きく異なります。夜間の睡眠の質が低下することで、昼間の集中力が落ちたり、作業効率が悪くなるといった悪影響が出ることもあります。
身体が慣れるまで眠気が起こることがある
新しく薬を飲み始めたときや、服用量が変更になったときには、身体が薬に慣れるまでの間、眠気が強く出ることがあります。これは一時的なものですが、生活に支障が出るほどの眠気が続く場合は、必ず主治医に相談してください。薬の種類を変える、服用時間を調整するといった方法で改善できるケースもあります。薬による眠気は「慣れるまでの一時的な副作用」であることも多いため、焦らずに医師と一緒に最適な治療方法を見つけていくことが大切です。
眠くなりやすい薬はどれ?眠気の作用を比較

抗うつ薬(SSRI・三環系抗うつ薬など)
精神疾患の治療に用いられる抗うつ薬の中には、眠気が強く出やすいものがあります。特に三環系抗うつ薬(アナフラニール、トフラニールなど)は、脳内のヒスタミンを抑制する作用があるため、副作用として強い眠気が出やすい薬です。また、NaSSA(リフレックス/レメロン)も鎮静作用が強く、服用直後に眠気を感じやすいことで知られています。
一方で、SSRI(ジェイゾロフト、レクサプロなど)は比較的眠気が少ないものもありますが、種類や個人差によっては強い眠気を伴うこともあるため注意が必要です。薬によっては、夜の睡眠改善につながる一方、日中の活動に影響を与える場合があります。
抗不安薬(ベンゾジアゼピン系など)
不安症状をやわらげる抗不安薬は、リラックス効果がある一方で鎮静作用が強く、眠気を引き起こしやすい特徴があります。特にベンゾジアゼピン系の薬は即効性が高いため、不眠や不安を改善する目的では有効ですが、日中の眠気が強くなり作業効率を下げることもあります。薬の服用タイミングを工夫することで、副作用を最小限に抑えられることもあるため、主治医と調整しながら使用することが大切です。
抗精神病薬(統合失調症治療薬など)
統合失調症や双極性障害の治療に用いられる抗精神病薬も、種類によっては強い眠気をもたらします。特に第二世代抗精神病薬(オランザピン、クエチアピンなど)は、抗ヒスタミン作用やセロトニン受容体への作用によって鎮静効果を示し、服用初期に強い眠気を伴うケースがあります。これらは症状の安定に役立つ一方で、日常生活に支障をきたす場合もあるため、医師の指導のもと慎重に使用されます。薬の種類によって眠気の程度は大きく異なることを理解することが大切です。
その他の薬との違い
精神疾患に用いられる薬以外にも、抗ヒスタミン薬(花粉症薬など)や鎮痛薬の一部には眠気を誘発するものがあります。ただし、精神疾患治療薬は脳内の神経伝達物質に作用するため、眠気の強さや持続時間が他の薬と比べて長くなることが多い点が特徴です。薬による眠気は単なる副作用ではなく、薬の作用機序と密接に関連しているため、「眠気がある=異常」というわけではありません。とはいえ、強い眠気によって生活に支障が出る場合は、自己判断せずに必ず医師に相談することが重要です。
薬以外の影響で眠気が起こることもある

精神症状によるもの(うつ病・不安障害など)
眠気は必ずしも薬だけが原因ではなく、精神疾患そのものの症状によって引き起こされることもあります。例えばうつ病では、夜中に何度も目が覚めたり、入眠困難が続いたりといった睡眠障害がよく見られます。その結果、日中に強い眠気が生じるのです。また、不安障害などでも睡眠の質が低下し、慢性的な疲労感や眠気を訴えるケースがあります。精神症状と眠気の関係を理解し、必要に応じて医師や専門家に相談することが大切です。
生活リズムや睡眠の質の悪化によるもの
薬を服用していなくても、生活リズムの乱れや睡眠環境の悪化によって眠気が出やすくなることがあります。夜更かしや昼夜逆転の生活は体内時計を狂わせ、脳や身体が本来のリズムを失ってしまいます。また、寝る前のカフェインやアルコール摂取、スマートフォンやPCのブルーライトも睡眠の質を低下させる要因です。規則正しい生活習慣を整えることは、精神疾患の治療においても副作用の軽減においても大きな効果があります。生活習慣の改善は眠気の緩和に直結するため、できる範囲から見直してみると良いでしょう。
女性ホルモンの減少によるもの
女性の場合、ホルモンバランスの変化も眠気に関係しています。生理周期の影響でプロゲステロンが増える時期には、強い眠気を感じやすくなります。また、更年期に入るとエストロゲンやプロゲステロンの分泌量が低下し、自律神経のバランスが崩れることで日中の眠気やだるさが増すことがあります。こうした女性特有のホルモン変化による眠気は薬の副作用とは異なり、疾患や年齢による自然な変化でもあります。眠気の背景には薬以外の要因も複雑に関わっているため、体調やライフステージに応じた対応が求められます。
薬の副作用で眠い場合の対策方法は?

医師と相談の上で行うべき対策
減薬
薬を増やしても効果が期待できない
別の薬に変更
副作用があってもメリットの方が大きい
副作用対策の薬を追加
精神疾患の薬による眠気は、多くの場合「副作用」として現れるものです。飲み始めてしばらくすると身体が慣れ、眠気が軽減されるケースもあります。しかし、生活に支障をきたすほど強い眠気が続く場合は、必ず主治医に相談することが重要です。自己判断で薬を減らしたり中断することは危険であり、症状の悪化につながる恐れがあるため避けましょう。
具体的な対策としては、服用量の調整や薬の種類変更が考えられます。また、副作用を抑えるために補助的な薬を追加することもあります。いずれも医師の判断のもとで行う必要があります。眠気を我慢し続けると仕事や勉強に支障が出るだけでなく、車の運転など重大な事故につながるリスクもあるため、早めの相談が望まれます。
睡眠の質を改善する
十分な睡眠時間を確保しても眠気が強い場合、睡眠の「質」が低下している可能性があります。寝る直前のスマホ利用や強い光、カフェインの摂取は睡眠の質を下げる原因です。夜は照明を落とし、リラックスできる環境を整えることで副作用の眠気を軽減できる場合があります。
短い昼寝を習慣にする
昼寝を上手に取り入れることも有効です。15〜20分程度の短い昼寝は、眠気を和らげ集中力を回復させます。ただし、長時間の昼寝は夜の不眠を悪化させるため注意が必要です。アラームを設定し、短時間で切り上げる工夫をしましょう。
薬の服用タイミングを調整してもらう
眠気の副作用が強く出る場合は、薬の服用時間を調整するだけで改善することもあります。例えば日中の活動に影響する薬を夜に回すなど、医師と相談してスケジュールを工夫するとよいでしょう。これは患者一人ひとりの生活リズムや疾患の状態に合わせて対応できるため、負担を減らす方法のひとつです。
薬物療法以外の治療方法は?
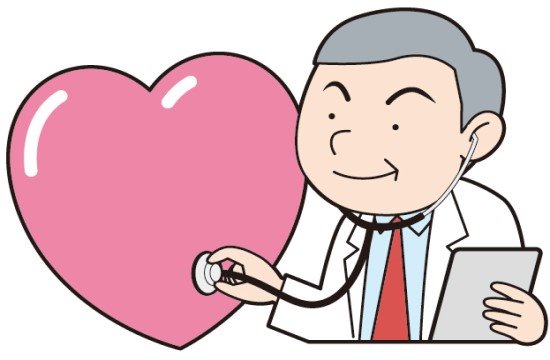
・認知行動療法
・対人関係療法
その他の治療法
・TMS治療 など
認知行動療法(CBT)
精神疾患の治療においては、薬による治療だけでなく心理的アプローチも重要です。その代表的なものが認知行動療法(CBT)です。これは思考や行動のパターンを分析し、否定的な考え方や行動を修正することで症状を改善する治療法です。薬で眠気が強く出る場合や副作用が気になる場合でも、認知行動療法を組み合わせることで治療効果を高め、薬の使用量を抑えることができるケースもあります。
カウンセリングや心理療法
臨床心理士やカウンセラーとの対話を通じて、不安や抑うつの原因を整理し、解決策を一緒に考える方法です。カウンセリングは精神的な支えとなり、疾患に伴うストレスを軽減します。薬だけに頼らず、心理的サポートを取り入れることで生活の質を向上させることができます。薬の副作用で眠いときでも心理療法を組み合わせればバランスをとりやすいのです。
生活習慣の改善(運動・食事・睡眠)
規則正しい生活リズムを整えることは、精神疾患の回復に欠かせません。軽い運動を取り入れることで脳内物質のバランスが改善され、気分の安定や不安軽減につながります。また、栄養バランスのとれた食事や十分な睡眠は、薬の副作用による眠気を軽減するサポートにもなります。例えば、寝る前のスマホ使用を控えたり、就寝前にリラックスできる習慣を取り入れることで、睡眠の質が高まり日中の眠気も和らぎやすくなります。薬物療法と生活改善を組み合わせることで、より効果的な治療が可能となります。
このように、薬物療法だけでなく心理療法や生活習慣の改善を取り入れることで、副作用のリスクを減らしながら症状の改善を目指せます。患者さんごとに合った方法を見つけることが大切です。
お悩みの方には精神科訪問看護もおすすめ!

精神科訪問看護とは?
精神科訪問看護
職種
・看護師
・准看護師
・作業療法士
訪問日数
原則週3日以内
精神疾患をお持ちの方の中には、薬の副作用で強い眠気を感じて外出や通院が難しい方もいらっしゃいます。そのようなときに役立つのが精神科訪問看護です。医師の指示のもと、看護師や作業療法士などがご自宅を訪問し、服薬管理や生活支援、病状の観察を行います。
精神科訪問看護は、うつ病や統合失調症、不安障害など幅広い疾患に対応しており、「薬を飲むと眠い」「症状が安定しない」といった悩みを持つ方にも安心して利用いただけるサポート体制です。通院が難しい方でも在宅で専門的な支援が受けられるのは大きなメリットです。
精神科訪問看護のサポート内容
訪問看護の内容は多岐にわたります。薬の飲み忘れを防ぐための服薬支援や、症状の観察、再発予防に向けた生活指導など、日常生活を安定させるための支援が中心です。また、家族へのサポートも行い、患者さんを取り巻く環境全体を整えることを目指します。
さらに、主治医や医療機関と連携し、病状や服薬状況を共有することで、より適切な治療やケアにつなげることができます。眠気の副作用が強くて日中の生活に支障が出る場合でも、訪問看護スタッフが状況を確認しながら調整できるため安心です。「薬による眠気」と「疾患の症状」を切り分けて対応できる専門職が支えてくれるのも特徴です。
また、外出が難しい方には在宅療養の継続支援を行い、必要に応じてデイサービスやショートステイなど他の制度利用の提案も可能です。精神疾患を抱える方が社会復帰を目指す過程でも、訪問看護は大きな役割を果たします。
精神疾患をお持ちならシンプレへ

シンプレ訪問看護ステーションの特徴
精神疾患全般
主な看護内容
・生活支援
・自立支援
・症状の悪化防止
・服薬支援
・社会復帰サポート
・家族の方への支援
シンプレ訪問看護ステーションは、うつ病や統合失調症、認知症など幅広い精神疾患に対応した訪問看護サービスを提供しています。薬を飲むと眠いなど副作用に悩む方でも、看護師や作業療法士がご自宅に訪問し、日常生活の工夫や服薬管理のサポートを行うため、安心して治療を継続できます。
また、シンプレでは利用者さまの生活の質を守りながら、疾患と向き合えるよう支援することを大切にしています。症状の再発予防や社会復帰のサポートも重視しており、利用者本人だけでなくご家族へのケアも手厚く行っています。「病気と共に生きながら自分らしさを取り戻す」ことを目指し、チーム体制で支援しています。
シンプレの対応エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリアは東京23区を中心に、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、府中市、東久留米市、さらには埼玉県の一部まで幅広くカバーしています。近隣の市区町村でも対応できる場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
訪問は週1〜3回を基本に、場合によっては週4回以上の訪問も可能です。1回の訪問は30分〜90分で、祝日や土曜日も対応しているため、ライフスタイルに合わせて利用できます。薬の副作用で眠気が強く、外出や通院が難しい方にとって、在宅で専門的な支援を受けられるのは大きな安心材料です。
さらに、対応可能な処置として胃ろう・自己導尿、ストーマ管理、在宅酸素療法、緩和ケアなど幅広いケアに対応しています。使用できる制度としては自立支援医療制度(精神通院)、生活保護、子ども医療費助成制度などがあり、経済的な負担を軽減しながらサービスを利用できます。「薬で眠いけど治療は続けたい」という方に寄り添ったサポートを提供できるのがシンプレの強みです。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ
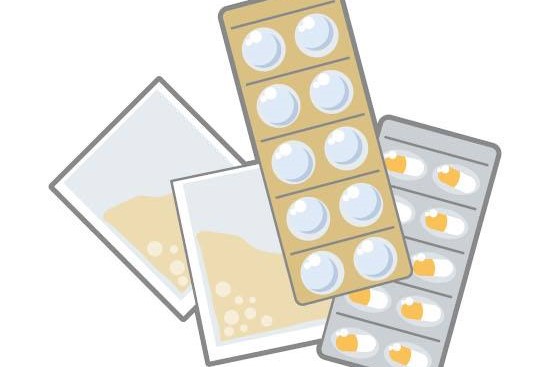
精神疾患の薬で眠気が起こるのはよくある副作用
精神疾患の治療薬には多くの場合、眠気という副作用がつきものです。特に抗うつ薬や抗不安薬、抗精神病薬の一部は脳の覚醒物質を抑える働きがあるため、眠くなりやすい特徴があります。薬の効果と副作用は表裏一体であり、眠気があるからといって必ずしも薬が合っていないとは限りません。副作用の眠気は一時的なものの場合も多く、体が慣れるにつれて軽減することもあります。
眠気の原因は薬だけでなく疾患や生活習慣にも関係
眠気の原因は薬だけではありません。うつ病や不安障害などの疾患そのものによる睡眠障害、生活リズムの乱れ、さらにはホルモンバランスの変化なども眠気に関与します。「眠い=薬のせい」とは限らないため、複数の要因を考慮することが大切です。生活習慣の改善や心理療法など薬以外の方法を取り入れることで、眠気の軽減や症状の改善につながることもあります。
気になる場合は必ず医師に相談を
薬による眠気が強く、仕事や日常生活に支障をきたす場合は、自己判断せずに必ず医師へ相談しましょう。服用量の調整や薬の切り替え、服薬時間の工夫などで改善できるケースもあります。放置すると症状の悪化や事故のリスクにつながるため、早めの対応が安心です。
また、眠気や副作用で外出や通院が難しい場合には、精神科訪問看護を利用するという選択肢もあります。看護師や作業療法士が自宅で支援を行い、服薬や生活面のサポートをしてくれるため、治療の継続がしやすくなります。精神疾患と向き合う上で「眠気にどう対応するか」は重要な課題です。正しい知識を持ち、専門家と協力しながら、自分に合った治療方法を見つけていきましょう。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (5)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



