医療保険で訪問看護を受けられる条件を解説|介護保険との違いや利用手順も紹介【シンプレ訪問看護】
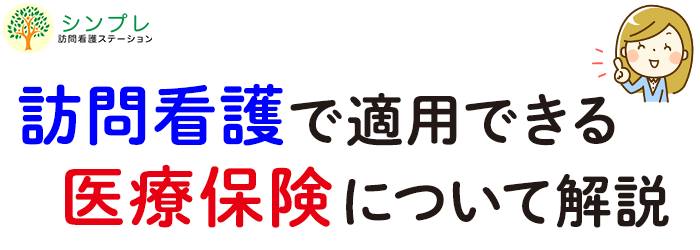
「訪問看護は医療保険が使えるの?」と気になっていませんか?
訪問看護は、自宅で療養を続ける方が安心して生活できるよう、看護師などの医療従事者がご自宅を訪問し、健康管理や治療のサポートを行うサービスです。
しかし、「介護保険と医療保険、どちらを使えばいいの?」「医療保険が使えるのはどんな場合?」など、制度の違いがわかりにくいと感じる方も多いでしょう。
この記事では、医療保険による訪問看護が適用される条件や、介護保険との違い、利用制限、実際の利用手続きまで詳しく解説します。
訪問看護を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
訪問看護に医療保険が適用されるケース

要介護・要支援認定を受けていない方
訪問看護は、要介護・要支援認定を受けていない方であっても、医療保険の対象となる場合があります。特に40歳未満の方や、介護保険の対象外となる疾患をお持ちの方が該当します。
介護保険と医療保険は同時に利用できず、基本的には要介護認定を受けている方は介護保険を優先して使用します。一方で、認定を受けていない方や、医師が必要と判断した場合は医療保険による訪問看護が可能です。
また、40歳以上でも要支援・要介護認定をまだ受けていない場合や、病状の悪化などで一時的に医療的支援が必要な場合にも、医療保険を使った訪問看護を利用できます。
厚生労働大臣が認める疾病をお持ちの方
厚生労働大臣が定める特定の疾病(末期の悪性腫瘍や進行性筋ジストロフィー症など)に該当する方は、介護認定の有無にかかわらず、医療保険で訪問看護を利用できます。
これらの疾病は、日常生活に医療的管理が必要な場合が多いため医療保険の対象として継続的な訪問看護が認められています。該当するかどうかは、主治医や訪問看護ステーションに確認すると良いでしょう。
急性増悪など医師が必要と判断したケース
慢性疾患の悪化や、肺炎・糖尿病の急性発作、心不全の悪化など、症状が急に悪化した場合(急性増悪)には、医療保険による訪問看護が認められます。
この場合、主治医の指示に基づいて看護師が訪問し、状態の安定化や再入院の防止を目的にケアを行います。訪問回数や内容は医師の判断で柔軟に設定されるため、状況に合わせたサポートが受けられます。
自己判断での対応は難しいため、症状の変化を感じたら早めに医療機関に相談し、主治医の診察を受けるようにしましょう。
医療保険と介護保険の違いを整理しよう

それぞれの対象条件をチェック
訪問看護を利用する際には、まず「医療保険」と「介護保険」のどちらが適用されるかを確認する必要があります。両者は似ているようでいて、対象となる人や利用できる条件が大きく異なります。
| 条件 | 介護保険
|
医療保険
|
|---|---|---|
| 書類交付の有無 | あり | あり |
| 年齢 | 40歳から | 年齢制限なし |
| 適用条件 | 要支援・要介護の認定を受けた方 | 要支援・要介護 非認定の方(65歳以上も対象) |
このように、介護保険は「介護が必要」と認定された方が対象であり、医療保険で訪問看護は認定を受けていない方や、医師が必要と判断した方を対象としています。
どちらの保険で訪問看護を利用するかは、本人の健康状態や年齢、介護認定の有無によって異なります。主治医や訪問看護ステーションに相談し、自分に合った保険制度を選ぶことが大切です。
医療保険は病気や怪我に幅広く対応
医療保険は、怪我や病気の治療費を補助するための保険制度です。日本では国民皆保険制度により、すべての人が何らかの医療保険に加入しています。病院を受診する際、保険証を提示することで医療費の一部を公的保険が負担してくれます。
この医療保険は、病院での診察や入院だけでなく、訪問看護や訪問リハビリといった在宅医療にも適用される場合があります。慢性疾患や精神疾患など、継続的なケアが必要なケースでは、医療保険で訪問看護を受けることができる点が大きな特徴です。
自己負担の割合は年齢や所得によって異なりますが、医療保険を使うことで医療費の負担を軽減し、自宅療養を継続しやすくなります。
介護保険は介護や生活支援に特化
一方で介護保険は、介護や生活支援を中心にしたサービスを提供する制度です。主に65歳以上で、介護が必要と認定された方が対象となります。介護保険を利用することで、訪問介護やデイサービス、福祉用具のレンタルなど、日常生活を支える支援を受けられます。
訪問看護についても、要介護認定を受けていれば介護保険の枠内で利用できます。ただし、医療的なサポートを中心としたケアが必要な場合は、医療保険による訪問看護が適していることもあります。
介護保険は生活の質を維持するための制度であり、医療保険は治療や健康管理を支援する制度という違いを理解しておくと、より適切にサービスを選ぶことができます。
医療保険を使った訪問看護の利用制限について

医療保険を利用した訪問看護には、利用回数や時間などに一定の制限が設けられています。これは、医療資源を適切に配分しながら、必要な方に必要なケアを届けるための仕組みです。
一般的には、訪問看護ステーションが医療保険を使ってサービスを提供する場合、1日あたりや週あたりの訪問回数、利用できるステーション数に上限が設けられています。
| 日数 | 回数
|
|---|---|
| 原則 | 1日1回 |
| 原則1週間 | 3回まで |
| 利用ステーション | 1箇所まで |
上記のように、医療保険による訪問看護は「1日1回・週3回まで」が基本的なルールです。これを超えて訪問する場合は、医師の特別な指示や厚生労働大臣が定める特定の条件を満たす必要があります。
また、訪問時間は1回あたり30分〜90分と定められており、体調や症状に応じて柔軟に調整されます。短時間での健康チェックや服薬管理を行う場合もあれば、長時間にわたってリハビリや生活支援を行うこともあります。
訪問看護を継続的に受ける場合には、利用者の状態を定期的に見直し、主治医と訪問看護ステーションが連携して内容や頻度を調整します。必要に応じて週4回以上の訪問も可能ですが、その際は医師の判断と特例の申請が求められます。
こうした制限は「医療保険で訪問看護」の公的制度の中で公平性を保つための仕組みであり、病状に応じた柔軟な対応が行われる点も特徴です。
医療保険の訪問看護で制限が解除されるケース

通常、医療保険で訪問看護には回数や時間の制限がありますが、患者さんの状態によってはこの制限が解除される場合があります。制限が解除されると、1日複数回や毎日の訪問など、より手厚い看護が受けられます。
ここでは、制限が外れる3つの主なケースについて解説します。いずれも厚生労働大臣が定める特定の状態・疾病・医師の判断に基づくもので、医療的な管理が特に必要な方が対象です。
厚生労働大臣が定める特定の状態
- 在宅で気管切開をしている方
- 人工肛門(ストーマ)や人工膀胱をお持ちの方
- 重度の褥瘡(真皮を超えるもの)を有する方
このような状態に該当する方は、生命維持や感染防止のために定期的かつ頻回な看護が必要と判断され、医療保険による訪問看護の回数制限が解除されます。
制限解除後は、1日複数回の訪問や、毎日の訪問も可能になります。たとえば、人工呼吸器の管理や吸引、褥瘡処置など、継続的な医療処置が必要な方には柔軟なスケジュールでサポートが提供されます。
厚生労働大臣が定める疾病がある場合
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患 など
これらの疾病は、厚生労働大臣が「継続的な医療管理が必要」と定めた疾患です。これらに該当する場合は、要介護・要支援認定を受けている方でも医療保険で訪問看護を利用できます。
対象疾患は複数あり、症状の進行度によっても適用が異なるため、主治医に確認することをおすすめします。特に、在宅での治療や療養が続く方にとって、医療保険のサポートは大きな安心につながります。
病状が急激に悪化したとき
- 急性感染症などで病状が急に悪化した場合
- 末期の悪性腫瘍以外の終末期にある場合
- 退院直後で頻回な訪問が必要と医師が判断した場合
病状の変化が激しい時期には、症状の観察や処置を頻繁に行う必要があるため、訪問回数の制限が一時的に解除されます。たとえば、退院直後の生活リズムの安定や服薬管理、創部処置などが該当します。
主治医の指示により週4回以上の訪問が可能となることもあり、病状が落ち着くまで重点的にサポートが行われます。この柔軟な対応により、入院を避けつつ在宅での療養を継続することが可能になります。
制限が解除される条件は、患者の状態や医師の判断によって異なります。不安がある場合は、主治医や訪問看護ステーションに相談して、自分が対象となるか確認しておくと安心です。
制限解除時の利用条件は?

| 日数 | 回数 |
|---|---|
| 1日 | 複数回の利用が可能 |
| 1週間 | 毎日の利用が可能 |
| 利用ステーション数 | 2箇所まで (状態と疾病によっては3箇所まで) |
表にまとめている通り、制限が解除されると受けられるサービスの幅は大きく広がります。1日に利用できる回数が1回から複数回に増え、毎日でも利用ができるようになります。
さらに、医師の指示がある場合、1つのステーションしか利用できなかったのが、2~3ステーションまで利用することができるようになります。
疾病等や状態によって毎日のサポートが必要と判断された場合、3か所のステーションを利用することができます。
医療保険の自己負担額は?

2割
6歳以上(義務教育就学後)~70歳未満
3割
70歳以上75歳未満
2割 現役並みの所得者は3割
75歳以上
1割 現役並みの所得者は3割
医療保険の自己負担額は、一番多い時は3割で一番少ない時は1割です。若いうちや働き盛りの年代は、体も元気で怪我や病気になるリスクが少ないので負担額は大目になります。
逆に高齢者は病気も怪我もリスクが高まるので、負担する金額は少なくなっています。また、定年後で収入も少なくなっている点も加味されての減額です。
そのため、高齢者でも収入が十分にあると判断されると、負担割合は3割負担となります。
医療保険を利用して訪問看護を受けるには?

「医療保険で訪問看護を利用したいけれど、どんな手続きが必要?」「どんなサポートが受けられるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
訪問看護は、かかりつけ医や主治医の指示に基づいて行われる在宅支援サービスです。医療保険を使うことで、病状の安定や再発予防、生活面のサポートなどを自宅で受けることができます。
訪問看護で受けられるサービス内容
| 資格 | ・看護師 ・准看護師  |
|---|---|
| 主な支援内容 | ・健康状態のアセスメント ・日常生活の支援 ・服薬管理や心理的支援 ・退院後の療養支援 |
訪問看護では、医師の指示のもとに専門の看護師がご自宅を訪問し、健康状態の観察や服薬管理、清潔ケア、医療処置などを行います。体や心の状態を総合的にサポートするため、医療保険を利用した在宅療養に欠かせない存在です。
また、ご家族への相談対応や介護負担の軽減にもつながるため、退院後や慢性疾患を抱える方の生活支援にも役立ちます。
医療保険で訪問看護を受ける際の相談先
- お近くの訪問看護ステーション
- 通院中の医療機関(主治医)
- 保健所・保健センター
まずは主治医へ相談し、訪問看護が必要かどうか判断してもらいましょう。主治医の指示書が発行されると、訪問看護ステーションで正式な契約・利用開始ができます。
また、保健所や自治体の保健センターにも相談窓口があり、医療保険で利用できるステーションや費用助成について案内してもらえます。
どの制度を使えばよいか迷う場合は、当ステーションのスタッフにご相談ください。状況に合わせて、医療保険・介護保険いずれの利用が最適かを一緒に検討いたします。
精神疾患の場合は「精神科訪問看護」が利用可能
うつ病・統合失調症・双極性障害などが対象
精神科訪問看護は、うつ病・統合失調症・双極性障害など、心の病気を抱える方が対象です。主治医が必要と認めた場合、医療保険を使って定期的に訪問看護を受けられます。
主治医の指示書に基づいて訪問可能
利用の際は、主治医が作成する「精神科訪問看護指示書」が必要です。これにより、医療保険を利用して安心してサービスを受けることができます。
服薬管理や生活リズムの支援など精神科特有のケア
訪問看護では、服薬管理や睡眠・食事のリズムを整える支援、再発予防のためのアドバイスなど、精神疾患に特化したケアを行います。<ご本人だけでなくご家族の支援も大切にし、安心して療養できる環境づくりを目指しています。
訪問看護ならシンプレ訪問看護ステーションへ!

「どの訪問看護ステーションを選べばいいのかわからない」「精神疾患にも対応しているの?」と迷う方へ。シンプレ訪問看護ステーションでは、精神科訪問看護に特化したサービスを提供しています。
うつ病や統合失調症、双極性障害など、心の不調を抱える方に対しても安心してご利用いただけるよう、医療機関との連携を密に行いながら、在宅療養を支えます。医療保険を使った訪問看護で、自宅にいながら専門的なサポートを受けられるのが特徴です。
シンプレ訪問看護ステーションとは?
シンプレは、精神疾患を中心に、在宅で療養を続けたい方を支援する訪問看護サービスです。外出が難しい方や、治療を中断しがちな方でも、ご自宅で継続的に医療サポートを受けることができます。
主治医の指示書に基づいて訪問を行い、症状の観察・服薬管理・生活リズムの調整などを通して、安定した生活をサポートします。必要に応じてご家族からの相談も受け付けており、安心できる療養環境を整えています。
精神科訪問看護に強い理由
精神疾患に精通したスタッフが在籍
当ステーションには、精神科での経験が豊富な看護師・准看護師・作業療法士が多数在籍しています。うつ病や統合失調症、パニック障害など、多様な精神疾患に対応できる専門知識と実践経験を活かし、利用者様の状態に合わせた柔軟なケアを行います。
医療保険を使って安心して利用できる
シンプレでは医療保険で訪問看護を活用できるため、自己負担を抑えつつ、定期的なサポートを受けることが可能です。介護保険との併用や自立支援医療制度にも対応しており、費用面の不安を軽減します。
ご家族の相談・ケアもサポート
ご本人だけでなく、ご家族のメンタルケアや生活支援も重視しています。看護師がご家族と連携し、接し方や支援方法などを一緒に考えることで、家庭全体で安心して療養を続けられる環境づくりを行います。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
シンプレ訪問看護ステーションでは、以下のエリアを中心に訪問を行っています。
- 東京都23区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、府中市、東久留米市
- 埼玉県一部地域(近隣エリアも応相談)
訪問は週1〜3回を基本とし、必要に応じて週4回以上の対応も可能です。土曜・祝日も訪問しており、1回あたり30〜90分のケアを提供しています。
まずはお電話・公式LINE・お問い合わせフォームなどからお気軽にご相談ください。病状や生活環境に合わせて、最適な訪問看護プランをご提案いたします。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ|医療保険で訪問看護を受ける条件を理解して安心のサポートを
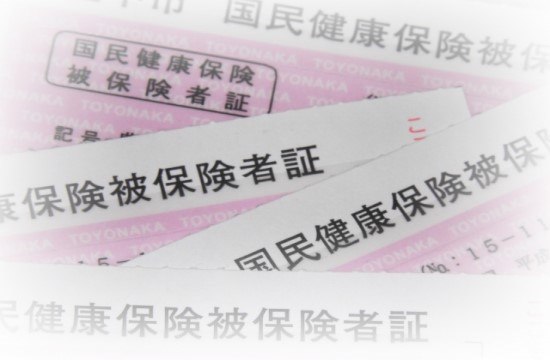
訪問看護は、医療保険と介護保険のどちらかが適用される仕組みですが、要介護認定の有無や病状によって使える保険が異なります。
基本的には、要介護・要支援認定を受けていない方や、厚生労働大臣が定める疾病をお持ちの方は、医療保険による訪問看護の対象となります。また、病状の急変や退院直後など、医師の判断によって制限が解除されるケースもあります。
医療保険による訪問看護は、病院に通わず自宅で医療的サポートを受けられるため、身体的・精神的な負担を軽減できるのが大きなメリットです。訪問回数や時間に制限がある場合でも、主治医や看護師と連携することで、より柔軟な支援を受けることができます。
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神疾患を中心に幅広い疾患に対応し、医療保険を使って安心して訪問看護を受けられる体制を整えています。うつ病・統合失調症・発達障害などの方も対象で、ご本人やご家族の不安を軽減できるよう丁寧にサポートします。
医療保険で訪問看護を検討している方は、まずは主治医や訪問看護ステーションに相談し、自分に合った制度とサポート内容を確認してみましょう。
シンプレ訪問看護ステーションでは、東京都23区・西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・東久留米市・埼玉県一部など幅広い地域に対応しています。
訪問看護や医療保険の利用でお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (5)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)





