摂食障害の症状とは?拒食症・過食症の特徴や原因・治療法を解説
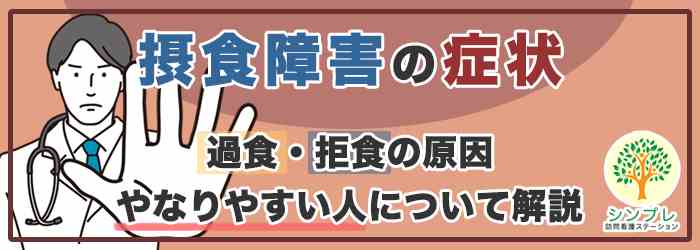
摂食障害の主な症状は、際限なく食べ続けてしまう「過食症」と食べることを拒んでしまう「拒食症」の二つに大別されます。
どちらも心身に深刻な影響を与える可能性があり、体重や食事への強いこだわりが日常生活を圧迫していきます。この記事では、摂食障害の症状の全体像を押さえつつ、原因やなりやすい人、治療の選択肢までわかりやすく解説します。気になるサインに心当たりがある場合は、ひとりで抱えこまず専門機関へ相談することが大切です。
摂食障害の症状は大きく二つに分けられる

ここでは、摂食障害の症状の中核である神経性無食欲症(拒食症)と神経性大食症(過食症)の特徴を整理します。共通するのは、体重や体型への強い恐怖や歪んだ認識が行動を駆動し、結果的に心身の不調へとつながる点です。
行動面の変化(食事制限、むちゃ食い、排出行為など)は目立ちやすい一方で、裏側には自己評価の低下や不安、抑うつといった心理的負担が潜んでいます。早めに気づき支援につながることが回復の近道となるため、客観的な情報で現状を見つめ直していきましょう。
神経性無食欲症(拒食症)の症状
拒食症は「太ること」への強い恐怖から、食事量の著しい制限や過度な運動を続け、低体重の状態を保とうとする病気です。数値の変化だけでなく、食や体型に関する考え方の偏りが行動を固定化させる点が特徴です。
身体的症状(極端な体重減少・無月経・冷え)
- 急激または持続的な体重減少、やせ細り
- 無月経/月経不順、手足の冷えや低体温
- 貧血・立ちくらみ・倦怠感などの体力低下
極端なエネルギー不足は内分泌系にも影響し、ホルモンバランスの乱れから無月経や骨量低下が起こりやすくなります。冷えやめまいが続く、体力が落ちて階段がつらい、といった生活上のサインも見逃せません。
筋肉量の減少は基礎代謝をさらに落とし、少量の食事でも「太るのでは」という不安を助長する悪循環を招きます。
精神的症状(強い自己否定・体型への歪んだ認識)
鏡を見るたびに「まだ太っている」と感じてしまうボディイメージの歪みや、「少しでも増えたら価値がない」といった極端な自己評価がみられます。
摂取カロリーや食品の種類に過度にこだわり、食事の場面を避ける、家族と別に食べるなどの行動が定着することもあります。完璧主義傾向が強いほど、「できなかった自分」を責める思考が強まり、社会活動や学業にも影響が及びます。
神経性大食症(過食症)の症状
過食症では、短時間に大量に食べてしまう「むちゃ食い」を繰り返します。多くの場合、その後に自己嘔吐や下剤・利尿剤の乱用、過度の運動などで体重増加を避けようとする排出行動が続き、心身の負担が重なります。
身体的症状(体重の増減・胃痛・歯の損傷)
- 体重の増減を頻繁に繰り返す
- 胃痛・腹部膨満感、脱水や電解質異常
- 吐きダコ、虫歯・歯のエナメル質の損傷
過食と排出のサイクルは食道・胃・口腔へ打撃を与えます。繰り返す嘔吐は電解質バランスを崩し、不整脈などのリスクを高めることも。
体重は増えたり減ったりを繰り返しがちで、「コントロールできない」という無力感を強化しやすいのが難点です。
精神的症状(罪悪感・自己嫌悪・抑うつ状態)
むちゃ食い後の強い罪悪感や自己嫌悪、「またやってしまった」という絶望感が続きます。
ストレスや孤独感を一時的に紛らわせるための行動が、かえって自己否定を深めるという悪循環に陥りやすく、不安や抑うつ症状を併発することも少なくありません。
そのほか特定不能の摂食障害(過食性障害・回避性摂食障害など)
拒食・過食の典型に当てはまらない場合でも、日常生活に支障をきたす食行動の問題は「特定不能の摂食障害」として適切な支援が必要です。
過食性障害はむちゃ食いを繰り返す一方、嘔吐などの排出を伴わない型では、肥満や生活習慣病のリスク増大が懸念されます。回避性摂食障害では味や食感、窒息への恐怖などが強く、栄養不足に陥ることがあります。早期の評価と継続支援が重要です。
こんな人が摂食障害になりやすい

摂食障害は、誰にでも起こりうる心の病ですが、とくに特定の性格傾向や環境にある人が発症しやすいとされています。
以下では、なりやすい人の特徴をタイプ別に解説します。自分や身近な人が当てはまる場合は、早めにサポートを受けることが大切です。
完璧主義・自己評価が低いタイプ
何事にも完璧を求め、少しの失敗でも自分を強く責めてしまう人は、摂食障害を発症しやすい傾向にあります。
「もっと頑張らなければ」「太るのは甘え」といった極端な思考が、食事制限や過食行動を引き起こします。自己評価の低さと完璧主義が共存するタイプほど、自分を許せず負のループに陥りやすいのが特徴です。
周囲の期待に応えようとする頑張り屋タイプも、知らず知らずのうちに自分を追い詰めてしまうことがあります。「できて当たり前」と思い込み、少しでも崩れると「自分には価値がない」と感じてしまうのです。
家族関係や人間関係の影響
家庭内での過干渉や支配的な関係、過度な期待なども発症の一因となります。
特に「親の期待に応えたい」「良い子でいなければ」という思いが強いと、自分の本音を抑え込んでストレスをためやすくなります。そのストレスが、食べる・食べないという形で表れやすくなります。
また、友人関係や職場での人間関係のストレスも、心のバランスを崩す要因の一つです。人と比べることが多い環境では、体型や見た目への意識が高まり、摂食障害のリスクを高めることがあります。
思春期・ストレス過多な環境にある人
思春期は体の変化や人間関係の悩みなど、心が不安定になりやすい時期です。この時期に「もっと痩せたい」「かわいく見られたい」といった願望が強まると、ダイエットがエスカレートし摂食障害に発展することがあります。
また、進学・就職・人間関係など環境の変化が多い時期も注意が必要です。ストレス過多な環境では食欲や睡眠リズムが乱れ、過食や拒食といった行動で気持ちをコントロールしようとする傾向が見られます。
SNSやメディアによる「理想体型」へのプレッシャー
現代ではSNSを通じて「痩せていること=美しい」といった価値観が広がり、無意識のうちに理想体型へのプレッシャーを感じてしまう人が増えています。加工された画像やモデル体型を日常的に見続けることで、現実とのギャップに苦しみ、自分の体に不満を抱くようになります。
こうした外的な影響が引き金となり、無理なダイエットや極端な食事制限を繰り返すケースも少なくありません。健康よりも見た目を優先してしまう風潮が、摂食障害のリスクを高めているといえます。
摂食障害の原因と患者数

摂食障害の背景には、心理的・環境的・生物学的な要因が複雑に絡み合っています。単なる「食の問題」ではなく、心のバランスが崩れた結果として現れる症状であることを理解することが大切です。
ここでは、主な原因と周囲が気づける前兆サイン、さらに近年の患者数の傾向について詳しく見ていきましょう。
摂食障害の主な原因(心理・環境・生物学的要因)
摂食障害の原因は一つではなく、性格や家庭環境、遺伝的な傾向などが重なって発症するといわれています。代表的な要因は以下の通りです。
- 心理的要因: 完璧主義、自己否定、ストレス耐性の低さなど
- 環境的要因: 家族関係の不和、学校や職場でのプレッシャー、SNSによる比較
- 生物学的要因: セロトニンなどの神経伝達物質の異常、ホルモンバランスの乱れ
特に「自分は価値がない」「頑張らなければ認められない」といった思考パターンがある人は、体型や食事をコントロールすることで安心感を得ようとする傾向があります。また、家庭環境や育った価値観が影響し、「痩せている=良い」といった固定観念が形成されているケースも多いです。
脳内の神経伝達物質が乱れることで、食欲や感情のコントロールが難しくなり、拒食や過食といった行動が強化されてしまうこともあります。
つまり、摂食障害は「心の問題」だけでなく、体の機能とも深く関係する病気なのです。
周囲の方から見た摂食障害の前兆サイン
摂食障害は初期の段階では本人も気づきにくく、周囲の観察が重要になります。以下のような行動変化が見られたら注意が必要です。
食事を避ける・隠れて食べる行動
家族や友人と一緒に食べたがらない、食事の量を極端に減らす、またはこっそり食べ物を隠すなどの行動は初期サインです。
「もう食べた」「お腹いっぱい」と言い訳をして食事を避ける傾向が強まります。
体型や体重への過剰なこだわり
少し体重が増えただけで強い不安を感じる、体重計を何度もチェックする、鏡を見るたびに「太った」と言うなど、自分の見た目に対する過度なこだわりが見られます。
周囲から見て十分に痩せていても、本人は「まだ太っている」と感じてしまうことがあります。
情緒不安・極端な気分の変化
感情の起伏が激しくなり、泣いたり怒ったりと気持ちが不安定になる場合もあります。
摂食障害はストレスや孤独感と密接に関係しており、気分の落ち込みや引きこもりが見られることも少なくありません。
周囲の人が「最近ちょっと変かも」と感じたら、早めに専門機関へ相談を促すことが重要です。本人が病気を自覚していないケースも多く、周囲の支えが回復の第一歩になります。
摂食障害の患者数と増加傾向
厚生労働省の調査では、日本国内の摂食障害患者数は年々増加傾向にあります。
現在は約22万人と推定されており、その多くが10代後半から20代前半の女性です。思春期に体型への関心が高まりやすく、ダイエット志向やSNSの影響を受けやすい年代が中心となっています。
また、男性の発症も近年増えつつあり、社会全体で「痩せている=正しい」という価値観が広がっていることが背景にあります。摂食障害の死亡率は約5%と高く、精神疾患の中でも重症化しやすい病気とされています。
摂食障害は、放置すると心身に深刻なダメージを与えることがありますが、早期に治療を始めることで十分に回復が見込めます。体調の変化や心の不調に気づいたときは、一人で抱え込まず、専門医やカウンセラーに相談することが大切です。
摂食障害の方がかかりやすい二次障害

摂食障害は、食行動の異常だけでなく、他の精神疾患や身体疾患を併発するケースが少なくありません。長期にわたる栄養不足や精神的ストレスが続くことで、体や心にさまざまな二次的な障害を引き起こすのです。
ここでは、代表的な二次障害として「不安障害」「うつ病」「低アルブミン血症」「骨粗しょう症や心臓障害」などについて解説します。
不安障害(対人不安・強迫的思考との関連)
- 人前で極度の緊張や恐怖を感じる
- 常に不安が続き、生活に支障が出る
摂食障害の方は、強いストレスや自己否定の影響で、不安障害を併発することがあります。中でも対人不安や社交不安は多く、「人に見られるのが怖い」「太っていると思われるのが嫌」といった恐怖心が日常生活を制限してしまうこともあります。
また、体重や食事に関して「〇〇しなければいけない」といった強迫的な思考が強くなる傾向もあります。こうした状態が続くと、外出や交流が減り、孤立が進んでしまうため、早期に支援を受けることが重要です。
うつ病(自己否定や孤独感の悪循環)
- 気分の落ち込み・無気力
- 自己否定・孤独感の強まり
摂食障害と深く関係しているのが「うつ病」です。
摂食障害の背景には、「自分は価値がない」「誰にも理解されない」といった自己否定があり、それがうつ状態を引き起こすことがあります。拒食症・過食症いずれも、栄養不足により脳の神経伝達物質が減少し、抑うつ症状が出やすくなります。
また、過食と自己嫌悪の繰り返しによって「どうせまた失敗する」と思い込み、さらに症状を悪化させる悪循環に陥ることもあります。適切な心理療法や薬物療法で感情の波を整えることが、回復の第一歩です。
低アルブミン血症(栄養不足による身体機能低下)
- 顔や手足のむくみ
- 体力・免疫力の低下
神経性無食欲症(拒食症)の方では、栄養不足によって血液中のタンパク質「アルブミン」が減少し、低アルブミン血症を引き起こすことがあります。
アルブミンは血液中の水分を保つ役割を持っており、減少すると水分が組織に漏れ出してむくみが生じます。
この状態が続くと、全身のだるさや倦怠感が強くなり、免疫力も低下。感染症にかかりやすくなるなど、身体全体の健康に深刻な影響を与えます。栄養補給と休養のバランスを保ちながら、医師の指導のもとで回復を図ることが重要です。
骨粗しょう症や心臓障害など身体的リスク
長期の拒食状態では、エストロゲンの減少によって骨密度が低下し、骨粗しょう症になるリスクが高まります。
軽い衝撃でも骨折しやすくなり、特に若年期の女性では将来の健康に影響する可能性があります。
また、極端な栄養不足や電解質バランスの乱れは、心臓への負担を増大させます。不整脈や心不全など命に関わる合併症を起こすケースもあり、摂食障害の重症化を防ぐためにも定期的な検査と医療介入が欠かせません。
このように、摂食障害は体重や食行動の問題だけでなく、全身に影響を及ぼす疾患です。精神的・身体的な二次障害を防ぐためにも、早期の発見と継続的なサポートが重要です。
摂食障害の治療法

摂食障害の治療は、心と体の両面からアプローチすることが基本です。単に食事量を増減させるだけではなく、考え方やストレスとの向き合い方を見直すことが大切です。
ここでは、代表的な治療法とその特徴、治療を進める際のポイントについて詳しく紹介します。複数の治療を組み合わせることで回復率が高まるとされています。
複数の治療法を組み合わせる
摂食障害は一つの治療法で完治することは少なく、患者の状態や性格、生活環境に合わせて複数の方法を組み合わせるのが一般的です。主な治療法には「環境調整」「対人関係療法」「行動認知療法」があります。
環境調整(生活リズム・家族支援)
環境調整とは、患者さんが安心して治療に取り組めるよう、生活環境を整えることを目的としています。学校や職場などで過剰なストレスを感じている場合は、一時的に休養を取り、心身の負担を軽減することが回復への第一歩です。
また、家族の理解と支援も不可欠です。家族が摂食障害を「意志の問題」ではなく「病気」として理解し、過度な干渉を避けながら見守ることが治療の成功につながります。
対人関係療法(人間関係の改善を重視)
対人関係療法は、患者さんの人間関係に焦点を当てて心の負担を軽くする治療法です。家庭や職場、友人関係などのストレス要因を整理し、より良いコミュニケーションを築くことで、自己肯定感を取り戻すことを目指します。
「他人の評価が気になる」「自分の気持ちを伝えられない」などの悩みを丁寧に扱うことで、摂食障害の根底にある心理的ストレスを解消していきます。
行動認知療法(思考のゆがみを修正する)
行動認知療法は、摂食障害に特有の「考え方のクセ」や「誤った認識」を修正していく治療法です。たとえば、「少し太ったら価値がない」といった極端な思考を「多少体重が増えても健康的でよい」と置き換えるなど、現実的な思考を身につけていきます。
日々の記録をつけながら、自分の感情と行動の関係を理解し、ストレスを感じたときに「食」以外の方法で気持ちを整える練習も行います。無理のないペースで行動変容を目指す点が特徴です。
薬物療法を補助的に行うこともある
摂食障害には、直接的に症状を治す薬はありませんが、うつ症状や不安が強い場合には抗うつ薬や抗不安薬を用いることがあります。薬物療法はあくまで心理療法を補助する位置づけであり、医師の指導のもと適切な量と期間で使用することが大切です。
薬による治療を行う際は、自己判断で中止したり、量を変えたりせず、定期的に医師と相談しながら進めるようにしましょう。薬の効果を過信せず、カウンセリングや環境改善と並行して行うことが重要です。
家族療法やグループ療法の活用
家族療法では、家族全体が摂食障害への理解を深め、サポート方法を学びます。家庭内の関係性が改善することで、本人の安心感や回復意欲が高まります。特に親子関係やパートナーシップの中にストレスがある場合、専門家の指導のもとで関係を再構築していくことが効果的です。
また、同じ悩みを持つ人たちと支え合う「グループ療法」も有効です。他の人の体験を聞くことで孤独感がやわらぎ、自分の回復への希望が持てるようになります。
摂食障害の治療は時間がかかるものですが、焦らずに少しずつ進めていくことが大切です。摂食障害は、正しい理解と継続的な支援によって回復が可能な病気です。自分を責めず、医師や専門家と二人三脚で向き合っていきましょう。
症状に悩んでいる方は無理せず相談を

摂食障害に悩んでいる方の中には、「自分で何とかできる」「病院へ行くほどではない」と感じ、長期間ひとりで抱え込んでしまう方も少なくありません。
しかし、摂食障害は心と体の両面に影響を与える病気であり、放置すると重症化することもあります。早めの相談と専門的なサポートが、回復への第一歩です。
早期発見・早期治療の重要性
摂食障害は早期に治療を始めることで、回復の可能性が大きく高まります。初期のうちにカウンセリングや医師による指導を受けることで、思考や行動のパターンを修正しやすくなります。
特に、「食事を避ける」「体型のことばかり考えてしまう」「体重の変動が激しい」といったサインがある場合は注意が必要です。心身の状態を自分で客観的に判断するのは難しいため、早めに専門家へ相談してみましょう。
摂食障害は意志の弱さではなく、心のバランスが崩れたことで起こる病気です。自分を責めるのではなく、治療を通して「自分を大切にする感覚」を取り戻すことが大切です。
相談先の選び方(医療機関・カウンセラー・家族)
摂食障害の相談先としては、以下のような選択肢があります。
- 精神科・心療内科(医師による診断・治療)
- 臨床心理士・公認心理師(カウンセリング・心理療法)
- 家族や信頼できる人への相談
- 摂食障害支援拠点病院や地域の精神保健福祉センター
「医療機関に行くのはハードルが高い」と感じる場合は、まず電話相談やオンラインカウンセリングを利用するのもおすすめです。全国には「よりそいホットライン」や「いのちの電話」など、無料で相談できる窓口もあります。
また、家族やパートナーに気持ちを伝えることも回復の助けになります。誰かに話すことで、これまで抱えてきた不安や孤独を少しずつ軽くすることができます。
一人で抱え込まないためのサポート体制
摂食障害は、時間をかけて少しずつ改善していく病気です。焦らず、自分のペースで治療に取り組むことが大切です。病院やカウンセラーと連携しながら、生活習慣を整えたり、ストレスを減らす工夫を続けていきましょう。
また、医療機関だけでなく、地域のサポート体制も活用できます。精神保健福祉センターでは専門スタッフが相談に応じ、必要に応じて治療機関や行政の支援につなげてくれます。近年では、訪問看護やオンライン支援サービスなども充実しており、自宅にいながら専門的なケアを受けることも可能です。
「もう限界かもしれない」と思ったときこそ、支援の手を借りるタイミングです。あなたの悩みを理解し、寄り添ってくれる人や機関を見つけましょう。
精神科訪問看護を利用する選択肢も

摂食障害に悩んでいる方の中には、「病院に行くのが不安」「通院を続けるのが難しい」と感じる方も多くいます。
そんなときに利用できるのが、精神科訪問看護です。専門の看護師などが自宅を訪問し、心と体のケアを継続的にサポートしてくれる制度で、外出が難しい方や治療を続けたい方にとって心強い支援手段となります。
精神科訪問看護とは?
精神科訪問看護とは、精神疾患や心理的な不調を抱える方のもとに、看護師・准看護師・作業療法士などの医療従事者が定期的に訪問し、生活支援や服薬管理、再発予防のためのケアを行う医療サービスです。
摂食障害の方の場合、食事や体調の管理を自宅でサポートしてもらえるため、病院への通院負担を軽減できます。また、医師の指示のもとで看護師が心身の状態を観察し、必要に応じて主治医や家族と連携をとることで、安定した生活を送る手助けになります。
精神科訪問看護のメリット(再発予防・安心できる支援)
- 自宅にいながら専門的なケアを受けられる
- 主治医と看護師が連携し、体調や服薬の管理をサポート
- 一人暮らしや外出が難しい方でも継続的なケアを受けることが可能
摂食障害は、再発を繰り返すことが多い病気です。精神科訪問看護では、生活リズムや食事状況の確認を通して、症状の再燃を早期に防ぐことができます。必要に応じて家族への助言や、社会復帰に向けた支援も受けられるのが特徴です。
また、訪問看護師が定期的に関わることで、「一人じゃない」という安心感を得られる点も大きなメリットです。孤独や不安を抱えやすい方にとって、心の支えとなる存在です。
精神科訪問看護の料金と利用の流れ
| 負担割合 | 月の初回訪問 | 2回目以降 |
|---|---|---|
1割負担 | 1,299円/回 | 855円/回 |
2割負担 | 2,598円/回 | 1,710円/回 |
3割負担 | 3,897円/回 | 2,565円/回 |
上記は週3回までの訪問料金となります。週4回以上訪問となる場合には料金が異なります。
精神科訪問看護では、医療保険を利用することにより自己負担を軽減できるメリットがあります。
30分を一区切りに利用可能。かかった費用については、年齢や所得によって変わり、医療費の1〜3割が自己負担となります。
また早朝や深夜などの時間外に依頼する場合や、長時間の訪問を行う場合は別途料金が発生します。
また自立支援医療制度という制度を利用すると料金が1割負担になるほか、所得に応じて自己負担が0円になる場合もございます。
精神科訪問看護は医療保険の対象となるため、経済的な負担を抑えて利用できます。訪問頻度は週1~3回が一般的で、1回あたり30分~90分ほどの訪問時間が設定されています。訪問内容や回数は、主治医の指示書に基づいて決定されます。
利用を希望する場合は、まず精神科・心療内科などの主治医に相談し、訪問看護指示書を発行してもらいます。その後、訪問看護ステーションと契約し、スケジュールを調整して訪問がスタートします。
訪問看護でできる具体的なサポート内容
・生活リズムの調整、家事や食事のアドバイス
・社会復帰に向けた目標設定や支援
症状の悪化防止・服薬支援
・心身の状態観察、再発予防のアドバイス
・薬の管理や服薬確認、医師との連携
家族への支援
・家族への説明・助言、介護や支援方法の提案
・利用できる福祉制度や社会資源の紹介
このように、精神科訪問看護は「病院に行くことが難しい人」「治療を中断してしまいがちな人」にとって、自宅で安心して支援を受けられるサービスです。摂食障害の症状の再発防止にもつながる有効な手段として、専門家のサポートを受けながら利用を検討してみましょう。
精神疾患をお持ちならシンプレへ

摂食障害などの精神疾患でお悩みの方にとって、信頼できるサポート体制を持つ訪問看護ステーションを選ぶことはとても重要です。シンプレ訪問看護ステーションでは、精神疾患に特化した専門スタッフがご自宅まで訪問し、一人ひとりの状態に寄り添いながら継続的な支援を行っています。安心して相談できる環境づくりを大切にし、再発予防や生活の安定を全力でサポートします。
シンプレの特徴
シンプレ訪問看護ステーションは、精神疾患や摂食障害・うつ病・発達障害・統合失調症など、幅広い症状に対応しています。精神科に特化しているため、病気の特性を理解した看護師・准看護師・作業療法士がチームで連携し、患者さまの生活を総合的にサポートします。
また、週1〜3回の訪問を基本とし、必要に応じて週4回以上の対応も可能です。祝日や土曜も訪問を行っているため、仕事や学校との両立をしながら治療を続けられます。
「病院へ行くのが難しい」「家族に負担をかけたくない」といった方でも、自宅で安心してケアを受けられるのが大きな特徴です。
シンプレの対応エリア
シンプレは東京都を中心に幅広い地域で訪問看護を行っています。対応エリアは以下の通りです。
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
上記以外の近隣エリアについても訪問可能な場合があります。お気軽にご相談ください。
訪問看護サービスを受けるまでの流れ
シンプレの訪問看護サービスは、次の流れでスムーズにご利用いただけます。
- お問い合わせ:お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
- 初回面談:ご自宅などで、現在の状況や希望を丁寧にヒアリングします。
- 主治医との連携:医師の指示書をもとに訪問看護計画を作成します。
- 訪問開始:ご利用者様の生活ペースに合わせて、週1〜3回の訪問を開始します。
利用できる制度には、自立支援医療制度(精神通院)や心身障害者医療費助成制度、生活保護制度などがあり、医療保険の適用によって費用負担を軽減できます。
シンプレは、摂食障害をはじめ、うつ病・不安障害・PTSD・認知症など幅広い精神疾患をサポート。ご本人だけでなく、ご家族の方への支援にも力を入れています。どんな小さな不安でもお気軽にご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

摂食障害の症状を理解し、早めの対応を
摂食障害は、単なる食の問題ではなく、心のバランスの崩れから生じる深刻な精神疾患です。拒食症・過食症などのタイプによって症状は異なりますが、共通して「体型へのこだわり」「自己否定」「ストレス」が関係しています。早期に気づき、適切な治療を始めることで回復の可能性は十分にあります。
特に、体重や食事へのこだわりが強くなったり、感情の起伏が激しくなったりした場合は、専門機関への相談を検討してください。一人で抱え込まずに支援を受けることが、症状の悪化を防ぐ最も効果的な方法です。
回復のためにできること・周囲ができる支援
摂食障害からの回復には、時間をかけて心と体の両面を整えることが必要です。まずは、自分を責めず、少しずつ「安心して食べる感覚」を取り戻していくことから始めましょう。カウンセリングや心理療法、訪問看護などを活用し、無理のないペースで治療を続けることが大切です。
周囲の家族や友人も、批判や指摘ではなく「見守る」「共感する」姿勢が求められます。本人のペースを尊重しながら、回復を支える環境を整えることが支援の第一歩です。
もし「どう支えたらいいかわからない」と感じる場合は、医療機関や支援センターに相談することをおすすめします。摂食障害に関する正しい知識を持つことで、本人にも周囲にも希望が生まれます。
シンプレ訪問看護ステーションでは、摂食障害をはじめとした精神疾患を抱える方やご家族に対し、在宅でのケア・服薬支援・再発予防などの支援を行っています。どんな小さな不安でも構いません。まずは気軽にご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



